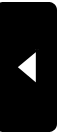2014年01月30日
灯籠流し
随想集Down to Earth-わが心 大地にあり- 散文編6
灯籠流し
青梅の花火を見にいったときに。
・・・そのうす青やみの川べりの道を、せせらぎわたる木立の道を、私たちは連れだって歩いた、忘れえぬ かの 夏の日の夕べ。葦の根洗う川のおもては白く照り映え、耳の底さらさらと たえまなく流れゆく調べ、蜻蛉が羽を休める川原の石は淡い柿色、なめらかな茜色、あるいは白いすじもように波のかたちを刻まれた青むらさき・・・ 小ぶりなのをひとつ、拾いあげて横ざまにつと飛ばせば、水のうねあいに波ひとつたて 岩間の川蝉をおどろかす、まるで光るトルコ石のつぶが、水面(みなも)かすめて飛びすさりゆく・・・
その宵方の土手の道を、山里とほき浅茅生の道を、私たちは手を取ってそぞろ歩いた、たぐひなく澄める かの おだやかな夕べ。みどりにうち重なった梢は蝉の声を降らせてますます色濃く、琥珀の精のすがしい蜜を、その芳しく野性の香気を地に充たし・・・ 木の葉のひとひら、なかば黄に、なかばみどりに、七宝のこまかなまだらを打ちながら、色あざやかに移りゆく そのみごとさに打ち捨ておけず、それをあなたに手渡した、苔むした小暗い道、羊歯の株、せりだした木の根、黒土の築地に守られたその細道よ。・・・
いでや、木下闇をうちいでて、流るる瀬のうえ、踏みゆくほどにぎしぎしときしみなる橋の上へ、弧を描いてせりあがったあの橋のうえへ登りゆこう・・・ 木肌なめらかに、すり減った欄干に手を突いて眺めやれば、ごらん、谷あいのこの広がり、眼前にぽっかりとうち開けた、山並みの悠々たるこの連なりよ。・・・ 川のいろいまだほのかなミルク色をたたえ、水の音ひびかせて流れゆく、両の木立はゆきひろがって山を包み、みどりから藍に、藍からあさぎに、かなたへかなたへ、山肌のうち重なってしだいに青くかすみゆく、そのあわいから 昼のあいだの火照りをゆっくりと逃がしてゆく・・・
空のいろは貝殻の裏がわの にぶい光宿したグラデエション、山ぎわに残るクリイム色のあかるみ、のみこんでのび広がりゆく 淡むらさきから菫色。・・・ その空の高いところを羽ばたいて、鳥たちがねぐらに還ってゆく、うかびあがる白鷺の白き翼、まぎれ沈む青鷺の暗き翼、・・・煤をまき散らしたように乱れとぶ燕たち、・・・烏や椋鳥たちよ。・・・ かくて佇みゆくほどに ゆっくりと宵闇の下りきて、川原の石の色あいもしだいに見分けがたく、両岸の木立のいろも暗く沈み、水のいろ空のいろも、やがてようよう沈みゆく・・・
かくて民べのつどい来る、橋のたもとへ、川原のもとへ、ぽつりぽつりとつどい来て、橋をわたって下りゆく、幻のごとく、影絵のごとく 私たちのうしろを通りすぎて、腰の折れまがった老婆に手をひかれ、薄地の帯かざり 金魚のひれのようにゆらめかしたわらは女(め)ども、ますらおの羊羹色の甚平や、紅おしろいの若い娘たちが。・・・ そのざわめきのなかに、華やいださざめきのなかに、そこはかとなく湛えられた愁ひの色は、あるいはこの時分、この風の涼みゆえのそら目なりしか、行き交ふ民のはざま、ふり向いたあなたのその象牙色の肌に、そのつややかなる黒髪に、まといつき、漂いながらほぐれていった、湯上がりの石鹸の残り香よ。・・・
日が沈んでしばらくしたあとの空のいろ、日が沈んでしばらくしたあとの河のいろ、その何ともうち言はれず 深み湛えたふしぎなブルー、ほのかに光宿せる幻惑のブルー、このいろをあなたに着せよう、ちぎれただよう雲の片はし、ゆらめく波の網目もようをも添えて、このいろを浴衣に仕立て、あなたの肩に着せかけよう・・・ 帯にはあの月のいろ、やはらかな乳白色に淡い金で、やや大ぶりの葦の柄を織りこんで、ふるえるように、ためらひがちに、灯の入ったばかりのランプみたいに、山あいからたったいま昇ったあの月のいろを配して。・・・
ゆく夏のおわり、灯籠流し。・・・ 今宵人びとはつどい来て、せせらぎひびく川のほとり、とりどりに美しく染めつけられ、叶えられた祈り、遂げられた願い、もたらされた日の光と雨と刈り入れのときとに礼して 篤心のことば書きつけられたる紙灯籠を、川の神に手向けて流す・・・ 思い思い、川原に下りては水の瀬に置かんとて身をかがむ、その姿は祈るひとのそれにも似て 静謐な叙情をたたえ。・・・ ぽっつりとやわらかな光を放つ灯籠がその手からはなたれ、今しもひとつ、ふたつ、流れにのって流されてゆく・・・ 子供らは声をあげ、飛沫をけちらして瀬のなかへ走りこむ、岸づたひに並んで走ってゆく、そのよび声が川風にのってかすかに届く・・・
闇のまさりゆくほど、しだいしだいに灯籠の数はふえ、あるいはたゆたいつ、あるいは流れにのって、川はばいっぱいに広がって流れゆく・・・ あるいはけざやにうち光り、あるいは心ぼそげにふるえつつ、そこの赤いの、向こうの青いの、手前の桔梗色、橙色、・・・檸曚色。 ・・・その光が水のおもてにうつってちろちろゆれる、どれもこれも、きっとあかるく灯しつづけよ、ゆめ その途上にやみ果てるなよ。・・・
とおく川上から しじまを渡ってくる笛太鼓の調べ、いくえに連ねた赤いぼんぼりを背に、ゆるやかに踊るシルエット、えいえいと伝えられてきた流儀、はるかな昔から変わることのない 山あいのひそやかな祭り。・・・ 山のかたちの移ることなく、月の満ち欠けのたゆむことのないように、彼らの暦もまた同じ、悠久の相をたたえてつづいてゆく。・・・
この村を私たちはゆき過ぎた、この山並みを私たちは宿した、数知れずふりつもった景色の底に。せまい山里に肩寄せあって暮らし、草深き通ひ路、そだの束 うず高く積みあげては往き来し、・・・鉈で打ち割る井戸の氷、うち傾いたわらぶきの屋根、わずかに切り開かれた花豆の畑。・・・
今も瞼によみがえる、柳の魚籠を腰に下げ、きらめくしぶきの間で釣り糸ひいた遠い夏の日、その光、いくたび通った草いきれの土手の道。・・・ 少年の日の私がよこぎって走りすぎたそのあとを、幼いあなたは自転車の荷台に揺られ、木もれ陽あびて揺られていった・・・ 月が大地をめぐるように、川の支流が出会うように、はるかな道のりを経めぐって いまひとたび、私たちはめぐりあった。・・・
ゆく河の流れ、灯籠流し。・・・ 生々流転の営みのなかで、混沌と青くうずまく銀河のなかで、いまひとたび めぐりあったことの奇蹟よ。・・・ どんな宿世の契りが結ばれたので、つひにあやまたず、ゆきたがふこともなく、かく互いの腕のなかへ辿り着くことができたのだろう・・・ 己れのうちに宿せる火を私たちは守りぬいた、その紅きほむらを葦風に吹き散らすこともなく、さかまく滝壺に呑みこまれてしまうこともなかった。・・・
ひと夏に燃えあがった恋を彩って花火があがる、いくつもいくつも大ぶりの菊が、そのやはらかな白金の花びらを夜空にひらき、すうと絵筆を走らせて 谷いっぱい、のびやかなその花びらを 藍染めの夜ぞらにひらき、・・・あとからあとから、それらはやがて天穹をおおふ枝垂れ柳となり、降りそそぎ流れくだる黄金色の驟雨となって、つひにはなごりの星のいくつぶとなりはてるまで、きらきらと 漂いながら、うち光りながら、その裾をひいて やがてしずかに消えてゆく・・・
橋の下をかいくぐって灯籠が流れ、私たちの恋が流れる、この川の瀬にうかべて流れゆく、あなたはいちばんあざやかに、皓々と光を放つあの灯籠だ、いかな巡りあわせからかその速水をそれて ひととき淀みのなかにとどまった、私はあの小さな葦の入り江だ・・・ 欄干に佇んであなたの背を抱き、そのあたたかみをこの肌に感じ・・・ 願はくは、あな 往かずもがな、ゆかずもがな、今宵もあすも、願はくは あたうかぎり長きにわたっていつの日までも、この比類なきともしびがきっと この腕のうちにとどまるようにと。・・・
03.Aug.
随想集Down to Earth-わが心 大地にあり- 目次へ
2014年01月30日
孤独
随想集Down to Earth-わが心 大地にあり- 散文編7
孤独
リンドバーグ夫人<海からの贈り物>をテーマに。
・・・そしてまたいつもの暗黙の諒解だった、いつもの無言の約束だった、それはあの深夜のカウンター、夜も更けて、人びとが常よりもよけいに打ちとけて己れの心を語る、あの居心地のよい、赤唐辛子色のぼんやりとやわらかな灯り、すり減った厚板のカウンターだった・・・ 組みあわせた両の手の上にあごをのせ、その犯しがたい厳しさを刻まれた横顔のライン まっすぐ前へ向けたまま、あなたはしずかな口調で言った、・・・二つの孤独な魂ですよ。・・・あんまり、べたべたしていてもね・・・ かくも互いに遠く隔たりながら、互いの心を推しはからんとしては 同じ光をもとめてえいえいと語らってきた長きにわたるこれらの日々の、これがその結論だった・・・
そしてこれらの日々、あなたの心は遠くナンタケットの青い海岸にあった、松林のあいだを潮風の吹きぬける、砂と貝がらと、水と空との果てしない広がりのほかにはただなにもない あのうつくしい浜辺に、あの白くあかるいみぎわに飛んでいた・・・ 季節はまだ早く、おもての夜風はまだ震えあがるほど冷たかったのに。・・・
かのひとの記したその小さな書物、それはそれほどにまであなたの心を動かしたので、その日あなたはそれを鞄からではなく、上着のポケットから取り出したのだった・・・
そしてそれらの日々、陽光あふれる浜辺の印象はすっかりあなたの心を奪ってしまった、その心を占拠してしまった、それであなたは松の木陰の小さな仮庵に私の姿を置き、その金褐色の髪が潮風に吹きなぶられ、波にぬれてはまた吹きなぶられるのを、塩気を残しながら吹きなぶられてはまた乾いてゆくさまを思い描いてみたりした、あるいはまた、浜辺の岩のあいだに身をうずめ、その肌に湿った白砂が押しつけられて、身を起こしてはぽろぽろと剥がれ落ちながらなおもくっついているさまを。・・・
その島で少女は一人だった、ただ飛び交う鴎たち、押し黙って沖を見つめるペリカンたちだけが友だちだった・・・ 茫漠とうち広がった大気のなかで両腕を拡げて踊る、その喜びは誰も知らない、その哀しみは誰にも責めを帰されない・・・ 彼女の日々はその足首に打ち寄せる波のようにあおく澄み、しゅうしゅうと泡たてて砂地にしみこんではまたあたらしく生まれてきた、風のように林を吹きぬけては梢をざわめかせ、その赴く先はだれも知らなかった、そしてあなたのその心もまた。・・・
孤独は海の貝がらのように、なかが空洞になったそれらはかくも容易に己れのうちに住まわせてしまう、風の音や砂つぶや海藻のかたまり、たまたま近くにいただけの、ほかの無数の小さな生き物たちを。・・・そうしなければいつまでも空っぽで、所在ないとでもいうように、あたかもそのそもそもの性質からして、どうしてもそのままではいられないとでもいうように。・・・
孤独は鏡のある部屋のように、ものごとのすがたを何倍にも大きくする、妄想はふくれあがって天井にまでのびあがり、音は地下のコンクリのガレージのように反響して すっかり空間を埋めつくしてしまう・・・
ひとりきりの時間を、ひとりきりの歳月を、あまりにも長いあいだずっとひとりでいたのちに見いだした私だったためだろうか、あなたの部屋の空っぽな椅子に、いつのまにやらどっかりと腰を据えてしまった私の面影、それをあなたはどうすべきだったのだろう?・・・
ひとりでいること、それは時としてひどく無防備で、危険だ、流砂のように、たちまち飲みこまれてしまう、あっというまもなく侵されてしまう、ひとりでいるときの感覚のすべてを。・・・あなたは揺れ動いていた、あなたは分裂して、矛盾にみちていた、あなたの内面は統合されていなかった・・・ 常に葛藤なのだ、あなたはそう言っていたっけ、そう、恐らくあなたはそういう人だから・・・ 私へと流れ落ちてゆこうとする己れの心を、腹立たしく思う夜もあったに違いない、激しい波のさなかにあって、己れの感情に屈して私の背を抱きしめているあいだ、私はひどく心配して、そう、あなたを揺らさぬよう、あなたを動かさぬよう、あなたがあとで後悔するであろうようなことをあなたにさせまいとして、身うごきひとつせぬままにじっと息をつめ、あなたの心を見守っていたのだった・・・ 私へと傾きかけた心見つめ、あやうい深淵のふちにある己れの心を知って、あの夜の抱擁にどんな意味を与えるべきか、あなた自身深く考えていたのにちがいない・・・
・・・二つの孤独な魂ですよ、そしてこれがその結論だった・・・
こうしてあなたは自分を守りぬいた、ひとたびは軌道をそれた惑星のように奇妙にも近づいたこの二つの道すじは 決して交わることなく、そしてふたたび遠ざかってゆくことだろう・・・ あなたはいっときの迷いを断ち切って、再び己れの道を歩きはじめるだろう・・・ こうしてあなたは正しかった、打ち寄せた波のはば広い、透明でなめらかな層の下でさあっと砂が退いてゆき、みるまに私をあなたから隔て はるか遠くへと運び去ってゆくような、どうしようもない淋しさを たとえ私に感じさせたとしても。・・・
それゆえ私は行かねばならない、あなたのそばから去らねばならない、あなたを安らかにあらしむために、これ以上かき乱さないために。・・・ なぜならあなたのその孤独は、あなたのうちにぽっかりと居座った空虚は、私の心に滲みて痛いのだ、あなたの孤独のかたちはガラスを透かして見るように、否が応でも生々しく、はっきりと見えてしまう・・・ それとも、こんなにはっきりと見えるのは私だけなのだろうか?・・・ あなたの孤独は、恐らくあなた自身の方がまだ耐えやすいのだろう、あなたはそれをこれまでずっと持ち運んできて、慣れているから。・・・
ひとりでいること。ふたりではなく。・・・
時にはふたりで、三人で、あるいはもっと多くの人びとのなかで過ごすとしても、さいごにはまたひとりになること。・・・
曖昧さに甘んじるということ、変わりやすさに堪えるということ、自分の立っている場所が、浜地の砂のようにたえず動きつづけることに慣れてゆくこと。・・・ 希望しないこと。所有しないこと。・・・ 恐らくそれが正しいあり方なのだ・・・ あなたの日夜通う、さびれた裏通りのごたごたと立てこんだ路地、非常階段の陰や荒れ放題の中庭や、さびついた水道栓のあたりに棲みついている、あのぶちや縞もようの美しい獣たち、その日の食物を手に入れるのも戦いであって、飢えと寒さはいつものことであり、誰もが羨むような自由を手にしながら、明日の命の保証はなく、やにだらけの、眼光鋭い目をして、敏捷で、人になつかず、うす汚れて不ぞろいな毛並みをした あの獣たちのように。・・・
ひとりでいること。ふたりではなく。・・・
それで事足りているわけではない、そんなことはありえない・・・ 耐えているのだ、必要なものが手に入らなくても、それで何とかやっていこうとしている・・・その気骨、そのりんとした風情は美しい。・・・ 生きてあること、それはつまり 何かを欠いているということではないのか?・・・ 生きてあること、それはつまり 痛みを感じているということではないのか?・・・ すっかり満たされてしまったとしたら、それはもう死と同じことではないのか?・・・ けれども尚、あるべきものを欠いたまま、痛みを感じつづけたまま ひとは無限にずっとやってゆけはしない、それゆえに、そう・・・ この世のいのちに限りがあるのは、おそらく神々の優しさなのだ・・・
これからまた 今までのように、夜昼あなたの窓辺を訪れる さまざまな種類の孤独があることだろう、それらは精霊たちのように、よいものもあれば悪いものもある、あるいは人間どうしの面倒なごたごたからあなたを引き離し、あなたの四方を壁で囲ってひとつのことがらに打ちこませる孤独、雲のいろ梢のかたちに心を留めて深く思いを至らせる孤独、あなたの想像力を広げさせて天の高みにまで導く孤独がある・・・ それらの何物にも代えがたい特質のゆえに、あなたはそれを大切に守ってきたのだ、じっさいあなたの成してきた仕事の大部分は、孤独のうちにしか成されえなかっただろう・・・ 無心に遊ぶ子供の孤独、それは孤独というべきだろうか、否、むしろ世界のほかのすべてのものからの自由というべきではないのか?・・・ そんなふうにいい塩梅だったのに、いつしかだんだんと苦い味のまじってくることもあるだろう・・・ 人を毒するたちの悪い孤独もある、しらじらとした午後の曇り空の孤独、雨のざあざあ打ちつける深夜の孤独、びしょぬれの傘、いくつかのつまらない野暮用、何でも自分でやらなくてはならないことの緩慢さ・・・ この世の誰にも待たれていないことの孤独、あなたのフィドルが響いていない間の孤独、それが歌っているときには影をひそめているが、死んでしまったわけではなく、その弓が置かれるや、またゆっくりと地平を覆いはじめるその孤独は。・・・
それはまた月のようにこの世界のおもてを渡ってゆき、あまたのイメージのかけらを、ちょうどそこへ光があたってきらめいた、いくつもの美しい断片を集めてゆくだろう、かくて再び孤独は鏡のある部屋にそれらを積みあげ、それらの姿を反響さすことだろう・・・ あなたの窓辺に、波はまた寄せては返し、寄せては返して、流木や貝がらのかけらや、あらゆるものを打ち寄せることだろう・・・ あなたの生にあまりにも深くなじんで、ほとんどあなたの一部となってしまった、あなたはあなたのその孤独を、舟にのせて漕ぎ進んでゆくことだろう・・・
・・・そしていつか、多くの歳月を重ねてのち、数知れぬ波を数えてのち、あなたの舟がついに辿り着く休息の地がある、もはや誰にもかき乱されることのない安息の地、詩人たちの魂の憩いつどうという かの西の最果てのくに、ひと呼んでトゥアハ・デ・ダナーン、かの地にあっては身にまとうものはただ夕映えの黄色い光のヴェールのみ、頭を飾るものはただ軽やかな蔓草の冠ばかり、人は裸足のままに歩きまわり、草の上にステップを踏み、地上の煩いごとをすべて忘れ去って笑いさざめき、杯を汲み交わすという・・・ かの地にあって私たちは互いの姿をそれと認めるだろうか、私にはあなたのことが分かるだろうか?・・・ きっと分かるだろうと私は思う、そしてそのとき、我々はもはや今ある立場も役割も捨て、何もよけいな飾りをつけない、素のままの魂に向きあうことができるだろう、今はただ慎み深さや、互いへの気遣いすらのゆえに隠されている、ありのままの姿を見ることができ、多くの事柄について、ありのままの言葉で語り合うことができるだろう・・・ きっとそうなるだろうと私は思う、そしてそのとき、二つの孤独な魂は、真に互いを見いだすことになるだろう・・・ その日を遠く思い見て、いま私は、私もまた 同じ孤独を運びゆくのだ・・・
03.Apr.
随想集Down to Earth-わが心 大地にあり- 目次へ
2014年01月30日
情交
随想集Down to Earth-わが心 大地にあり- 散文編8
情交
トマス・ハーディの<リールを弾くフィドラー>からの翻案による。
そのさいしょの日に、はじめてあなたの音色を耳にしたときに、それはすでに情交だった・・・ 物語は遅れてやってきたにすぎない、ほかの幾千のそれと変わらないその物語は。・・・
あれはオコンネルの家の収穫の祝いの席だった、溢れんばかりに実った 金色の小麦の香りも新たな暖炉の間、思い思いの楽器を手にして集うた村人たちのその中に、さいしょは目立たぬ暗がりに、荒野を吹き寄せられてきた一枚の枯れ葉のように どこからともなく現れた流れ者のあなたはいた・・・ いつに変わらぬ陽気な宴、弓は舞い跳ね、鼓笛は踊り、老いも若きもこぞって床の上にステップを踏んだ、にぎやかで騒々しいさざめきのうちに酒杯の重ねられ、とぶように時間の過ぎてゆく・・・ かくていつしか夜も更けて 話の種も尽き、音楽もとだえて人びとの散ってゆき、盛大な炎も踊り尽くして ただ灰を透かしてあかくうち光るばかり、すっかり閑散として 祭りのあとの、あのどんよりとしたもの悲しさの淀み沈むころ、・・・問はず語りにしずかに弾き出した そのゆるやかな もの悲しい調べ。・・・ 風吹き渡る荒野の音を そのとき私はこの耳に聞いた、露にぬれたヒースの花の冷たい手ざわりを たしかにこの手に感じ取った、大理石もようの陰影を打ち出した曇り空を まざまざとこの目に見た・・・ あんな音色はかつて今まで聞いたことがなかった。・・・
ロッホ・ブキャナン、谷あいの小さな村。・・・ 私たちのこの世界で、私たちの代に至るまで 私たちはなべてこんなふうに生きてきた・・・ 父祖の代から これが私たちの生き方だった、その一生を自らこの地に繋ぎ留め、野に出ては鍬を振るい、炉端には糸を紡ぎ、狭い輪の中で愛したり憎んだりして 幾歳月の雨風を肩寄せあってしのぎあい、かくて抜けようもなく その刻印をおのが身に刻んできた・・・ 私たちには私たちの 黒く煤けたパン焼き窯があった、手になじんだつるべと素焼きの壺とが、数知れぬ教えと習わしとが複雑に織りなされてできあがった 生の枠組みがあった・・・
あなたは違う、私たちの一人ではなかった、あなたはこの囲いのものではない黒い羊、毛色の違ったよそ者だった・・・ 風に吹かれるよもぎぐさ、彼方から此方へと彷徨い歩き、携えるとてはただ わずかな手荷物と一本のフィドル、草の根を枕に 久遠の郷愁を追いゆくもの・・・ 明日の身は知らず、ただ大いなる自由だけを喜びとし そのマントは暁の霧にまぎれ、その足どりは野の獣のごとく、ドアが開いて入ってくるとき、あなたはその身にまとうてみずみずしい樫の木の大枝の、野性の興趣を運んできた・・・
かくてあなたは私たちの一人ではなかったのに、いったいどういうわけだろう、あんなにも あなたの紡ぎ出す調べに私の弦は共鳴してふるえた、あたかもそれを耳にした瞬間に、ひとすじの黒羊の血が自分の中に、この自分の中にも流れることを知ったかのように。・・・ あなたは目を閉じてずっと弾きつづけ、私には目もくれなかった、それなのに、ちょうど心の中で考えたことを 通りすがりにぴたりと言い当てられたように、私は思いがけなさにどきっとして振り向いた・・・ あたかもずっと気づかずながら、そしてあなたと同じように、自分もまた孤独であったことを、突如として悟ったかのように。・・・ 用意するひまもなく、それは心に入ってきた、私の要塞の閂は引き抜かれ、石の上にかたりと落ちて響きわたった、あっというまもなかった、我に返るひまもなかった。・・・ この突然の侵略に戸惑い、一瞬 口にすることもできないようなイマージュが暗闇のなかに浮かんで消えた、何かやわらかいオレンジ色の光の オーロラのようにからみあうイマージュが。・・・
その弦の上にあって、なおもあなたのその指は 何と優しかったことだろう、うなじに指をすべらせるように、あなたは弦に指をすべらせる、心のひだに分け入るように、ひとつひとつの音をそんなにも大切に弾く、ただひとつとて決してなおざりにしない、すみずみにまで魂を打ちこめて・・・ その調べは滴り落ちる蜜のように甘く、この世ならぬ美酒のように人を酔い惑わす、それは荒ららぎだつ海をもしずめてあおく澄ませ、島々に魔法をかけて時ならぬ花を咲かせ、石の心をもとろかして思いのままに操っただろう・・・ なおもその内に秘めた思いの激しさは幻獣のように この地上の躯をとおく離れ去って、人知れず 月あかりの岩棚に身をのばす、そのしなやかにのびた背中のたてがみ 浮かびあがらせる逆光の銀色のシルエット、首すじを逆さになであげられるように 思わず身震いさせるほどに 極端に駆け上がりゆくその旋律の、切り立った岩山をひらりひらりと飛び移るように、あなたはそのてっぺんから手を延ばして 星をひとつ取ろうとした。・・・
そのかみ、教会から呪われ、追放されて、陰の身に、流浪の身に甘んじたフィドル弾きたち、酒場の暗がりのなかで心をかき乱す調べを奏でては 敬虔な娘たちをたぶらかし、いつのまにかその心のたがを外し去って熱い衝動のなかへ引きずりこんだ辻音楽師たち、荒野で秘密の修行を積み、悪魔と契約を結んで、人間業を越えた不可解な魔法を手に入れた詩人たち・・・ 伝説に聞く彼らの音色がどんなものだったか、私は今たしかに知った、彼らと同じ血をたしかにあなたも受け継いでいた・・・ 彼らを教会が排斥したのももっともなことだ!・・・ いったい誰があなたに、そんなふうに弾くことを許したのだろう、そんなふうに弾いてもいいと言ったのだろう?・・・ その響きを人々は認めないのか、いったい気がつかないなんてことがあるだろうか、どうして彼らはあなたに自由に弾かせておくのだろう、野放しにしておくのだろう、こんなにも危険で有害な、取り返しのつかない過ちに誘う調べを?・・・
それでもなお、あなたにはまだ 何か足りないものがあった、私にはそれが分かった、あなたは何かを探していた。・・・ はるか遠くを思い見て 憑かれたように探し求める、それはたぶん 一角獣の角の先についた宝石のように この世にないもの、決して見つかるはずのない愛を 永遠に求めつづけているような、・・・ そして私の中にもうひとつの空虚を見いだして まるで私を、この私を探しているようだった・・・ 何と言い表したらいいのだろう、その 胸をかきむしるように切ない調子を、ひたむきに疾駆するような 暗い森の中を 火の馬にまたがったゴブリンの乗り手、こずえの影ごしに飛びすさる、妖しいゆらめき、ほの光る艶。・・・ とぎれなく 高く低く歌いつづけ、奏でつづける、ときどき掠れがちに、心の高ぶりにつれてますます速度をはやめ、まるで伝えきれぬことばかりが溢れ出て胸を塞ぎ 言葉にならずに、ただその吐息だけが辛うじて思いを伝えようとするかのように ときどき掠れながら、奏でつづけるその旋律がこの胸を突き通し、痛いばかりに刺し貫くとき、それはすでに情交だった・・・ それは私の心を貝がらのように守っていた 私の孤独から私を引き剥がし、もしかしたらもう一つの魂を、もう一つの同じ魂を見いだしたのかと・・・ それは私を打ち落とし、それは私を屈伏させてしまう、それは私を内部から浸蝕し、炎のまわりでみるみる蝋が溶けてアラベスクの浮き彫りをなすように、私はあなたの音色に溶かされて白い半透明のアラベスクとなった、その金色の光をかこんで私の心はいくつにも裂かれ、あなたのまわりを輪舞する・・・
かくて私は焔の烙印を受けた、この身を焼かれる苦しみを持て余し、あなたの面影に焦がれて何軒の店を梯子したことだろう、幾夜虚しく待ちつづけたことだろう・・・ 窓に灯るやわらかなオレンジのあかり、身内のように気心の通じた村びとたち、心楽しいざわめきがあり、酒杯と陽気な音楽とがあっても、あなたがいなければ ただ何もないに等しかった・・・ 月あかりの五マイルの道 歩いて帰る、夜明けにはまた起きて家の仕事をするために。・・・
かくてはじめてあなたの音色を聞いた、あの日以来 世界は旋律を奏ではじめた、まるでいっせいに小鳥たちのさえずりはじめる 暁の訪れを受けたように。・・・朝の窓辺にさす光にしばし佇み、あなたを思う、胸にあふれるはかの調べ。・・・ どこにいても、何をしていても、私は世界があなたのフィドルに合わせて歌っているのを聞くようになった。その面影を抱いて村の辻々を往きめぐるとき、荷馬車はあやういところで私をよけて泥水と罵声とを浴びせかけ、乳搾りの娘たちは私をからかった、頭の中に藁くずでも詰まっているようだと、まるであらぬ方を眺めては ぼんやり思いに耽っているといって。・・・
かくてあの日以来 世界はその色相を変えた、まるで妖精の目薬を この瞳にふりかけられたように、それは突如この目を見開かせた。・・・ 谷間へ下ってゆくとき、燃え上がるような紅や琥珀に色づいた木々の梢の、その葉の一枚一枚はあなたの旋律をひびかせる音色だった、光に透かした葉脈の繊細なラインに至るまで、それらの打ち重なり、まだらに折り重なってまじりあい、豊かにどこまでも拡がってゆく、その息を呑むほどのあざやかさは、溢れんばかりのその豊かさは まるで信じがたいほどに、それは魔法の杖で私を打ち 圧倒する、どうしていいか分からないほどに。・・・ やがて季節の移り過ぎて 木立がしだいに色を失ってくすみ、すっかり葉を落としてさむざむと沈みゆくころに、炉端でまわす糸車のしずかなリズムに再びあなたの旋律が響きはじめた、あたらしい春のために力を蓄えながら眠る大地の歌が、しずかに力強く。・・・
単調な毎日のつづくこれら長き冬の日々、私たちのところに あなたはひきつづきとどまっていた。なおもこれらの日々、あなたが弾くと聞けば、どんなに遠いところへでも出掛けていった、流れ者のあなたが、私の知らぬまに いつまた別の土地へ去ってしまうだろうかと怖れながら。・・・ あなたが弓をつがえて奏ではじめ、瀟洒な蔓草もようで飾られた そのめくるめく渦巻く旋律のうねりの中に私をとらえ、私の四肢をからめて否応なくひきずりこむとき、それは情交だった・・・ あなたが弾きつづけるかぎり、私はステップを踏み、くるくるとまわりながら踊りつづける、やがて青いボンネットを後ろへはねのけ、木靴を床の上に脱ぎ捨てて、エールの滲みこんだ床板の上で踊りつづける、そのささくれが裸足の指に突き刺さっても まるで感じないほどに我を忘れて。・・・ あの子をごらん、ほら、あんなに頬をあかくほてらせて。どうしちゃったんだろう、まるで魔法にかけられたようだ・・・ ほかの娘たちが踊り疲れてやめてしまっても、あなたは私を休ませてくれない、みんなは私のために場所をあける、私のうしろで、異様な面持ちでひそひそと囁きあう、どうしたんだ、いったいあの子は、私はただ あなたに奏でられるだけの楽器となってしまった。・・・
かの狂おしく 熱に浮かされた日々のあいだ、どれだけの旋律が私を流れ過ぎていったことだろう、そしてそれらの日々のあいだ、あなたの奏でつづけたその調べは、川面にうかぶ泡つぶほどに数も尽きせぬその調べは つかまえてもつかまえてもたちまち私の指の間からこぼれ落ちていってしまう、けれどもその響きは、私はそれを決して忘れないだろう・・・ あなたの紡ぎだすその繊細な音色に その思い激しさを支えきれず、その音色は同じ流れのなかで不安定にゆれうごいて ふいにぐっと深くなったかと思えばふっと浅瀬になりして 川のように流れのように 尚も途切れることなく、おわることのない物語を綴るようにつづいてゆき、ついにあなたが弓を持つ手をとめた後も 私のなかでたえまなく響きつづける。・・・
長くつづいた冬のおわりの、あれは聖パトリックのお祭りの日、薄灰色の曇り空はまだ肌寒く、春の兆しはそちこちの梢にわずかに見えるばかり、それでも村には華やぎがみち、うきうきとした喜びにみちていた・・・ 女たちは朝早く起きてお祝いのパンを焼き、子供たちはよそいきを着せられて走り回り、楽隊を連ねて大通りを練り歩くあざやかな装いのパレードに、思い思いの衣装で加わったりした・・・ 綺麗だった、モノトーン一色だった村の情景に、ぱっと彩りが添えられて。通りの上には家々の窓から窓へ、旗を連ねた飾りが渡され、花火やクラッカーが打ち鳴らされた・・・ ああ、春がそこまで、もうそこまで来ている、人々は心かきたてられ、その足どりをいっそう急き立ててやろうと、銘々楽器を持ち出しては、街角のあちこちで奏ではじめた。・・・
あなたもまた どこかの家で弾いているはずだった、けれどもいったいどこにいるんだろう、シャムロックの女王の仮装のまま、心当たりをたずねてまわったのに、どこにも見つけることはできなかった。・・・ マクガイアの店でついさっきまで弾いていたと、店の主人が教えてくれた、踊り疲れて上気した人々の顔に、居心地のよいざわめきのなかに、あなたの調べのかきたてた熱気がまだ少しとどまっているようだった。・・・ 店を出て通りを歩きまわった、向こうの四つ辻で今しがた見かけたと、ファーガソンの娘が教えてくれた、とんがり帽子をかぶった若者たちも、長い首飾りをかけたおばあちゃんたちも、みんないっしょに踊り回っていたと、あんなふうに踊っているのは見たことがなかったと。・・・ 行き交う人々の間を縫って、あなたの調べの余韻が少しずつほどけながら 漂い流れて消えていった。・・・ そこにもかしこにもあなたはいた、けれどもその姿をつかまえることはできなかった。・・・ それとも私にだけ、その姿は見えなくなってしまったのだろうか?・・・
あてどもなく彷徨ううち、にぎやかな祭礼の一日はやがてゆっくりと暮れていった、窓辺には灯が灯されて、グラスにはなみなみとビールが注がれ、次から次へと人々のあいだを回されてゆく、音楽はますます熱気を帯びて盛り上がり、開け放たれた扉の向こうから街路へ流れだした、がやがやと歌声と威勢のいい掛け声とが、そしてそれは例によって一晩じゅうつづくのだ・・・
夜半、しずかに降りだした雨は、しだいに勢いを増して通りの石畳を洗い流した、パレードは引き揚げてしまい、旗飾りはぐしょぬれの惨めな姿になって雫を滴らせた・・・ すっかり閑散とした場末の路地の、さいごの店を虚し手に出てきてガス燈のもとに立ち尽くし、そのあかりが降り注ぐ雨のひとすじひとすじをきらきらと輝かせるのを見上げながら、私はあなたが行ってしまったことを知った。・・・ あなたはあなたの探している星を、この村に見いだすことができなかったのだ、それであなたは失望して、別の土地へ去っていったのだ・・・ あなたは気がついただろうか、ほんの少しでも気づいていただろうか、あなたのそのフィドルの調べが、どれほどこの胸を響かせたかを。・・・ 滴り落ちる雨の雫をちりばめて、緑色のガラスでできたシャムロックの冠は宝石のように光り輝いた、雨はまた私のガウンの一面にビーズ刺繍を縫い取りして、銀ねず色にきらめかせた・・・ 手折られた若枝の、徒らな奢り、一目ともあなたに見てもらえぬまま ただうつくしく飾られながら、なおもその調べの絶えることなく この胸に響きつづけるままに、私は降り注ぐ雨の中に立ち、暗闇の中に目を凝らした、あなたがどっちへ行ったのか知ろうとして、西の街道を下っていったのか、それとも北の荒野へ分け入っていったのかと。・・・
できることなら、あなたの奏でるそのフィドルになり代わりたかった、ひとたびその響きを耳にしてのち、それまで知っていた喜びの全ては意味を失い、色褪せてしまうと知っていた。・・・ いつか、いつかまた、あなたはやって来るだろうか、いや、そんなことはあてにできないと、私は私の孤独を抱いて、再び自分の生まれた村へ、自分の家の者たちのもとへ還ってゆかなくてはならないのだと、知ってはいても。・・・ 今となってはただ、どこから力を得ることができよう、あなたは行ってしまった、ひとたび情を交わした この世でただひとりのあなたは。・・・ 雨のなかに打ち棄てられて、悲しみのあまり張り裂けたフィドル、ただガス燈の青白い光が照らすばかり、二度と調べを奏でることはない・・・ 雨はやすみなく注ぎつづけ、夜の闇は明けることなく、そしてその日以来、私は虚空の中でただ あなたの音色を探しているのだ・・・
03.Mar.
随想集Down to Earth-わが心 大地にあり- 目次へ