2020年03月07日
アレクサンドルIII世橋(ショートフィルム)
アレクサンドルIII世橋(ショートフィルム)

(画像をクリックすると動画サイトが開きます)
去年撮ったフィクションの短いフィルムを公開したので、ご紹介します。
相当昔から構想しているもので、ちゃんと撮ると2時間の長編映画になるような作品ですが、
今回は全体のストーリーの要となる部分のみを撮影。
この記事では、作品のあらすじや撮影の経緯などについて記します。
***
<あらすじ>
シルヴィーはモンパルナスの貧しい踊り子だった。
ある日、彼女は裕福な実業家ジュスタンと出会う。
手に手を取って スターダムを駆け上がった二人。
だが ある晩…
というような物語。
これは実は遠い昔、夢で見たことをそっくり再現したものなのです。
あの頃はフランスに行ったことさえなかったけれど、たぶんあれはオペラ座だったと思う。
夢の中で私はシルヴィーを演じていた。というか、シルヴィーを生きていた。
最後の場面では、ほんとに心が打ち砕かれる思いがした。
目が覚めたとき、「なんて哲学的な夢だろう!」と思って、忘れないように書き留めておいた。
***
この場面のキーパーソンである<赤い男>の風貌や存在感が、ほんとに独特で。
これを映画で再現できたら面白いなあ、でもあの役柄を演じられる人はそうそういないだろうな、と思っていた。
ところが、去年、2019年の春先、ちょうど1年くらい前のことになるのだけど、
大学の映画制作クラスのさいしょの授業で、あらわれた講師の先生というのが…
ひと目見たとき、「あ、この人は<赤い男>だ!」って。
顔立ちや喋り方までも、夢で見たのとそっくり。
「ぜひともあの場面をこの授業で撮らなきゃ! そして、この人に<赤い男>を演じてもらわなきゃ!」と。
すぐさまシノプシスを送って、何度も頼み込んで、
「いや自分はプロの俳優じゃないから…」と渋るのを説得して、口説き落として、撮影にこぎつけたのです。
そのほかの登場人物は、クラスメートに頼んだり、その先生の知り合いの役者さんに声をかけてもらったり。
みんなほんとに親切に協力してくれました。ほんと、ありがたかった。
自分のプロジェクトとなると、いくら面倒でもちっとも苦にならないですね。
やることや準備すべきものが山ほどあったのだけど、楽しくて仕方なかった。
構内の撮影許可をどこに申請したらいいのか誰も知らなくて、4か所くらいたらい回しされたり。
カフェでも撮りたかったので撮影を願い出たけど、5件くらいまわってことごとく断られたり。
シナリオやデクパージュももちろん自分で書いて。
衣装はリサイクルショップで探したり、友だちが貸してくれたり。
シルヴィーのドレスのスカートの部分は自分でつくったのです。
モンマルトルの問屋街まで生地を買いに行ったりして。
知らなかったのだけど、有名なんですね。上野とか、あのへんの問屋街みたいな感じ。
そうそう、マスカレードの仮面もつくったのでした。
ネットでいろんな仮面の画像を検索して、参考にしたりして。
仮面に使う金紙売ってるお店探してまわったりした。
音楽もぜんぶオリジナルです。
台本書き、場所探し、衣装づくり、みんなへの連絡…。
なんか、やってること、劇団のときとほぼほぼ変わらない。w
去年の5月と7月に集まってもらって撮って、すぐに仕上げたかったのですが、
夏以来なぜだか編集ソフトが開かなくなってしまってね。
すごい四苦八苦して、ようやくまた開くやり方を見つけて。
おもにその技術的な問題で、今までかかってしまいました。
まあ、いろいろと不充分な点はありますが、目下の自己ベストです。
いつかこれ、物語の全体を撮れたらいいなあ。
レオス・カラックスの<ポン・ヌフの恋人>のためにつくられたパリの街のセットを、
使わせてくれたりしたらうれしいな。
この物語は文筆作品としても執筆中で、仕上がったらここにも乗せる予定です。

(画像をクリックすると動画サイトが開きます)
去年撮ったフィクションの短いフィルムを公開したので、ご紹介します。
相当昔から構想しているもので、ちゃんと撮ると2時間の長編映画になるような作品ですが、
今回は全体のストーリーの要となる部分のみを撮影。
この記事では、作品のあらすじや撮影の経緯などについて記します。
***
<あらすじ>
シルヴィーはモンパルナスの貧しい踊り子だった。
ある日、彼女は裕福な実業家ジュスタンと出会う。
手に手を取って スターダムを駆け上がった二人。
だが ある晩…
というような物語。
これは実は遠い昔、夢で見たことをそっくり再現したものなのです。
あの頃はフランスに行ったことさえなかったけれど、たぶんあれはオペラ座だったと思う。
夢の中で私はシルヴィーを演じていた。というか、シルヴィーを生きていた。
最後の場面では、ほんとに心が打ち砕かれる思いがした。
目が覚めたとき、「なんて哲学的な夢だろう!」と思って、忘れないように書き留めておいた。
***
この場面のキーパーソンである<赤い男>の風貌や存在感が、ほんとに独特で。
これを映画で再現できたら面白いなあ、でもあの役柄を演じられる人はそうそういないだろうな、と思っていた。
ところが、去年、2019年の春先、ちょうど1年くらい前のことになるのだけど、
大学の映画制作クラスのさいしょの授業で、あらわれた講師の先生というのが…
ひと目見たとき、「あ、この人は<赤い男>だ!」って。
顔立ちや喋り方までも、夢で見たのとそっくり。
「ぜひともあの場面をこの授業で撮らなきゃ! そして、この人に<赤い男>を演じてもらわなきゃ!」と。
すぐさまシノプシスを送って、何度も頼み込んで、
「いや自分はプロの俳優じゃないから…」と渋るのを説得して、口説き落として、撮影にこぎつけたのです。
そのほかの登場人物は、クラスメートに頼んだり、その先生の知り合いの役者さんに声をかけてもらったり。
みんなほんとに親切に協力してくれました。ほんと、ありがたかった。
自分のプロジェクトとなると、いくら面倒でもちっとも苦にならないですね。
やることや準備すべきものが山ほどあったのだけど、楽しくて仕方なかった。
構内の撮影許可をどこに申請したらいいのか誰も知らなくて、4か所くらいたらい回しされたり。
カフェでも撮りたかったので撮影を願い出たけど、5件くらいまわってことごとく断られたり。
シナリオやデクパージュももちろん自分で書いて。
衣装はリサイクルショップで探したり、友だちが貸してくれたり。
シルヴィーのドレスのスカートの部分は自分でつくったのです。
モンマルトルの問屋街まで生地を買いに行ったりして。
知らなかったのだけど、有名なんですね。上野とか、あのへんの問屋街みたいな感じ。
そうそう、マスカレードの仮面もつくったのでした。
ネットでいろんな仮面の画像を検索して、参考にしたりして。
仮面に使う金紙売ってるお店探してまわったりした。
音楽もぜんぶオリジナルです。
台本書き、場所探し、衣装づくり、みんなへの連絡…。
なんか、やってること、劇団のときとほぼほぼ変わらない。w
去年の5月と7月に集まってもらって撮って、すぐに仕上げたかったのですが、
夏以来なぜだか編集ソフトが開かなくなってしまってね。
すごい四苦八苦して、ようやくまた開くやり方を見つけて。
おもにその技術的な問題で、今までかかってしまいました。
まあ、いろいろと不充分な点はありますが、目下の自己ベストです。
いつかこれ、物語の全体を撮れたらいいなあ。
レオス・カラックスの<ポン・ヌフの恋人>のためにつくられたパリの街のセットを、
使わせてくれたりしたらうれしいな。
この物語は文筆作品としても執筆中で、仕上がったらここにも乗せる予定です。
2020年03月07日
海岸通りのデュラスへ(ドキュメンタリーフィルム)
海岸通りのデュラスへ(ドキュメンタリーフィルム)
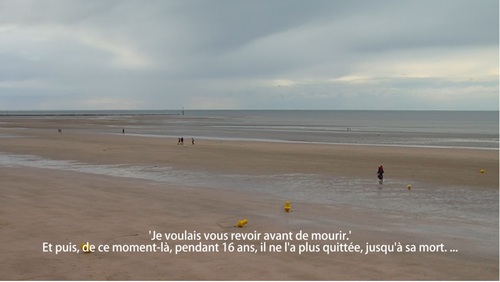
(画像をクリックすると動画サイトへ移動します)
ずっと前からとりかかっていた作品が、ようやく形になったのでご紹介します。
作家マルグリット・デュラスと、その晩年の恋人ヤン・アンドレアの軌跡をたどりながら、愛の本質について思いを巡らすドキュメンタリー。
2012年のはじめてのフランスへの旅の目的だった作品です。
って、どれだけ時間かかってるんだ…。
いまや住んで6年になろうというのに、フィルムの中の私はいまだ、フランスに着いたばっかりです。やれやれ。
というわけでこの記事では、この作品に取りかかってきた経緯と、作品のテーマについて少し記します。
***
映像の大部分は、2012年の旅行当時に撮影。ゆく先々、列車やバスの窓からカメラを回していました。
(ちなみにこのときの旅行についてはブログ記事にも書いています。
左のカテゴリバーの下のほうにある<仏蘭西紀2012>、および<仏蘭西紀2012その2>からどうぞ。)
ナレーションのテキストは、日本語で2014年に。
さいしょの語学学校の奨学金への応募の作文として書いた。
おかげで学費がだいぶ浮いたので、家計にも貢献したわけです。
そのフランス語訳は、2016年。こちらの院への応募のプロジェクトとして書き上げた。
院は落ちてしまったけれど、これつくっておいたおかげで今回すごい助かった。
当時の自分にはずいぶん背伸びした、無謀な企てで、しかも〆切までの時間との戦い。
でもやりたいことをやっていたので、作業のさなかは熱中して楽しかったな。
全体で10ページ以上あったのに、語学学校の先生、ひと晩で見て、直してくれて、ありがたかった。
2016年の夏には、夕方から夜にかけてのシーンに使うパリの街の風景をけっこうな量撮り直した。
旅行した2012年当時は、時間的な制限があったうえ、カメラのバッテリーの持続時間の問題もあって、
なかなか撮りたいだけ撮るというわけにいかなかったのです。
その点、「住んでる」というのは撮影には最強よね。
同じ年に、BGMに使う曲を5,6曲つくった。
久びさにバイオリンを引っぱり出してきて、肩あてのゴム管が劣化してしまっていたので買い替えたりしたっけ。
バイオリンの音色を使いたい曲があって、一週間くらい練習したけど、結局下手くそすぎてお蔵入り。w
結局ほぼすべてピアノとシンセサイザーで仕上げることに。
今回はそのうち4曲くらいを使っている。
2019年の春、大学の映画クラスの課題のひとつとして、これのダイジェスト版をまず制作。
そのときは不評だったが、それが今回のベースとなった。
そして秋学期の別のクラスで、めんどくさい心理戦のすえに何とか課題としてねじこむことに成功し
次から次へと降ってくるほかの授業の課題に邪魔されながらも、クリスマスからの2週間の突貫編集で
ほぼ形になるまで仕上げ。その後、細部の手直しを果てしなく繰り返して今に至るー。
今回、字幕として使うことになったフランス語のテキストは、このときもずいぶん直された。
学期中の大部分、この細部の表現のニュアンスをめぐってああでもない、こうでもないとやっていた。
この調子じゃいつまでたっても終わらない、と思えたほど。
でも、非ネイティヴの書いた独特な面白さがあるらしく、自分では分からないのだけど、
「そういう部分は、あなたのオリジナルだから、残しておく」と言われた。そう言ってくれるのは親切ね。
こんな感じに仕事や授業や何やのすきまを縫って、そのときどきの外からの要求をなるだけ利用して取りこみ、
擦り合わせながら、レンガをひとつずつ積み上げるように進めてきた。
形にしたいという思いはずっと持っていたから、さいごにはかなったけど… それにしても時間かかったな。
撮りためた映像や写真がとにかくいっぱいあって、すきま時間で整理しているとその中で迷子になってしまい、
ぜんぶ見終わったころには最初のほうがどうだったか忘れてる。その繰り返し。
全体を俯瞰し把握するというのは、まとまった時間がないとできないことだ。
それがこれまでかなわなかった最大の要因。
***
ところで、これは言っておかないと無責任だと思うので、言っておく。
これは「こうあってほしい」というのを体現した「私のフランス」にすぎない。
綺麗な映像ばかりのように見えるかもしれないが、上位1%のいちばん綺麗な上澄みを掬い取ったにすぎない。
ともかく、現実のフランスは、この100倍くらいイやなとこばっかりと思ってほしい。
あまりにイやなとこばっかりなので、せめて自分の作品の中でくらいは綺麗であってほしいと思ったの。
あ、でもいい人もいますよ、もちろん。これも言っておかないと。
***
作品のテーマについて。
長い時間をかけてひとつの作品をつくったときにありがちなのだけど、
作り手のものの考え方感じ方も変わってゆくから、今の私自身はあまりこういった問題について考えていない。
愛というのは深遠で普遍的なテーマで、いちどはとことん掘り下げてみるのもいいと思うけれど、
正直そんなにいつまでも、死ぬまでずっと考え続けるような問題でもないと思う。
このへんはいろいろ論争のあるところかもしれないけれど。
愛というコトバのイメージ、それがポジティヴかネガティヴかと言われると、私にとっては、それはネガティヴだ。
愛と言われると、まぁそういう育ち方をしているから仕方ないのだけれど、いまだに、まずさいしょに
キリスト教でいう愛のイメージを考えてしまう。神を愛せ、人を愛せ的な。
そしていまだにこのコトバに、かすかに首を絞められるような息苦しさを覚える。
つまり、私にとってそれはまず命令されるもの、要求されるものだったから。
愛というのが人類の追い求めるべき至上の価値のように言われているのは、考えてみるとふしぎだと思いませんか。
キリスト教国ならともかく、文化的にも政治的にもあんまりキリスト教とは関係のない日本においてさえ、
ほかの色んな価値を差し置いて、ちょっと別格で、特別なものに思われている気がする。でもほんとにそうだろうか。
そもそも、人が生きていくのに愛ってほんとうに必要? 私は必要とするだろうか?
愛とは なくてもやっていけるときに はじめて手に入るらしい… 興味深い考えではある。
けれど… 一周して戻ってきて、私はやっぱり、愛とは掛け心地のよいソファのようなものであってほしい。
それは変わらない。
なくてもやっていけるときにしか手に入らないものって、はっきり言って何になるの?
ゆっくり体を休めることもできず、場所を取るだけのソファなんて? ってことになってしまう。
愛とは掛け心地のよいソファのような… これが私のしぜんな感覚なのだけれど、
これが椅子でもベッドでもなくて、ソファっていうところが示唆的だなと思う。
ソファって、まぁ嗜好品よね。ぜったいないと生きていけないっていうようなものではない。
しかもほんとに掛け心地のよいソファなんて究極的にはあまり実在せず、
だいたいが体重をかけると潰れてしまうというもの。
こんなことを言うと恐れ多いようだけど、だったらそれほど意味ないのでは?
こうして受け取る側に対して保証できないうえ、愛はまた、与える側に対しても大変な負担を強いる。
愛は人の尊厳を奪う。けなされても罵倒されても耐えているヤンの姿。
愛している側の人間としてかくあるべきとは思うけれど、やっぱり…
見ているとこっちも惨めな気分になる。はっきり言ってあまり気持ちのいいものではない。
できればだれにも、あんな状況にあってほしくないと思ってしまう。
愛というのはもらうにしても与えるにしても、ちょっと重苦しすぎて要求が大きすぎる気がする。
私のために一生を捧げ、生きるも死ぬも私しだいなんて、
そんな類の愛を誰かに要求するのは、あまりに暴力的で、失礼で、気の毒すぎる。
今の私はそう思う。
このことはまた書くかもしれないけれど、長くなるので、とりあえずはこのへんで。
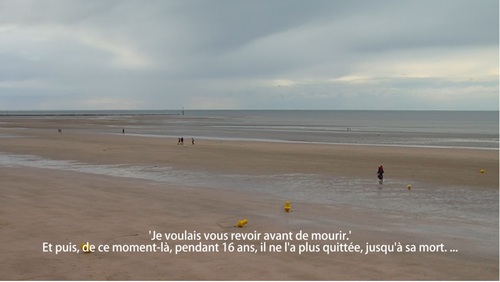
(画像をクリックすると動画サイトへ移動します)
ずっと前からとりかかっていた作品が、ようやく形になったのでご紹介します。
作家マルグリット・デュラスと、その晩年の恋人ヤン・アンドレアの軌跡をたどりながら、愛の本質について思いを巡らすドキュメンタリー。
2012年のはじめてのフランスへの旅の目的だった作品です。
って、どれだけ時間かかってるんだ…。
いまや住んで6年になろうというのに、フィルムの中の私はいまだ、フランスに着いたばっかりです。やれやれ。
というわけでこの記事では、この作品に取りかかってきた経緯と、作品のテーマについて少し記します。
***
映像の大部分は、2012年の旅行当時に撮影。ゆく先々、列車やバスの窓からカメラを回していました。
(ちなみにこのときの旅行についてはブログ記事にも書いています。
左のカテゴリバーの下のほうにある<仏蘭西紀2012>、および<仏蘭西紀2012その2>からどうぞ。)
ナレーションのテキストは、日本語で2014年に。
さいしょの語学学校の奨学金への応募の作文として書いた。
おかげで学費がだいぶ浮いたので、家計にも貢献したわけです。
そのフランス語訳は、2016年。こちらの院への応募のプロジェクトとして書き上げた。
院は落ちてしまったけれど、これつくっておいたおかげで今回すごい助かった。
当時の自分にはずいぶん背伸びした、無謀な企てで、しかも〆切までの時間との戦い。
でもやりたいことをやっていたので、作業のさなかは熱中して楽しかったな。
全体で10ページ以上あったのに、語学学校の先生、ひと晩で見て、直してくれて、ありがたかった。
2016年の夏には、夕方から夜にかけてのシーンに使うパリの街の風景をけっこうな量撮り直した。
旅行した2012年当時は、時間的な制限があったうえ、カメラのバッテリーの持続時間の問題もあって、
なかなか撮りたいだけ撮るというわけにいかなかったのです。
その点、「住んでる」というのは撮影には最強よね。
同じ年に、BGMに使う曲を5,6曲つくった。
久びさにバイオリンを引っぱり出してきて、肩あてのゴム管が劣化してしまっていたので買い替えたりしたっけ。
バイオリンの音色を使いたい曲があって、一週間くらい練習したけど、結局下手くそすぎてお蔵入り。w
結局ほぼすべてピアノとシンセサイザーで仕上げることに。
今回はそのうち4曲くらいを使っている。
2019年の春、大学の映画クラスの課題のひとつとして、これのダイジェスト版をまず制作。
そのときは不評だったが、それが今回のベースとなった。
そして秋学期の別のクラスで、めんどくさい心理戦のすえに何とか課題としてねじこむことに成功し
次から次へと降ってくるほかの授業の課題に邪魔されながらも、クリスマスからの2週間の突貫編集で
ほぼ形になるまで仕上げ。その後、細部の手直しを果てしなく繰り返して今に至るー。
今回、字幕として使うことになったフランス語のテキストは、このときもずいぶん直された。
学期中の大部分、この細部の表現のニュアンスをめぐってああでもない、こうでもないとやっていた。
この調子じゃいつまでたっても終わらない、と思えたほど。
でも、非ネイティヴの書いた独特な面白さがあるらしく、自分では分からないのだけど、
「そういう部分は、あなたのオリジナルだから、残しておく」と言われた。そう言ってくれるのは親切ね。
こんな感じに仕事や授業や何やのすきまを縫って、そのときどきの外からの要求をなるだけ利用して取りこみ、
擦り合わせながら、レンガをひとつずつ積み上げるように進めてきた。
形にしたいという思いはずっと持っていたから、さいごにはかなったけど… それにしても時間かかったな。
撮りためた映像や写真がとにかくいっぱいあって、すきま時間で整理しているとその中で迷子になってしまい、
ぜんぶ見終わったころには最初のほうがどうだったか忘れてる。その繰り返し。
全体を俯瞰し把握するというのは、まとまった時間がないとできないことだ。
それがこれまでかなわなかった最大の要因。
***
ところで、これは言っておかないと無責任だと思うので、言っておく。
これは「こうあってほしい」というのを体現した「私のフランス」にすぎない。
綺麗な映像ばかりのように見えるかもしれないが、上位1%のいちばん綺麗な上澄みを掬い取ったにすぎない。
ともかく、現実のフランスは、この100倍くらいイやなとこばっかりと思ってほしい。
あまりにイやなとこばっかりなので、せめて自分の作品の中でくらいは綺麗であってほしいと思ったの。
あ、でもいい人もいますよ、もちろん。これも言っておかないと。
***
作品のテーマについて。
長い時間をかけてひとつの作品をつくったときにありがちなのだけど、
作り手のものの考え方感じ方も変わってゆくから、今の私自身はあまりこういった問題について考えていない。
愛というのは深遠で普遍的なテーマで、いちどはとことん掘り下げてみるのもいいと思うけれど、
正直そんなにいつまでも、死ぬまでずっと考え続けるような問題でもないと思う。
このへんはいろいろ論争のあるところかもしれないけれど。
愛というコトバのイメージ、それがポジティヴかネガティヴかと言われると、私にとっては、それはネガティヴだ。
愛と言われると、まぁそういう育ち方をしているから仕方ないのだけれど、いまだに、まずさいしょに
キリスト教でいう愛のイメージを考えてしまう。神を愛せ、人を愛せ的な。
そしていまだにこのコトバに、かすかに首を絞められるような息苦しさを覚える。
つまり、私にとってそれはまず命令されるもの、要求されるものだったから。
愛というのが人類の追い求めるべき至上の価値のように言われているのは、考えてみるとふしぎだと思いませんか。
キリスト教国ならともかく、文化的にも政治的にもあんまりキリスト教とは関係のない日本においてさえ、
ほかの色んな価値を差し置いて、ちょっと別格で、特別なものに思われている気がする。でもほんとにそうだろうか。
そもそも、人が生きていくのに愛ってほんとうに必要? 私は必要とするだろうか?
愛とは なくてもやっていけるときに はじめて手に入るらしい… 興味深い考えではある。
けれど… 一周して戻ってきて、私はやっぱり、愛とは掛け心地のよいソファのようなものであってほしい。
それは変わらない。
なくてもやっていけるときにしか手に入らないものって、はっきり言って何になるの?
ゆっくり体を休めることもできず、場所を取るだけのソファなんて? ってことになってしまう。
愛とは掛け心地のよいソファのような… これが私のしぜんな感覚なのだけれど、
これが椅子でもベッドでもなくて、ソファっていうところが示唆的だなと思う。
ソファって、まぁ嗜好品よね。ぜったいないと生きていけないっていうようなものではない。
しかもほんとに掛け心地のよいソファなんて究極的にはあまり実在せず、
だいたいが体重をかけると潰れてしまうというもの。
こんなことを言うと恐れ多いようだけど、だったらそれほど意味ないのでは?
こうして受け取る側に対して保証できないうえ、愛はまた、与える側に対しても大変な負担を強いる。
愛は人の尊厳を奪う。けなされても罵倒されても耐えているヤンの姿。
愛している側の人間としてかくあるべきとは思うけれど、やっぱり…
見ているとこっちも惨めな気分になる。はっきり言ってあまり気持ちのいいものではない。
できればだれにも、あんな状況にあってほしくないと思ってしまう。
愛というのはもらうにしても与えるにしても、ちょっと重苦しすぎて要求が大きすぎる気がする。
私のために一生を捧げ、生きるも死ぬも私しだいなんて、
そんな類の愛を誰かに要求するのは、あまりに暴力的で、失礼で、気の毒すぎる。
今の私はそう思う。
このことはまた書くかもしれないけれど、長くなるので、とりあえずはこのへんで。


