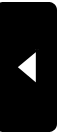2011年08月18日
今年は花火見た?
毎年夏は時間の流れを考えさせられる季節。
あれからもう一年たったのか! とかびっくりさせられるし、やりたかったのにやり残してることが今年もいっぱいあって焦る。
花火は毎年必ず見に行くことにしてるのがふたつばかりあって、今年も行った。夏公演を控えてバタバタとしながらも、意地で。
花火は、モニターで見てもちっちゃくてつまらない。
やっぱりその場行ってライヴで見ないと。
で、また、そこで写真撮ったりビデオ撮ったりしてもあとでいまいち迫力が伝わらないんだな。
ほんとに、ライヴが命!
だから、忘れないように毎年見に行かないといけない。
イギリスとアイルランドを半年旅していたときも、唯一なくてさびしかったのが日本の花火だった。
いつもきれいだなと思うのは、小ぶりで色とりどりのスターマイン。
地上から噴水のように吹きあがって、3段階くらいの高さで順にはじけてく、音楽にあわせて、絵のようですてき。
5尺玉、6尺玉もいろいろ。
みどりと群青のすずしげなとりあわせもすてき。
山下清とか、花火の絵を描きたくなるのも分かるなぁ。
ミントグリーンと淡いオレンジのとりあわせ、きれい。
はじけるようなショッキングピンクから淡い桃色まで、さまざまな階調のピンク。
今年印象的だったのはひまわり花火。
きらきらオレンジ色で、ダイナミックで、ほんとにゴッホのひまわりの群れを夜空に描いたよう。
真ん中の部分、丸みがあって、ほんとの花みたいに写実的。
それで、打ち上がった角度によって花弁部分が色んな方向を向くから、すごく動きがあっていきいきして見える。
あれはほんとにすてきだった。
アイボリーのしゅーっと筆で描いたような花びらが次々に開いて金色の雨となって降り注ぎ、星のように夜空に散って余韻を残して、きらきらとゆっくり消えてゆく・・・
あの、プラネタリウムみたいに不自然にきらきらした、消えてゆく余韻のところが好き。
あの火花、ひとつだけいつまでも消えないな、と思ってるとほんとの星だったり。
さいごのきらきらが消えるとき、めらめらっと音をたてるやつもあるよね。
夏の情熱の激しさとはかなさを同時に象徴するよう。
ビッグバンのように、はじけ散るマルチカラーの大輪。
客席からどよめきが上がる。
フィナーレ近く、色んな色のえのぐをパレットにぶちまけたみたいなスターマイン。
淡みどり色や、紺やピンクや、いくつもの星雲が爆発する。・・・
花火の会場では、まわりみんな知らない人たちでもなんとなくほわっとした共感がただよっていて好き。
みんな楽しみに来てる、きれいなもの見に来てる人たちだもの。
ぎすぎすしてなくて、みんな楽しそう。
会場をぶらぶらして雰囲気を味わうのも、花火の楽しみのひとつ。
浴衣を着た女の子たちや、屋台で売ってる色んな色に光るおもちゃや、きれいな色のヨーヨーや。
そういうの色々見て歩くの好き。
ときどき、はっとするほど浴衣の着こなしの見事な人がいたりして、見とれてしまう。
そうそう、いつも行く神社の花火では、やぐらを組んだまわりでみんなで盆踊りを踊るのだけど、そこで毎年必ず、なぜか<バハマママ>をかけるのだ。
ほかの曲はみんな炭坑節とか東京音頭とかふつうの盆踊りの曲なのに、そこにまじってなぜか必ずこれが入る。
<バハマママ>は、80年代ディスコで流行ってた曲だそう。
振り付けもそんな感じで、けっこうお年を召して神社のおそろいのきちっとした浴衣着たおばさま方がみんなでこれ踊ってるのはかなりフシギな光景。
さいしょ、何の曲だか知らなくて、でもやけにファンキーで耳につくし、振り付けがなんか明らかにほかの盆踊りとちがうよなぁ、と思って気になっていた。
こういう曲を神社のお祭りでかけちゃうの、日本独特のアニミズム的発想?!
これ、振り付け、覚えたいのだけど、見れるのが一年に一回とか二回とかだからなかなか覚えられない。
神社の婦人部とかに入ればいいのか?(笑)
なんかレディー・ガガとか、知ったら気に入りそうだな。
それはそうと、ここのお祭りでいつも必ず買うのがかき氷と、ほんとのカニ爪をあしらったカニクリームコロッケ。
けど、今年は売り切れで買えなかった。
コロッケは、お店じたい出してなかったっぽい。
ショック・・・。
かき氷といえば、デニーズの抹茶あずきが大好き。
今でもあるのかな・・・
抹茶とあずきにまさる取り合わせってないと思う。
私は白玉はないほうがいい派。
あ、でもこないだ団地のお祭りで食べたマンゴーのもおいしかったな。
あと、焼きそばと焼き鳥!!
たちまち売り切れてしまうくらいの人気で、すっごくおいしいの。
今年はちゃんと買えて有意義でした!!
あとは何かやり残してたかな。
みなさんも、どうぞ、いい夏を!!!
あれからもう一年たったのか! とかびっくりさせられるし、やりたかったのにやり残してることが今年もいっぱいあって焦る。
花火は毎年必ず見に行くことにしてるのがふたつばかりあって、今年も行った。夏公演を控えてバタバタとしながらも、意地で。
花火は、モニターで見てもちっちゃくてつまらない。
やっぱりその場行ってライヴで見ないと。
で、また、そこで写真撮ったりビデオ撮ったりしてもあとでいまいち迫力が伝わらないんだな。
ほんとに、ライヴが命!
だから、忘れないように毎年見に行かないといけない。
イギリスとアイルランドを半年旅していたときも、唯一なくてさびしかったのが日本の花火だった。
いつもきれいだなと思うのは、小ぶりで色とりどりのスターマイン。
地上から噴水のように吹きあがって、3段階くらいの高さで順にはじけてく、音楽にあわせて、絵のようですてき。
5尺玉、6尺玉もいろいろ。
みどりと群青のすずしげなとりあわせもすてき。
山下清とか、花火の絵を描きたくなるのも分かるなぁ。
ミントグリーンと淡いオレンジのとりあわせ、きれい。
はじけるようなショッキングピンクから淡い桃色まで、さまざまな階調のピンク。
今年印象的だったのはひまわり花火。
きらきらオレンジ色で、ダイナミックで、ほんとにゴッホのひまわりの群れを夜空に描いたよう。
真ん中の部分、丸みがあって、ほんとの花みたいに写実的。
それで、打ち上がった角度によって花弁部分が色んな方向を向くから、すごく動きがあっていきいきして見える。
あれはほんとにすてきだった。
アイボリーのしゅーっと筆で描いたような花びらが次々に開いて金色の雨となって降り注ぎ、星のように夜空に散って余韻を残して、きらきらとゆっくり消えてゆく・・・
あの、プラネタリウムみたいに不自然にきらきらした、消えてゆく余韻のところが好き。
あの火花、ひとつだけいつまでも消えないな、と思ってるとほんとの星だったり。
さいごのきらきらが消えるとき、めらめらっと音をたてるやつもあるよね。
夏の情熱の激しさとはかなさを同時に象徴するよう。
ビッグバンのように、はじけ散るマルチカラーの大輪。
客席からどよめきが上がる。
フィナーレ近く、色んな色のえのぐをパレットにぶちまけたみたいなスターマイン。
淡みどり色や、紺やピンクや、いくつもの星雲が爆発する。・・・
花火の会場では、まわりみんな知らない人たちでもなんとなくほわっとした共感がただよっていて好き。
みんな楽しみに来てる、きれいなもの見に来てる人たちだもの。
ぎすぎすしてなくて、みんな楽しそう。
会場をぶらぶらして雰囲気を味わうのも、花火の楽しみのひとつ。
浴衣を着た女の子たちや、屋台で売ってる色んな色に光るおもちゃや、きれいな色のヨーヨーや。
そういうの色々見て歩くの好き。
ときどき、はっとするほど浴衣の着こなしの見事な人がいたりして、見とれてしまう。
そうそう、いつも行く神社の花火では、やぐらを組んだまわりでみんなで盆踊りを踊るのだけど、そこで毎年必ず、なぜか<バハマママ>をかけるのだ。
ほかの曲はみんな炭坑節とか東京音頭とかふつうの盆踊りの曲なのに、そこにまじってなぜか必ずこれが入る。
<バハマママ>は、80年代ディスコで流行ってた曲だそう。
振り付けもそんな感じで、けっこうお年を召して神社のおそろいのきちっとした浴衣着たおばさま方がみんなでこれ踊ってるのはかなりフシギな光景。
さいしょ、何の曲だか知らなくて、でもやけにファンキーで耳につくし、振り付けがなんか明らかにほかの盆踊りとちがうよなぁ、と思って気になっていた。
こういう曲を神社のお祭りでかけちゃうの、日本独特のアニミズム的発想?!
これ、振り付け、覚えたいのだけど、見れるのが一年に一回とか二回とかだからなかなか覚えられない。
神社の婦人部とかに入ればいいのか?(笑)
なんかレディー・ガガとか、知ったら気に入りそうだな。
それはそうと、ここのお祭りでいつも必ず買うのがかき氷と、ほんとのカニ爪をあしらったカニクリームコロッケ。
けど、今年は売り切れで買えなかった。
コロッケは、お店じたい出してなかったっぽい。
ショック・・・。
かき氷といえば、デニーズの抹茶あずきが大好き。
今でもあるのかな・・・
抹茶とあずきにまさる取り合わせってないと思う。
私は白玉はないほうがいい派。
あ、でもこないだ団地のお祭りで食べたマンゴーのもおいしかったな。
あと、焼きそばと焼き鳥!!
たちまち売り切れてしまうくらいの人気で、すっごくおいしいの。
今年はちゃんと買えて有意義でした!!
あとは何かやり残してたかな。
みなさんも、どうぞ、いい夏を!!!
2011年08月17日
トラス・オス・モンテス 勝手にノベライズ
ポルトガルという国も、実は昔から何となく惹かれている場所のひとつ。
ポルトガルを舞台にした私の作品もあるんですよ。行ったことないのに。(笑)
北ポルトガルの海辺を舞台とした夏の物語。
まだ読んでない方はぜひどうぞ。今の季節にぴったりの作品です。
http://ballylee.tsukuba.ch/c6965.html
それはそうと、2010年の秋に東京国立近代美術館フィルムセンターというところでポルトガル映画祭があって、17作品ほど上映したんです。
できればぜんぶ見に行きたいくらいだったんだけど、絞って、ふたつだけ見に行った。
そのうちのひとつ、アントニオ・レイスとマルガリータ・コルディロ監督・編集、アカシオ・ド・アルメイダ撮影の<トラス・オス・モンテス Tras-os-Montes >(1976年、108分、35ミリ、カラー)という作品。
パンフの紹介文をちょっと引用すると、
「ポルトガル現代詩を代表するアントニオ・レイスが、マルガリータ・コルデイロとともにつくった初長編。
川遊びに興じる子供たちの姿を中心に、遠い山奥のきらきらと輝く宝石のような日々を夢幻的な時間構成により浮かびあがらせる。
公開当時、フランスの批評家たちを驚嘆させ、のちにペドロ・コスタにも影響を与えたという伝説的フィルム。」
あまりにすばらしくて、忘れたくなくて、勝手にノベライズしちゃいました。
実は、さいきん新しいポルトガル大使さんとお友だちになりまして。
その記念にちょっとアップします。だいたい感じは伝わると思う。
**************************************
<トラス・オス・モンテス>ノベライズ版 by 中島迂生
1976年、ポルトガル。
プロの俳優でなく、すべて地元の村人が出てる。
その日常生活を追ったドキュメンタリーのようでいて、ふしぎな飛躍やシンボリズム、シュールなところがところどころ、突然出てきて、何の説明もなくそのまま平然と進んでいく。
色といい、音の丸みといい、古き良きアナログ。
はてしなく四方の果てにまで連なる丘陵の風景。
森のみどりと、牧草地の淡みどりがまだらのパッチワークになって広がっている。
男の子、アルマントの羊を追う掛け声。
村の納屋。外から見えるつくりの石段。
家の中へ入ってく。家は石造りで、内壁はしっくい塗りだ。
おとながおとぎ話を語り聞かせている声。
「父王が私たちを殺そうとしています。逃げなくては」と、<白い花>が言いました。
「厩から<心の馬>を引いてきてください」
そこで王子は厩へ行きましたが、間違えて<風の馬>を連れてきました。
<白い花>は気になりましたが、時間がありません。
二人が<風の馬>に乗って逃げていると、気づいた父王が追いかけてきました。
そこで<白い花>が砂をつかんで投げつけると、そこに大きな海が広がって父王のゆく手をはばみました・・・
(付記。私の<石垣の花嫁>に、ほんとに似た場面があるんですよ・・・読んでくれた方は知ってると思うけど。もちろん、書いたのはずっと前だからこの映画については知ってませんでした。世界中にある類型なんでしょうね。)
黄色いワンピースを着た、アルマントの妹。
アルマント、となりに座って一緒に聞きはじめる。
ランプに火が入れられ、アングルが変わって、おとぎ話のつづき・・・だが話がだいぶ飛んでる。
・・・王子が母親の額にキスすると、<白い花>のことを忘れてしまいました。
七年たってやっと思い出して、探してみると、<白い花>は奴隷として売られて、バビロンの塔のてっぺんに閉じこめられていることが分かりました。
そこは一度入ったら出てくることのできないところで・・・
転換。
アルマントの妹が木の机で塗り絵している。
ルイズが入ってきて、腕を彼女の首にまわし、「何してるの?」って聞く。
ルイズはお父さんからのおみやげのボールを持っている。
ボール遊びする男の子たち。
村の一角に人々が集まって、フィドルとマンドリンの演奏で踊っている。
あそこに君の姉さんがいるぜ。・・・
いや、よく似た別人だ。姉さんには、去年嫁にいって以来、会ってない。・・・
アルマントの回想シーン。
みじかい草が生える平地に川が流れて、両岸にポプラが茂っている。
そこを渡ってくるアルマントの姉。ロバに乗り、民族衣裳を着て、白い頭飾りをつけている。
納屋の入り口のところに恋人がいて、アルマントもいる。
姉、入ってゆくと、飲み物をもって出てきて、恋人に渡す。
回想シーン終わり。
川へ行こうぜ。急に、アルマントが言い出す。
君の姉さんの結婚式のときにも、川へ行ったね。
草地の斜面の道を駆け出す男の子たち。
冬の川のシーン。激しい音を立てて流れる水。ごつごつした岩地の川床。
水についた木の枝のまわりに氷がついていたりする。
岸沿いの川面が凍っているのを割ってみたり、死んだ魚が氷に閉じこめられているのを見つけたりして遊ぶ子供たち。
ツイードのコート着てたり、今見てもなかなかおしゃれだ。
そうそう、村の風物は昔のままで、文明の面影はほとんど感じられないのに、子供たちの着てる服だけはカラフルで、工場生産品だ。
それは子供たちだけで、大人たちは黒いショールを羽織っていたり、昔ながらの格好をしてる。
ルイズの家のシーン。
椅子に腰かけてる母親のところにルイズがやってきて、言う。
「川には何でもあるんだよ。水晶もダイヤモンドも、トパーズもオニキスも何もかも」
母親はにこにこしながら聞いている。それから、
「あした、おじいさんのお屋敷に行ってもいいわよ」って言う。「船をもらってきてもいいわよ」
お屋敷のシーン。ルイズとアルマント。
石壁に瓦屋根、スペイン風のつくり。まんなかに中庭があって、回廊みたいのがついてる。
がらんとしたかびくさい暗い部屋を次々と探検していくふたり。
真っ黒くなった肖像画とか、本棚の本とか。
そのうちルイズが古い蓄音器を見つけだして、かけてみると、大昔の酒場でかかっていたような古き良き音楽が流れ出す。聞き入るふたり。
ふたり、帰る。ルイズが母親に、「古い蓄音器を見つけたよ。あれ、くれないかな。どうしてもほしいんだけどな」って言う。
船はもらってきた?・・・ あ、忘れた。・・・
その晩、ルイズ、母親に、おじいさんのことを尋ねる。
お金持ちだったの?・・・ いいえ。アルゼンチンに、働きに行ってたのよ。・・・
母親の少女時代の回想シーン。
馬に乗って遠ざかっていく姿をいつまでも見送る。
ルイズ、眠りにつく。翌朝、ベッドから起き出して身支度。
昔風の白いねまき。
鉄線の洗面台にほうろうびきの洗面器、水差し。
水道なんてついてない。ただ洗面器がぴったりはまるようになってる台。
いまでもアンティークの家具屋に行くとそういうのがある。
そこで顔洗ってリネンでふいたあと着替えるのだけれど、なんかふしぎな中世みたいな服。
あとから、これが伏線だったのかも、って思える。
赤いチュニックにおそろいの赤い帽子、それに白いタイツ。
アルマントと落ち合って野へ出ていくのだが、こちらも同じような、青のチュニックに青い帽子。
ふたり、薪を集めながら、草の中に寝っ転がったり、木登りしたり、木のほらの中に入りこんだりして遊ぶ。
ごつごつした岩地の川ぞいにさしかかると、急にふしぎな光景にぶつかる。
大きな平たい岩の上に二人の女が向き合って座っている。
ひとりは真っ赤なドレスを着て、頭につけた白い長いヴェールがドレスのすそを超えて大きく広がり、もうひとりは黒づくめだ。
うしろには岩山がそびえ、割れ目があって、洞窟になっている。
そこから白いハトや濃灰色のハトが一羽ずつ飛び出してきて、飛び去ってゆく。
あなたたち、いつからいたの? と、黒づくめの女の方が訊く。
さっきからです。・・・
あなたたちも、ここに一緒にいなさい。・・・
いいえ、うちに帰ります。・・・帰ります。・・・
ルイズとアルマント、何だか怖くなって、逃げるように彼女たちのもとを去って走り出す。
ようやく村を見おろせるところまでくる。
あれ、モンテジーニョかな? なんか家並みが違うような気がするんだけど・・・
あれがぼくの家だ。あれ? 違うかもしれない・・・
二人、村まで降りていって、地下室の階段のところにいる二人の老人に尋ねる。
モンテジーニョは?・・・ ここだよ。・・・
ルイズ・****とアルマント・****は?・・・
わしらの七代前の先祖だよ。なぜ今になってふたりの名前を持ち出す?・・・
ふたりは顔を見合わせる。・・・ぼくらがルイズとアルマントです。・・・
いいかげんなことを言うな。おとなをからかうんじゃない。・・・
老人たちは本気で怒っている。ふたり、肩を落として立ち去る。
ルイズがつぶやく。
あの洞窟のところにいたあいだに、時間がたったのかもしれない。
一羽のハトが飛び去るごとに、ひとつの季節が。・・・
ルイズが、父親への手紙を書いている。
母親が、書くべきことを口で言ってやり、それをルイズが書きとっている。
お父さん、お元気ですか。ぼくたちは元気です。・・・
去年お金を送ってもらったけれど、それだけでは足りません。
子牛を一頭売りました。ぼくらのところのいちばんいい子牛ですが、わずかなお金にしかなりません・・・
それから、母親、つづけて、全く同じおだやかな調子で。
ふたつの羊の群れがいる。川を挟んでこちら側に白い羊の群れが、向こう側に黒い羊の群れが。
白い羊が鳴くたびに、黒い羊が川をわたっていって、白い羊になる。
黒い羊が鳴くたびに、白い羊が川をわたっていって、黒い羊になる。・・・
川岸にポプラの木が生えている。
片側半分はもえる炎に包まれ、もう半分は青々と茂っている。・・・
次のシーンからはナレーションが入る。
彼らの村は実は炭鉱村で、村に働き盛りの男たちがいないのはどうやらみんな炭鉱夫として働きに出ているからであるらしいことが明らかになってくる。
賃金は少なく、地盤の落下で死ぬ者も多い。
それでも炭鉱もしだいに衰退して、村を出ていく者も増える一方、どんどん人は少なくなっている。
吊り橋を渡ってゆき、廃屋となった炭鉱施設の中を探検するアルマント。
心配して探しにやってくるのは老人だ。
それから、この村がいかに隔絶した場所であるかが語られる。
(どうやら、ここから急に何百年も前へ遡っているらしい。)
都のことは話に聞くだけで、誰も行ったことがない、どこにあるのかも、そもそもそれがほんとうにあるのかどうかも知らない。・・・
国王の存在など、伝説にひとしい。
法律は、ひとにぎりの力あるものがこの国を牛耳る方便にすぎない・・・
法律はただ都から一方的に村々へ伝えられ、みんながそれを受け入れる。
この国の民は何と我慢強い者たちであることか!・・・
石造りの会堂に、黒いヴェールに身を包んだ人々がいっぱいいる。
なかにひとり、赤いみじかいワンピースを着た女がひとりいて、ひとりだけ明らかに場違いだ。
演説台の前に、ひげを蓄えたひとりの男が立って、文書を読み上げる。
ポルトガル国王である吾輩は、ここにいる女性****に、どこそこの領土の所有権とそれに付随する諸権利のすべてを与えることを証する。
このことは汝の肉体の売買を伴わない。
13**年、6月28日。・・・
すると、赤いワンピースの女が黙って立ち上がる。
それからカメラは順々に、会堂の壁ぎわに腰かける黒頭巾の人々の顔を映し出してゆく。
男も女もいる。さいごのほうには黒頭巾でない、どう見ても20世紀のレインコートみたいの身に付けた人びとも列に連なっている。
時間の流れがずーっと途切れることなく連続して流れている感じをあらわしたいのだと思う。
それからまた村の暮らしのようすが淡々と映し出される。
ずっと見ていると、この地方の風景は、基本森と牧草地、それから岩地、ときどきものすごい岩山、という感じ。
カルスト地形みたいな大岩がごつごつ突き出たところを、ロバにのって横切っていく女。
・・・どこそこの家に子どもが生まれるようだよ。・・・じゃあ、ようすを見に行かなくちゃね。・・・
炭鉱で働いているパパから手紙が届く。・・・読んで、読んで!・・・ 戸口で読み上げる男の子。
舗装されていない泥の道、石造りの家々。
・・・マリアンヌが家を出るそうだよ。・・・ますます人が減っちまうね。・・・
夜明けの鉄道駅で待つマリアンヌ。
やがて、夜明け近く、ようやくものの姿が見え始めた野を突っきって、轟音とともにもくもくと煙をあげて去ってゆく列車。・・・
ポルトガルを舞台にした私の作品もあるんですよ。行ったことないのに。(笑)
北ポルトガルの海辺を舞台とした夏の物語。
まだ読んでない方はぜひどうぞ。今の季節にぴったりの作品です。
http://ballylee.tsukuba.ch/c6965.html
それはそうと、2010年の秋に東京国立近代美術館フィルムセンターというところでポルトガル映画祭があって、17作品ほど上映したんです。
できればぜんぶ見に行きたいくらいだったんだけど、絞って、ふたつだけ見に行った。
そのうちのひとつ、アントニオ・レイスとマルガリータ・コルディロ監督・編集、アカシオ・ド・アルメイダ撮影の<トラス・オス・モンテス Tras-os-Montes >(1976年、108分、35ミリ、カラー)という作品。
パンフの紹介文をちょっと引用すると、
「ポルトガル現代詩を代表するアントニオ・レイスが、マルガリータ・コルデイロとともにつくった初長編。
川遊びに興じる子供たちの姿を中心に、遠い山奥のきらきらと輝く宝石のような日々を夢幻的な時間構成により浮かびあがらせる。
公開当時、フランスの批評家たちを驚嘆させ、のちにペドロ・コスタにも影響を与えたという伝説的フィルム。」
あまりにすばらしくて、忘れたくなくて、勝手にノベライズしちゃいました。
実は、さいきん新しいポルトガル大使さんとお友だちになりまして。
その記念にちょっとアップします。だいたい感じは伝わると思う。
**************************************
<トラス・オス・モンテス>ノベライズ版 by 中島迂生
1976年、ポルトガル。
プロの俳優でなく、すべて地元の村人が出てる。
その日常生活を追ったドキュメンタリーのようでいて、ふしぎな飛躍やシンボリズム、シュールなところがところどころ、突然出てきて、何の説明もなくそのまま平然と進んでいく。
色といい、音の丸みといい、古き良きアナログ。
はてしなく四方の果てにまで連なる丘陵の風景。
森のみどりと、牧草地の淡みどりがまだらのパッチワークになって広がっている。
男の子、アルマントの羊を追う掛け声。
村の納屋。外から見えるつくりの石段。
家の中へ入ってく。家は石造りで、内壁はしっくい塗りだ。
おとながおとぎ話を語り聞かせている声。
「父王が私たちを殺そうとしています。逃げなくては」と、<白い花>が言いました。
「厩から<心の馬>を引いてきてください」
そこで王子は厩へ行きましたが、間違えて<風の馬>を連れてきました。
<白い花>は気になりましたが、時間がありません。
二人が<風の馬>に乗って逃げていると、気づいた父王が追いかけてきました。
そこで<白い花>が砂をつかんで投げつけると、そこに大きな海が広がって父王のゆく手をはばみました・・・
(付記。私の<石垣の花嫁>に、ほんとに似た場面があるんですよ・・・読んでくれた方は知ってると思うけど。もちろん、書いたのはずっと前だからこの映画については知ってませんでした。世界中にある類型なんでしょうね。)
黄色いワンピースを着た、アルマントの妹。
アルマント、となりに座って一緒に聞きはじめる。
ランプに火が入れられ、アングルが変わって、おとぎ話のつづき・・・だが話がだいぶ飛んでる。
・・・王子が母親の額にキスすると、<白い花>のことを忘れてしまいました。
七年たってやっと思い出して、探してみると、<白い花>は奴隷として売られて、バビロンの塔のてっぺんに閉じこめられていることが分かりました。
そこは一度入ったら出てくることのできないところで・・・
転換。
アルマントの妹が木の机で塗り絵している。
ルイズが入ってきて、腕を彼女の首にまわし、「何してるの?」って聞く。
ルイズはお父さんからのおみやげのボールを持っている。
ボール遊びする男の子たち。
村の一角に人々が集まって、フィドルとマンドリンの演奏で踊っている。
あそこに君の姉さんがいるぜ。・・・
いや、よく似た別人だ。姉さんには、去年嫁にいって以来、会ってない。・・・
アルマントの回想シーン。
みじかい草が生える平地に川が流れて、両岸にポプラが茂っている。
そこを渡ってくるアルマントの姉。ロバに乗り、民族衣裳を着て、白い頭飾りをつけている。
納屋の入り口のところに恋人がいて、アルマントもいる。
姉、入ってゆくと、飲み物をもって出てきて、恋人に渡す。
回想シーン終わり。
川へ行こうぜ。急に、アルマントが言い出す。
君の姉さんの結婚式のときにも、川へ行ったね。
草地の斜面の道を駆け出す男の子たち。
冬の川のシーン。激しい音を立てて流れる水。ごつごつした岩地の川床。
水についた木の枝のまわりに氷がついていたりする。
岸沿いの川面が凍っているのを割ってみたり、死んだ魚が氷に閉じこめられているのを見つけたりして遊ぶ子供たち。
ツイードのコート着てたり、今見てもなかなかおしゃれだ。
そうそう、村の風物は昔のままで、文明の面影はほとんど感じられないのに、子供たちの着てる服だけはカラフルで、工場生産品だ。
それは子供たちだけで、大人たちは黒いショールを羽織っていたり、昔ながらの格好をしてる。
ルイズの家のシーン。
椅子に腰かけてる母親のところにルイズがやってきて、言う。
「川には何でもあるんだよ。水晶もダイヤモンドも、トパーズもオニキスも何もかも」
母親はにこにこしながら聞いている。それから、
「あした、おじいさんのお屋敷に行ってもいいわよ」って言う。「船をもらってきてもいいわよ」
お屋敷のシーン。ルイズとアルマント。
石壁に瓦屋根、スペイン風のつくり。まんなかに中庭があって、回廊みたいのがついてる。
がらんとしたかびくさい暗い部屋を次々と探検していくふたり。
真っ黒くなった肖像画とか、本棚の本とか。
そのうちルイズが古い蓄音器を見つけだして、かけてみると、大昔の酒場でかかっていたような古き良き音楽が流れ出す。聞き入るふたり。
ふたり、帰る。ルイズが母親に、「古い蓄音器を見つけたよ。あれ、くれないかな。どうしてもほしいんだけどな」って言う。
船はもらってきた?・・・ あ、忘れた。・・・
その晩、ルイズ、母親に、おじいさんのことを尋ねる。
お金持ちだったの?・・・ いいえ。アルゼンチンに、働きに行ってたのよ。・・・
母親の少女時代の回想シーン。
馬に乗って遠ざかっていく姿をいつまでも見送る。
ルイズ、眠りにつく。翌朝、ベッドから起き出して身支度。
昔風の白いねまき。
鉄線の洗面台にほうろうびきの洗面器、水差し。
水道なんてついてない。ただ洗面器がぴったりはまるようになってる台。
いまでもアンティークの家具屋に行くとそういうのがある。
そこで顔洗ってリネンでふいたあと着替えるのだけれど、なんかふしぎな中世みたいな服。
あとから、これが伏線だったのかも、って思える。
赤いチュニックにおそろいの赤い帽子、それに白いタイツ。
アルマントと落ち合って野へ出ていくのだが、こちらも同じような、青のチュニックに青い帽子。
ふたり、薪を集めながら、草の中に寝っ転がったり、木登りしたり、木のほらの中に入りこんだりして遊ぶ。
ごつごつした岩地の川ぞいにさしかかると、急にふしぎな光景にぶつかる。
大きな平たい岩の上に二人の女が向き合って座っている。
ひとりは真っ赤なドレスを着て、頭につけた白い長いヴェールがドレスのすそを超えて大きく広がり、もうひとりは黒づくめだ。
うしろには岩山がそびえ、割れ目があって、洞窟になっている。
そこから白いハトや濃灰色のハトが一羽ずつ飛び出してきて、飛び去ってゆく。
あなたたち、いつからいたの? と、黒づくめの女の方が訊く。
さっきからです。・・・
あなたたちも、ここに一緒にいなさい。・・・
いいえ、うちに帰ります。・・・帰ります。・・・
ルイズとアルマント、何だか怖くなって、逃げるように彼女たちのもとを去って走り出す。
ようやく村を見おろせるところまでくる。
あれ、モンテジーニョかな? なんか家並みが違うような気がするんだけど・・・
あれがぼくの家だ。あれ? 違うかもしれない・・・
二人、村まで降りていって、地下室の階段のところにいる二人の老人に尋ねる。
モンテジーニョは?・・・ ここだよ。・・・
ルイズ・****とアルマント・****は?・・・
わしらの七代前の先祖だよ。なぜ今になってふたりの名前を持ち出す?・・・
ふたりは顔を見合わせる。・・・ぼくらがルイズとアルマントです。・・・
いいかげんなことを言うな。おとなをからかうんじゃない。・・・
老人たちは本気で怒っている。ふたり、肩を落として立ち去る。
ルイズがつぶやく。
あの洞窟のところにいたあいだに、時間がたったのかもしれない。
一羽のハトが飛び去るごとに、ひとつの季節が。・・・
ルイズが、父親への手紙を書いている。
母親が、書くべきことを口で言ってやり、それをルイズが書きとっている。
お父さん、お元気ですか。ぼくたちは元気です。・・・
去年お金を送ってもらったけれど、それだけでは足りません。
子牛を一頭売りました。ぼくらのところのいちばんいい子牛ですが、わずかなお金にしかなりません・・・
それから、母親、つづけて、全く同じおだやかな調子で。
ふたつの羊の群れがいる。川を挟んでこちら側に白い羊の群れが、向こう側に黒い羊の群れが。
白い羊が鳴くたびに、黒い羊が川をわたっていって、白い羊になる。
黒い羊が鳴くたびに、白い羊が川をわたっていって、黒い羊になる。・・・
川岸にポプラの木が生えている。
片側半分はもえる炎に包まれ、もう半分は青々と茂っている。・・・
次のシーンからはナレーションが入る。
彼らの村は実は炭鉱村で、村に働き盛りの男たちがいないのはどうやらみんな炭鉱夫として働きに出ているからであるらしいことが明らかになってくる。
賃金は少なく、地盤の落下で死ぬ者も多い。
それでも炭鉱もしだいに衰退して、村を出ていく者も増える一方、どんどん人は少なくなっている。
吊り橋を渡ってゆき、廃屋となった炭鉱施設の中を探検するアルマント。
心配して探しにやってくるのは老人だ。
それから、この村がいかに隔絶した場所であるかが語られる。
(どうやら、ここから急に何百年も前へ遡っているらしい。)
都のことは話に聞くだけで、誰も行ったことがない、どこにあるのかも、そもそもそれがほんとうにあるのかどうかも知らない。・・・
国王の存在など、伝説にひとしい。
法律は、ひとにぎりの力あるものがこの国を牛耳る方便にすぎない・・・
法律はただ都から一方的に村々へ伝えられ、みんながそれを受け入れる。
この国の民は何と我慢強い者たちであることか!・・・
石造りの会堂に、黒いヴェールに身を包んだ人々がいっぱいいる。
なかにひとり、赤いみじかいワンピースを着た女がひとりいて、ひとりだけ明らかに場違いだ。
演説台の前に、ひげを蓄えたひとりの男が立って、文書を読み上げる。
ポルトガル国王である吾輩は、ここにいる女性****に、どこそこの領土の所有権とそれに付随する諸権利のすべてを与えることを証する。
このことは汝の肉体の売買を伴わない。
13**年、6月28日。・・・
すると、赤いワンピースの女が黙って立ち上がる。
それからカメラは順々に、会堂の壁ぎわに腰かける黒頭巾の人々の顔を映し出してゆく。
男も女もいる。さいごのほうには黒頭巾でない、どう見ても20世紀のレインコートみたいの身に付けた人びとも列に連なっている。
時間の流れがずーっと途切れることなく連続して流れている感じをあらわしたいのだと思う。
それからまた村の暮らしのようすが淡々と映し出される。
ずっと見ていると、この地方の風景は、基本森と牧草地、それから岩地、ときどきものすごい岩山、という感じ。
カルスト地形みたいな大岩がごつごつ突き出たところを、ロバにのって横切っていく女。
・・・どこそこの家に子どもが生まれるようだよ。・・・じゃあ、ようすを見に行かなくちゃね。・・・
炭鉱で働いているパパから手紙が届く。・・・読んで、読んで!・・・ 戸口で読み上げる男の子。
舗装されていない泥の道、石造りの家々。
・・・マリアンヌが家を出るそうだよ。・・・ますます人が減っちまうね。・・・
夜明けの鉄道駅で待つマリアンヌ。
やがて、夜明け近く、ようやくものの姿が見え始めた野を突っきって、轟音とともにもくもくと煙をあげて去ってゆく列車。・・・
2011年08月16日
夏公演 無事終了!

暑いなかですが楽しく終えることができました。
わざわざ足を運んでくださった皆さん、それから来れなかったけど気にかけていてくださった皆さん、ありがとうございました!!
いつもお世話になってる劇団アンラッキーボーイズの方々をはじめ、近所の幼なじみの友人や、久しぶりにお会いする方たち、はじめて見に来て下さった方たちなど、色んな方にご来場いただけました。
こんな片田舎なのに、何人ものアイリッシュに来ていただけたのもうれしい。
セントパトリックスフェスの企画でお世話になっているカトリック土浦教会のマイケル神父および教会の方々、お忙しいところお目にかかれてほんとによかった。ありがとうございました!!
私のボスのもうひとりのマイケル氏もわざわざ足を運んでくれました。感謝!!
今回は、宣伝もけっこう頑張りました。
さいきんちゃんと広報活動に身を入れてないなぁ、と反省して思い立ち、この一週間ほど、劇中衣裳の格好をしてTXの駅前でちらし配りを。
そのために何百枚ものちらしに訂正シールをせっせと貼りました。
花火大会の会場に公演の看板をかけた竜を持ち込んで走らせたりもしました。
駅でちらしもらいました、と言って見に来てくださった方がいた。感激しました。
上演の直前には、手の空いてる団員さんが呼び込みにいってくださり、それで見に来て下さった方も。
中身、宣伝活動ともに、さらにさらにガンガンいきたいと思います。
劇団バリリー座、これからもどうぞよろしく!!!
************************
以下は座長の個人的備忘であります。
<よかった点>
・何度も稽古を重ねるにつれ、同じ音源を使っていても身ぶり手ぶりのヴァリエーションが増えていく。今回はみんなずいぶん体の動きが表情ゆたかになったと思う。
・リハのときはスポットライト忘れていて何となく暗かった。今回忘れなくてよかった。
・音源の気になっていた部分を少しだけだけど改良できた。ひと晩かかった。
音源の改良はかなり細かい仕事。ほかの部分がちゃんと保たれるように、プロジェクトファイルの保存やら再生リストの編集やらいろいろと最新の注意を払わなくては。
・竜の羽根を改良してぴんと立つようにできた。これもひと晩かかった。それまでネコが耳をふせたみたいにへたっていて気になってたのだ。ただ、骨組みが、車に入りきらなくて窓から突き出たまま運搬するはめになった・・・。
・とりあえず宣伝がんばりました。いろいろ新しいことやってみた。衣裳着て<劇団バリリー座>と大書したたすきかけて駅前でちらし配りしたり、花火会場に竜を持ちこんで走らせたり。公演の週には衣裳着て仕事行った。話題にはなりました・・・。ライヴバーのオープンマイクに衣裳着て出るのはいつものこと。
・あとは団員さんの各自が責任もって自分の持ち場をしっかり守ってやってくれた。
・さいしょの部分、ナレーションだけで視覚的に何もないのでお客さん退屈しないだろうか・・・というのはいつも心配するところなんだけど、「あそこのところでイマジネーションが広がってよかった」と言ってくれた人がいた。ふむ、そういう考え方もあるのか。
・これは良かった点でもあり反省点でもあるのだけど・・・。
今回、演出を最大変えた点は、舞台をステージ上だけでなく客席全体にまで広げたこと。
馬車と竜をステージではなく下のところにスタンバイしておいて、キーナの一行が嫁入りする旅の場面になるとそこからスタートして、ぐるっと回ってホールの奥へ。そして、マグアの出てくる場面はここでやってしまう。再び馬車が動いてステージ下まで来て、着いたステージがこんどは石の国、という設定。
後半、キーナと若者が石の国を逃げ出す場面でも、二人はステージ上から駆け降りて、客席のあいだをぐるぐるほんとうに走り回る。
このほうが絶対面白いに違いない、と思ったのだけど、いざやってみたらお客さん、みんな前向いたままで後ろ見てくれなかった。登場人物がみんな後ろ行ったらふつう後ろ見るだろう、と何の疑いもなく思いこんでたので焦った。
「ただ今こっちがステージになってます」とか言うべきか? と思いつつ、自分の役のセリフが流れてるなかでそれも変かと迷い・・・。ここ重要なシーンなのに・・・と焦り・・・。
前もって言っとくべきだったかなぁ? でもあれはサプライズだから面白いのに・・・。
自分の役の反省点としては、
・仕度に手間取って、つけるはずったイヤリング、ネックレス、ブレスレットとか一式みごとにぜんぶ忘れてた。忘れてたことに、ステージが終わってからようやく思い至った。まぁ、遠目だからたいして変わんないか。
・さいしょ、なんか妙に緊張して動きがぎこちなかった
・結婚式の踊りのとき、いまいちキレがなかった。まわるときその場で回ってた。あんまりダイナミックに回ると脱ぎ捨てたマントふんづけて滑りそうっていうのもあったんだけど。
・ヴェールぬぐの忘れててもたもたした
・この大岩を・・・のセリフまでに大岩の設置が間に合わなかった。ここはかなりかっこ悪~!! ほんと申し訳ない。
<全体的な反省点>
・会場の黒カーテン閉めとくべきだった。竜と馬車が通るとき、逆光になってしまった。
・知ってる人が来てくれると挨拶しないわけにいかないし、しかしそれやってるとなかなか時間どおりに始まれない。どうしたものか。
それでも今回は5分過ぎくらいには始まれたけど。
・森の神の冠が途中で脱げてしまったのは、ほんとに残念!!
・石の神の金のベルト、ぎゅっとしめるといつも細くなってしまう。厚みを保つには縫いつけるしかないか。
あとは・・・
前日までに(というか、当日の朝までに)根詰めてあれこれがんばりすぎ、当日、会場に着いただけでなんか疲れきってしまった。くらーっとしてきて、スイッチが入るまでにしばらくかかった。ほかの団員さんたちに申し訳なかった。
しかし、だからって準備に手を抜くわけにもいかんし・・・悩みどころ。
とにかく、夏に公演をやるのはもうやめよう! と思った次第。
この尋常じゃない暑さのなか、稽古に通うのも、お客さんが来て下さるのも大変。やるのが屋内ならいいってもんじゃない。季節も考えないと!!
<公演前一週間くらいにやってたこと>
・最終練習/そのための道具積み込み/団員間でいろいろ連絡
・ちらしの訂正シール貼り
・宣伝のためのたすきや看板づくり
・駅前やらあちこちでちらし配り
・ブログ告知、プレスリリース、ML、facebook やら mixi やらいろいろ
・そのための、動画から写真を切り取ったりする作業
ビデオスタジオでその機能がなぜか使えず、さんざん苦闘したあげく諦めてムーヴィーメイカーを使用して作業することに。ただ、こっちだと画像が微妙に縦長になってしまううえに自動的に240×320の小さなサイズになってしまう。
ブログに上げるにはいいんだけど
・リハ映像をユーチューブにアップしようとして苦闘したあげくいったん挫折
・会場へ、時間変更の申請しにいく
・撮影係さんにビデオ渡したりSDカード買いに行ったり
・竜の翼部分の改良
・音源の改良 例によってオーダシティとWMPを使用
・告知のために出るオープンマイクのための曲練習
・ダンスを少し改良したりあらたに加えたりしたので、その練習
<道具類・衣裳類リスト>
私の手元にある分。またやるとき忘れないよう。
・大岩
・チェス盤
・森(イミテ植物+ネット)
・鳥の大群
・大洪水(ブルーシート)
・竜・・・布部分、人が入る頭部分骨組み、胴体部分骨組み、ハンガーポール(これ意外に忘れがちなんで重要!!)
・馬車・・・台車×2、プラダン板×2、ロープ、カーテンレールの棒
・森の神と石の神の玉座のカバー・・・森の神のほうは、みどり布+みどりワンピ
・音源CD、CDプレイヤー
・森の神・・・冠、桂冠、みどりのマント、マントの鎖
・石の神・・・冠、かつら、ひげ、衣、マント、金ベルト、マントの鎖
・キーナ・・・ドレス、ティアラ×2、ヘアピン5本、アクセ類、ヴェール、鏡、マント
・マグア・・・赤衣、マント、スカーフ、杖
・アンガス・・・かつら、茶衣、マント、マントの鎖、剣
・会場使用許可書、あといちおう台本
予備として持っていったもの
・ガムテープとはさみ
・紙ばさみ
・安全ピン(大事!)
・ヘアピン
・ロープ
・裁縫セット