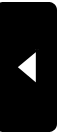2010年08月31日
幻の雄鹿
目次へ戻る
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇4
幻の雄鹿 The Haunted Stag
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 物語<幻の雄鹿>
2. 夕暮れのタリヴァン山へ
*******************************************
1. 物語<幻の雄鹿>

まわりが何と言おうとも彼は揺るがず、己れのヴィジョンをさいごまで追いつづけてやまなかった。・・・
この物語には、ドレのそれのような緻密な銅版画。あの説教臭いラ・フォンテーヌの寓話につけられた、本文自体よりもはるかにいきいきとしてすばらしい、ギュスターヴ・ドレのそれのような。・・・
コンウィイ・ヴァリイ・・・ 平和で美しい場所である、眺め渡してもなだらかな丘々が切れめなくどこまでも連なって広がり、日の出るときは、その光がどの斜面にも均一に降り注ぐ、どこを見渡してもガチガチの鋭い断絶や、不気味な暗い陰などはない・・・
だから当地でやってくる物語もそのようである、比較的のどやかで牧歌的なのが多い、あんまりガチガチした鋭さや、不気味な暗い影などはない・・・
けれども、かなたに海のおもてのうち光るところからぐるりと首をめぐらせて、右手の山の背の向こうにまで目を向けるとき、そこから少し調子の違う、茶色いごつごつした不毛の山岳地帯のはじまりがちょっぴり見えるのが分かるだろう。
あの辺りから本式の山が始まって、ずっとずっとかなた、オグウェンにまで至る壮大な山地を形成する、それはそのさいしょのところなのだ・・・
だからこの物語のコレクションの中にも、あの険しい山地の切りたった鋭さを、ちょっぴり取り入れるのはふさわしいし、変化がついていいだろう・・・
眺めわたして、右肩の向こう、あの山々の鋭いシルエットを見出したほとんどその瞬間に、物語はやってきたのだった、岩山のあいだを風のように駆け抜けてゆく、かの雄鹿の幻影とともに。・・・
* *
月の光のような銀色と、墨のような黒色のぶちの雄鹿・・・銀色と黒のぶちで、腹と尾は白かった、その角のりっぱなことは、樫の木の大枝のようだった・・・そんなのを、このあたりに住むだれもかつて今まで見たことがなかった。・・・
昔、このあたりの山奥に近い村のひとつに、日ごとに犬を連れて険しい山深くをめぐり、けものをとって身を立てる猟師があった・・・まじめで信頼のおける男で、おまけに猟の腕前は、この地方一帯で右に出る者がいなかった。
私はこの猟師に、かつての農場を引き継いだこのコテッジの名、リュウ、この名を与えたい・・・リュウ、ウェールズ語で<険しい場所>を意味する。このコテッジが、ロウウェンの村からずいぶん登った険しいところにあるのと同様、この猟師も人里離れた険しい場所を日々の生活の場としていたからだ。・・・
この猟師が、あるとき、そういうふしぎな姿をした雄鹿を見て、三日三晩、犬どもを連れて追いつづけたが、見失ってしまった。
彼は村に戻ってきて、酒場でその話をした・・・彼は真っ正直な男で、嘘をついたこともなかったから、みんなが彼の言うことを信じた。おいらもぜひそんなのを見てみたいもんだ、とみんなは言った。こんど見つけたら、きっとうまいこと仕留めなよ。お前さんならできる、大丈夫だとも。・・・
それからしばらくして、雄鹿は再び彼の前に姿を現した。激しい追跡が繰り返された・・・
しかし、こんども同じだった。雄鹿は岩山のあいだに巧みに道をとり、猟師の弾の届く距離まで、どうしても彼を近づけなかった。
俺のプライドにかけて、必ずあいつを仕留めてみせる、そう彼は心に誓った。
いくたびか、雄鹿は現れた・・・そのたびにそれはみごとに逃げきり、犬どもは尾を垂らして、すごすごと引き返してくるのだった。・・・
雄鹿を仕留めるのが彼の執念になった。
開けても暮れても岩のあいだにその姿を探し求め、夢の中にまでそのあとを追いつづけた・・・酒場に来ても、もうそのことしか喋らなくなった。村人たちは半ば呆れ、半ば恐れて、しだいに彼の相手をしなくなった・・・彼が入ってくると、潮が引くように、みんな彼のそばを離れてゆくのだった。ひとりきりのカウンターにもたれ、つぶれるまで酔っぱらっては、酒場の主人を相手に同じことを繰り返した、俺は必ず仕留めてみせる、今度こそ!・・・
さいごの追跡は一週間つづいた・・・彼も犬たちも、もう力の限界だった、雄鹿は相も変わらず、軽々と風のように駆けてゆく、あるいはそれは獣なのか、この世ならぬもの、幻影か、あるいは姿を変えた神なのか?・・・ それはどこへ彼らを連れてゆこうとするのか、気づけば今まで足を踏み入れたこともない山奥である、木もなく人の手になるものもなく、ただ荒涼とした岩山と、群れ生えたるワラビやハリエニシダがどこまでも広がるばかり、もう帰り道も分からない・・・
彼はけれども、もう何も気にかけなかった、雄鹿を仕留めることのほか、何もかもどうでもよかった・・・切りたった岩山のふち、目も眩む谷底をはるかにのぞむ、今しもかの雄鹿が身のこなしも優雅に駆け去ったところを、彼はぜいぜい喘ぎ、息も絶えだえに追った、と、そのとき、足もとで岩が崩れた、足場を失って彼はよろめき、一瞬ののち、岩ころの二つ三つをともに、深い谷底へ落ちていった。・・・
犬どもが、足を引きずり引きずり、痩せこけて汚ない姿になって村に辿りついたのは、彼らが出かけてから十日もあとのことだった。
彼らは村人たちを案内しようとしたが、途中から、あまりに山が険しいので誰もそのあとを追ってゆくことができなかった。ずっとずっとあとになって、この村を訪れた旅人が、深い谷の底で人の骨を見たという話をした。それで、それがたぶんあの猟師なのだろうと、みんなが思ったわけだった。彼らはみな猟師のことを気の毒に思った・・・やつは狂気に憑かれちまった、そう考えたのだ。・・・
ところがそのあと、しばらくたって、村人のなかに、そんなふうな鹿を見た、という者が現れた。あの猟師が言っていたとおり、黒と銀色のぶちで、樫の大枝のような角をもっていたと。・・・
みんなは気味悪がった・・・死んだ男の霊にとりつかれたのだと思ったのだ。けれども、そのあとに二人、三人と、やはり見たという者が現れて、同じことを言った。いずれも深い山奥でのことだった。
それでみんなは考えを変えて、やはり雄鹿はほんとうにいるらしいということになった。中には向う見ずにも、そいつを仕留めてやろうと出かけた者たちもあった・・・だが、ついに誰にも仕留められなかったのは言うまでもない。多くの場合、雄鹿は彼らの前に姿を現しさえしなかった。あいつがあんなにまでして、だめだったのだ。ほかの奴らがやってみるだけ無駄さ。・・・彼らは、そう言い言いした。・・・
それにしても、奴は気の毒な男だったよ、というのがみんなの全体的な意見だった・・・あのけものにとり憑かれてから、まるでひとが違ってしまった、あいつのせいで命を落としたのだと。・・・しかしほんとうにそうだろうか?・・・
私は思うのだった・・・奴はほんとうに、ただ気の毒なだけの男だったのだろうか? これと定めた獲物だけを追いつづけて、ほかのすべてを捨てて顧みなかった・・・まわりが何と言おうとも・・・彼はそうすることで、猟師の本分を貫いたのではなかろうか、それは誇り高い猟師にふさわしい最期ではなかっただろうか?・・・
2. 夕暮れのタリヴァン山へ

宿を過ぎてさらに上へ上へ、ずっと道はつづいていて、その道沿いには石器時代の墓標やストーンサークルがあるのだった。宿のスクラップブックに、モノクロの挿画の入った散策案内の地図があって、炉端でよくそれを眺めていたのだ。けれどもこのところずっと晴天つづきであまりに暑く、これ以上山道を登ってゆく気にはあまりなれずにいたのだった。
ある日の夕方、涼しくなったと思われるころ、ちょっとこの道を上まで行ってくると、宿の老人に告げてぶらりと出かけた・・・暗くなる前に戻るよ。
夏の日は長く、出たときにはもう六時を過ぎていたけれども、斜めに射す日はまぶしくて、まだとても暑かった。
村からまっすぐ登ってきてさらにずっとつづくこの一本道はローマ道ということになっていたが、ローマ時代から変わっていないのではないかと思われるようなゴロゴロした石の道で、水の細い流れもそこをいっしょに流れている。両側を石垣に挟まれてつづく、そのうち木立も途切れてしまって、荒涼とした山の景色になる・・・目につく木といえばさんざしのねじくれた梢が、山から下る風に吹きさらされて風下へ曲がって生えているばかり、あるいは花の咲き残ったゴースの茂みが、木立を遠くから眺めたふうにまるくぽこぽこと広がっていたり、みどりのワラビが元気に茂ってそこらじゅうを埋め尽くしていたり、あるいはまた、鋭くのびたスゲガヤや、イラクサの群れや、ピンクのジギタリス・・・層になって上へ上へと折り重なってつづく、でこぼこした短い草地の斜面には、ごつごつと岩が突き出ている・・・
羊、羊、羊・・・そこらじゅうに羊がいる、近づくとスタコラ逃げていくくせに、ひとが木戸によじ登って景色を眺めていたりすると、すぐうしろまで寄ってきて不審げにじろじろ見る・・・遠くで、近くで、四六時中たえずメエメエ鳴き交わしている、何をそんなに伝達すべき重要な知らせがあるんだろうか、どうせ一日中この単調な山の上で草を食んでいるばかりだというのに?・・・
メエメエ声にも実にさまざまな階調があることに驚かされる・・・か細い少女のように甲高いメエーから、年とった男がふざけて真似をしているのではあるまいかというような、しわがれた、ぞっとするように低いベエエまで。・・・
子羊が駆け寄って、前ひざを折って母親の乳を飲む、ぷるぷるとぜんまい仕掛けのように尾っぽを振れる。・・・それから日も傾いて涼しくなった丘の斜面で、ひっくり返って四つ足を宙に浮かせてみたりする・・・
道ゆくうち、古代の墓標、アイルランドのプルナブローンと瓜ふたつの、ミニチュア版のような<詩人の石>はすぐに見つかった。
そのほかの石柱やストーンサークルは、ずいぶん探しまわったにもかかわらず、ついに見つからなかった・・・妖精の塚のように、見わたす限り、あらゆる形をした岩ころだらけなのだ・・・
あきらめて道に引き返すころ、ようやく山かげに日も没しておだやかに沈みゆく光のなかで、かなたの広大な山肌の、細い割れ目のような川すじや、うす青やみのなかに広がる 荒涼とした山景色、眺めゆくほどに、手をのばせば触れうるほどに、物語はそこに、すぐそばにあった・・・あの雄鹿の物語は。
思いに耽りながら、夕やみの迫りくる山道を、一歩一歩私は降りていった・・・宿の見えるところまで来ると、老人がおもてに出てきて、所在なげにあたりをうろうろしているのが見えた、私のことを心配したのに違いない、私は足を速めた・・・
そうしてごろごろした岩道を急ぎ下りながら、私のうしろの峰々のどこかで、あの幻の雄鹿が・・・黒と銀のぶちの、大枝のような角をもったあの雄鹿が、青い宵闇のなかで鼻づらを高くもちあげ、向こうの大岩に向かって力強く跳躍する姿を、心の目にありありと見たのだった・・・

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇3 コンウィイの霧の娘
次章 ロウウェン篇5 安らえぬ魂
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇4
幻の雄鹿 The Haunted Stag
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 物語<幻の雄鹿>
2. 夕暮れのタリヴァン山へ
*******************************************
1. 物語<幻の雄鹿>

まわりが何と言おうとも彼は揺るがず、己れのヴィジョンをさいごまで追いつづけてやまなかった。・・・
この物語には、ドレのそれのような緻密な銅版画。あの説教臭いラ・フォンテーヌの寓話につけられた、本文自体よりもはるかにいきいきとしてすばらしい、ギュスターヴ・ドレのそれのような。・・・
コンウィイ・ヴァリイ・・・ 平和で美しい場所である、眺め渡してもなだらかな丘々が切れめなくどこまでも連なって広がり、日の出るときは、その光がどの斜面にも均一に降り注ぐ、どこを見渡してもガチガチの鋭い断絶や、不気味な暗い陰などはない・・・
だから当地でやってくる物語もそのようである、比較的のどやかで牧歌的なのが多い、あんまりガチガチした鋭さや、不気味な暗い影などはない・・・
けれども、かなたに海のおもてのうち光るところからぐるりと首をめぐらせて、右手の山の背の向こうにまで目を向けるとき、そこから少し調子の違う、茶色いごつごつした不毛の山岳地帯のはじまりがちょっぴり見えるのが分かるだろう。
あの辺りから本式の山が始まって、ずっとずっとかなた、オグウェンにまで至る壮大な山地を形成する、それはそのさいしょのところなのだ・・・
だからこの物語のコレクションの中にも、あの険しい山地の切りたった鋭さを、ちょっぴり取り入れるのはふさわしいし、変化がついていいだろう・・・
眺めわたして、右肩の向こう、あの山々の鋭いシルエットを見出したほとんどその瞬間に、物語はやってきたのだった、岩山のあいだを風のように駆け抜けてゆく、かの雄鹿の幻影とともに。・・・
* *
月の光のような銀色と、墨のような黒色のぶちの雄鹿・・・銀色と黒のぶちで、腹と尾は白かった、その角のりっぱなことは、樫の木の大枝のようだった・・・そんなのを、このあたりに住むだれもかつて今まで見たことがなかった。・・・
昔、このあたりの山奥に近い村のひとつに、日ごとに犬を連れて険しい山深くをめぐり、けものをとって身を立てる猟師があった・・・まじめで信頼のおける男で、おまけに猟の腕前は、この地方一帯で右に出る者がいなかった。
私はこの猟師に、かつての農場を引き継いだこのコテッジの名、リュウ、この名を与えたい・・・リュウ、ウェールズ語で<険しい場所>を意味する。このコテッジが、ロウウェンの村からずいぶん登った険しいところにあるのと同様、この猟師も人里離れた険しい場所を日々の生活の場としていたからだ。・・・
この猟師が、あるとき、そういうふしぎな姿をした雄鹿を見て、三日三晩、犬どもを連れて追いつづけたが、見失ってしまった。
彼は村に戻ってきて、酒場でその話をした・・・彼は真っ正直な男で、嘘をついたこともなかったから、みんなが彼の言うことを信じた。おいらもぜひそんなのを見てみたいもんだ、とみんなは言った。こんど見つけたら、きっとうまいこと仕留めなよ。お前さんならできる、大丈夫だとも。・・・
それからしばらくして、雄鹿は再び彼の前に姿を現した。激しい追跡が繰り返された・・・
しかし、こんども同じだった。雄鹿は岩山のあいだに巧みに道をとり、猟師の弾の届く距離まで、どうしても彼を近づけなかった。
俺のプライドにかけて、必ずあいつを仕留めてみせる、そう彼は心に誓った。
いくたびか、雄鹿は現れた・・・そのたびにそれはみごとに逃げきり、犬どもは尾を垂らして、すごすごと引き返してくるのだった。・・・
雄鹿を仕留めるのが彼の執念になった。
開けても暮れても岩のあいだにその姿を探し求め、夢の中にまでそのあとを追いつづけた・・・酒場に来ても、もうそのことしか喋らなくなった。村人たちは半ば呆れ、半ば恐れて、しだいに彼の相手をしなくなった・・・彼が入ってくると、潮が引くように、みんな彼のそばを離れてゆくのだった。ひとりきりのカウンターにもたれ、つぶれるまで酔っぱらっては、酒場の主人を相手に同じことを繰り返した、俺は必ず仕留めてみせる、今度こそ!・・・
さいごの追跡は一週間つづいた・・・彼も犬たちも、もう力の限界だった、雄鹿は相も変わらず、軽々と風のように駆けてゆく、あるいはそれは獣なのか、この世ならぬもの、幻影か、あるいは姿を変えた神なのか?・・・ それはどこへ彼らを連れてゆこうとするのか、気づけば今まで足を踏み入れたこともない山奥である、木もなく人の手になるものもなく、ただ荒涼とした岩山と、群れ生えたるワラビやハリエニシダがどこまでも広がるばかり、もう帰り道も分からない・・・
彼はけれども、もう何も気にかけなかった、雄鹿を仕留めることのほか、何もかもどうでもよかった・・・切りたった岩山のふち、目も眩む谷底をはるかにのぞむ、今しもかの雄鹿が身のこなしも優雅に駆け去ったところを、彼はぜいぜい喘ぎ、息も絶えだえに追った、と、そのとき、足もとで岩が崩れた、足場を失って彼はよろめき、一瞬ののち、岩ころの二つ三つをともに、深い谷底へ落ちていった。・・・
犬どもが、足を引きずり引きずり、痩せこけて汚ない姿になって村に辿りついたのは、彼らが出かけてから十日もあとのことだった。
彼らは村人たちを案内しようとしたが、途中から、あまりに山が険しいので誰もそのあとを追ってゆくことができなかった。ずっとずっとあとになって、この村を訪れた旅人が、深い谷の底で人の骨を見たという話をした。それで、それがたぶんあの猟師なのだろうと、みんなが思ったわけだった。彼らはみな猟師のことを気の毒に思った・・・やつは狂気に憑かれちまった、そう考えたのだ。・・・
ところがそのあと、しばらくたって、村人のなかに、そんなふうな鹿を見た、という者が現れた。あの猟師が言っていたとおり、黒と銀色のぶちで、樫の大枝のような角をもっていたと。・・・
みんなは気味悪がった・・・死んだ男の霊にとりつかれたのだと思ったのだ。けれども、そのあとに二人、三人と、やはり見たという者が現れて、同じことを言った。いずれも深い山奥でのことだった。
それでみんなは考えを変えて、やはり雄鹿はほんとうにいるらしいということになった。中には向う見ずにも、そいつを仕留めてやろうと出かけた者たちもあった・・・だが、ついに誰にも仕留められなかったのは言うまでもない。多くの場合、雄鹿は彼らの前に姿を現しさえしなかった。あいつがあんなにまでして、だめだったのだ。ほかの奴らがやってみるだけ無駄さ。・・・彼らは、そう言い言いした。・・・
それにしても、奴は気の毒な男だったよ、というのがみんなの全体的な意見だった・・・あのけものにとり憑かれてから、まるでひとが違ってしまった、あいつのせいで命を落としたのだと。・・・しかしほんとうにそうだろうか?・・・
私は思うのだった・・・奴はほんとうに、ただ気の毒なだけの男だったのだろうか? これと定めた獲物だけを追いつづけて、ほかのすべてを捨てて顧みなかった・・・まわりが何と言おうとも・・・彼はそうすることで、猟師の本分を貫いたのではなかろうか、それは誇り高い猟師にふさわしい最期ではなかっただろうか?・・・
2. 夕暮れのタリヴァン山へ

宿を過ぎてさらに上へ上へ、ずっと道はつづいていて、その道沿いには石器時代の墓標やストーンサークルがあるのだった。宿のスクラップブックに、モノクロの挿画の入った散策案内の地図があって、炉端でよくそれを眺めていたのだ。けれどもこのところずっと晴天つづきであまりに暑く、これ以上山道を登ってゆく気にはあまりなれずにいたのだった。
ある日の夕方、涼しくなったと思われるころ、ちょっとこの道を上まで行ってくると、宿の老人に告げてぶらりと出かけた・・・暗くなる前に戻るよ。
夏の日は長く、出たときにはもう六時を過ぎていたけれども、斜めに射す日はまぶしくて、まだとても暑かった。
村からまっすぐ登ってきてさらにずっとつづくこの一本道はローマ道ということになっていたが、ローマ時代から変わっていないのではないかと思われるようなゴロゴロした石の道で、水の細い流れもそこをいっしょに流れている。両側を石垣に挟まれてつづく、そのうち木立も途切れてしまって、荒涼とした山の景色になる・・・目につく木といえばさんざしのねじくれた梢が、山から下る風に吹きさらされて風下へ曲がって生えているばかり、あるいは花の咲き残ったゴースの茂みが、木立を遠くから眺めたふうにまるくぽこぽこと広がっていたり、みどりのワラビが元気に茂ってそこらじゅうを埋め尽くしていたり、あるいはまた、鋭くのびたスゲガヤや、イラクサの群れや、ピンクのジギタリス・・・層になって上へ上へと折り重なってつづく、でこぼこした短い草地の斜面には、ごつごつと岩が突き出ている・・・
羊、羊、羊・・・そこらじゅうに羊がいる、近づくとスタコラ逃げていくくせに、ひとが木戸によじ登って景色を眺めていたりすると、すぐうしろまで寄ってきて不審げにじろじろ見る・・・遠くで、近くで、四六時中たえずメエメエ鳴き交わしている、何をそんなに伝達すべき重要な知らせがあるんだろうか、どうせ一日中この単調な山の上で草を食んでいるばかりだというのに?・・・
メエメエ声にも実にさまざまな階調があることに驚かされる・・・か細い少女のように甲高いメエーから、年とった男がふざけて真似をしているのではあるまいかというような、しわがれた、ぞっとするように低いベエエまで。・・・
子羊が駆け寄って、前ひざを折って母親の乳を飲む、ぷるぷるとぜんまい仕掛けのように尾っぽを振れる。・・・それから日も傾いて涼しくなった丘の斜面で、ひっくり返って四つ足を宙に浮かせてみたりする・・・
道ゆくうち、古代の墓標、アイルランドのプルナブローンと瓜ふたつの、ミニチュア版のような<詩人の石>はすぐに見つかった。
そのほかの石柱やストーンサークルは、ずいぶん探しまわったにもかかわらず、ついに見つからなかった・・・妖精の塚のように、見わたす限り、あらゆる形をした岩ころだらけなのだ・・・
あきらめて道に引き返すころ、ようやく山かげに日も没しておだやかに沈みゆく光のなかで、かなたの広大な山肌の、細い割れ目のような川すじや、うす青やみのなかに広がる 荒涼とした山景色、眺めゆくほどに、手をのばせば触れうるほどに、物語はそこに、すぐそばにあった・・・あの雄鹿の物語は。
思いに耽りながら、夕やみの迫りくる山道を、一歩一歩私は降りていった・・・宿の見えるところまで来ると、老人がおもてに出てきて、所在なげにあたりをうろうろしているのが見えた、私のことを心配したのに違いない、私は足を速めた・・・
そうしてごろごろした岩道を急ぎ下りながら、私のうしろの峰々のどこかで、あの幻の雄鹿が・・・黒と銀のぶちの、大枝のような角をもったあの雄鹿が、青い宵闇のなかで鼻づらを高くもちあげ、向こうの大岩に向かって力強く跳躍する姿を、心の目にありありと見たのだった・・・

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇3 コンウィイの霧の娘
次章 ロウウェン篇5 安らえぬ魂
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
2010年08月31日
コンウィイの霧の娘
目次へ戻る
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇3
コンウィイの霧の娘 Mistress of Conwy Valley
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 物語<コンウィイの霧の娘>
2. ロウウェン周辺
3. ミステリアスな石たち
**********************************************
1. 物語<コンウィイの霧の娘>

コンウィイの霧の娘がドラム山の山の神に恋をする・・・ラファエロ前派の絵にあるような、青衣の乙女のイメージ。・・・
北ウェールズの谷間の夏は青い印象である・・・
夜明け、すもも色と紺と青むらさきとに染め分けられた丘々の陵線、そのドラマティックなことは、劇場の幕開けを見ているようだ・・・
日が高く昇るにつれ、谷間は朝もやに包まれて青くおぼろげに微笑み、逆光のなかで木立の輪郭だけが浮かびあがる。・・・
もやが溶け去るにつれ、透明な強い日射しがいっぱいに溢れ、丘々の果てまで、ずっとずっと遠くまで、欣々と、青い光に照り輝いて。・・・
昼の日射しまでが青いのだ、青い光が木立や牧草地を染める、空の青が滲み出していたかのように。空気がとても澄んでいるからだ・・・
やがて丘々のかなたから、鈍い銀色と真珠色の雲むらがあらわれて谷の上に広がり、重なりあったひだのすそを灰紫にけぶらせて、ゆっくりと海の方へ流れ動いてゆく・・・
夕刻になると霧が出てきて、谷間は青みがかってぼうっとかすむ、あらゆる水のおもてから、海からも川からも霧が立ち昇って、谷間のかなたまで、川すじに沿ってうっすらかすむ・・・
その中に町の灯が、オレンジの光が潤みながら煌めいて、コンウィイ湾のあたり、光のつぶを連ねた首飾りのように、ちろちろと瞬き光る・・・
やがて砂洲を残して、しずかな鏡のような海のおもてが白くなって、・・・そう、ちょうどそんな時分である、夕べの涼しさに誘はれて、ひとときばかりそぞろ歩きしようと、あの娘のおぼろな姿が 川すじの霧のなかに立ち現れるのは。・・・
霧の娘はコンウィイ湾の、きらめく海のほとりに住んでいた・・・毎日、青い夕闇のとばりに包まれて、水のおもてから霧が立ち昇るころ、娘は霧に立ちまぎれて川ぞいに登ってゆき、谷のあいだを彷徨い歩くのだった・・・朝になる前に戻らなくてはならなかった、日が昇ると、霧の娘は光の中に溶け去って消えてしまうからだ・・・
ある日の夕方だった、霧の娘はいつものように川ほとりを散歩していて、ちょうどドラム山の山の神がふもとへ下ってくるのに出会った。
山の神は革の腰帯に横笛を下げ、その目はいきいきと澄んで、その青銅の足はしっかりと地を踏んで、颯爽と歩いてやってきた。
霧の娘は目を奪われて、立ちどまった。「何とすらりとして、美しい若者だろう」と娘は思った。
山の神のほうも、娘の姿を目に留めて、「何と清らかな乙女だろう」と思った。
そこで山の神は娘の手をとって、ドラム山の頂上へ連れてゆき、二人は並んで腰をおろした。
青い夕闇のなかに、すばらしいパノラマが広がっていた。
霧の娘はそれまでいちども山に登ったことがなかったので、そこからの眺めにすっかり夢中になった。
自分の住んでいる海が、はるか遠くまで広がっているようすにびっくりした。
彼らは、そこから見える山々や、丘々を指しては語り合った。
あちこちの山の名や、その土地のようすなどを、山の神は話して聞かせた。
地上がすっかり闇に閉ざされてしまうと、空には満天の星が輝き出した。
霧の娘は、こんなにたくさんの星を、こんなに間近で見たことがなかった。
山の神は、星々の名やその軌道について、あれこれと話して聞かせた。
二人は一晩中、たのしく語りあった。
やがて東の山々の陵線が白みはじめた。
「帰らなくては。朝が近い」と、コンウィイの霧の娘は思った。
けれども、山の神は娘の体をしかと抱きすくめて放そうとしなかったし、娘のほうも、甘い眠りに身も心もとろけたようになって、どうしてもふりほどくことができなった。
朝のさいしょの光が射した。
山の神の腕の中で、娘の体はふっと透き通ったかと思うと、またたくまに光の中に溶けて、すっかりかき消えてしまった。
山の神は嘆き悲しんで、娘を想って横笛を吹いた。
淋しい、ほそい笛のひびきが、ドラム山の険しい山肌にひびき通った・・・
いまでも夕暮れどき、川沿いにうっすらと霧の立ち昇るころ、ふたたび霧のなかからあたらしく生まれて、川のほとりを歩いてゆく娘のすがたを目にすることがある・・・
青いヴェールをまとい、その軽やかな足取りはほとんど地のおもてにもつかぬばかり、永遠に清らかな面立ちをたたえて、恋人に、ドラム山の山の神に会いにゆくのだ・・・
ああ・・・ほんとうに、何と綺麗なのだろう、コンウィイ谷の夏の夕べ。・・・
午後の九時半ばかり、丘のこちら側の影がだんだんに伸びていって、谷を挟んで向こう側の丘々をすっかり覆ってしまう、するとがらりと表情が変わって、地のおもてはうち沈む。・・・
そのうち、丘々の色あいが空の色あいとさほど変わらなくなる、かすかに紫色を帯びた、同じ青色に染まって。・・・
やがてしだいに風景の細部、ヘッジや石垣のラインなどもうまぎれて見分けがつかなくなって、パッチワークのなかで黄色とかベージュの牧草地だけが、ぼんやりと四角く浮かびあがる、黄色みを失って、蒼ざめたチーズみたいに。・・・
しまいに大地ぜんたいが暗やみの中に沈み、宵の空は夢のような青色にぼうっと霞んでゆく・・・このどこまでも限りなく広い、豪勢な眺め・・・
丘々のはじのところ、折り重なった陵線が遠く遠くはるかにけぶる、大気全体が青く染まる、窓辺のガラスも、コーヒーカップも、わが身も心もすっかり青く染まる、コンウィイの谷のうらけき宵辺である・・・
2. ロウウェン周辺

以下の数節は、リュウのコテッジにあった散策案内をざっと訳したものである。
当地の風土をつかんでいただくための資料として添える。著者名なし。
固有名詞はウェールズ語である。主として当地で入手した<ウェールズ語の地名の読み方>という小冊子に照らし、また当地の人びとにたずねた子音の発音なども参考にしてカタカナ表記を起こした。 致らぬ点ご教示願う。
ロウウェン周辺 Around Rowen
このあたりの土地のおもてには、数知れぬ歴史的な、あるいは古代からのしるしが刻み残されている。
リュウのコテッジをすぎてつづく道は、ずっと下の方の谷のコンウィイ川 the Afon Conwy に沿って下ったところにあるカノヴィウム砦 the fort of Canovium から上がってくる古代ローマ道が今に残ったものである。両方とも北ウェールズの軍事的征服のために使われた。さいしょは紀元58年ごろローマ軍によって、そののちには告白者エドワードによって、さらにのちには<丸頭>たち the roundheads によって。
ローマ道路のこの道すじはやがて開けた山の上に至る。
そこは北にタリヴァン山 Tal-y-fan の高みを、南にはドラム山 Drum のいただきをのぞむ<ブルク・ズヴァーン> Bwlch-y-ddeufaen (二つの石のあいだ)である。道のいちばん高いところにある二つの石は、年代のはっきりしない有史以前の一本石である。それをすぎて、さらに遠く、ローマ道路はアベル滝 the Aber falls の下にあるアベル Aber へ向かって進んでゆく。
このあたりでもっともよく知られた古代遺物はおそらく、リュウのコテッジから道を半マイル登ったところにある<マーンヌ・バルズ> Maen-y-bardd (吟遊詩人の石)であろう。
それは石器時代の巨石墓である。たてに立てられたいくつかの石の上に、大きな平たい石がひとつのっかってできている。道をもっと行くと矢石群とストーン・サークルがある。この墓は、北ウェールズにある他のものと同じく、おそらく族長の墓標である。この地域の1:25000の縮尺の地図をよく見ると、このあたりにはたくさんのケルンや、墳墓や、ストーンサークルがあるのが分かる。そのことは、このあたりが、新石器時代の人々の中心地であったことを示している。
タリヴァン山の東側、まるい塚を形成している山の突出部分の上には<カール・バック> Caer Bach (小さな砦)がある。それは二すじの塁に取り囲まれている。そこから遠くないところに聖ケルニン St. Celynin の古代の教会がある。その主な部分は十三世紀の建立である。
谷を横切って南へ向かう、いちばん近い丘の上には<ペナ・ガール> Pen-y-Gaer (峠の砦)がある。塁や壕、とがった石や環状の兵舎群がはっきり識別できる、ドラマティックな峰の上の古代丘砦である。
3. ミステリアスな石たち

(これもコテッジにあったものの訳。)
コテッジをすぎ、山を越えてアベル Aber へ至る小径は、地図上ではローマンのものということになっている。しかし、ここにはローマ軍による占領のはっきりした痕跡はなく、もっと早い時代の土木事業の遺跡が数多く見られる。四千年か五千年前にここに住んでいた人々は、そのしるしを埋葬室や、立石や、ストーン・サークルのかたちで残している。
コテッジから道なりに丘を登っていくと、<マーンヌ・バルズ> Maen-y-bardd に行きあたる。三つのどっしりした石が、四つ目の石を支えているかたちの建造物である。その名は<吟遊詩人の石>を意味し、かつての(しかし今は否定された)ドルイドの生贄説と関係がある、何か不吉な含みをもっている。
それは現在では、ドルイドの時代よりずっと以前の埋葬室であるとされる。今それを見る限り、こうした建造物を埋葬のために使うことの実用性を理解することは少し難しい。それゆえ人は、ここにもうひとつの説が浮上したゆゑんを見ることだろう。
立石や、人の手で刻まれた巨大な石のかたまりの目的についても、それらは同じ神秘に包まれている。それらは小径のゆく手に次々と現れる。それらは何か宗教的な意味をもっていたのか、あるいは単に古代の道すじをしるしづける目印にすぎなかったのだろうか?
ブルグ・ズヴァーン(二つの石の道)に至るみちみち、いくつの石を数えられるか見てみるといい。二つよりはるかにたくさん数えられるだろう。

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇2 タリヴァンの雲男
次章 ロウウェン篇4 幻の雄鹿
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇3
コンウィイの霧の娘 Mistress of Conwy Valley
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 物語<コンウィイの霧の娘>
2. ロウウェン周辺
3. ミステリアスな石たち
**********************************************
1. 物語<コンウィイの霧の娘>

コンウィイの霧の娘がドラム山の山の神に恋をする・・・ラファエロ前派の絵にあるような、青衣の乙女のイメージ。・・・
北ウェールズの谷間の夏は青い印象である・・・
夜明け、すもも色と紺と青むらさきとに染め分けられた丘々の陵線、そのドラマティックなことは、劇場の幕開けを見ているようだ・・・
日が高く昇るにつれ、谷間は朝もやに包まれて青くおぼろげに微笑み、逆光のなかで木立の輪郭だけが浮かびあがる。・・・
もやが溶け去るにつれ、透明な強い日射しがいっぱいに溢れ、丘々の果てまで、ずっとずっと遠くまで、欣々と、青い光に照り輝いて。・・・
昼の日射しまでが青いのだ、青い光が木立や牧草地を染める、空の青が滲み出していたかのように。空気がとても澄んでいるからだ・・・
やがて丘々のかなたから、鈍い銀色と真珠色の雲むらがあらわれて谷の上に広がり、重なりあったひだのすそを灰紫にけぶらせて、ゆっくりと海の方へ流れ動いてゆく・・・
夕刻になると霧が出てきて、谷間は青みがかってぼうっとかすむ、あらゆる水のおもてから、海からも川からも霧が立ち昇って、谷間のかなたまで、川すじに沿ってうっすらかすむ・・・
その中に町の灯が、オレンジの光が潤みながら煌めいて、コンウィイ湾のあたり、光のつぶを連ねた首飾りのように、ちろちろと瞬き光る・・・
やがて砂洲を残して、しずかな鏡のような海のおもてが白くなって、・・・そう、ちょうどそんな時分である、夕べの涼しさに誘はれて、ひとときばかりそぞろ歩きしようと、あの娘のおぼろな姿が 川すじの霧のなかに立ち現れるのは。・・・
霧の娘はコンウィイ湾の、きらめく海のほとりに住んでいた・・・毎日、青い夕闇のとばりに包まれて、水のおもてから霧が立ち昇るころ、娘は霧に立ちまぎれて川ぞいに登ってゆき、谷のあいだを彷徨い歩くのだった・・・朝になる前に戻らなくてはならなかった、日が昇ると、霧の娘は光の中に溶け去って消えてしまうからだ・・・
ある日の夕方だった、霧の娘はいつものように川ほとりを散歩していて、ちょうどドラム山の山の神がふもとへ下ってくるのに出会った。
山の神は革の腰帯に横笛を下げ、その目はいきいきと澄んで、その青銅の足はしっかりと地を踏んで、颯爽と歩いてやってきた。
霧の娘は目を奪われて、立ちどまった。「何とすらりとして、美しい若者だろう」と娘は思った。
山の神のほうも、娘の姿を目に留めて、「何と清らかな乙女だろう」と思った。
そこで山の神は娘の手をとって、ドラム山の頂上へ連れてゆき、二人は並んで腰をおろした。
青い夕闇のなかに、すばらしいパノラマが広がっていた。
霧の娘はそれまでいちども山に登ったことがなかったので、そこからの眺めにすっかり夢中になった。
自分の住んでいる海が、はるか遠くまで広がっているようすにびっくりした。
彼らは、そこから見える山々や、丘々を指しては語り合った。
あちこちの山の名や、その土地のようすなどを、山の神は話して聞かせた。
地上がすっかり闇に閉ざされてしまうと、空には満天の星が輝き出した。
霧の娘は、こんなにたくさんの星を、こんなに間近で見たことがなかった。
山の神は、星々の名やその軌道について、あれこれと話して聞かせた。
二人は一晩中、たのしく語りあった。
やがて東の山々の陵線が白みはじめた。
「帰らなくては。朝が近い」と、コンウィイの霧の娘は思った。
けれども、山の神は娘の体をしかと抱きすくめて放そうとしなかったし、娘のほうも、甘い眠りに身も心もとろけたようになって、どうしてもふりほどくことができなった。
朝のさいしょの光が射した。
山の神の腕の中で、娘の体はふっと透き通ったかと思うと、またたくまに光の中に溶けて、すっかりかき消えてしまった。
山の神は嘆き悲しんで、娘を想って横笛を吹いた。
淋しい、ほそい笛のひびきが、ドラム山の険しい山肌にひびき通った・・・
いまでも夕暮れどき、川沿いにうっすらと霧の立ち昇るころ、ふたたび霧のなかからあたらしく生まれて、川のほとりを歩いてゆく娘のすがたを目にすることがある・・・
青いヴェールをまとい、その軽やかな足取りはほとんど地のおもてにもつかぬばかり、永遠に清らかな面立ちをたたえて、恋人に、ドラム山の山の神に会いにゆくのだ・・・
ああ・・・ほんとうに、何と綺麗なのだろう、コンウィイ谷の夏の夕べ。・・・
午後の九時半ばかり、丘のこちら側の影がだんだんに伸びていって、谷を挟んで向こう側の丘々をすっかり覆ってしまう、するとがらりと表情が変わって、地のおもてはうち沈む。・・・
そのうち、丘々の色あいが空の色あいとさほど変わらなくなる、かすかに紫色を帯びた、同じ青色に染まって。・・・
やがてしだいに風景の細部、ヘッジや石垣のラインなどもうまぎれて見分けがつかなくなって、パッチワークのなかで黄色とかベージュの牧草地だけが、ぼんやりと四角く浮かびあがる、黄色みを失って、蒼ざめたチーズみたいに。・・・
しまいに大地ぜんたいが暗やみの中に沈み、宵の空は夢のような青色にぼうっと霞んでゆく・・・このどこまでも限りなく広い、豪勢な眺め・・・
丘々のはじのところ、折り重なった陵線が遠く遠くはるかにけぶる、大気全体が青く染まる、窓辺のガラスも、コーヒーカップも、わが身も心もすっかり青く染まる、コンウィイの谷のうらけき宵辺である・・・
2. ロウウェン周辺

以下の数節は、リュウのコテッジにあった散策案内をざっと訳したものである。
当地の風土をつかんでいただくための資料として添える。著者名なし。
固有名詞はウェールズ語である。主として当地で入手した<ウェールズ語の地名の読み方>という小冊子に照らし、また当地の人びとにたずねた子音の発音なども参考にしてカタカナ表記を起こした。 致らぬ点ご教示願う。
ロウウェン周辺 Around Rowen
このあたりの土地のおもてには、数知れぬ歴史的な、あるいは古代からのしるしが刻み残されている。
リュウのコテッジをすぎてつづく道は、ずっと下の方の谷のコンウィイ川 the Afon Conwy に沿って下ったところにあるカノヴィウム砦 the fort of Canovium から上がってくる古代ローマ道が今に残ったものである。両方とも北ウェールズの軍事的征服のために使われた。さいしょは紀元58年ごろローマ軍によって、そののちには告白者エドワードによって、さらにのちには<丸頭>たち the roundheads によって。
ローマ道路のこの道すじはやがて開けた山の上に至る。
そこは北にタリヴァン山 Tal-y-fan の高みを、南にはドラム山 Drum のいただきをのぞむ<ブルク・ズヴァーン> Bwlch-y-ddeufaen (二つの石のあいだ)である。道のいちばん高いところにある二つの石は、年代のはっきりしない有史以前の一本石である。それをすぎて、さらに遠く、ローマ道路はアベル滝 the Aber falls の下にあるアベル Aber へ向かって進んでゆく。
このあたりでもっともよく知られた古代遺物はおそらく、リュウのコテッジから道を半マイル登ったところにある<マーンヌ・バルズ> Maen-y-bardd (吟遊詩人の石)であろう。
それは石器時代の巨石墓である。たてに立てられたいくつかの石の上に、大きな平たい石がひとつのっかってできている。道をもっと行くと矢石群とストーン・サークルがある。この墓は、北ウェールズにある他のものと同じく、おそらく族長の墓標である。この地域の1:25000の縮尺の地図をよく見ると、このあたりにはたくさんのケルンや、墳墓や、ストーンサークルがあるのが分かる。そのことは、このあたりが、新石器時代の人々の中心地であったことを示している。
タリヴァン山の東側、まるい塚を形成している山の突出部分の上には<カール・バック> Caer Bach (小さな砦)がある。それは二すじの塁に取り囲まれている。そこから遠くないところに聖ケルニン St. Celynin の古代の教会がある。その主な部分は十三世紀の建立である。
谷を横切って南へ向かう、いちばん近い丘の上には<ペナ・ガール> Pen-y-Gaer (峠の砦)がある。塁や壕、とがった石や環状の兵舎群がはっきり識別できる、ドラマティックな峰の上の古代丘砦である。
3. ミステリアスな石たち

(これもコテッジにあったものの訳。)
コテッジをすぎ、山を越えてアベル Aber へ至る小径は、地図上ではローマンのものということになっている。しかし、ここにはローマ軍による占領のはっきりした痕跡はなく、もっと早い時代の土木事業の遺跡が数多く見られる。四千年か五千年前にここに住んでいた人々は、そのしるしを埋葬室や、立石や、ストーン・サークルのかたちで残している。
コテッジから道なりに丘を登っていくと、<マーンヌ・バルズ> Maen-y-bardd に行きあたる。三つのどっしりした石が、四つ目の石を支えているかたちの建造物である。その名は<吟遊詩人の石>を意味し、かつての(しかし今は否定された)ドルイドの生贄説と関係がある、何か不吉な含みをもっている。
それは現在では、ドルイドの時代よりずっと以前の埋葬室であるとされる。今それを見る限り、こうした建造物を埋葬のために使うことの実用性を理解することは少し難しい。それゆえ人は、ここにもうひとつの説が浮上したゆゑんを見ることだろう。
立石や、人の手で刻まれた巨大な石のかたまりの目的についても、それらは同じ神秘に包まれている。それらは小径のゆく手に次々と現れる。それらは何か宗教的な意味をもっていたのか、あるいは単に古代の道すじをしるしづける目印にすぎなかったのだろうか?
ブルグ・ズヴァーン(二つの石の道)に至るみちみち、いくつの石を数えられるか見てみるといい。二つよりはるかにたくさん数えられるだろう。

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇2 タリヴァンの雲男
次章 ロウウェン篇4 幻の雄鹿
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
2010年08月31日
タリヴァンの雲男
目次へ戻る
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇2
タリヴァンの雲男 The Cloud Man of Tal-y-fan
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 物語<タリヴァンの雲男>
2. リュウの宿にて
3. ロウウェンの午後
4. リュウでの一日
********************************************
1. 物語<タリヴァンの雲男>

大らかで、ユーモラスな話。
先の、太陽と風の娘たちの物語が、優雅で繊細な水彩画だとしたら、こちらは太い線の、墨の筆で一気に描きあげたような力強い調子の口絵が似合いそうだ。・・・
誰でも知っているように、ウェールズは雲が多い・・・たいていの場合、雲はいくつもの塊になって彼方からやってきては、次から次へ、そろって海のほうへ流れ去ってゆく・・・
空の表情は千変万化してとどまるところを知らず、地のおもてもまた、流れゆく雲むらの影を映してまだらに染まりながら、目まぐるしく濃淡の色あいを変えて尽きることがない・・・
雲の晴れ間から、雲男が大股に丘々を跨ぎ越えてゆく姿が見えることもある・・・そういうときの雲男は、頬をいっぱいに膨らませて雲の群れを追い立てながら、ぼろぼろの着物の裾をひらひらさせ、革紐で縛り上げたブーツのかかとを高く蹴上げて軽々と走ってゆく・・・
そうかと思うと、時には急にものぐさの気にとりつかれて、ごろんとひっくり返ったまま麦わらを噛みかみ、空をぼんやり眺めるほかは何もしない、それこそ指一本動かさなくなることもある。
そうすると地上はすっぽりと雲に覆われたまま、一条の光も射さなくなって、どんよりと暗くなる。・・・
むかし、そういうことがいちどロウウェンの山の上であった。
ロウウェンの村の真上、タリヴァン山の頂き近くに四十日間もどっかりと雲が垂れこめて、日を遮り、かといって雨を降らすまでもなく、ひたすら重苦しい曇天が来る日も来る日もつづいた。
花は色褪せて落ち、雌牛は乳を出さなくなり、人びともふさぎこんでつまらぬことで苛々として争った。
そのころ、村の羊飼いにホニンという若者がいた。
彼は村人たちの元気のないようすを見て心を痛めていたが、とりわけ恋人のメサビのやつれようときたら見るも哀れだった・・・日に日に食事も喉を通らなくなって透き通るばかりにやせ衰え、しまいに家の中に閉じこもって窓さえ見ようとしなくなった。
・・・どれもこれもこの変てこな天気のせいだ。こんなふうにどんよりと曇ってばかりいるのは、山の上に雲男が居座っているせいに違いない、と人びとは言い言いした。
そこでホニンは雲男と話をつけようと、いつものように背嚢を背負い、羊飼いの杖をついて、タリヴァン山のてっぺんへ登っていった。
そこで彼は、毛あしの長いじゅうたんのように一面敷きつめられた雲の上で、雲男がごろんとひっくり返って眠りこけている姿を見出した。ぽかんと大口を開けて、ものすごいいびきをかいていた。
彼がいびきをかくたびに、山々は震動してがたがた震えるのだった。おかげでホニンは耳がおかしくなりそうだった。
そこでホニンは、ありったけの大声でどなった。
「やい起きろ、このぐうたらの雲男め」
すると、少しして、いびきがとまった。雲男がのっそり身を起して、目をこすってぱちくりやった。
「何だ、このちびの虫けらめが。お前はいったい、何者だ」
「俺は、ロウウェンの村の羊飼いだ」とホニンは言った。
「お前のおかげで、俺たちはたいへんな迷惑をしているのだ。いつまでこの村の上に居座っているつもりなのだ?」
すると、雲男は頬をぼりぼり掻いて、それからうーんと伸びをしながら、あごが外れそうな大あくびをした・・・たちまちすさまじいつむじ風が起こり、ホニンはすんでのところで雲男の口の中にすっぽり吸いこまれそうになったけれども、何とか岩にしがみついて踏みとどまった。
「虫けらのくせに、大層な口をきくもんだな」雲男は、めんどくさそうに言った。
「誰に向かって喋っていると思ってるんだ・・・お前の羊の群れに向かってか」
「自分のほうが場所をとるからって、偉いと思うなよ」と、ホニンは叫んだ。
「俺にとっては、羊も雲も変わりやしない・・・言うことを聞かない奴は、杖で追い立ててやるまでだ」
そうしたら、雲男はふふんと鼻で笑った・・・「できるもんなら、やってみるこった」
そうしてまた、ごろんとひっくり返ってしまった。
けれども、ホニンが耳元でぴょんぴょん飛び跳ねてどなりつづけるので、ぐっすり眠るわけにはいかなかった。
ちっぽけな存在だからといって、大きな相手を悩ますことができないわけではない・・・たとえば、蚊や蝿がいい例だ。あのちっぽけな体で、自分より何百倍も大きな牛や人間を、どれだけ悩ませられるか考えてみるといい。
ホニンの場合も、ちょうど同じようなわけだった。
雲男はひっくり返ったまま片手をのばしてホニンを捕まえようとしたが、彼は器用に身をかわしてさっと指のあいだをすり抜け、ますます力を得てどなりつづけるのだった・・・
とうとう雲男は腹を立て、飛び起きると、本気でホニンのことを追いかけ始めた。
ホニンは、喜んで叫び声をあげた。あっちへ、こっちへ、さんざんに引きまわして雲男をへとへとに疲れさせてから、急に向きを変えると、雲男の股のあいだを走り抜けるついでに羊飼いの杖でその足をひっかけてやったので、彼はもんどりうってどしんと雲の上に尻もちをついた。
あとで聞いたら、下界ではどんがらがっしゃん、すさまじい雷がひびいてこの世の終わりかと思われたそうだ。・・・
雲男が態勢を立て直せないでいるまに、ホニンは背嚢から羊の毛を刈る鋏を取り出すと、えいやっと雲男の尻に突き立てた。
とたんに雲男は吠え声をあげて六ヤードも飛び上がり、毒づきながら転げるようにタリヴァン山の山裾を駆け下っていった・・・自分のまわりの雲の群れも、残らずあとに引き連れていった。
それが、タリヴァン山で雲男を見たさいごだった。・・・
そのとき、ロウウェンの村には四十日ぶりに光が射したかと思うと、まもなく大空いっぱいに太陽が、眩しく照り輝きだした。人びとは家から走り出てきて、眩しそうに目を細めて、久方ぶりの青空を仰ぎ見た・・・
ホニンが山から下ってくると、村人たちは牧草地の上にテーブルを持ちだして、酒瓶やあらゆるごちそうを並べ、盛大な宴会を始めたところだった。
けれどもホニンがいちばんうれしかったのは、恋人のメサビの家の扉が開いて、彼女がとうとう姿を見せたことで、まだ青白かったけれども、あかるい日の光のおかげで、そのおもてにはばら色の微笑みが戻っていたのだ。・・・
そのときからこのかた、タリヴァン山の上に雲が長くとどまることはめったにない。
雲男がここを通りかかるといつも、刈り鋏でしたたか突かれたことを思い出しては、尻をさすりさすり、雲の群れを追い立てて、足早に駆け去って行ってしまうからだ。・・・
* *
2. リュウの宿にて

リュウでのさいしょの滞在はことのほか印象深かったので記しておきたいと思う。
タリヴァン山の中腹のそのコテッジは、前章に書いたようにとても険しいところにあって、辿りついたときには疲れきっていた。
夜までラウンジで本を読みながら熱い紅茶を飲み、ビスケットを少しかじった。
そのうちに窓の外で谷間がゆっくりと青く暮れてゆくほど、宿の主人が暖炉に火を焚きつけてくれる・・・ 火ははじめのうち気乗りのしないようすでつむじを曲げていたが、やがて勢いよく石炭をなめて燃え上がった。
ここに輪の中心ができて、人びとが集まってくる。・・・
山の上の淋しい宿だが、客は私ひとりではなかった。
幼い子供を連れた家族もあって、夜になると小さい女の子たちが賑やかに駆けまわり、そのうちにバラバラッと色鉛筆の箱を取り出して、窓辺のところに座って絵を描きはじめた。・・・
外の闇と淋しさが私たちを結びつけ、ここににわか仕立ての家族がひとつできあがって、夜更くるまでとりとめもなく、ぽつりぽつりと静かな会話がつづいてゆくのだった。・・・
山の上だけあってひどく冷えた。・・・
水はといえば、山から直接引いてくる、氷のように冷たい水だ。
だからぱちぱちとはぜる炎や、ちくちくする灰色の毛布の手触りが快よいのだった。・・・
その山に宿したさいしょの晩、私は奇妙な夢を見た。夢の中で、私は今以上に無力であり、飛翔するための翼をもたなかった少年の日に戻ってしまっており、・・・あろうことかそのうえあとにしてきたはずの故郷の地に戻っているのであった。私は何かうまい具合に言いくるめられて、故国へ戻る機上に乗せられてしまったのだ。・・・
こういうことには覚えがあった・・・幼いときから、何度も何度も。・・・
何度我々は言いくるめられ、肝心な点を告げられず、己れの望まない木戸へ追いこまれ、角を矯められ、骨抜きにされてきたことか。・・・それらはみな、ゆくゆくはより大きな力に我々を服従させるための、周到に練られた下準備だったのだと、今では分かる。けれども、それと分かった今、もはや屈してしまうわけにはいかないのだ。・・・
身近な人びと、あるいは融通のきかぬ制度というかたちをとった不可知の力、私の身の自由を奪おうとする、善意にみちた力に対して、私はもはやかの遠い日々にしたように屈してしまいはしなかった、私は決然として戦った、私は狂ったように暴れた・・・ 「この地にいられるあいだのただの一日でさえも、私にとってどんなに貴重だか、あなたたちには全然分かっていない!・・・」
そう叫んでいるところで、私は目を覚ましたのだった。
私は興奮冷めやらぬままベッドを出て、窓辺へ寄った。・・・
窓の外には、曇り空の、ウェールズの景色が広がっていた。・・・風がびゅうびゅう吹いて、寒そうで、夜明けだった。・・・朝霧にかすんで木立はうっすら青みを帯び、半ばまだ眠っているようだ。・・・
私はしずかな喜びが、深ぶかと心の底にまで滲みとおってゆくのを感じた。・・・
あゝよかった!・・・ 私が決然として戦ったので、こうしてまたこの地に戻ってくることができたのだ。・・・
そこでほっと吐息をつくと、朝までもうひと眠りしようと、心も穏やかに再びベッドにもぐりこんだのだった。・・・
3. ロウウェンの午後

二度目に目を覚ましたとき、しずかな雨が降り出していいた。
こういう日にはいちにち宿で過ごして、熱いお茶などすすりながら書きものをするのに限る・・・
昼過ぎまで食堂に残り、居心地のいい窓辺から降りつづく雨を眺めて過ごした。
宿には誰もいない、ひっそりとしずか、ただ鳴き交わす羊の声がひびくばかりだ・・・
午後になって、少し小降りになったところを、ぶらぶら村へ下ってゆく。・・・
宿のまわりは、森と牧草地が半々くらいだろうか、ただ道は大方木立のなかを抜け、牧草地に接するところでも道沿いにはずっと木が茂っている、道のきわにはしだ類が群れ生え、清水のふちに沿ってごろごろまるい岩ころがみどり色の苔に包まれて、空気は冷たく、単調なみどり一色だ。木々のみどりと湿った苔の葉の匂い・・・ 何千という葉の一枚一枚から雫を滴らせ、休みないしずかな雨音である・・・
当地の石垣、荒々しい石を組んで築かれた、モルタルを加えぬままの、何やら古代遺跡のような原始的な迫力のあるあの石垣、それからメドウのところどころ、木立に半分隠れている石造りの家々・・・それらは何かを思い出させる、そう、田舎で昔ながらのやり方で焼かれる、どっしりとして重たい灰茶色のパンの塊、あれにとてもよく似ている・・・ それから草を食む羊たち、重なりあって上へ上へとつづくメドウ・・・ウェールズの風景。・・・
村に近づくにつれ、あの独特の、<歯をもった>石垣が目につく・・・ へりのところに不ぞろいな薄い石板をラックの皿のように隙間なく並べていて、それで歯をもった下顎のように見えるのだ。たぶん、いつか天から上顎が下りてきて、ガッチャン! と組み合わさるのだろう。その日、石垣の上に腰掛ける者は災いである・・・
ロウウェンの村を歩くのは、絵のなかを歩くようだ。
どの家もどの家もばらが花盛り、道の両側にはだれが植えたでもなく、マーガレットや黄色いラグウォートや、色んな花が溢れ咲いている・・・
家々はどれも重厚だがわりと小ぶりで、平屋も多い、どれも窓枠やドアをきれいな色で塗ってあって、どの村も同じ、村のいちばん中心に、いちばん古くて感じのいい家並が残っている。


家々のひとつずつが今でも目に浮かぶ・・・ 山道を下って村へ入る、Y字路のところの家、石壁に、窓枠は黒塗り、それに赤とピンクのばら、そして石垣にふちどられた草道が裏手へ回っている・・・
ハイ・ストリイトから右手に折れるところに斜めに建つ家は、漆喰で塗りつぶした白壁に水色の窓、それが群れ咲くコスモス色のむくげの花によく映える・・・
その向かいはくすんだ風合いをそのままに残した石壁で、深紅と薄黄色のばら、それに青紫のラヴェンダー。
Lavender's blue, lavender's blue, lavender's green...
If I were a king, then you'll be a queen...
どの窓辺にも小ぎれいなカーテンがかけられ、彩色されたお城だの、せともののネコだの、ガラスや真鍮でできた妖精たちだの、そういうしょうもない小物たちが大切に飾られている。・・・
そんなふうな窓辺を見て歩いていると、私の心には祖母の代の人びとの、どんながらくたでも心をこめて丁寧に扱うその手つきが思い起こされてくる・・・その心のこもった手つきのせいで、何の役にも立たない飾りものたちは何かしら価値を帯びて、オーラを放ちはじめるのだった。・・・
雨足が強くなってきたので村のパブに入る。・・・
薄暗いなかに、客はわずかに二、三人である・・・ なかのひとりはカウンターの真ん中に陣取って、パブの親父をつかまえ、さっきからえんえんと喋りつづけている・・・
ビールを半パイントだけ注文して窓のそばに座り、高く低く喋りつづけるだみ声を聞くともなしに聞き流し、通りに降り注ぐ雨を眺めた。・・・
雲の垂れこめる日は、暗くなるのが早い。
ランプが明るみを増し、村人たちが集まりだした頃合いを見てパブをあとにした。
山の上の宿に着く頃には、とっぷりと青い夕闇のなかで、下界の村々にぽつりぽつり、小さく灯りがともっているのが遥かに見渡されるばかりである。・・・
4. リュウでの一日

あくる朝、目覚めると雨はあがっていた。
がらんと誰もいない階下へ降りてゆくと、食堂のテーブルに窓からしらじらした薄日が射して、何やらしみじみと懐かしい・・・
この安っぽいビニールびきの、陽気な花模様のテーブルクロスと云ひ、使いこんですり減った木の椅子と云ひ、祖母の家の朝の食卓なのだった。
それから私は思い出す、日の光の射しこむなかに漂うコーヒーの香りや、ハムエッグののった皿からほんわり匂ひたつ湯気、トーストに塗る苺ジャムの瓶や、ハート型の柳編みのパン籠・・・
異国にあって呼び覚まされる、遠い日の記憶である、ここに時間はまどろみのなかで沈澱し、ただその表面だけが、しずかにゆらゆらとしてイマージュの連鎖をいざなふ。・・・
朝のあいだに雲は吹き払われて、広々と青く晴れ渡った。
その日はいちにち、何もしないで、ただ眼下に広がるコンウィイ・ヴァリイのようすを眺めて過ごした。
たしかにそれだけの価値はあったのだ・・・あまり際限なく広いので、じっくり見るには一日では足りないくらいだ。
こんなすばらしい眺めが、私の訪れなかった計り知れず長い年月、来る日も来る日もそこにあって、来る日も来る日も日の光と月の光に照らされ、雨風を受けてきたのだった。
それは信じがたいことだった、考えると眩暈を覚えた・・・
谷あいの斜面は緑ゆたかだ、かなりの割合をもこもこしたカーペットのような森が占め、それがコンウィイ川の流域近く駆け下り、あるいは丘々の中腹を駆け上るにつれてかすれたように疎らになって、ブロッコリの株がボコボコと立ち並んでいるのを遠目に眺めたような具合になる。
丘の上のほうの木が生えない部分では、牧草地を区切った幾何学もようの生垣や石垣が、地平のかぎりほんとうにどこまでも、幾千となくひとつひとつくっきり見える。・・・
夕刻になって、中へ入ってほどなく、さあっと雨が降りはじめた。
日の光のなかで、どこまでもくっきりとしているのもいいが、少し雨まじりに青くかすんでいるのはもっといい。 そのようすを窓から眺めているのもいいものだ・・・冷たい雨に包まれた山々の情景を、ぬくぬくと居心地のいい窓の内から。・・・
夢の中で<太陽と四人の娘>の物語が訪れてきたのは、その晩のことだった。
リュウでのこのさいしょの滞在はほんの三日ほどだったが、その二年後にこんどはもう少しゆっくり過ごすことができた。この章の<タリヴァンの雲男>をはじめ、そのほかの物語は、その二度目の滞在のときにやってきたものだ。

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇1 太陽と4人の娘
次章 ロウウェン篇3 コンウィイの霧の娘
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇2
タリヴァンの雲男 The Cloud Man of Tal-y-fan
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 物語<タリヴァンの雲男>
2. リュウの宿にて
3. ロウウェンの午後
4. リュウでの一日
********************************************
1. 物語<タリヴァンの雲男>

大らかで、ユーモラスな話。
先の、太陽と風の娘たちの物語が、優雅で繊細な水彩画だとしたら、こちらは太い線の、墨の筆で一気に描きあげたような力強い調子の口絵が似合いそうだ。・・・
誰でも知っているように、ウェールズは雲が多い・・・たいていの場合、雲はいくつもの塊になって彼方からやってきては、次から次へ、そろって海のほうへ流れ去ってゆく・・・
空の表情は千変万化してとどまるところを知らず、地のおもてもまた、流れゆく雲むらの影を映してまだらに染まりながら、目まぐるしく濃淡の色あいを変えて尽きることがない・・・
雲の晴れ間から、雲男が大股に丘々を跨ぎ越えてゆく姿が見えることもある・・・そういうときの雲男は、頬をいっぱいに膨らませて雲の群れを追い立てながら、ぼろぼろの着物の裾をひらひらさせ、革紐で縛り上げたブーツのかかとを高く蹴上げて軽々と走ってゆく・・・
そうかと思うと、時には急にものぐさの気にとりつかれて、ごろんとひっくり返ったまま麦わらを噛みかみ、空をぼんやり眺めるほかは何もしない、それこそ指一本動かさなくなることもある。
そうすると地上はすっぽりと雲に覆われたまま、一条の光も射さなくなって、どんよりと暗くなる。・・・
むかし、そういうことがいちどロウウェンの山の上であった。
ロウウェンの村の真上、タリヴァン山の頂き近くに四十日間もどっかりと雲が垂れこめて、日を遮り、かといって雨を降らすまでもなく、ひたすら重苦しい曇天が来る日も来る日もつづいた。
花は色褪せて落ち、雌牛は乳を出さなくなり、人びともふさぎこんでつまらぬことで苛々として争った。
そのころ、村の羊飼いにホニンという若者がいた。
彼は村人たちの元気のないようすを見て心を痛めていたが、とりわけ恋人のメサビのやつれようときたら見るも哀れだった・・・日に日に食事も喉を通らなくなって透き通るばかりにやせ衰え、しまいに家の中に閉じこもって窓さえ見ようとしなくなった。
・・・どれもこれもこの変てこな天気のせいだ。こんなふうにどんよりと曇ってばかりいるのは、山の上に雲男が居座っているせいに違いない、と人びとは言い言いした。
そこでホニンは雲男と話をつけようと、いつものように背嚢を背負い、羊飼いの杖をついて、タリヴァン山のてっぺんへ登っていった。
そこで彼は、毛あしの長いじゅうたんのように一面敷きつめられた雲の上で、雲男がごろんとひっくり返って眠りこけている姿を見出した。ぽかんと大口を開けて、ものすごいいびきをかいていた。
彼がいびきをかくたびに、山々は震動してがたがた震えるのだった。おかげでホニンは耳がおかしくなりそうだった。
そこでホニンは、ありったけの大声でどなった。
「やい起きろ、このぐうたらの雲男め」
すると、少しして、いびきがとまった。雲男がのっそり身を起して、目をこすってぱちくりやった。
「何だ、このちびの虫けらめが。お前はいったい、何者だ」
「俺は、ロウウェンの村の羊飼いだ」とホニンは言った。
「お前のおかげで、俺たちはたいへんな迷惑をしているのだ。いつまでこの村の上に居座っているつもりなのだ?」
すると、雲男は頬をぼりぼり掻いて、それからうーんと伸びをしながら、あごが外れそうな大あくびをした・・・たちまちすさまじいつむじ風が起こり、ホニンはすんでのところで雲男の口の中にすっぽり吸いこまれそうになったけれども、何とか岩にしがみついて踏みとどまった。
「虫けらのくせに、大層な口をきくもんだな」雲男は、めんどくさそうに言った。
「誰に向かって喋っていると思ってるんだ・・・お前の羊の群れに向かってか」
「自分のほうが場所をとるからって、偉いと思うなよ」と、ホニンは叫んだ。
「俺にとっては、羊も雲も変わりやしない・・・言うことを聞かない奴は、杖で追い立ててやるまでだ」
そうしたら、雲男はふふんと鼻で笑った・・・「できるもんなら、やってみるこった」
そうしてまた、ごろんとひっくり返ってしまった。
けれども、ホニンが耳元でぴょんぴょん飛び跳ねてどなりつづけるので、ぐっすり眠るわけにはいかなかった。
ちっぽけな存在だからといって、大きな相手を悩ますことができないわけではない・・・たとえば、蚊や蝿がいい例だ。あのちっぽけな体で、自分より何百倍も大きな牛や人間を、どれだけ悩ませられるか考えてみるといい。
ホニンの場合も、ちょうど同じようなわけだった。
雲男はひっくり返ったまま片手をのばしてホニンを捕まえようとしたが、彼は器用に身をかわしてさっと指のあいだをすり抜け、ますます力を得てどなりつづけるのだった・・・
とうとう雲男は腹を立て、飛び起きると、本気でホニンのことを追いかけ始めた。
ホニンは、喜んで叫び声をあげた。あっちへ、こっちへ、さんざんに引きまわして雲男をへとへとに疲れさせてから、急に向きを変えると、雲男の股のあいだを走り抜けるついでに羊飼いの杖でその足をひっかけてやったので、彼はもんどりうってどしんと雲の上に尻もちをついた。
あとで聞いたら、下界ではどんがらがっしゃん、すさまじい雷がひびいてこの世の終わりかと思われたそうだ。・・・
雲男が態勢を立て直せないでいるまに、ホニンは背嚢から羊の毛を刈る鋏を取り出すと、えいやっと雲男の尻に突き立てた。
とたんに雲男は吠え声をあげて六ヤードも飛び上がり、毒づきながら転げるようにタリヴァン山の山裾を駆け下っていった・・・自分のまわりの雲の群れも、残らずあとに引き連れていった。
それが、タリヴァン山で雲男を見たさいごだった。・・・
そのとき、ロウウェンの村には四十日ぶりに光が射したかと思うと、まもなく大空いっぱいに太陽が、眩しく照り輝きだした。人びとは家から走り出てきて、眩しそうに目を細めて、久方ぶりの青空を仰ぎ見た・・・
ホニンが山から下ってくると、村人たちは牧草地の上にテーブルを持ちだして、酒瓶やあらゆるごちそうを並べ、盛大な宴会を始めたところだった。
けれどもホニンがいちばんうれしかったのは、恋人のメサビの家の扉が開いて、彼女がとうとう姿を見せたことで、まだ青白かったけれども、あかるい日の光のおかげで、そのおもてにはばら色の微笑みが戻っていたのだ。・・・
そのときからこのかた、タリヴァン山の上に雲が長くとどまることはめったにない。
雲男がここを通りかかるといつも、刈り鋏でしたたか突かれたことを思い出しては、尻をさすりさすり、雲の群れを追い立てて、足早に駆け去って行ってしまうからだ。・・・
* *
2. リュウの宿にて

リュウでのさいしょの滞在はことのほか印象深かったので記しておきたいと思う。
タリヴァン山の中腹のそのコテッジは、前章に書いたようにとても険しいところにあって、辿りついたときには疲れきっていた。
夜までラウンジで本を読みながら熱い紅茶を飲み、ビスケットを少しかじった。
そのうちに窓の外で谷間がゆっくりと青く暮れてゆくほど、宿の主人が暖炉に火を焚きつけてくれる・・・ 火ははじめのうち気乗りのしないようすでつむじを曲げていたが、やがて勢いよく石炭をなめて燃え上がった。
ここに輪の中心ができて、人びとが集まってくる。・・・
山の上の淋しい宿だが、客は私ひとりではなかった。
幼い子供を連れた家族もあって、夜になると小さい女の子たちが賑やかに駆けまわり、そのうちにバラバラッと色鉛筆の箱を取り出して、窓辺のところに座って絵を描きはじめた。・・・
外の闇と淋しさが私たちを結びつけ、ここににわか仕立ての家族がひとつできあがって、夜更くるまでとりとめもなく、ぽつりぽつりと静かな会話がつづいてゆくのだった。・・・
山の上だけあってひどく冷えた。・・・
水はといえば、山から直接引いてくる、氷のように冷たい水だ。
だからぱちぱちとはぜる炎や、ちくちくする灰色の毛布の手触りが快よいのだった。・・・
その山に宿したさいしょの晩、私は奇妙な夢を見た。夢の中で、私は今以上に無力であり、飛翔するための翼をもたなかった少年の日に戻ってしまっており、・・・あろうことかそのうえあとにしてきたはずの故郷の地に戻っているのであった。私は何かうまい具合に言いくるめられて、故国へ戻る機上に乗せられてしまったのだ。・・・
こういうことには覚えがあった・・・幼いときから、何度も何度も。・・・
何度我々は言いくるめられ、肝心な点を告げられず、己れの望まない木戸へ追いこまれ、角を矯められ、骨抜きにされてきたことか。・・・それらはみな、ゆくゆくはより大きな力に我々を服従させるための、周到に練られた下準備だったのだと、今では分かる。けれども、それと分かった今、もはや屈してしまうわけにはいかないのだ。・・・
身近な人びと、あるいは融通のきかぬ制度というかたちをとった不可知の力、私の身の自由を奪おうとする、善意にみちた力に対して、私はもはやかの遠い日々にしたように屈してしまいはしなかった、私は決然として戦った、私は狂ったように暴れた・・・ 「この地にいられるあいだのただの一日でさえも、私にとってどんなに貴重だか、あなたたちには全然分かっていない!・・・」
そう叫んでいるところで、私は目を覚ましたのだった。
私は興奮冷めやらぬままベッドを出て、窓辺へ寄った。・・・
窓の外には、曇り空の、ウェールズの景色が広がっていた。・・・風がびゅうびゅう吹いて、寒そうで、夜明けだった。・・・朝霧にかすんで木立はうっすら青みを帯び、半ばまだ眠っているようだ。・・・
私はしずかな喜びが、深ぶかと心の底にまで滲みとおってゆくのを感じた。・・・
あゝよかった!・・・ 私が決然として戦ったので、こうしてまたこの地に戻ってくることができたのだ。・・・
そこでほっと吐息をつくと、朝までもうひと眠りしようと、心も穏やかに再びベッドにもぐりこんだのだった。・・・
3. ロウウェンの午後

二度目に目を覚ましたとき、しずかな雨が降り出していいた。
こういう日にはいちにち宿で過ごして、熱いお茶などすすりながら書きものをするのに限る・・・
昼過ぎまで食堂に残り、居心地のいい窓辺から降りつづく雨を眺めて過ごした。
宿には誰もいない、ひっそりとしずか、ただ鳴き交わす羊の声がひびくばかりだ・・・
午後になって、少し小降りになったところを、ぶらぶら村へ下ってゆく。・・・
宿のまわりは、森と牧草地が半々くらいだろうか、ただ道は大方木立のなかを抜け、牧草地に接するところでも道沿いにはずっと木が茂っている、道のきわにはしだ類が群れ生え、清水のふちに沿ってごろごろまるい岩ころがみどり色の苔に包まれて、空気は冷たく、単調なみどり一色だ。木々のみどりと湿った苔の葉の匂い・・・ 何千という葉の一枚一枚から雫を滴らせ、休みないしずかな雨音である・・・
当地の石垣、荒々しい石を組んで築かれた、モルタルを加えぬままの、何やら古代遺跡のような原始的な迫力のあるあの石垣、それからメドウのところどころ、木立に半分隠れている石造りの家々・・・それらは何かを思い出させる、そう、田舎で昔ながらのやり方で焼かれる、どっしりとして重たい灰茶色のパンの塊、あれにとてもよく似ている・・・ それから草を食む羊たち、重なりあって上へ上へとつづくメドウ・・・ウェールズの風景。・・・
村に近づくにつれ、あの独特の、<歯をもった>石垣が目につく・・・ へりのところに不ぞろいな薄い石板をラックの皿のように隙間なく並べていて、それで歯をもった下顎のように見えるのだ。たぶん、いつか天から上顎が下りてきて、ガッチャン! と組み合わさるのだろう。その日、石垣の上に腰掛ける者は災いである・・・
ロウウェンの村を歩くのは、絵のなかを歩くようだ。
どの家もどの家もばらが花盛り、道の両側にはだれが植えたでもなく、マーガレットや黄色いラグウォートや、色んな花が溢れ咲いている・・・
家々はどれも重厚だがわりと小ぶりで、平屋も多い、どれも窓枠やドアをきれいな色で塗ってあって、どの村も同じ、村のいちばん中心に、いちばん古くて感じのいい家並が残っている。


家々のひとつずつが今でも目に浮かぶ・・・ 山道を下って村へ入る、Y字路のところの家、石壁に、窓枠は黒塗り、それに赤とピンクのばら、そして石垣にふちどられた草道が裏手へ回っている・・・
ハイ・ストリイトから右手に折れるところに斜めに建つ家は、漆喰で塗りつぶした白壁に水色の窓、それが群れ咲くコスモス色のむくげの花によく映える・・・
その向かいはくすんだ風合いをそのままに残した石壁で、深紅と薄黄色のばら、それに青紫のラヴェンダー。
Lavender's blue, lavender's blue, lavender's green...
If I were a king, then you'll be a queen...
どの窓辺にも小ぎれいなカーテンがかけられ、彩色されたお城だの、せともののネコだの、ガラスや真鍮でできた妖精たちだの、そういうしょうもない小物たちが大切に飾られている。・・・
そんなふうな窓辺を見て歩いていると、私の心には祖母の代の人びとの、どんながらくたでも心をこめて丁寧に扱うその手つきが思い起こされてくる・・・その心のこもった手つきのせいで、何の役にも立たない飾りものたちは何かしら価値を帯びて、オーラを放ちはじめるのだった。・・・
雨足が強くなってきたので村のパブに入る。・・・
薄暗いなかに、客はわずかに二、三人である・・・ なかのひとりはカウンターの真ん中に陣取って、パブの親父をつかまえ、さっきからえんえんと喋りつづけている・・・
ビールを半パイントだけ注文して窓のそばに座り、高く低く喋りつづけるだみ声を聞くともなしに聞き流し、通りに降り注ぐ雨を眺めた。・・・
雲の垂れこめる日は、暗くなるのが早い。
ランプが明るみを増し、村人たちが集まりだした頃合いを見てパブをあとにした。
山の上の宿に着く頃には、とっぷりと青い夕闇のなかで、下界の村々にぽつりぽつり、小さく灯りがともっているのが遥かに見渡されるばかりである。・・・
4. リュウでの一日

あくる朝、目覚めると雨はあがっていた。
がらんと誰もいない階下へ降りてゆくと、食堂のテーブルに窓からしらじらした薄日が射して、何やらしみじみと懐かしい・・・
この安っぽいビニールびきの、陽気な花模様のテーブルクロスと云ひ、使いこんですり減った木の椅子と云ひ、祖母の家の朝の食卓なのだった。
それから私は思い出す、日の光の射しこむなかに漂うコーヒーの香りや、ハムエッグののった皿からほんわり匂ひたつ湯気、トーストに塗る苺ジャムの瓶や、ハート型の柳編みのパン籠・・・
異国にあって呼び覚まされる、遠い日の記憶である、ここに時間はまどろみのなかで沈澱し、ただその表面だけが、しずかにゆらゆらとしてイマージュの連鎖をいざなふ。・・・
朝のあいだに雲は吹き払われて、広々と青く晴れ渡った。
その日はいちにち、何もしないで、ただ眼下に広がるコンウィイ・ヴァリイのようすを眺めて過ごした。
たしかにそれだけの価値はあったのだ・・・あまり際限なく広いので、じっくり見るには一日では足りないくらいだ。
こんなすばらしい眺めが、私の訪れなかった計り知れず長い年月、来る日も来る日もそこにあって、来る日も来る日も日の光と月の光に照らされ、雨風を受けてきたのだった。
それは信じがたいことだった、考えると眩暈を覚えた・・・
谷あいの斜面は緑ゆたかだ、かなりの割合をもこもこしたカーペットのような森が占め、それがコンウィイ川の流域近く駆け下り、あるいは丘々の中腹を駆け上るにつれてかすれたように疎らになって、ブロッコリの株がボコボコと立ち並んでいるのを遠目に眺めたような具合になる。
丘の上のほうの木が生えない部分では、牧草地を区切った幾何学もようの生垣や石垣が、地平のかぎりほんとうにどこまでも、幾千となくひとつひとつくっきり見える。・・・
夕刻になって、中へ入ってほどなく、さあっと雨が降りはじめた。
日の光のなかで、どこまでもくっきりとしているのもいいが、少し雨まじりに青くかすんでいるのはもっといい。 そのようすを窓から眺めているのもいいものだ・・・冷たい雨に包まれた山々の情景を、ぬくぬくと居心地のいい窓の内から。・・・
夢の中で<太陽と四人の娘>の物語が訪れてきたのは、その晩のことだった。
リュウでのこのさいしょの滞在はほんの三日ほどだったが、その二年後にこんどはもう少しゆっくり過ごすことができた。この章の<タリヴァンの雲男>をはじめ、そのほかの物語は、その二度目の滞在のときにやってきたものだ。

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇1 太陽と4人の娘
次章 ロウウェン篇3 コンウィイの霧の娘
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。