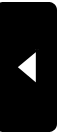2020年03月20日
小説・アレクサンドルⅢ世橋 3. 跳躍
小説・アレクサンドルⅢ世橋 3. 跳躍
リハビリの辛さは、言葉にできないくらいだった。肉体的にもそうだが、いちばん辛いのは、先が見えないこと。いったいいつになったら自由な動きを取り戻せるのか、そもそもそんな日が来るのか、誰にも分からなかった。
それでもシルヴィーは歯を食いしばって続け、やり遂げた。何か月もかかってやっとギプスが取れ、どうにかこうにか、杖なしで歩けるようになった。だが、それではまだ、ようやくふりだしに戻っただけだ。踊り手として果たしてまたものになるのか、それはまだ未知数だった。
ジュスタンがコーチをつけてくれて、シルヴィーは再びバレエの練習を始めた。踊り子は、一日でも休むと感覚が鈍る。この繊細な感覚を保ち、体のコンディションを一定にキープするためには、毎日の練習が欠かせない。これが何か月ものブランクとなると、ほとんど一からやり直すに等しかった。そのうえこの傷を負った体だ。
「奇蹟を起こしてみせる」とシルヴィーは自分に言い聞かせた。「ぜったいに舞台へ戻るのだ。こんなことに邪魔されてたまるか」
彼女の強い決意もあっただろう。まだ若かったためもあるだろう。ともかく、練習は成果を上げ、彼女はまた以前のように、軽々と宙を舞うようなステップを踏むことができるようになった。それはまったく奇蹟といってよかった。
こうして調子が戻ったころ、シルヴィーは右岸の一等地にかまえるオランピア劇場に所属が決まった。時を同じくしてジュスタンは彼女のためにその近くに住まいを用意し、それまで住んでいた小さなアパルトマンから、人をやって必要なものを取ってこさせた。邸宅には使用人をつけ、そこから新しい劇場へ通うための専用の馬車と御者もつけてやった。
シルヴィーにとっては予想外の展開だった。
リハビリはあまりにも長かった。そのあいだ、ジュスタンはろくに見舞いにも来なかった。彼はもう自分には興味を失ったのだろう。自分はきのうジュスタンの愛人になったばかりだ。明日には捨てられる。ただ踊り子としてどこかの劇場で舞台に戻れればそれでいい。そう思っていた。
邸宅に足を踏み入れるとき、シルヴィーは震えていた。
オランピアはジュスタンが資金を出しているいくつもの文化施設のひとつで、シルヴィーを恭しく迎え入れた。テアトル・サンジャックより歴史は浅いが、ずっと大きく、造りもりっぱで、舞台の質の高さはパリで5本の指に入るといわれた。そこでシルヴィーは、ひと足先に移っていたポーリーヌと合流した。彼女はジュスタンに、ポーリーヌのことを頼みこんでおいたのだった。
「あの子、しばらくは舞台に立てる状態じゃないと思うから、どうぞ少し助けてあげて。今のままでは生活していけないわ。もし彼女にまたステージに立つ気もちが戻ったなら、どうかいい劇場を手配してあげてね」
ポーリーヌは幸いなことにすでに元気になって、舞台を踏み始めていた。オランピアの広さや新しさが気に入って、とても喜んでいるようだった。今のところ、仲間うちでいやな目に遭うようなこともないようだ。
当然ながら彼女もシルヴィーの受けた仕打ち(あれが事故だったなんて誰が信じよう?)のことで心を痛めていたから、はじめて彼女がオランピアに姿を見せたときにはうれしさのあまり涙を流した。
これまで培ったテクニックに、さらに磨きをかける舞台の訓練。シルヴィーはそれまでにもまして真剣に取り組んだ。
ジュスタンがチャンスをくれたのだ、と彼女は考えた。あの事故で、自分は死んだも同然だったのに。ほかに若くて健康な女などいくらでもいるのに。ジュスタンはそれでも自分を捨てなかったのだ。これは普通のことではない。何としてもこの世界でトップに立って、彼に報いなくては。
シルヴィーの練習ぶりはすさまじかった。みんなが帰ったあとまでひとりで暗い舞台に立って、憑かれたように踊りつづけた。
彼女が舞台に集中できたのは、これまでのような生活の心配から解放されたことも大きかった。
生まれ変わったように、がらりと違う暮らし。今やシルヴィーは地面に足をつけることもなく、自分の馬車でどこでも好きなところへ行き来できるのだ。華の都とは名ばかりで、当時のパリは舗装も不十分、下水設備も整っているとはいえず、そういう状況から解放されたのはほんとうにうれしかった。
広々とした邸宅の中は、使用人がいつでもきれいに整えておいてくれた。彼女がいちばんかわいがっていたのは、最年少で、16になったばかりのヴィヴィエンヌだった。毎朝、目が覚めるころに朝食を銀のお盆に乗せて寝室へ運ばせ、ネグリジェ姿でくつろぎながらおしゃべりにつきあわせたり、鏡に向かってくしけずらせたりした。日に日に多忙を極めるなかにあって貴重な、ゆっくりと息をつける時間だった。
成功者の常として、ジュスタンも各分野ごとに何人もの弁護士を抱えていた。そのうちもっとも信頼していたクロードを、彼はシルヴィーの財産管理の担当にあてた。血色のいいばら色の頬、つやつやした禿げ頭、恰幅のいい背恰好はまるでハンプティ・ダンプティのようだった。ほどなく、行政上の手続きから日常のこまごまとした事柄に至るまで、彼はシルヴィーの心強い相談相手となった。
それとともに、ジュスタンはあちこちの集まりに顔を出すのに、しばしば彼女を伴うようになった。彼はシルヴィーを、パリの社交界に徹底的に売り込む決意をしていた。
当時の女たちの間で、舞台出身者の地位は低かった。大衆の見世物になっているような女は売春婦と変わらない。それが上流社会の一般的な感覚で、実情からそうかけ離れているとも言いがたかった。女優や踊り子で社交界入りした者は、その出自を隠し、ことさら保守的な装いに身を固めることが多かった。シルヴィーもさいしょはさる亡命貴族の娘ということになっていた。
まばゆい光、錚々たる面々(なのだろう、誰が誰だか分からないけれど)…シャンパングラス、夜会服、贅を尽くした調度… はじめは気後れするばかりだった。けれどジュスタンにエスコートされ、人々に紹介されつづけるうち、やがてそうした場にもなじみ、だんだんと振舞いも堂に入ってきた。
ジュスタンはソワレのたびに仕立屋に新しいドレスをつくらせたので、シルヴィーのクロゼットはすぐに美しいドレスでいっぱいになった。前の小さなアパルトマンでは、とっくに溢れ出ていただろう。扉を開けるたび、彼女はうっとりとして淡い色あいの上質な生地や、レースやチュール、ビーズ細工などの繊細な手仕事に眺め入った。ほんの少し前まで、彼女はこうしたドレスを客のために仕立てる側だった。貧しい自分がまとうことなど、想像したこともなかった。
***
ギヨノー商会の内情についても、少しずつシルヴィーは知るようになった。つましい貿易会社としてはじまった商会はジュスタンの才覚によって頭角を現し、競合相手の買収を繰り返していまや巨大企業に成長していた。ジュスタン以下、目下のツートップはテオドールとダミアン。テオドールはジュスタンがまだ無名だったころからの弟分で、彼がその窮地を救ってやったことのある男だった。義理堅く、忠義に厚く、ジュスタンのためなら死地へでも赴いただろう。だが、生き馬の目を抜く実業界にあっては少しばかり人がよすぎるきらいがあった。
一方のダミアンは諸刃の剣だった。切れ者で、何事も手早く効率がよく、ものごとの采配を振るうのに長けていた。買収案件の多くは彼の手掛けたものだった。しかし同時に大変な野心家で、策略家でもあり、気を抜けなかった。
ジュスタンの妻ロズリーンとの結婚は15年ほど前のことだ。当時の彼にとって、それはゲームを進めるのにもっとも有利な駒だった。おもな理由の一つは、彼女が王族に近い格式高い貴族の出であったためで(こちらはほんとうに)、それは身分のない彼が上流社会に入り込むための通行手形だった。もうひとつ大きな理由は彼女の叔父のイジスが金融庁の次官であったことだ。この結婚によって彼とのつながりが生まれたことで、ギヨノー商会の大きなプロジェクトがいくつも進展を遂げたのだった。だが、引き換えに飲まざるを得なかった条件もある。そのひとつがイジスの愛人の子で、つまりロズリーンの従兄弟にあたるダミアンを商会の、しかも上級管理職に迎えることだったのだ。
そんなわけで、ダミアンの手腕を高く買いながらも、ジュスタンは彼の手にあまり権力が集中しないよう、商会内の人事を注意深く調整していた。いまのところはうまくいって、組織は彼とテオドールのふたりを軸として順調にまわっていた。
実業界のあれこれ、政界との絡み、スペクタクルの世界とのつながり…。前と同じ暮らしをしていたら、一生知らずに終わった世界だった。それはまた、テアトル・サンジャックの小さな輪の中とは桁違いに、大きな金が動き、複雑に絡んだ思惑や欲望の渦巻く、魑魅魍魎の世界だ。ここに身を置くなら、うまく渡ってゆくすべを知らないといけない。足をとられたがさいご、二度と這い上がれないかもしれない。
だが、目下のところ、ジュスタンの快進撃は向かうところ敵なしといったところだ。君は幸運の女神だ、と彼は言い言いした。シルヴィーと出会ってからこのかた、さまざまな取引がことのほかうまくいくようになったのだと。ふたりはゴージャスなカップルとして人目を惹いた。
オランピア劇場での、シルヴィーの初舞台は<ライモンダ>。主役ではなかったが、彼女の演技は大きな評判を呼んだ。事故などものともせずみごとな復活を遂げて、今や一流と呼ばれるにふさわしい踊り手となったのは明白だった。
7か月ののち、<オデュッセイア>のセイレーン役でシルヴィーは初主演を果たした。二番手となったイヴェットのほうが技量は上だという声も根強かった。それはほんとうだったかもしれない。だがこの世界では、誰を情人に持っているかも実力のうちだった。劇場のパトロンが、機は熟したと判断したのだ。逆らえるものはいなかった。
その賭けは正しかったことを、シルヴィーの舞台は証明した。ひとつ突き抜けたように、自由で力強く、流麗な動き。自ら考案した斬新なデザインの衣装も相まって、見るものに、逆巻く渦潮の動きそのものを見ているような錯覚を起こさせた。何か今までにない、新しいものを見ているという感覚を与えたのだ。舞台は大成功となった。新聞が注目し始め、舞台の世界の外にも、シルヴィーの名は少しずつ知られるようになった。
このころから、シルヴィーはあらゆる面で彼女独自の色を打ち出し始めた。演技のスタイルや舞台衣裳ばかりではない。ソワレのたびにつくらせるドレスも、流行を追うばかりでは飽き足らなくなり、お針子時代の知識や技術を生かしてあれこれと口を挟むようになった。
次々と、人目を驚かすようなデザインのドレスが登場した。<オデュッセイア>の上演中は宣伝も兼ね、ギリシャ風の流れるようなラインのドレスをまとい、髪も古代ギリシャの乙女のように結い上げた。あるいは神話の女神たちを描いたボッティチェリの絵のような、半透明の風そのものをふわりとまとうようなドレス。バレエの舞台をそのまま夜会の席に持ち込んだような、軽やかなチュチュ風のもの。大輪のばらをそのままドレスに仕立てたようなもの…。
彼女はもう、踊り手であることを隠さなかった。河原乞食が、と叩かれもした。だが、彼女の装いは目あたらしくて自由なだけでなく、優雅で、その顔立ちや蜂蜜色の髪、やや華奢な体のラインによく似合っていた。それらはセンセーションを巻き起こし、このころのお決まりだったコルセットで締めつけるような大仰なスタイルのドレスを、一気に堅苦しく古臭いものに変えてしまった。社交界のなかにも、彼女のスタイルを真似るものが現れはじめた。
***
オランピア劇場で二番手に甘んじていたイヴェットは、やがてトップの座をその手に取り戻すことになる。国家事業として完成したばかりのオペラ・ガルニエに、シルヴィーがプリマドンナとして迎えられることになったのだ。オペラ・ガルニエはナポレオンⅢ世の即位を記念してつくられ、彼に献じられたもので、皇帝と皇妃のための専用の玉座が観客席の最上部に設けられていた。
その除幕式を兼ねた<エスメラルダ>の初演にあたり、シルヴィーは皇帝に謁見の機会を得た。並み居る政府高官やもろもろの権力者たちのなか、銀白のドレスに身を包んだ彼女は玉座の前に進み出、恭しく身をかがめ、みじかい祝辞を読み上げた。
体が震えていなかったとは言えない。だが、彼女を支えていたのは一見奇妙にも思えるひそかな思いだった。彼女独特の、皇帝へのある種の親近感ー彼だって結局のところ、成り上がり者なのだ。王族の血筋などではないもとは市井の人間、自分と同じだ。そしてそれは恥ずべきことなどではない。この街では、身を危険に賭し、決然と突き進む者だけが頂点を手にするのだ。いつだって、<パリよ、俺とお前だ!>なのだ…。
そのころ、ジュスタンの実業家としてのキャリアも新しい、大きな局面を迎えていた。彼には、相当前からひそかに準備を進め、着々と布石を打ってきた壮大な計画があった。それは今まで誰にもなし得なかった、いや、考えもしなかったであろう企てーあの国営企業を傘下に引き入れるという企てだった。いまのジュスタンには、それだけの目算と財力があった。あとは、いかにうまくやるかだけだった。
すでに最大の取引先である鉄鋼業のヴァンデル一族とは深い結びつきがあり、口出ししてきそうな業界トップや経済省の官僚たちともコネをつなげてきたので、ここがさいごの山場といってよかった。
その日、新聞はこぞって一面トップで事の次第を報じ、フランスじゅうに衝撃を与えた。あくまで平和的な合併、と表向きは発表された。相手への全面的な譲歩を示すため、彼はギヨノー商会の名を捨てることさえした。しかし実のところ、それは買収に他ならなかった。実権はジュスタンにあった。
念願の買収を果たしたことで、市場は事実上、ジュスタンの独占状態となった。今や彼は栄光の頂点に立っていた。
リハビリの辛さは、言葉にできないくらいだった。肉体的にもそうだが、いちばん辛いのは、先が見えないこと。いったいいつになったら自由な動きを取り戻せるのか、そもそもそんな日が来るのか、誰にも分からなかった。
それでもシルヴィーは歯を食いしばって続け、やり遂げた。何か月もかかってやっとギプスが取れ、どうにかこうにか、杖なしで歩けるようになった。だが、それではまだ、ようやくふりだしに戻っただけだ。踊り手として果たしてまたものになるのか、それはまだ未知数だった。
ジュスタンがコーチをつけてくれて、シルヴィーは再びバレエの練習を始めた。踊り子は、一日でも休むと感覚が鈍る。この繊細な感覚を保ち、体のコンディションを一定にキープするためには、毎日の練習が欠かせない。これが何か月ものブランクとなると、ほとんど一からやり直すに等しかった。そのうえこの傷を負った体だ。
「奇蹟を起こしてみせる」とシルヴィーは自分に言い聞かせた。「ぜったいに舞台へ戻るのだ。こんなことに邪魔されてたまるか」
彼女の強い決意もあっただろう。まだ若かったためもあるだろう。ともかく、練習は成果を上げ、彼女はまた以前のように、軽々と宙を舞うようなステップを踏むことができるようになった。それはまったく奇蹟といってよかった。
こうして調子が戻ったころ、シルヴィーは右岸の一等地にかまえるオランピア劇場に所属が決まった。時を同じくしてジュスタンは彼女のためにその近くに住まいを用意し、それまで住んでいた小さなアパルトマンから、人をやって必要なものを取ってこさせた。邸宅には使用人をつけ、そこから新しい劇場へ通うための専用の馬車と御者もつけてやった。
シルヴィーにとっては予想外の展開だった。
リハビリはあまりにも長かった。そのあいだ、ジュスタンはろくに見舞いにも来なかった。彼はもう自分には興味を失ったのだろう。自分はきのうジュスタンの愛人になったばかりだ。明日には捨てられる。ただ踊り子としてどこかの劇場で舞台に戻れればそれでいい。そう思っていた。
邸宅に足を踏み入れるとき、シルヴィーは震えていた。
オランピアはジュスタンが資金を出しているいくつもの文化施設のひとつで、シルヴィーを恭しく迎え入れた。テアトル・サンジャックより歴史は浅いが、ずっと大きく、造りもりっぱで、舞台の質の高さはパリで5本の指に入るといわれた。そこでシルヴィーは、ひと足先に移っていたポーリーヌと合流した。彼女はジュスタンに、ポーリーヌのことを頼みこんでおいたのだった。
「あの子、しばらくは舞台に立てる状態じゃないと思うから、どうぞ少し助けてあげて。今のままでは生活していけないわ。もし彼女にまたステージに立つ気もちが戻ったなら、どうかいい劇場を手配してあげてね」
ポーリーヌは幸いなことにすでに元気になって、舞台を踏み始めていた。オランピアの広さや新しさが気に入って、とても喜んでいるようだった。今のところ、仲間うちでいやな目に遭うようなこともないようだ。
当然ながら彼女もシルヴィーの受けた仕打ち(あれが事故だったなんて誰が信じよう?)のことで心を痛めていたから、はじめて彼女がオランピアに姿を見せたときにはうれしさのあまり涙を流した。
これまで培ったテクニックに、さらに磨きをかける舞台の訓練。シルヴィーはそれまでにもまして真剣に取り組んだ。
ジュスタンがチャンスをくれたのだ、と彼女は考えた。あの事故で、自分は死んだも同然だったのに。ほかに若くて健康な女などいくらでもいるのに。ジュスタンはそれでも自分を捨てなかったのだ。これは普通のことではない。何としてもこの世界でトップに立って、彼に報いなくては。
シルヴィーの練習ぶりはすさまじかった。みんなが帰ったあとまでひとりで暗い舞台に立って、憑かれたように踊りつづけた。
彼女が舞台に集中できたのは、これまでのような生活の心配から解放されたことも大きかった。
生まれ変わったように、がらりと違う暮らし。今やシルヴィーは地面に足をつけることもなく、自分の馬車でどこでも好きなところへ行き来できるのだ。華の都とは名ばかりで、当時のパリは舗装も不十分、下水設備も整っているとはいえず、そういう状況から解放されたのはほんとうにうれしかった。
広々とした邸宅の中は、使用人がいつでもきれいに整えておいてくれた。彼女がいちばんかわいがっていたのは、最年少で、16になったばかりのヴィヴィエンヌだった。毎朝、目が覚めるころに朝食を銀のお盆に乗せて寝室へ運ばせ、ネグリジェ姿でくつろぎながらおしゃべりにつきあわせたり、鏡に向かってくしけずらせたりした。日に日に多忙を極めるなかにあって貴重な、ゆっくりと息をつける時間だった。
成功者の常として、ジュスタンも各分野ごとに何人もの弁護士を抱えていた。そのうちもっとも信頼していたクロードを、彼はシルヴィーの財産管理の担当にあてた。血色のいいばら色の頬、つやつやした禿げ頭、恰幅のいい背恰好はまるでハンプティ・ダンプティのようだった。ほどなく、行政上の手続きから日常のこまごまとした事柄に至るまで、彼はシルヴィーの心強い相談相手となった。
それとともに、ジュスタンはあちこちの集まりに顔を出すのに、しばしば彼女を伴うようになった。彼はシルヴィーを、パリの社交界に徹底的に売り込む決意をしていた。
当時の女たちの間で、舞台出身者の地位は低かった。大衆の見世物になっているような女は売春婦と変わらない。それが上流社会の一般的な感覚で、実情からそうかけ離れているとも言いがたかった。女優や踊り子で社交界入りした者は、その出自を隠し、ことさら保守的な装いに身を固めることが多かった。シルヴィーもさいしょはさる亡命貴族の娘ということになっていた。
まばゆい光、錚々たる面々(なのだろう、誰が誰だか分からないけれど)…シャンパングラス、夜会服、贅を尽くした調度… はじめは気後れするばかりだった。けれどジュスタンにエスコートされ、人々に紹介されつづけるうち、やがてそうした場にもなじみ、だんだんと振舞いも堂に入ってきた。
ジュスタンはソワレのたびに仕立屋に新しいドレスをつくらせたので、シルヴィーのクロゼットはすぐに美しいドレスでいっぱいになった。前の小さなアパルトマンでは、とっくに溢れ出ていただろう。扉を開けるたび、彼女はうっとりとして淡い色あいの上質な生地や、レースやチュール、ビーズ細工などの繊細な手仕事に眺め入った。ほんの少し前まで、彼女はこうしたドレスを客のために仕立てる側だった。貧しい自分がまとうことなど、想像したこともなかった。
***
ギヨノー商会の内情についても、少しずつシルヴィーは知るようになった。つましい貿易会社としてはじまった商会はジュスタンの才覚によって頭角を現し、競合相手の買収を繰り返していまや巨大企業に成長していた。ジュスタン以下、目下のツートップはテオドールとダミアン。テオドールはジュスタンがまだ無名だったころからの弟分で、彼がその窮地を救ってやったことのある男だった。義理堅く、忠義に厚く、ジュスタンのためなら死地へでも赴いただろう。だが、生き馬の目を抜く実業界にあっては少しばかり人がよすぎるきらいがあった。
一方のダミアンは諸刃の剣だった。切れ者で、何事も手早く効率がよく、ものごとの采配を振るうのに長けていた。買収案件の多くは彼の手掛けたものだった。しかし同時に大変な野心家で、策略家でもあり、気を抜けなかった。
ジュスタンの妻ロズリーンとの結婚は15年ほど前のことだ。当時の彼にとって、それはゲームを進めるのにもっとも有利な駒だった。おもな理由の一つは、彼女が王族に近い格式高い貴族の出であったためで(こちらはほんとうに)、それは身分のない彼が上流社会に入り込むための通行手形だった。もうひとつ大きな理由は彼女の叔父のイジスが金融庁の次官であったことだ。この結婚によって彼とのつながりが生まれたことで、ギヨノー商会の大きなプロジェクトがいくつも進展を遂げたのだった。だが、引き換えに飲まざるを得なかった条件もある。そのひとつがイジスの愛人の子で、つまりロズリーンの従兄弟にあたるダミアンを商会の、しかも上級管理職に迎えることだったのだ。
そんなわけで、ダミアンの手腕を高く買いながらも、ジュスタンは彼の手にあまり権力が集中しないよう、商会内の人事を注意深く調整していた。いまのところはうまくいって、組織は彼とテオドールのふたりを軸として順調にまわっていた。
実業界のあれこれ、政界との絡み、スペクタクルの世界とのつながり…。前と同じ暮らしをしていたら、一生知らずに終わった世界だった。それはまた、テアトル・サンジャックの小さな輪の中とは桁違いに、大きな金が動き、複雑に絡んだ思惑や欲望の渦巻く、魑魅魍魎の世界だ。ここに身を置くなら、うまく渡ってゆくすべを知らないといけない。足をとられたがさいご、二度と這い上がれないかもしれない。
だが、目下のところ、ジュスタンの快進撃は向かうところ敵なしといったところだ。君は幸運の女神だ、と彼は言い言いした。シルヴィーと出会ってからこのかた、さまざまな取引がことのほかうまくいくようになったのだと。ふたりはゴージャスなカップルとして人目を惹いた。
オランピア劇場での、シルヴィーの初舞台は<ライモンダ>。主役ではなかったが、彼女の演技は大きな評判を呼んだ。事故などものともせずみごとな復活を遂げて、今や一流と呼ばれるにふさわしい踊り手となったのは明白だった。
7か月ののち、<オデュッセイア>のセイレーン役でシルヴィーは初主演を果たした。二番手となったイヴェットのほうが技量は上だという声も根強かった。それはほんとうだったかもしれない。だがこの世界では、誰を情人に持っているかも実力のうちだった。劇場のパトロンが、機は熟したと判断したのだ。逆らえるものはいなかった。
その賭けは正しかったことを、シルヴィーの舞台は証明した。ひとつ突き抜けたように、自由で力強く、流麗な動き。自ら考案した斬新なデザインの衣装も相まって、見るものに、逆巻く渦潮の動きそのものを見ているような錯覚を起こさせた。何か今までにない、新しいものを見ているという感覚を与えたのだ。舞台は大成功となった。新聞が注目し始め、舞台の世界の外にも、シルヴィーの名は少しずつ知られるようになった。
このころから、シルヴィーはあらゆる面で彼女独自の色を打ち出し始めた。演技のスタイルや舞台衣裳ばかりではない。ソワレのたびにつくらせるドレスも、流行を追うばかりでは飽き足らなくなり、お針子時代の知識や技術を生かしてあれこれと口を挟むようになった。
次々と、人目を驚かすようなデザインのドレスが登場した。<オデュッセイア>の上演中は宣伝も兼ね、ギリシャ風の流れるようなラインのドレスをまとい、髪も古代ギリシャの乙女のように結い上げた。あるいは神話の女神たちを描いたボッティチェリの絵のような、半透明の風そのものをふわりとまとうようなドレス。バレエの舞台をそのまま夜会の席に持ち込んだような、軽やかなチュチュ風のもの。大輪のばらをそのままドレスに仕立てたようなもの…。
彼女はもう、踊り手であることを隠さなかった。河原乞食が、と叩かれもした。だが、彼女の装いは目あたらしくて自由なだけでなく、優雅で、その顔立ちや蜂蜜色の髪、やや華奢な体のラインによく似合っていた。それらはセンセーションを巻き起こし、このころのお決まりだったコルセットで締めつけるような大仰なスタイルのドレスを、一気に堅苦しく古臭いものに変えてしまった。社交界のなかにも、彼女のスタイルを真似るものが現れはじめた。
***
オランピア劇場で二番手に甘んじていたイヴェットは、やがてトップの座をその手に取り戻すことになる。国家事業として完成したばかりのオペラ・ガルニエに、シルヴィーがプリマドンナとして迎えられることになったのだ。オペラ・ガルニエはナポレオンⅢ世の即位を記念してつくられ、彼に献じられたもので、皇帝と皇妃のための専用の玉座が観客席の最上部に設けられていた。
その除幕式を兼ねた<エスメラルダ>の初演にあたり、シルヴィーは皇帝に謁見の機会を得た。並み居る政府高官やもろもろの権力者たちのなか、銀白のドレスに身を包んだ彼女は玉座の前に進み出、恭しく身をかがめ、みじかい祝辞を読み上げた。
体が震えていなかったとは言えない。だが、彼女を支えていたのは一見奇妙にも思えるひそかな思いだった。彼女独特の、皇帝へのある種の親近感ー彼だって結局のところ、成り上がり者なのだ。王族の血筋などではないもとは市井の人間、自分と同じだ。そしてそれは恥ずべきことなどではない。この街では、身を危険に賭し、決然と突き進む者だけが頂点を手にするのだ。いつだって、<パリよ、俺とお前だ!>なのだ…。
そのころ、ジュスタンの実業家としてのキャリアも新しい、大きな局面を迎えていた。彼には、相当前からひそかに準備を進め、着々と布石を打ってきた壮大な計画があった。それは今まで誰にもなし得なかった、いや、考えもしなかったであろう企てーあの国営企業を傘下に引き入れるという企てだった。いまのジュスタンには、それだけの目算と財力があった。あとは、いかにうまくやるかだけだった。
すでに最大の取引先である鉄鋼業のヴァンデル一族とは深い結びつきがあり、口出ししてきそうな業界トップや経済省の官僚たちともコネをつなげてきたので、ここがさいごの山場といってよかった。
その日、新聞はこぞって一面トップで事の次第を報じ、フランスじゅうに衝撃を与えた。あくまで平和的な合併、と表向きは発表された。相手への全面的な譲歩を示すため、彼はギヨノー商会の名を捨てることさえした。しかし実のところ、それは買収に他ならなかった。実権はジュスタンにあった。
念願の買収を果たしたことで、市場は事実上、ジュスタンの独占状態となった。今や彼は栄光の頂点に立っていた。
2020年03月20日
小説・アレクサンドルⅢ世橋 4. 頂点
小説・アレクサンドルⅢ世橋 4. 頂点
だれでも15分のあいだは有名になれる…いみじくもそう言ったのは誰だっただろう?
オペラ・ガルニエでのナポレオンⅢ世への謁見、それにつづく<エスメラルダ>の成功で、シルヴィーの名は突如、パリじゅうに知られることになった。巻き起こるすさまじい熱狂…舞台の彼女のギリシャ風のスタイルや髪型をみんなが真似し、彼女のブロマイドがパリ土産のあたらしい定番となる。いまやみんながシルヴィーに夢中だ… 老舗の靴ブランドが彼女の名を冠したダンス靴を売り出して爆発的な人気を博し、次いでジュエリー・ショップや婦人服店がこぞって彼女をミューズに起用した。いまや彼女をめぐって大きな富が動いていた。名実ともに女王だった…
名が知れるほど、敵もまた多い。シルヴィーをけなす者も、擁護する者も、非難する者も、憧れる者も…ともかく誰もがシルヴィーのことを話していた。新聞や雑誌は彼女を追いかけまわした。向けられる質問には、ジュスタンへの明らかなあてこすりも多かった。たとえば、<レピュブリカン>紙の記者がした、「ご自分はとても運がいいとお考えでしょうね?」というような。
「運がいいですって?」シルヴィーはきっとなって相手を見返した。「たしかにそれもあるでしょうね。でも自分が努力したからでもあるわ」
「多くの人が努力しているのに成功しないようですが」
「そうでしょうね。でも私は、人より十倍も、百倍も努力してきた。ひどい目にも遭ってきたし、犠牲も払ってきた。私はそれだけの値打ちのある人間だと思っているわ」
「私はそれに値する」-この言葉は大きな論争を巻き起こし、結果としてシルヴィーをさらに有名にしたのだった。
かつては夢想だにしなかった名声にも、今ではすっかり慣れてしまった。まるで生まれてこのかた、地面に足をつけたことがないよう。その肝の据わった振る舞いっぷりにはジュスタンも感嘆するばかりだった。
「大したもんだ、私には真似ができないな。金のかかった服に身を包み、馬車を乗りまわしてはいても、私の中身はいまだに粗野な田舎者だ。いまの暮らしには、どこか違和感がある。ずっと目指して登りつめてきたというのに、皮肉だな」
「あら、私だってそうだわ」とシルヴィーは言うのだった。「心の奥底ではね。そうでなければ、こんな虚飾の世界に耐えられないでしょうね。きっと、舞台の上で今までいくつもの人生を演じてきたから、どんな役柄を演じることにも慣れたのでしょうね」
シルヴィーの中には舞台を夢見た幼い少女が今もいて、ガラス越しに煌びやかな別世界にあこがれるように、手をつき、目を見開いて、今や自分を取り巻く夢のような世界をあっけに取られて眺めていた。いつかは夢から醒めて冷たい現実に引き戻されることを、この少女は心のどこかで知っていたのかもしれない。
ジュスタンはシルヴィーの邸宅に泊まっても、必ず朝早くに出て行った。夜明けの青い窓辺、ジュスタンが出て行ったあとのひとときほど、ぽっかりと大きな虚無を抱えこむことはなかった。彼の存在を強く感じることはなかった。正しく言えば、彼の不在を。…のちのち彼のことを考えると、決まって思い出されるのは夜明けのたびに窓辺を染めた、その独特な深いブルーの色だった。それを彼に向かっては、決して言いはしなかったけれども。…
人目を惹くエキゾティックな装いのシルヴィーと、銀色にうねる髪をていねいになでつけ、猛禽を思わせる鋭いまなざしのジュスタン、この二人の組み合わせは同時代のアイコンとなった。
シルヴィーはその強靭な肉体を愛した。ギリシャの遺跡から掘り出されたマッシヴな彫像のような、日に焼けた強靭な肉体を。それは頑固で容易に屈しない、彼の精神そのもののようだった。それはまた、シルヴィーの精神でもあった。見た目はまるで違っても、彼らふたりは双子のようだった。己の意志するところを成し遂げんとする固い決意、固い絆で結ばれていた。恋人同士というよりも戦友のようだった。いつしか人々は二人をセットとして見るようになり、切り離しては考えられなくなった。神話の中のカップルのように、同じ波長のもとにある人たちのように、線や顔立ちもどことなく似てきたようだった。
シルヴィーの名声はとどまるところを知らなかった。ぜいたくな暮らしぶりからマリー・アントワネットと揶揄されても、やっかみと受け流して気にしなかった。舞台での斬新なスタイルから、古典的なやり方が身についていないと批判されもした。貧しい出自を隠さなかったことで成り上がりと陰口も叩かれたが、庶民層にはかえって人気になった。
いつも山のような仕事と、山のような使用人を抱え、劇場と華やかなパーティの場を忙しく行き来していた。ジュスタンの関係者たちに顔をつなぐため、パリでもっとも贅沢な晩餐の席には必ず姿を現した。あちこちのソワレやイベントに出るのが仕事のようになった。その一方で、厳しい稽古も欠かさない… 敵たちの口を封じるためにも、技量はつねに最高を保っていなくてはならなかった。
<エスメラルダ>の次のオペラ・ガルニエでの演目は<椿姫>だった。これは物議を醸した… ヒロインの役柄が役柄だったからだ。彼女がジュスタンの情人であることを快く思わないものたちから、ここぞとばかり、轟々の非難が巻き起こった。シルヴィーは気にも留めなかったが、以前にもまして、行く先々で記者たちからしつこく追い回されることになった。
「私を怒らすためだけに、わざわざパリ随一の劇場で<椿姫>の企画を?」
ことさら意地悪な問いを向けてきた記者のひとりに、こう言ってやりこめたことがある。
「まあまあ、なんて光栄なことなんでしょう! 私も出世したものね!」…
ジュスタンと二人で馬車に乗りこんだところへ<ル・フィガロ>の記者に割って入られたこともある。
「ムッシュー、奥方については、どのようにお考えですか? 愛する旦那様に裏切られて、悲痛な思いをされているのでは?…」
「そうでもないと思うよ」 ジュスタンは鷹揚に答えた…そのわざとらしい、扇情的な調子にむっとしながらも。
「彼女のほうも、私にはいささかうんざりしているようなのでね。彼女の情人たちに、私からよろしくと伝えてくれ」
「私からもね」
と、横からシルヴィーがつけ加えた。
このひと幕はゴシップ欄で尾ひれつきで大々的に報じられ、彼らふたりをますます有名にしたのだった。
喝采と非難と喧騒と… 熱狂の渦に巻き込まれ、時は夢のように過ぎた… こんな栄光を夢見ていたころ、ここまでのめまぐるしさを想像だにしたことがあっただろうか?… 立ち止まって考えているひまなどない、腹を括って流れに身を任せるよりほかなかった…
ふたたび冬が巡ってきた。長い灰色の日々、陰鬱なのは同じだが、もう空を見上げているひまもない、いまやまばゆいシャンデリアの光りと劇場の照明が、シルヴィーの毎日をあますところなく彩っている…
ノエルが近づくと<火の鳥>の稽古が始まった。真っ赤な衣裳に炎の羽を飾ったシルヴィーはこれまで以上に観客席を魅了した… イヴの晩には再びナポレオンⅢ世夫妻の臨席のもと、華々しく幕を閉じた。
ノエルの束の間の平和なひととき、彼女はジュスタンの暮らすホテルで過ごした。大窓からガス燈の光にかがやくにぎやかなブルヴァールを見下ろしながら、はじめてこの部屋に招かれた晩のことが数世紀前のことのように、はるかに思い出された。…
ディナーのあと、ジュスタンは彼女にプレゼントを贈った。鉱山関連の人脈を駆使して世界中探したと思われる、大粒のダイヤモンドの輝く指輪だ。…シルヴィーも彼に贈るプレゼントがあった。スイスの最高の職人に特別に注文してつくらせた金時計だった。…
だが、どんな贅沢も、ふだんよりほんの少し長く互いの腕の中で過ごせる歓びには替えられない。夜明けの青い窓辺でジュスタンの鋼のような熱い肢体に身を沿わせ、夢うつつにまどろむひととき、ふとベッドごとゆっくりと回転しながら上昇してゆくような、くらくらするような感覚が訪れてくる…ふと、すべてが夢なのではないかという、深淵を覗きこむような怖ろしい感覚、絶頂に立ちながら、これ以上の上がなくなったことの不安とよんどころのなさの入り混じった、ぞっとするような微かな感覚が。… 飽和状態の幸福、それはほとんど死に近かった。…
だれでも15分のあいだは有名になれる…いみじくもそう言ったのは誰だっただろう?
オペラ・ガルニエでのナポレオンⅢ世への謁見、それにつづく<エスメラルダ>の成功で、シルヴィーの名は突如、パリじゅうに知られることになった。巻き起こるすさまじい熱狂…舞台の彼女のギリシャ風のスタイルや髪型をみんなが真似し、彼女のブロマイドがパリ土産のあたらしい定番となる。いまやみんながシルヴィーに夢中だ… 老舗の靴ブランドが彼女の名を冠したダンス靴を売り出して爆発的な人気を博し、次いでジュエリー・ショップや婦人服店がこぞって彼女をミューズに起用した。いまや彼女をめぐって大きな富が動いていた。名実ともに女王だった…
名が知れるほど、敵もまた多い。シルヴィーをけなす者も、擁護する者も、非難する者も、憧れる者も…ともかく誰もがシルヴィーのことを話していた。新聞や雑誌は彼女を追いかけまわした。向けられる質問には、ジュスタンへの明らかなあてこすりも多かった。たとえば、<レピュブリカン>紙の記者がした、「ご自分はとても運がいいとお考えでしょうね?」というような。
「運がいいですって?」シルヴィーはきっとなって相手を見返した。「たしかにそれもあるでしょうね。でも自分が努力したからでもあるわ」
「多くの人が努力しているのに成功しないようですが」
「そうでしょうね。でも私は、人より十倍も、百倍も努力してきた。ひどい目にも遭ってきたし、犠牲も払ってきた。私はそれだけの値打ちのある人間だと思っているわ」
「私はそれに値する」-この言葉は大きな論争を巻き起こし、結果としてシルヴィーをさらに有名にしたのだった。
かつては夢想だにしなかった名声にも、今ではすっかり慣れてしまった。まるで生まれてこのかた、地面に足をつけたことがないよう。その肝の据わった振る舞いっぷりにはジュスタンも感嘆するばかりだった。
「大したもんだ、私には真似ができないな。金のかかった服に身を包み、馬車を乗りまわしてはいても、私の中身はいまだに粗野な田舎者だ。いまの暮らしには、どこか違和感がある。ずっと目指して登りつめてきたというのに、皮肉だな」
「あら、私だってそうだわ」とシルヴィーは言うのだった。「心の奥底ではね。そうでなければ、こんな虚飾の世界に耐えられないでしょうね。きっと、舞台の上で今までいくつもの人生を演じてきたから、どんな役柄を演じることにも慣れたのでしょうね」
シルヴィーの中には舞台を夢見た幼い少女が今もいて、ガラス越しに煌びやかな別世界にあこがれるように、手をつき、目を見開いて、今や自分を取り巻く夢のような世界をあっけに取られて眺めていた。いつかは夢から醒めて冷たい現実に引き戻されることを、この少女は心のどこかで知っていたのかもしれない。
ジュスタンはシルヴィーの邸宅に泊まっても、必ず朝早くに出て行った。夜明けの青い窓辺、ジュスタンが出て行ったあとのひとときほど、ぽっかりと大きな虚無を抱えこむことはなかった。彼の存在を強く感じることはなかった。正しく言えば、彼の不在を。…のちのち彼のことを考えると、決まって思い出されるのは夜明けのたびに窓辺を染めた、その独特な深いブルーの色だった。それを彼に向かっては、決して言いはしなかったけれども。…
人目を惹くエキゾティックな装いのシルヴィーと、銀色にうねる髪をていねいになでつけ、猛禽を思わせる鋭いまなざしのジュスタン、この二人の組み合わせは同時代のアイコンとなった。
シルヴィーはその強靭な肉体を愛した。ギリシャの遺跡から掘り出されたマッシヴな彫像のような、日に焼けた強靭な肉体を。それは頑固で容易に屈しない、彼の精神そのもののようだった。それはまた、シルヴィーの精神でもあった。見た目はまるで違っても、彼らふたりは双子のようだった。己の意志するところを成し遂げんとする固い決意、固い絆で結ばれていた。恋人同士というよりも戦友のようだった。いつしか人々は二人をセットとして見るようになり、切り離しては考えられなくなった。神話の中のカップルのように、同じ波長のもとにある人たちのように、線や顔立ちもどことなく似てきたようだった。
シルヴィーの名声はとどまるところを知らなかった。ぜいたくな暮らしぶりからマリー・アントワネットと揶揄されても、やっかみと受け流して気にしなかった。舞台での斬新なスタイルから、古典的なやり方が身についていないと批判されもした。貧しい出自を隠さなかったことで成り上がりと陰口も叩かれたが、庶民層にはかえって人気になった。
いつも山のような仕事と、山のような使用人を抱え、劇場と華やかなパーティの場を忙しく行き来していた。ジュスタンの関係者たちに顔をつなぐため、パリでもっとも贅沢な晩餐の席には必ず姿を現した。あちこちのソワレやイベントに出るのが仕事のようになった。その一方で、厳しい稽古も欠かさない… 敵たちの口を封じるためにも、技量はつねに最高を保っていなくてはならなかった。
<エスメラルダ>の次のオペラ・ガルニエでの演目は<椿姫>だった。これは物議を醸した… ヒロインの役柄が役柄だったからだ。彼女がジュスタンの情人であることを快く思わないものたちから、ここぞとばかり、轟々の非難が巻き起こった。シルヴィーは気にも留めなかったが、以前にもまして、行く先々で記者たちからしつこく追い回されることになった。
「私を怒らすためだけに、わざわざパリ随一の劇場で<椿姫>の企画を?」
ことさら意地悪な問いを向けてきた記者のひとりに、こう言ってやりこめたことがある。
「まあまあ、なんて光栄なことなんでしょう! 私も出世したものね!」…
ジュスタンと二人で馬車に乗りこんだところへ<ル・フィガロ>の記者に割って入られたこともある。
「ムッシュー、奥方については、どのようにお考えですか? 愛する旦那様に裏切られて、悲痛な思いをされているのでは?…」
「そうでもないと思うよ」 ジュスタンは鷹揚に答えた…そのわざとらしい、扇情的な調子にむっとしながらも。
「彼女のほうも、私にはいささかうんざりしているようなのでね。彼女の情人たちに、私からよろしくと伝えてくれ」
「私からもね」
と、横からシルヴィーがつけ加えた。
このひと幕はゴシップ欄で尾ひれつきで大々的に報じられ、彼らふたりをますます有名にしたのだった。
喝采と非難と喧騒と… 熱狂の渦に巻き込まれ、時は夢のように過ぎた… こんな栄光を夢見ていたころ、ここまでのめまぐるしさを想像だにしたことがあっただろうか?… 立ち止まって考えているひまなどない、腹を括って流れに身を任せるよりほかなかった…
ふたたび冬が巡ってきた。長い灰色の日々、陰鬱なのは同じだが、もう空を見上げているひまもない、いまやまばゆいシャンデリアの光りと劇場の照明が、シルヴィーの毎日をあますところなく彩っている…
ノエルが近づくと<火の鳥>の稽古が始まった。真っ赤な衣裳に炎の羽を飾ったシルヴィーはこれまで以上に観客席を魅了した… イヴの晩には再びナポレオンⅢ世夫妻の臨席のもと、華々しく幕を閉じた。
ノエルの束の間の平和なひととき、彼女はジュスタンの暮らすホテルで過ごした。大窓からガス燈の光にかがやくにぎやかなブルヴァールを見下ろしながら、はじめてこの部屋に招かれた晩のことが数世紀前のことのように、はるかに思い出された。…
ディナーのあと、ジュスタンは彼女にプレゼントを贈った。鉱山関連の人脈を駆使して世界中探したと思われる、大粒のダイヤモンドの輝く指輪だ。…シルヴィーも彼に贈るプレゼントがあった。スイスの最高の職人に特別に注文してつくらせた金時計だった。…
だが、どんな贅沢も、ふだんよりほんの少し長く互いの腕の中で過ごせる歓びには替えられない。夜明けの青い窓辺でジュスタンの鋼のような熱い肢体に身を沿わせ、夢うつつにまどろむひととき、ふとベッドごとゆっくりと回転しながら上昇してゆくような、くらくらするような感覚が訪れてくる…ふと、すべてが夢なのではないかという、深淵を覗きこむような怖ろしい感覚、絶頂に立ちながら、これ以上の上がなくなったことの不安とよんどころのなさの入り混じった、ぞっとするような微かな感覚が。… 飽和状態の幸福、それはほとんど死に近かった。…
2020年03月20日
小説・アレクサンドルⅢ世橋 6. 幽閉
小説・アレクサンドルⅢ世橋 6. 幽閉
病室の白いガウンを思い出させる消毒液のにおい、気の滅入るような ま四角な石灰岩の建物。
長い廊下がどこまでも続き、突き当たりのいちばん奥の部屋、いちばん広く、調度も大仰なその部屋に、葬り去るようにジュスタンは閉じこめられている。
来る日も来る日も、特別誂えの優美な車椅子に身をもたせたまま、うなだれ、その瞳は生気を宿さぬままに。
そこにいても、そこにはいない、生ける屍だ。
さいしょ発見されたときは、拘束しようとすると大暴れして、六人がかりで取り押さえねばならないほどだった。
混乱のなかでなかのひとりが目を打たれ、重傷を負った。あやうく失明に至るところだった。
以降、ジュスタンはとりわけ凶暴な患者として厳重に隔離されることになった。
だが、それ以降は特に何も問題を起こすことはなかった。というか、奇妙におとなしい。無抵抗というより無反応、無感情なのだ。
精神科医は幾度となく彼に会い、何がしかの話を、少なくとも反応を引き出そうとする。
すべては無駄な試みに終わる、問いかけにも、ロールシャッハのどのイマージュにも、何の反応も示さない…まるで魂を誰かに人質に取られてしまったかのようだ。
これがほんとうに、つい昨日まで社交界の花形で、実業界を牛耳っていた男だろうか?…
いろいろ試みたあげく、ともかく今はどうしようもない、と彼は匙を投げる。
それにしても、こんなふうに籠りきりというのはよくない、少なくとも外気にあて、何がしかの刺激を与えたほうがよいだろう…
そこで専任の介添人があてがわれ、ジュスタンの車椅子を押して散歩に連れ出すことになる。
毎朝、彼はジュスタンに身支度させ、マントに身を通させて出かける。
街のいろいろな光景を目にしても、彼は特別の反応を示さない。彼の眼には何ものも、何の意味も持っていないようだ。
その頭は一方の端に傾いたまま、面差しは虚ろ。
介添人は、指示された病院の近くのコースを毎回巡るのに早々に飽きてしまい、あちこちと、新しい道や通りへ彼を引っぱりまわすようになった。
それでも状況は何ら変わることはなかった。
ただひとつだけ、彼がいつも欲しがるものがあった。病院の門を出てしばらく行ったところ、角を曲がると小さなキオスクがあって、新聞やらボンボンやらこまごまとしたものを売っている。
そこで小さなブーケを見るといつも欲しがるのだった。それも必ず、白い花のブーケだ。それを毎日のように買ってやるのが日課となった。
ブーケを与えられると、彼はたいがい、散歩が終わるまで片手に握りしめ、そのあとは看護婦が小さな壜に水を入れて部屋に飾っておく。
ただ、奇妙な癖が… 街中でもどこでも、小さな虫の死骸を見つけると、彼はブーケの花びらをむしってその上へはらりと落とした。鳩や小鳥が死んでいるのを見つけると、花をひとつ、首のところからちぎってぽとりと落とした。何かの死骸に出くわすと、いつでも同じ反応を見せた。
「自分もまあ、死んでいるようなものだからな」と介添人はひそかに思うのだった。「同病相憐れむってところだろうよ」
それだけだった… 帝政崩壊の混乱のなかで、ジュスタンの存在はたちまち忘れられ、病院の中ですら、その存在は死人のように、しだいにひっそりと忘れ去られていくようだった。
病室の白いガウンを思い出させる消毒液のにおい、気の滅入るような ま四角な石灰岩の建物。
長い廊下がどこまでも続き、突き当たりのいちばん奥の部屋、いちばん広く、調度も大仰なその部屋に、葬り去るようにジュスタンは閉じこめられている。
来る日も来る日も、特別誂えの優美な車椅子に身をもたせたまま、うなだれ、その瞳は生気を宿さぬままに。
そこにいても、そこにはいない、生ける屍だ。
さいしょ発見されたときは、拘束しようとすると大暴れして、六人がかりで取り押さえねばならないほどだった。
混乱のなかでなかのひとりが目を打たれ、重傷を負った。あやうく失明に至るところだった。
以降、ジュスタンはとりわけ凶暴な患者として厳重に隔離されることになった。
だが、それ以降は特に何も問題を起こすことはなかった。というか、奇妙におとなしい。無抵抗というより無反応、無感情なのだ。
精神科医は幾度となく彼に会い、何がしかの話を、少なくとも反応を引き出そうとする。
すべては無駄な試みに終わる、問いかけにも、ロールシャッハのどのイマージュにも、何の反応も示さない…まるで魂を誰かに人質に取られてしまったかのようだ。
これがほんとうに、つい昨日まで社交界の花形で、実業界を牛耳っていた男だろうか?…
いろいろ試みたあげく、ともかく今はどうしようもない、と彼は匙を投げる。
それにしても、こんなふうに籠りきりというのはよくない、少なくとも外気にあて、何がしかの刺激を与えたほうがよいだろう…
そこで専任の介添人があてがわれ、ジュスタンの車椅子を押して散歩に連れ出すことになる。
毎朝、彼はジュスタンに身支度させ、マントに身を通させて出かける。
街のいろいろな光景を目にしても、彼は特別の反応を示さない。彼の眼には何ものも、何の意味も持っていないようだ。
その頭は一方の端に傾いたまま、面差しは虚ろ。
介添人は、指示された病院の近くのコースを毎回巡るのに早々に飽きてしまい、あちこちと、新しい道や通りへ彼を引っぱりまわすようになった。
それでも状況は何ら変わることはなかった。
ただひとつだけ、彼がいつも欲しがるものがあった。病院の門を出てしばらく行ったところ、角を曲がると小さなキオスクがあって、新聞やらボンボンやらこまごまとしたものを売っている。
そこで小さなブーケを見るといつも欲しがるのだった。それも必ず、白い花のブーケだ。それを毎日のように買ってやるのが日課となった。
ブーケを与えられると、彼はたいがい、散歩が終わるまで片手に握りしめ、そのあとは看護婦が小さな壜に水を入れて部屋に飾っておく。
ただ、奇妙な癖が… 街中でもどこでも、小さな虫の死骸を見つけると、彼はブーケの花びらをむしってその上へはらりと落とした。鳩や小鳥が死んでいるのを見つけると、花をひとつ、首のところからちぎってぽとりと落とした。何かの死骸に出くわすと、いつでも同じ反応を見せた。
「自分もまあ、死んでいるようなものだからな」と介添人はひそかに思うのだった。「同病相憐れむってところだろうよ」
それだけだった… 帝政崩壊の混乱のなかで、ジュスタンの存在はたちまち忘れられ、病院の中ですら、その存在は死人のように、しだいにひっそりと忘れ去られていくようだった。