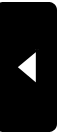2018年02月16日
小説 ホテル・ノスタルジヤ(16) 空の彼方へ

16.
街路樹の枝々も芽吹きはじめたある日のこと、朝食を終えて部屋に戻ったイレーヌは、ベッドの上でのんびり雑誌をめくっていた。
と、だしぬけにメルバがバサバサッ!! と大きく羽ばたいたので、部屋じゅうの新聞やら紙類やらが、風にあおられて舞い上がった。
「ちょっとちょっと!」イレーヌは注意した。「飛ぶ練習をするときは、予め言ってよね! ぜんぶごちゃごちゃになっちゃったじゃないの!」
「今日あたり、いけそうな気がするのです」馬はまじめな表情で言った。「ちょっとやってみたいのです。窓を開けてもらえませんか?」
イレーヌが開け放った窓からメルバは身を乗り出し、思いきって翼を広げると飛び立った。はじめはやや覚束なかったが、やがてしっかり安定した羽ばたき方になると、円を描いて二周、三周してから満足げに戻ってきた。
「さあ、背中に乗って!」バルコンの手すりに蹄をかけて、メルバは元気よく言った。
「もういいの? すっかり大丈夫なの?」
「大丈夫ですとも。何年というもの、人をこの背中に乗せてきたんですからね。そして、イレーヌ--色々ありがとう。今日でお別れです」
あっけにとられたまま、イレーヌは窓枠に足を掛け、メルバの背にまたがった。彼女を乗せると、メルバは勢いよく壁を蹴って飛び立ち、翼を広げて、天高く駆け上がっていった。みるみる下界の家並は小さくなり、やがて広々とした丘の連なりのかなたまで、パリ市街を一望するまでに高く高く… イレーヌは全身を切る冷たい風に震えながら、メルバの長いたてがみにしがみつき、高鳴る胸をおさえてはるかな街並を見下ろした。突如、何もかも--今までこの馬を守り通すために、山ほど味わってきた苦労や不安や心配や、そうしたものすべて、一瞬のうちに彼女の心から消え去った。この大空を前にしてはただ、人生はすばらしい、無限の可能性に充ちている… そうした圧倒的な思いしかなかった。…この目に映る、かなたへ広がる地平のように、どこまでも限りがない…そんな思いが熱くほとばしり出て、うねり高まる大波のように彼女を飲みこんだ… そう、何ひとつあのころと変わりはなかった、光こぼれる夏草の戸口から一歩踏み出せば…王様の宮殿へも、鏡の国やグリーンランドへでも…
「ああ…素敵ね…空を飛べるって、ほんとに…」イレーヌは溜め息をついた。
「そうですとも」かつてない誇りに満ち溢れて、メルバは答えた。「およそこの世に、これほどすばらしいものはありません」…
やがて二人が青空を背景に真っ白に聳え立つサクレ・クールに近づくと、イレーヌはモンマルトルの坂道の途中に、見覚えのある親子連れの、豆粒のような後ろ姿を見つけた。
「あの子だわ! マリアン!…あなたの名前を知っていたあの女の子よ。あそこに停まって、あの子も乗せてあげて!」
「よろしい」メルバはしずかに言った。「あの子は、私がこの街で乗せるさいごの子供になるでしょう」
彼はぐいと顎を引いて角度を変えると、地上の一点を目指してまっすぐに駆け下っていった。
やがて空を切る羽音に顔を上げた、マリアンの目がぱっと明るくなった。
「メルバ!」
親子の前に降り立ったメルバのもとへ、マリアンは転げるように駆け寄ってきた。
「もうよくなったの?」
「そうよ、約束どおり迎えに来たわ。…お母さんも、よくなったのね?」
マリアンは溢れんばかりの笑みを浮かべて、頷いた。
「よかった… メルバも、ほらね? また飛べるようになったのよ…」
イレーヌはマリアンを抱き上げると、自分の前に座らせた。ふたりを乗せたメルバは再び羽ばたき、舞い上がった。
「すぐ戻ります!」イレーヌは慌てて母親に向かって叫んだ。
メルバはぐいぐいと、またたくまに天高く駆け登り、それから彼らのために、街の上で何度も大きく円を描いてみせた。
「ごらん、あれがセーヌ…銀色のリボンみたいにきらきらして見えるでしょう。あの小さな島に建ってるのがノートルダム… 向こうに見えるのがエッフェル塔よ」
イレーヌはひとつひとつ、指さして教えてやった。
マリアンは顔を輝かせ、夢中になって眺めていた…が、しばらくすると、ふとその顔が翳った。
「メルバ、あなたは行ってしまうの? もう戻ってこないの?」
「私は世界を見にいくのですよ」と、メルバは答えた。「今までずっと、狭いひとつの世界しか知らなかったのでね」
マリアンは何も言わなかった。涙がひとすじ、頬を伝ってこぼれ落ちた。
イレーヌはその肩をそっと包んだ。
「今この瞬間を覚えておいてね。おとなになっても、ずっと忘れないようにね」
「さあ、そろそろ行きましょうか」…メルバはしずかに言って、サクレ・クールの白い頂を目印に、再びモンマルトルを目指した。
マリアンを母親のもとに送り届け、それからイレーヌひとりを乗せてホテルまで向かうあいだ、メルバはつと無言になった。
「このあとどこへ行くの、メルバ?」
イレーヌが尋ねると、彼は答えた。
「私はヴェニスへ行くのです。覚えているでしょう、私のいたメリーゴーラウンドに、ヴェニスのゴンドラがおりましてね。ことあるごとに、ヴェニスがどんなに美しい街かってことを吹きこむもんですから、ここを逃げ出したら真っ先に行ってやろうと、ずっと心に決めていたのです。そのあとは、たぶん…世界一周の旅に出るでしょうね。生まれてこのかた、フランスを出たことがないのでね。エジプトのピラミッドも見てみたいし、アマゾンのジャングルへも行ってみたいし… ほかの色々なところへ、行ってみたいのです」
イレーヌを<ホテル・ノスタルジヤ>の窓辺まで無事に送り届けると、彼はあらたまって言った。
「それでは、ほんとうにありがとう。これでお別れです」
「わかったわ。それじゃ、すてきな旅をね。さよなら」
メルバは再び力強く羽ばたいて、窓枠を蹴って飛び上がった。遠く遠く、真っ白なその姿が青空の中の一点となり、やがて吸いこまれるように消えてゆくまで、イレーヌは窓辺に身を乗り出してずっと見送った。
「…あいつ、行っちまったんだな」
ふと声がして、下を見ると、いつのまにかジャンが通りの端に立っていた。煙草屋から戻ってきたところだったようで、小脇に新聞を抱え、ポケットに手を突っこんで、メルバが消えていった同じ方向を眺めていた。
「ええ」
「あの野郎、さんざん世話を掛けやがって、俺には挨拶していかなかった」
「あら、そのつもりだったのよ」とイレーヌは急いで言った。
「あの画家の方にもたいへんお世話になりました、くれぐれもよろしくお伝えくださいって言ってたわ」
「ふん」
ジャンは肩をすくめると、煙草の吸いさしを地面に投げつけて、ドアを開けて中へ姿を消した。
2018年02月15日
小説 ホテル・ノスタルジヤ(15) 画家と見習い



15.
例の一件以来、ジャンには合わせる顔がなく、避けてまわっていたのだった。
だが、思いきってはじめて北の角部屋へ出向くと、大きく息を吸いこんで扉を叩いた。
どうか、いませんように!…というひそかな願いも虚しく、ごそごそ物音がしてギイと扉が開いた。
「なんだ、まだ何か文句があるのか」
相変わらず不機嫌な仏頂面が突き出した。
「文句なんかないわよ!」
つられて、イレーヌもついけんか腰になった。
「ただ、花の描き方を、教えてほしいの!」
「俺があんたに絵を教えてるほど、ひまだと思ってるのか」
「そんなにものすごく忙しいようにも見えないわよ」
負けずに言い返しながら、イレーヌは扉が閉まる前に急いで中へ滑りこんだ。
「だいたい、俺が花の絵なんか描くか」
「私よりはましでしょうよ!」
ジャンはぶすっとして、ストーヴのところへ行くと、やかんを持ち上げてコーヒーを注いだ。
「あ、私にもちょうだい!」
イレーヌはそのへんのマグカップのひとつをすかさず差し出すと、ジャンはむっとした顔をしながらもそちらにも注いでやった。
「俺は教えられんぞ、ともかく」
壁にもたれて、ポケットに手を突っ込みながら言った。
「教えたこともないしな。そもそも、絵なんて習うもんじゃない。生まれつき描けなきゃ、そりゃ、描けないってことだ。諦めるんだな」
「そんなこと言ってられないのよ!」と、イレーヌは言い張った。「メルバを、食べさせなきゃならないんですもの!」
「あいつ、まだいるのか?…プフーッ!」ジャンは天を仰いで、呆れた顔をした。
「やっかいだな、全く!」
「いえ、そんなことない…ええと、まあ…多少は…」
ジャンは窓に背を向け、眉を寄せて思案した。
煙草の匂いがしみついた部屋の、キャンヴァスや画材で足の踏み場もなくとっちらかったようすを、そのまにイレーヌはしげしげと観察した。
ジャンは部屋のすみに埋もれた書棚から、シャガールやヤン・ブリューゲルの画集など2,3冊引っぱり出してくると、埃を吹き払った。
「まあ、とりあえずは、模写でもやるんだな。低俗な奴らのやることだがね」
それからちょくちょく、イレーヌはジャンのところで模写に取り組むようになった。
もちろん、いきなりブリューゲルのように描けるようになるわけはない。あくまで、イレーヌ流だ。
しばしば似ても似つかないものになりはしたが、それでも、何もないよりはよほどよかった。
どうにも歯が立たないときには、助言を求めることもできた…だからといって、返事が返ってくるとは限らなかったが。
ジャンは部屋にいることもあったし、いないこともあったが、たいてい鍵はかけていなかった。そこでイレーヌは猫のように勝手に出入りしていた。
窓から差し込む陽も、ずいぶんと優しく、あたたかくなっていた。しんとしたなかで黙々と描いていると、しばしば眠気を誘われた。
「ねえ、ジャン、」と画集を片手に、がらくたの山を踏み越えて、イーゼルに向かうジャンのところへ行ってみると、どうも見覚えのある姿をキャンヴァスに見つけたこともある。
「まあ、これ、私?!」
イレーヌは、びっくりした拍子に、聞こうと思っていたことを忘れてしまった。
自分のことを絵に描かれるなどはじめてだったこともあるし、何となく、ジャンは壁や窓の絵しか描かないと思っていたのだ。
「いいから、向こうへ行って、続けてろ」
絵筆を持つ手を止めずに、ジャンは言った。「あんまり、頭を動かすなよ」
「へーえ。ほんとに、画家だったのね」
「何だと思っていた?」煙草を口の端にくわえたまま、ジャンは相変わらずの憎まれ口をたたいた。「魚屋か?」…
イレーヌの腕が少しずつ上がってきたのか、それとも飢えには逆らえなかったのか、メルバも、彼女の描く花を少しずつ食べるようになっていた。
ほんとうの花よりも絵の具のほうが、メルバの体には直接に影響するようだった。色とりどりの花を食べたあとには、しばしばその純白の毛並みが、全身、絵の具をぶちまけたパレットのように色とりどりになってしまうのだった。
それはそれで、なかなかに芸術的な感じがしたが…。
「白限定で、描くようにした方がいいかしらね?」
イレーヌは心配したが、意外にもメルバはたいして気にしなかった。
「だいじょうぶ、だいじょうぶ。半日くらいすれば、たいてい元に戻りますから。むしろ、いろんな色を体に取り入れたほうがいいんです。それぞれ、栄養素が違いますからね」
「へええ、そういうものかしらね」
たまには、自分の部屋で描くこともあった。するとしばしば、メルバがやってきてスケッチブックをのぞきこみ、イレーヌが描くそばから一輪ずつ、くわえ上げてむしゃむしゃ食べてしまうのだった。
「ちょっと、それまだ描きかけだったのに!」
「描き込みすぎは、煮込みすぎのシチュウみたいなものでね」
メルバは平然と、講釈を垂れた。
「なにごとも、過ぎたるは及ばざるがごとし。ちょうどいいところで、火を止めることを学ばないとね」
注記: このシリーズでは、画像を長辺500でアップしているのですが、なぜか昨日くらいから、何度やっても320で反映されてしまいます。以前からときどきこの現象が起こります。目下、お手上げです。
2018年02月14日
小説 ホテル・ノスタルジヤ(14) さいごの手段



14.
彼女にしてみれば、終わりは全く唐突にやってきた。
ある日、イレーヌがいつものようにその花屋に顔を出すと、年老いたムッシュウの代わりに眼鏡をかけた中年のマダムがいた。
店内は妙にがらんとして、いつもいっぱいにみずみずしい花を生けたバケツもなにか疎らだった。
「こんにちは、」入った手前挨拶をしたが、イレーヌはためらった。
「あのう…ムッシュウは?」
「今日はいないよ」マダムは無愛想に答えた。「ご注文でも?」
「いえ…」
病気の父親の作り話が通用するような手合いではなさそうだ。イレーヌは用心深く身を引いた。
「いいんです、また来ます。ありがとう」
翌日、ふたたび訪れてみると、イレーヌは目を疑った。店内はすっかり空っぽになり、カウンターや、花を置く台も取っ払われて、廃墟のようだった。
左官屋がひとり、脚立に乗ってT字型の道具でせっせと壁紙を剥がしている。
「あのう、こんにちは」面食らいながら、イレーヌは声をかけた。
「ここにあった花屋さん…」
「あぁ、もうないよ」彼は働き者らしい、きびきびとした調子で朗らかに答えた。
「店を売ってしまったのさ。こんど、ここはサロン・ド・テになるんだよ。来月オープンだよ」
「そうなんですか、へーえ…」
あっけに取られたまま、イレーヌは店を後にするしかなかった。
その日、戻ってくるときには、イレーヌは大きなスケッチブックと絵の具箱を抱えていた。
こうなったら、さいごの手段だわ! というわけだった。
絵のことは分からないけど、やるしかない… 花ならこれまでさんざん見てきたのだから、何とかなるでしょうよ。
彼女はベッドの上にスケッチブックを広げると、何の花を描こうか、どんなようすをしていたか、思い出そうとした。ところが、いざ描こうとすると、さっぱり見当もつかない。
ともかくコップに水を汲んでくると、絵の具を色々に混ぜあわせて、何とかやってみようとした。
1時間後、紙面いっぱいに描きなぐったのを、メルバの鼻先に突き出した。
「どうかしら?」
メルバはふんふんと匂いをかいで、やや攻撃的な青いダリアの花を、気乗りのしない様子でくわえ上げた。もぐもぐと噛みながら、しかめっ面をした。
「粉のよく混ざっていない、生焼けのケーキみたい、」と評した。「…って、マダム・ヴィオラなら言うところでしょうね」
「まあ、ひどい!」
イレーヌは憤慨したが、そうそうすばらしい出来でもないのは自分でも分かっていた。
彼女は1枚目をビリッと破り捨て、気を取り直して別なのに取り掛かった。
するとメルバがやってきて、肩越しにのぞきこんだ。イレーヌが描くのを眺めながら、首を振ったり、鼻を鳴らしたりするものだから、気になって集中できない。
「これは、ばらですか? それともひまわり?」
「うるさいな!」
アネモネのつもりだったとは、言えなかった。
あきらめて勿忘草を描こうとしたけれども、筆でこまかな花房を描くのは難しく、南国のハイビスカスのレイみたいになってしまった。
「どう?」
ふたたびスケッチブックをメルバの前に広げると、匂いをかいだが、手をつけようとはしなかった。
「まあ、ひとつ行ってみなさいよ。せっかく描いたんだから!」
メルバはしぶしぶ花房のひとつの端をくわえ、引っぱり上げた。噛みづらそうに、首を傾けて、ちょっと振り回してみたが、床の上に取り落としてしまった。
「すみませんけど、私の胃では消化する自信がありません」
「失礼ね!」
すると、その途端、メルバのお腹がグーッと鳴った。メルバはごまかそうとして、えっへんと咳払いした。
イレーヌはため息をついた。…どうにも仕方ないわね。