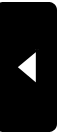2010年08月31日
中島迂生ライブラリー

サングラスをかけたライオン
ジャングルの中で、象といっしょに住んでいる7才の少女トザエモの物語。
ある日、久しく連絡のなかった母親からのことづてを発端に、次々と事件が起こり…。
14才のときの作品です。ポール・オースターの<幽霊たち>を読んで、あんなふうな斬新な作品を書いてみたいと思って構想しました。
のちに少し推敲してすっきりさせましたが、文章はほぼそのまま。
Kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBFD8WHH
章立てと挿絵もさらに増やしてリニューアル。
パソコンからもスマホからも読めます。
Kindle inlimited ならいつでも無料。
note
https://note.com/ussay_nakajima/n/ncd7f678cda00
Kindle版と同じ内容をこちらからも読めます。
じゅずかけばと
運命の命ずるまま、仲間とともに世界じゅうをさまよい旅する少年ボルビーゲルのゆきつく果てとは。
これも14のときの構想で、前半3分の1ほどは当時の文章そのまま。
ハドソンの The Green Mansion (「緑の館」)や Little Child Lost (「夢を追う子」)がとても好きでした。
ああいう神秘的で異教的な雰囲気が色濃く出ていると思います。
うるわしのフォーリヤ
天国のような美しい土地にひとり暮らす少年ヴィクトールと、ある日出会ったふしぎな生き物ジョルジョムをはじめ、
さまざまな隣人たちとの織りなす日々の暮らし。
2002年頃の構想。「理想のすみか」のエッセンスをぎゅっと詰めこんだ小さな宝石箱のような小品。
オタ・パヴェルとか、そういう東欧の田舎っぽい雰囲気かな。
潮騒のスケルツォ
北ポルトガルの寒村、灯台守の家に暮らしはじめた孤独な作曲家グレゴールと、その調べに魅せられた人魚とのひと夏の物語。
構想は2003年くらい。7年後に時を得て書きあがりました。
「灯台に暮らす」というイメージはたぶん、ドーデの<風車小屋だより>のコルシカ島の章から。(当時は意識していなかったけど)
雰囲気的には、マルグリット・デュラスっぽい。<モデラート・カンタービレ>みたいな。
夏の物語「魔法使いナンジャモンジャと空飛ぶバイオリン」(中篇)
note
https://note.com/ussay_nakajima/n/n2843d34eddee
ある日突然空を飛び始めた、小さな町のデパート、ラ・フォンテーヌ。
ユマとリオナは、それがとあるバイオリンと関係あることを突き止め、魔法を解くため冒険の旅に出る…。
この物語は、基本、12歳のときに書いたものです。
友だちと二人で町のデパートに行ったところまでは実話。
書き上げるとその友だちにあげてしまったので、私の手元には残っていません。
さいきんもう一度読みたたくなり、思い出しながら復元して書きました。
冬の物語「黒山羊の家の紡ぎ歌」 (中篇)
note
https://note.com/ussay_nakajima/n/n41cddf7fbe91
至急電報を受け取ったグレゴールは、雪に閉ざされた山奥の「黒山羊の家」にやってきます。そこから奇妙な世界に巻き込まれ…。
これも14才のときの構想で、「サングラスをかけたライオン」とほぼ同時期。
でも難しくて、当時書けたのは7割ていどまででした。
いつか書き上げたいなとずっと思っていたものです。
秋の物語「ポプラ小路のハロウィンニャンコたち」(短編)
note
https://note.com/ussay_nakajima/n/n10a3ac0dffc9
霧にけぶる10月の夕暮れ 街灯のぼんやりした光が石畳を照らすころ
手に手にお菓子の袋を抱えたニャンコたちが そっと闇にまぎれて
秘密の会合へ急ぎます
魔女の仮装に身を包み 物置から引っぱりだした箒にまたがったら
風を切って 夜空も飛べそう…
パリの片隅に住むネコたちの一夜の冒険。
小説「アレクサンドルⅢ世橋」
https://ballylee.tsukuba.ch/c14979.html
19世紀、第二帝政末期のパリ。
貧しい踊り子のシルヴィーは、気鋭の実業家ジュスタンに見初められて一躍トップの座に。二人は手に手を取って荒波の中を登りつめ、頂点を目指すが、突如、不可解な夢のような出来事に巻き込まれて…。
夢幻譚のようでもありつつ、ギリシャ悲劇のように重厚な一篇。
(ノベライズ)
トラス・オス・モンテス ノベライズ
<トラス・オス・モンテス Tras-os-Montes >(1976年、ポルトガル、アントニオ・レイスとマルガリータ・コルデイロ監督、108分、35ミリ、カラー)
という映画作品があまりにすばらしかったので、備忘のため勝手にノベライズ。
「ポルトガル現代詩を代表するアントニオ・レイスが、マルガリータ・コルデイロとともにつくった初長編。
川遊びに興じる子供たちの姿を中心に、遠い山奥のきらきらと輝く宝石のような日々を夢幻的な時間構成により浮かびあがらせる。
公開当時、フランスの批評家たちを驚嘆させ、のちにペドロ・コスタにも影響を与えたという伝説的フィルム。」
-当時見たポルトガル映画祭のパンフの紹介文より。
詞華集 カフェ・ジュヌヴィエーヴ
おもに16から19歳くらいの頃に書きためた小品のうち、なんとなくノスタルジックな感じのを集めたもの。
カフェ・ジュヌヴィエーヴは旅行雑誌のスナップや昔のパリの写真集なんかからつくりあげた架空のカフェで、当時の私の心の中にあったカフェのイデー。
夢想集 ムーア・イーフォック
16から19歳くらいの頃に書きためた小品のうち、ちょっと不気味だったり訳わからない感じのものを中心に。
ムーア・イーフォックはディケンズのエピソードから。あるときコーヒー・ルームのガラス戸を開けて入ろうとしたら、
ガラスの文字が左右逆に映ったMOOR EEFFOC という文字が目に飛び込んできて、その瞬間まざまざと、荒涼としたイーフォック荒野の情景が広がったのだという。
日常のふとした瞬間に突如出会う異界の感覚。
随想集 Down to Earth-わが心 大地にあり-
2001年ころから2004年6月までの、ある恋の記録。
といっても、じっさいのエピソードというより、イメージの描写とか、心象風景みたいのがおもです。
ものすごくエネルギーをかけて、上質な仕上がりになったと思うので、いまも満足のゆく作品。
愛蘭土物語(あいるらんどものがたり)
西の果てアイルランドの大地から託された、16篇の壮大な太古の物語。
現地を旅した2004年から2010年くらいまで、執筆に7年くらいの歳月を費やした大作です。
劇団バリリー座上演作品<エニスの修道士>、<風神の砦>、<石垣の花嫁>、<湖底の都>もこちらに収録。
姉妹篇に<瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり)>があります。
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり)
上記、愛蘭土物語(あいるらんどものがたり)の姉妹篇。
風吹きすさぶ北ウェールズの山々から託された、12篇の暗くドラマティックな物語。
こちらは現地を訪れたのが2004年と2006年で、やはり2010年くらいまでかかって書き上げました。
とくに<魔の山>、<異界の丘>は圧巻です。(ちょっと前置きが長いけど)
これらのシリーズはみな「やってきた」物語で、自分で考えたわけではないのでね。
ホテル・ノスタルジヤ
パリ14区、モンパルナスの片隅にひっそりと佇む小さなホテル。
ある日ふらりとやってきた少女イレーヌは、メリーゴーラウンドから逃げ出した小さな美しいペガサスを
匿うはめになり、さまざまな騒動が…。
構想は2005年ころ。当時まだ訪れたことのなかったパリを舞台に、空想のままに楽しんで書いた小品。
海岸通りのデュラスへ~いくたび嵐に打ち墜とされて翼を折りながら、なおも風をまって求め続ける飛翔についての物語~
劇団を活動停止してから、2012年にはじめてフランスを訪れ、マルグリット・デュラスの軌跡をたどる旅を通じて移住を決意するまで。
なので、ほぼほぼノンフィクション。文体は、やはりデュラスっぽいと思います。
実はフランスでさいしょに通った語学学校に、奨学金の申請のために提出したもの。
この作品のおかげで奨学金、無事通りましたw
(翻訳)
オーチャード、グランチェスター
英国ケンブリッジの郊外の静かな村、グランチェスターのはずれにある、伝説的なティールーム<オーチャード>の由来を記したリーフレットの日本語訳。
この場所は20世紀初頭、詩人のルパート・ブルックを中心とする<グランチェスター・グループ>の集う憩いの場となっていた。
このリーフレットは<オーチャード>に無料でおいてあり、気軽にこの場所の歴史に親しめる。
この訳をネットでさっと見られたら、当地を訪れる日本人にとって便利だろうなと思って2007年くらいに訳出。
竜一点描
昔、母校である竜ヶ崎一高を卒業するとき、中島迂生がノートに書き残していった小品。
当時、色んな先生方からあたたかい感想をいただきました。
今もいただく。ありがたいことです。
創造的な不幸―愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ―
大学の卒論。
主題や内容は、なかなか興味深いと思うのですが、文体が…残念ながら、
ちょっと無意味に難解すぎて、あんまり読む人のことを考えてるとは言いがたいかも。
学内誌への掲載をめぐって、大学側とごたごたした。
映像作品<Je peins avec les yeux de mon cœur 心の目で描く人 ─祖父・中島三郎の物語─>
https://youtu.be/_GgpQRWchvk
”いちど母が聞いたことがある。「目が見えないのにどうやって描いてるの?」
すると、祖父は答えた。「心の目で描いてるんだよ」…”
祖父・中島三郎の生涯と作品を、本人の油絵と、私の文章と、合計100枚ほどの絵画で綴った物語。パリ第8大学院映画科の卒業制作。仏語ナレーション・日本語字幕。
Ma mère lui a demandé une fois :
"Comment peux-tu peindre sans voir ?"
Alors il a répondu :
"Je peins avec les yeux de mon cœur"
L'histoire de la vie et de l'art de mon grand-père Saburo Nakajima, racontée à travers ses propres peintures à l'huile, mon texte et un total d'environ 100 dessins. Film de fin d'études de l'Université Paris 8, Département Cinéma.
Voix-off en français, sous-titres en japonais.
<Je peins avec les yeux de mon cœur 心の目で描く人 ─祖父・中島三郎の物語─>Kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CCKB2ZTN
映像作品ではカットした部分も含め、電子書籍にまとめました。
日本語・フランス語併記。
Kindle Unlimited ならいつでも無料。
(2023年8月更新)
2010年08月31日
オズモンド姫の物語
目次へ戻る
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇6
オズモンド姫の物語 Princess Odsmonde
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. <オズモンド姫の物語>
2. リュウの宿の思い出
3. 出発の日
********************************************
1. <オズモンド姫の物語>

かの姫君のおぼろな優しい面影を思い出すたび、私は、一日日に照りつけられて、日のなくなったあとまでも熱をとどめた石のコテッジの、蒸し暑い空気のこもった屋根裏部屋を思い出すのだった・・・
太陽との結婚を拒んだために、だれも住まない高い山の上の塔に閉じこめられてしまう。
・・・ウィリアム・モリスのタペストリ、おだやかな色調と、有機的な植物柄のあのデザインをもった。・・・
こんなふうに、ほとんどひとりきりで山にこもり、来る日も来る日も誰とも口をきかずに暮らしていると、・・・まわりにいる生き物といったら羊だけで、下界から訪れてくるものといえばつばめたちばかり、来る日も単調で粗末な食事をして、ただ眺めだけは世界一すばらしい、そんな暮らしをつづけていると・・・
しだいこんなふうに思われてくるのだった、こんなふうに、たったひとりで山の上から世界を眺めおろしている人間がだれかほかにもいるのではないかと、どこか別の、けれどもちょうどこんなふうな場所からこの眺めを、もう千年以上も前からたったひとりで、同じ眺めを見守りつづけている者が、だれかほかにもいるのではないかと。・・・
何か遠い声に呼び寄せられて、私は今、そのひとの視点で見ながら、そのひとの暮らしと重なりあうような日々を送り、そうすることでそのひとの心に近づき、いま、その物語を語り告げられようとしているのではないかと。・・・
夕刻、下界が青いうすもやにぼうっとけぶり、部屋のなかは仄暗く、もうランプなしに書物を読むことはできない・・・ そういう時刻に、私はドアを開け、部屋の奥の古い曇った鏡の中に、おぼろな乙女の面影を見た・・・
金色の髪は長く垂れ、透き通るばかり白くほっそりとした面だちをして、その眼差しは悲しげに、だが同時にとこしえの穏やかさを湛えていた・・・ それがそのひとだと私には分かった、それがかのオズモンド姫の姿だと。・・・
* *
オズモンド姫ははるかな昔、ウェールズの王のひとり娘だった・・・その髪はゆたかに長く、その面だちはやさしく美しく、心根も清らかで、すべての者に愛されていた。
あるとき、城の階上の間を歩いているその姿を太陽が見染めて、妻にと所望した・・・けれども姫は断った、その心に、ひそかに想う者があったからだ。・・・
すると太陽は怒って姫を連れ去り、だれも住まない高い山の上の塔のなかに閉じこめてしまった。
「そこでゆっくり考え直すがいい」と太陽は言った、「太陽のことばに従わぬとは、頑なで愚かな女よ」・・・
そこで姫は幽閉されて暮らした、まわりにいる生き物といったら羊だけで、下界から訪れてくるものといえばつばめたちばかり、来る日も単調で粗末な食事をして、ただ眺めだけは世界一すばらしかった・・・
そのうちに、太陽がやってきて言った、「私はかんばつを起こして、お前の国を滅ぼしてやろう。お前はそこから、ただ手を拱いて見ているよりほかないのだ。そうしたら、お前は自分の愚かさのほどを知るだろう」
それを聞くと、姫はひそかに、つばめに伝言をたのんで父王に伝えさせた、「太陽は私のことを怒って、かんばつを起こしてこの国ぜんたいを滅ぼそうとしています・・・どうぞ民のすべてに告げて備えをしてください」
そこで、すぐさま夜を徹してあらたにたくさんの井戸が掘られ、溜め池がつくられ、ありとあらゆる器にはありったけの水が蓄えられた。
そのうち、かんかん照りの日照りがくる日もくる日もつづき、まるひと夏のあいだ、一滴の雨も降らなかった。谷間の川すじはすっかり干上がってしまい、木々は次々と枯れていった。
人も動物も、不慣れな暑さにあえぎ苦しんだが、水の蓄えのおかげでもちこたえ、ついに一匹の羊も死なすことなしに切り抜けた。・・・
やがて、太陽はふたたび姫のもとにやってきて言った、「どうしてか、この民にはこたえないようだ。日照りが平気だというなら、こんどは大水で苦しめてやろう」
すると、姫はふたたびつばめをたのんで伝言させた、「太陽はまだ怒っています。こんどは大水がやってきますから、どうぞ備えをしてください」
そこで、地上はまだからからで、干し草が触れあっただけで火がつきそうだったが、高台に次々と避難小屋が建てられ、低地に住む者たちはそこへ移り住んだ。
舟という舟は山の中腹まで引き上げられ、石垣や柵は補修され、水に浸かってだめになる前に、作物もすっかり収穫された。
さいごに地のおもての羊たちのすべてが呼び集められて、家畜小屋に入れられた。
そののち、突然天が引き裂かれたかのように水が流れ下ってきて、それからひと月ほどもの間、くる日もくる日も激しい雨が降りつづいた。
川床にはまたたくまに水が溢れ、茶色く濁った逆巻く流れとなって急ぎ下っていった。
たくさんの木が枯れて、土を掴んでおく根の力もなくなっていたから、大量の土砂が岩ころとともに、山肌から削られて押し流されていった。
低地はすっかり水浸しになって、胸まで水につかって歩かねばならなかった。
けれども、あれやこれやの備えのおかげで、ついに一匹の羊も溺れ死ぬことはなかった。
やがて太陽は姫のもとにやってきて言った。「どうにも懲りないようだな。洪水も平気だというなら、こんどは風あらしを送ってやろう」
すると、姫はみたびつばめに伝言を託した、「太陽はまだ気もちがおさまらないようです。こんどは風あらしがやってきます。どうぞ備えをしてください」
そこで、いまだ水が引かず、地上はなかば海のようになっていたが、人々はおもてに出てきて、屋根や壁の補修にかかりきった。
そのころからウェールズの家は石造りで、スレート葺きだった。隙間という隙間をモルタルでしっかり固めておきさえすれば、吹っ飛ばされる心配はまずなかった。
それから、風に飛びそうなものは残らず家の中へしまいこまれ、大きすぎてしまいこめないものは残らず手近の木とか岩とかに縛りつけられた。
りんごや何かもすっかり収穫されて箱詰めされ、羊たちは再び呼び集められて、家畜小屋に入れられた。
と思う間もなく、峰々のあいだから猛烈な風あらしが巻き起こって、弱っていた木々を根こそぎなぎ倒し、人の家ほどもある岩ころを山の上から転がし落とした。
おもてでは誰ひとり、立っていることも息をすることもできぬほどだった。
風あらしは洪水の水を残らず海へ押し流したので、もとの地面が顔を出し、何もかも泥水でまっ茶色になって、押し流されたり吹っ飛ばされたりしたものがごちゃごちゃと折り重なってそこらじゅうに散乱していたが、この風あらしがおさまったとき、はじめてもとの面影を取り戻した。
彼らはこんども無傷で切り抜けた。
太陽は姫のもとにやってきて言った、「お前の国の民は、どうやら私が思っていたよりも賢いようだ。私は、もううんざりした。私はもう放っておくことにしよう」
そうして太陽は行ってしまった。
そののち、しばらくたってから、父王はつばめに伝言をもたせてオズモンド姫のところへ送った。
「太陽は、お前のことをもう忘れてしまったに違いない。・・・私も私の国の者たちも、お前がいないことを心から悲しんでいる・・・私はえり抜きの兵士の一隊を送って、お前の塔の鍵を打ち壊し、お前の塔の壁を打ち崩して、お前をこの国へ連れ戻そう。・・・どうかお前のいる正確な場所を教えてほしい」
しかし、こんどもまた、姫はつばめを送り返して言うのだった。
「はばかりながら、父上、あなたは太陽の嫉妬ぶかさをご存じないのです。・・・この塔の鍵は人の手では開けることができず、この塔の壁は人の力では打ち崩すことができません。・・・
たとい実際に打ち崩すことができて、私があなたのもとに帰ることができたとしても、ひとたび太陽に愛されたがゆえに、私は呪われた身です・・・ここを出ていったならば、私はゆく先々で災いのもととなるでしょう。ここを出ていったならば、太陽は私を見、私のことを思い出して、私に関わる者たちを破滅させ、私を愛する者を殺すでしょう。・・・
だが、ここにとどまる限り、私は忘れられて、それゆえに災いを引き起こすこともありません。・・・
私にとっては、その方がよいのです。
私はここにとどまって、天と地とを見守りつづけ、また何かよくないことが起こりそうになったら、また私のつばめたちに言伝てて、あなたとあなたの国の人々に害が及ばないように力を尽くしましょう。
私はちっとも淋しくありません。いつでもこの山の上から、あなた方のようすを見ることができるのですから。
ですからどうぞあなた方も、私のことは心配なさらないでくださいますように。・・・」
こうして姫は山の上にとどまった・・・そのときからこのかた、ウェールズは、二度とふたたび、かつてのようなすさまじい災いに悩まされることはなくなった。
彼らは今でもつばめを大切にする、あの鳥はオズモンド姫の使いだからと。
彼らは今もそこにしるしを読み取ろうとする、つばめの飛び方、鳴き交わす声、あるいは春先にさいしょに姿をあらわす日の早いか遅いかで、天候の異変や、その年の夏がどんなふうであるかを知ろうとするのだ。・・・
今でも、羊を追い追い、山の深くまで分け入るうち、それと知らぬまに人間の領域を踏み越えてしまった羊飼いの若者が、うつつか幻かも定かならず、はるかな山の上に築かれた目も眩むばかりの塔を目にすることがある・・・
塔のてっぺんの小さな窓から、塔のあるじのこの世ならぬ姿を見たものもある、
おぼろな乙女の面影、こがね色の髪は長く垂れ、透き通るばかりのほっそりした面だち、そのまなざしはしずかな悲しみと、同時にとこしえの穏やかさを湛えた、ウェールズの守りの天使、かのオズモンド姫の姿を。・・・
その面影を心に描き、私ははるかに思いを馳せる・・・
けれども姫は断った、その心に、ひそかに想う者があったからだ。・・・
オズモンド姫のひそかに想う者とは誰だったのだろう?・・・
ここを出ていったならば、私はゆく先々で災いのもととなるでしょう・・・ここを出ていったならば、太陽は私に関わる者たちを殺し、私を愛する者を破滅させるでしょう。・・・
それゆえに姫はそこにとどまった・・・
姫がそこにとどまったのは、父王のため、民のすべてのため、ウェールズの大地のためであり、とりわけその心に想う者の幸福を願うためであったのだ。・・・
彼女の心に秘められたしずかな決意と、己れを殺す強さ。・・・
わが心は塔のごとし。・・・
その心に想う者とは誰だったのだろう?・・・
それはたぶん、どこの王子でも貴族の息子でもなくて、ひとりの名もない羊飼いの若者だったのだと私は思う。・・・
誇り高く顔を上げて、日をあびて丘の向こうからやってくる、赤銅の肌を持ち、万人のなかでもっともうるわしい者、雅歌の娘が、ソロモンの求愛すらも退けてその想いを貫いたような。・・・
姫のその想いのゆえに、ウェールズの羊たちは今も守られ、彼女のとこしえの瞳のもとに、優しく見守られつづけているのだと私は思う。・・・
* *
2. リュウの宿の思い出

もうひとつの週末が来て、去ってゆくあいだに、宿はまた少しばかり客を迎えて活気づいた。
なかでも印象的だったのは、白髪の老夫婦とその子供夫婦、それから孫たちという家族連れで、とくにその老夫婦のほうだった。
老人のほうは堂々たる恰幅で、モーゼのようにゆたかな髭を生やし、細君のほうは少し茶色みの残った、長い波打つ髪を、髷にしないでうしろで一つに結んで垂らしていた。真っ白でしわくちゃで、ふしぎに美しい顔をしていた。
朝食のあいだ、彼らふたりは窓ぎわの特等席に陣取って、ゆっくりと時間をかけてもりもり食べ、孫たちがゆで卵を運んだり皿を拭いたりして給仕していた。
彼女のほう、ひどく痩せているのに、みごとな食べっぷりだった。
トーストにバターとジャムをごってりと載せ、お茶にはドボドボとクリームを注ぐ。
こんなに年とってから、平気でこんな山の中までやってきて、窓辺の席で豪勢な朝ごはん。
それはなにか、ふしぎに感動的な光景だった。
コテッジのすべての窓にかけられていた、同じ柄のきれいなカーテン。これについても書いておきたい。・・・
この色調もまた、リュウの山の上でのあの日々を思い起こすにつけ、さいしょに鮮やかによみがえってくるもののひとつなのだ。・・・
剥き出しのままの石壁に木の床の、質素なコテッジの内装に、その華やかな彩りは引き立ってよく映えた。
たてのストライプのなかに、幾何学もようとアラベスクを組み合わせたデザインで、色合いはステンドグラスのよう、オレンジがかった澄んだ赤に、深いマリンブルー、こくのある水色に、ぱっと目を引くあかるい黄緑色、そしてやわらかい卵色。・・・
くもり空の朝の薄あかりに、透かして見るとくっきりと際だって映え、ぱっきりとクリアな陽光のもとでも、それはそれでよく映えた。
朝、目を覚まして、そのぱっと明るい色を目にするだけで、ああ、まだここにいられるのだ!・・・ と、幸福な思いでいっぱいになった。・・・
滞在中、私を好きにさせておいてくれた、寛大な宿の老人。・・・
見たところそう頑健そうな体格ではないのだが、これが驚くべき健脚の持ち主である。
ひとり離れに寝起きして、朝は誰よりも早く起きだして、暖炉に火を焚きつける。床の掃除や、あれこれの仕事をすませたあと、今度は用足しや買い物や、あるいはシーツの束を洗濯屋に出したりなどするために、毎日徒歩で山を下ってゆくのだ。・・・
帰ってくると、その日見たもののあれこれや、このあたりの色んな場所について話してくれる。
この前のイースターの休暇には、歩いてスノウドンを踏破したそうである。・・・
夕方には谷をのぞむ庭の芝生に置かれた椅子に腰かけて、新聞のクロスワード・パズルをやっている。
私がこの谷の眺めをスケッチしていると、見にやってきて、感心した。
よかったら、できあがったら複写を送りましょうか、と言ったらとても喜んだ。
それでその年のクリスマス、それは私がくにへ帰ってからのことだったが、スケッチの複写とクリスマス・カードを送ると、彼もカードと手紙を送ってくれた。
ところがその手紙というのがたいへんに独特な筆記体で、残念ながら一部はいまだに解読できずにいる。・・・

3. 出発の日

ロウウェンを発つ日である。
村の家々、いくどか行き交ううち、目になつかしいものとなっていた、とりわけ美しい何軒かをスケッチして、色鉛筆で色を塗りたい、などと考えつつ、結局できないで終わってしまった。
一軒ずつ、今でも思い出す・・・
リュウのコテッジにはかなり長く過ごしたけれども、荷物をまとめて下りてくるときには、みどりの坂道が、苔むした岩々やしだの群れや斜めに生えた木々のこずえが、特別な力をもって引き留めようとして、立ち去り難かった。
タリヴァン山をくだりゆく、山の向こうから灰色の雲むらがみるみると掻き曇り、ああ、雨を降らせるな・・・と見ていて分かった、雲が冷たい空気を掻きたてるように、ぞくぞくと心掻きたてられて嬉しくなる・・・
ウェールズの山には雨が似合う。・・・

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇5 安らえぬ魂
次章 オグウェン篇1 魔の山
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
中島迂生ライブラリーへ戻る
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇6
オズモンド姫の物語 Princess Odsmonde
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. <オズモンド姫の物語>
2. リュウの宿の思い出
3. 出発の日
********************************************
1. <オズモンド姫の物語>

かの姫君のおぼろな優しい面影を思い出すたび、私は、一日日に照りつけられて、日のなくなったあとまでも熱をとどめた石のコテッジの、蒸し暑い空気のこもった屋根裏部屋を思い出すのだった・・・
太陽との結婚を拒んだために、だれも住まない高い山の上の塔に閉じこめられてしまう。
・・・ウィリアム・モリスのタペストリ、おだやかな色調と、有機的な植物柄のあのデザインをもった。・・・
こんなふうに、ほとんどひとりきりで山にこもり、来る日も来る日も誰とも口をきかずに暮らしていると、・・・まわりにいる生き物といったら羊だけで、下界から訪れてくるものといえばつばめたちばかり、来る日も単調で粗末な食事をして、ただ眺めだけは世界一すばらしい、そんな暮らしをつづけていると・・・
しだいこんなふうに思われてくるのだった、こんなふうに、たったひとりで山の上から世界を眺めおろしている人間がだれかほかにもいるのではないかと、どこか別の、けれどもちょうどこんなふうな場所からこの眺めを、もう千年以上も前からたったひとりで、同じ眺めを見守りつづけている者が、だれかほかにもいるのではないかと。・・・
何か遠い声に呼び寄せられて、私は今、そのひとの視点で見ながら、そのひとの暮らしと重なりあうような日々を送り、そうすることでそのひとの心に近づき、いま、その物語を語り告げられようとしているのではないかと。・・・
夕刻、下界が青いうすもやにぼうっとけぶり、部屋のなかは仄暗く、もうランプなしに書物を読むことはできない・・・ そういう時刻に、私はドアを開け、部屋の奥の古い曇った鏡の中に、おぼろな乙女の面影を見た・・・
金色の髪は長く垂れ、透き通るばかり白くほっそりとした面だちをして、その眼差しは悲しげに、だが同時にとこしえの穏やかさを湛えていた・・・ それがそのひとだと私には分かった、それがかのオズモンド姫の姿だと。・・・
* *
オズモンド姫ははるかな昔、ウェールズの王のひとり娘だった・・・その髪はゆたかに長く、その面だちはやさしく美しく、心根も清らかで、すべての者に愛されていた。
あるとき、城の階上の間を歩いているその姿を太陽が見染めて、妻にと所望した・・・けれども姫は断った、その心に、ひそかに想う者があったからだ。・・・
すると太陽は怒って姫を連れ去り、だれも住まない高い山の上の塔のなかに閉じこめてしまった。
「そこでゆっくり考え直すがいい」と太陽は言った、「太陽のことばに従わぬとは、頑なで愚かな女よ」・・・
そこで姫は幽閉されて暮らした、まわりにいる生き物といったら羊だけで、下界から訪れてくるものといえばつばめたちばかり、来る日も単調で粗末な食事をして、ただ眺めだけは世界一すばらしかった・・・
そのうちに、太陽がやってきて言った、「私はかんばつを起こして、お前の国を滅ぼしてやろう。お前はそこから、ただ手を拱いて見ているよりほかないのだ。そうしたら、お前は自分の愚かさのほどを知るだろう」
それを聞くと、姫はひそかに、つばめに伝言をたのんで父王に伝えさせた、「太陽は私のことを怒って、かんばつを起こしてこの国ぜんたいを滅ぼそうとしています・・・どうぞ民のすべてに告げて備えをしてください」
そこで、すぐさま夜を徹してあらたにたくさんの井戸が掘られ、溜め池がつくられ、ありとあらゆる器にはありったけの水が蓄えられた。
そのうち、かんかん照りの日照りがくる日もくる日もつづき、まるひと夏のあいだ、一滴の雨も降らなかった。谷間の川すじはすっかり干上がってしまい、木々は次々と枯れていった。
人も動物も、不慣れな暑さにあえぎ苦しんだが、水の蓄えのおかげでもちこたえ、ついに一匹の羊も死なすことなしに切り抜けた。・・・
やがて、太陽はふたたび姫のもとにやってきて言った、「どうしてか、この民にはこたえないようだ。日照りが平気だというなら、こんどは大水で苦しめてやろう」
すると、姫はふたたびつばめをたのんで伝言させた、「太陽はまだ怒っています。こんどは大水がやってきますから、どうぞ備えをしてください」
そこで、地上はまだからからで、干し草が触れあっただけで火がつきそうだったが、高台に次々と避難小屋が建てられ、低地に住む者たちはそこへ移り住んだ。
舟という舟は山の中腹まで引き上げられ、石垣や柵は補修され、水に浸かってだめになる前に、作物もすっかり収穫された。
さいごに地のおもての羊たちのすべてが呼び集められて、家畜小屋に入れられた。
そののち、突然天が引き裂かれたかのように水が流れ下ってきて、それからひと月ほどもの間、くる日もくる日も激しい雨が降りつづいた。
川床にはまたたくまに水が溢れ、茶色く濁った逆巻く流れとなって急ぎ下っていった。
たくさんの木が枯れて、土を掴んでおく根の力もなくなっていたから、大量の土砂が岩ころとともに、山肌から削られて押し流されていった。
低地はすっかり水浸しになって、胸まで水につかって歩かねばならなかった。
けれども、あれやこれやの備えのおかげで、ついに一匹の羊も溺れ死ぬことはなかった。
やがて太陽は姫のもとにやってきて言った。「どうにも懲りないようだな。洪水も平気だというなら、こんどは風あらしを送ってやろう」
すると、姫はみたびつばめに伝言を託した、「太陽はまだ気もちがおさまらないようです。こんどは風あらしがやってきます。どうぞ備えをしてください」
そこで、いまだ水が引かず、地上はなかば海のようになっていたが、人々はおもてに出てきて、屋根や壁の補修にかかりきった。
そのころからウェールズの家は石造りで、スレート葺きだった。隙間という隙間をモルタルでしっかり固めておきさえすれば、吹っ飛ばされる心配はまずなかった。
それから、風に飛びそうなものは残らず家の中へしまいこまれ、大きすぎてしまいこめないものは残らず手近の木とか岩とかに縛りつけられた。
りんごや何かもすっかり収穫されて箱詰めされ、羊たちは再び呼び集められて、家畜小屋に入れられた。
と思う間もなく、峰々のあいだから猛烈な風あらしが巻き起こって、弱っていた木々を根こそぎなぎ倒し、人の家ほどもある岩ころを山の上から転がし落とした。
おもてでは誰ひとり、立っていることも息をすることもできぬほどだった。
風あらしは洪水の水を残らず海へ押し流したので、もとの地面が顔を出し、何もかも泥水でまっ茶色になって、押し流されたり吹っ飛ばされたりしたものがごちゃごちゃと折り重なってそこらじゅうに散乱していたが、この風あらしがおさまったとき、はじめてもとの面影を取り戻した。
彼らはこんども無傷で切り抜けた。
太陽は姫のもとにやってきて言った、「お前の国の民は、どうやら私が思っていたよりも賢いようだ。私は、もううんざりした。私はもう放っておくことにしよう」
そうして太陽は行ってしまった。
そののち、しばらくたってから、父王はつばめに伝言をもたせてオズモンド姫のところへ送った。
「太陽は、お前のことをもう忘れてしまったに違いない。・・・私も私の国の者たちも、お前がいないことを心から悲しんでいる・・・私はえり抜きの兵士の一隊を送って、お前の塔の鍵を打ち壊し、お前の塔の壁を打ち崩して、お前をこの国へ連れ戻そう。・・・どうかお前のいる正確な場所を教えてほしい」
しかし、こんどもまた、姫はつばめを送り返して言うのだった。
「はばかりながら、父上、あなたは太陽の嫉妬ぶかさをご存じないのです。・・・この塔の鍵は人の手では開けることができず、この塔の壁は人の力では打ち崩すことができません。・・・
たとい実際に打ち崩すことができて、私があなたのもとに帰ることができたとしても、ひとたび太陽に愛されたがゆえに、私は呪われた身です・・・ここを出ていったならば、私はゆく先々で災いのもととなるでしょう。ここを出ていったならば、太陽は私を見、私のことを思い出して、私に関わる者たちを破滅させ、私を愛する者を殺すでしょう。・・・
だが、ここにとどまる限り、私は忘れられて、それゆえに災いを引き起こすこともありません。・・・
私にとっては、その方がよいのです。
私はここにとどまって、天と地とを見守りつづけ、また何かよくないことが起こりそうになったら、また私のつばめたちに言伝てて、あなたとあなたの国の人々に害が及ばないように力を尽くしましょう。
私はちっとも淋しくありません。いつでもこの山の上から、あなた方のようすを見ることができるのですから。
ですからどうぞあなた方も、私のことは心配なさらないでくださいますように。・・・」
こうして姫は山の上にとどまった・・・そのときからこのかた、ウェールズは、二度とふたたび、かつてのようなすさまじい災いに悩まされることはなくなった。
彼らは今でもつばめを大切にする、あの鳥はオズモンド姫の使いだからと。
彼らは今もそこにしるしを読み取ろうとする、つばめの飛び方、鳴き交わす声、あるいは春先にさいしょに姿をあらわす日の早いか遅いかで、天候の異変や、その年の夏がどんなふうであるかを知ろうとするのだ。・・・
今でも、羊を追い追い、山の深くまで分け入るうち、それと知らぬまに人間の領域を踏み越えてしまった羊飼いの若者が、うつつか幻かも定かならず、はるかな山の上に築かれた目も眩むばかりの塔を目にすることがある・・・
塔のてっぺんの小さな窓から、塔のあるじのこの世ならぬ姿を見たものもある、
おぼろな乙女の面影、こがね色の髪は長く垂れ、透き通るばかりのほっそりした面だち、そのまなざしはしずかな悲しみと、同時にとこしえの穏やかさを湛えた、ウェールズの守りの天使、かのオズモンド姫の姿を。・・・
その面影を心に描き、私ははるかに思いを馳せる・・・
けれども姫は断った、その心に、ひそかに想う者があったからだ。・・・
オズモンド姫のひそかに想う者とは誰だったのだろう?・・・
ここを出ていったならば、私はゆく先々で災いのもととなるでしょう・・・ここを出ていったならば、太陽は私に関わる者たちを殺し、私を愛する者を破滅させるでしょう。・・・
それゆえに姫はそこにとどまった・・・
姫がそこにとどまったのは、父王のため、民のすべてのため、ウェールズの大地のためであり、とりわけその心に想う者の幸福を願うためであったのだ。・・・
彼女の心に秘められたしずかな決意と、己れを殺す強さ。・・・
わが心は塔のごとし。・・・
その心に想う者とは誰だったのだろう?・・・
それはたぶん、どこの王子でも貴族の息子でもなくて、ひとりの名もない羊飼いの若者だったのだと私は思う。・・・
誇り高く顔を上げて、日をあびて丘の向こうからやってくる、赤銅の肌を持ち、万人のなかでもっともうるわしい者、雅歌の娘が、ソロモンの求愛すらも退けてその想いを貫いたような。・・・
姫のその想いのゆえに、ウェールズの羊たちは今も守られ、彼女のとこしえの瞳のもとに、優しく見守られつづけているのだと私は思う。・・・
* *
2. リュウの宿の思い出

もうひとつの週末が来て、去ってゆくあいだに、宿はまた少しばかり客を迎えて活気づいた。
なかでも印象的だったのは、白髪の老夫婦とその子供夫婦、それから孫たちという家族連れで、とくにその老夫婦のほうだった。
老人のほうは堂々たる恰幅で、モーゼのようにゆたかな髭を生やし、細君のほうは少し茶色みの残った、長い波打つ髪を、髷にしないでうしろで一つに結んで垂らしていた。真っ白でしわくちゃで、ふしぎに美しい顔をしていた。
朝食のあいだ、彼らふたりは窓ぎわの特等席に陣取って、ゆっくりと時間をかけてもりもり食べ、孫たちがゆで卵を運んだり皿を拭いたりして給仕していた。
彼女のほう、ひどく痩せているのに、みごとな食べっぷりだった。
トーストにバターとジャムをごってりと載せ、お茶にはドボドボとクリームを注ぐ。
こんなに年とってから、平気でこんな山の中までやってきて、窓辺の席で豪勢な朝ごはん。
それはなにか、ふしぎに感動的な光景だった。
コテッジのすべての窓にかけられていた、同じ柄のきれいなカーテン。これについても書いておきたい。・・・
この色調もまた、リュウの山の上でのあの日々を思い起こすにつけ、さいしょに鮮やかによみがえってくるもののひとつなのだ。・・・
剥き出しのままの石壁に木の床の、質素なコテッジの内装に、その華やかな彩りは引き立ってよく映えた。
たてのストライプのなかに、幾何学もようとアラベスクを組み合わせたデザインで、色合いはステンドグラスのよう、オレンジがかった澄んだ赤に、深いマリンブルー、こくのある水色に、ぱっと目を引くあかるい黄緑色、そしてやわらかい卵色。・・・
くもり空の朝の薄あかりに、透かして見るとくっきりと際だって映え、ぱっきりとクリアな陽光のもとでも、それはそれでよく映えた。
朝、目を覚まして、そのぱっと明るい色を目にするだけで、ああ、まだここにいられるのだ!・・・ と、幸福な思いでいっぱいになった。・・・
滞在中、私を好きにさせておいてくれた、寛大な宿の老人。・・・
見たところそう頑健そうな体格ではないのだが、これが驚くべき健脚の持ち主である。
ひとり離れに寝起きして、朝は誰よりも早く起きだして、暖炉に火を焚きつける。床の掃除や、あれこれの仕事をすませたあと、今度は用足しや買い物や、あるいはシーツの束を洗濯屋に出したりなどするために、毎日徒歩で山を下ってゆくのだ。・・・
帰ってくると、その日見たもののあれこれや、このあたりの色んな場所について話してくれる。
この前のイースターの休暇には、歩いてスノウドンを踏破したそうである。・・・
夕方には谷をのぞむ庭の芝生に置かれた椅子に腰かけて、新聞のクロスワード・パズルをやっている。
私がこの谷の眺めをスケッチしていると、見にやってきて、感心した。
よかったら、できあがったら複写を送りましょうか、と言ったらとても喜んだ。
それでその年のクリスマス、それは私がくにへ帰ってからのことだったが、スケッチの複写とクリスマス・カードを送ると、彼もカードと手紙を送ってくれた。
ところがその手紙というのがたいへんに独特な筆記体で、残念ながら一部はいまだに解読できずにいる。・・・

3. 出発の日

ロウウェンを発つ日である。
村の家々、いくどか行き交ううち、目になつかしいものとなっていた、とりわけ美しい何軒かをスケッチして、色鉛筆で色を塗りたい、などと考えつつ、結局できないで終わってしまった。
一軒ずつ、今でも思い出す・・・
リュウのコテッジにはかなり長く過ごしたけれども、荷物をまとめて下りてくるときには、みどりの坂道が、苔むした岩々やしだの群れや斜めに生えた木々のこずえが、特別な力をもって引き留めようとして、立ち去り難かった。
タリヴァン山をくだりゆく、山の向こうから灰色の雲むらがみるみると掻き曇り、ああ、雨を降らせるな・・・と見ていて分かった、雲が冷たい空気を掻きたてるように、ぞくぞくと心掻きたてられて嬉しくなる・・・
ウェールズの山には雨が似合う。・・・

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇5 安らえぬ魂
次章 オグウェン篇1 魔の山
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
中島迂生ライブラリーへ戻る
2010年08月31日
安らえぬ魂
目次へ戻る
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇5
安らえぬ魂 Those Unrested Souls
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 当地の伝説と神話
2. <巨人とその犬>の物語に想う
3. <巨人とその妻>の物語に想う
4. 再びコンウィイへ
5. 羊たちと、鳥たちと
*******************************************
1. 当地の伝説と神話
それでこの山々のあいだには、これら安息を得ぬ魂が、今でも彷徨っているのだという。・・・
黒インキのフロッタージュ。・・・
ただこれらの日々、私がこの山の上にいた間にこの土地が私に聞かせてくれた物語ばかりでなく、ずっと以前からここに住んでいた人々のもとに、とうより語り伝えられてきた物語をも、ここで紹介しておくのはよいことだろう。・・・
次に引用するのは、宿の暖炉のマントルピースの上で見つけた、当地の伝説のいくつかをごくごく簡明にまとめたもので、それを私がざっと訳してみたものだ。
著者名も出典もなし。
それゆえ、ここにも載せようがない。・・・
伝説と神話
当地の風景を彩る変わった風物の由来を説明するために、いくつもの寓話が語り伝えられている。・・・
宿のうしろの丘のうえ、道より20ヤードばかりのところに、地面から60度の角度で突き出ている石があって、これはフォンヌ・ガウル、巨人の杖と呼ばれている。
ひとりの巨人とその犬が、山の上で羊を追っていた。あるとき、犬が、もうこれ以上羊を追うことはできないと言った。すると、巨人は怒って犬を殺そうと、持っていた杖を投げつけた。すると杖は石に変わってしまった。それは記憶と警告のしるしとして、今でもそこに残っている。・・・
もうひとつ岩があって、こちらはエスギッド・ガウル、巨人の靴と呼ばれている。
これは、巨人が怒って犬に自分の靴の片方を投げつけたのが石に変わったのだということである。
巨人とその犬は、暗くなったあと、今でもタリヴァン山の上を彷徨うのだと言われている。
そして星のない晩には、彼らの叫びが今でも聞こえてくるのだと。・・・
タリヴァン山についてはもうひとつの話がある。
ひとりの巨人とその妻が、新しい住みかを求めて南ウェールズの方からやって来た。
彼らは新しい家を建てるための材料をかついできた。
タリヴァン山のてっぺんに着いてひと休みしたとき、彼らは大きな島アングルシーに目を留めて、あれこそ求めていた約束の地だと考えた。
そこで彼らは喜びのあまり、もってきた材料すべてをその場に投げ出して、いっさんに駆けていった。・・・
それで、ドアの柱のための二つの石が<トズズー>と<カーロック>となり、別のいくつかの石は、<スル・プルフィアド>(飛び上がった場所)に落ちて、<バルクロディアドゥ・ガウレス>(巨人たちの、エプロンのひと抱え)となった。
彼らは、メナイ海峡を泳いで渡ろうとしたが、溺れて死んでしまった。
それで、彼らの幽霊はタリヴァン山に戻ってきて、がっかりして再び腰を下ろした。・・・
この宿の各部屋の扉には、彼らの記憶に敬意を表して、彼らの名がひとつずつ刻まれている。
それは、あなたがベッドの中でよく眠れるよう、そして夜の深みのなかで、これら安らえぬ魂があなたを悩ますことがないようにとはかってのことである。・・・
2. <巨人とその犬>の物語に想う
これらの物語は、もちろん前々からざっと目を通してはいたけれども、正直あまりよくできた話だとは思えなかった。
何より楽しくない・・・何でこんな楽しくない、救いのない話をわざわざ語り伝えてきたのか?・・・ それが当初の印象だった。・・・
けれども、少しばかりウェールズの歴史をかじったり、人から聞いたりしてみると、これらもまた、この土地の精霊たちの守り伝えてきた、ウェールズの人々の民俗的記憶なのだ、そのことが実感されてくる・・・
何度ここの人たちは侵略を受け、故郷の土地を追われ、痛めつけられ、追い立てられてきたことか。・・・
彼らは実に追われに追われてきた・・・巨人たちでさえもが。・・・犬が疲れ果て、それ以上働くことができなくなるまでに。・・・それでもなお、休むことは許されなかったのだ。・・・
山の上まで少し足をのばした日の次の日、日が暮れて、青いとばりがすっぽりと谷を覆うころ、老人と私は二人きりの食卓について粗末なスープをすすっていた。
「きのう、あんたが戻ってきたころ、ちょうど今くらい暗くなっていたよ」
窓辺のほうを見やりながら、老人が言った。
「あんた暗くなる前に戻るって言ってただろう。だから少し心配になってね」
ぽつりぽつりと言葉を交わしながら、我々はしずかにさじを運んだ。
ちょうど会話が途切れたとき、闇のなかで急に甲高い叫び声が上がった・・・クウェ~ッ、キェッキェッキェッキェッ!・・・ と、老人は手をとめて、一心に耳をすませた。
「あれ、聞こえるかい?・・・ フクロウだよ。仲間に呼びかけてるんだ」
私は少し驚いた。
「あれがフクロウ?・・・ ホッホーって鳴くんじゃなくて?」
「うん。あれはああいう種類のフクロウなんだ」
私もいっしょになって耳をすませた。何とも異様な響きだった。
そののちも、その奇妙なフクロウの呼び声は何度か聞いた。
夜、ひとりきりで床のなかにいて、真っ暗ななかでその声を聞いていると、当地の伝説の巨人やその犬の息づかいが、昼間日の光のもとにいるときよりもずっと身近に感じられてくるのだった。
星のないまっくらな晩、たぶん風も強くて、うずまく雲の群れが次々と不吉なマーブル模様を描いて低い空を流れ去ってゆく、それまでにもう来る日も来る日も休みなくずっと、彼らは羊を追いつづけてきた、故郷の土地を追いたてられ、そこにも休み場を得られぬままに、ごつごつと不毛なる山々の尾根をずっと。・・・
犬はもう疲れきっている、だらりと舌を垂らし、暗闇のなかで目を凝らしながら、それでも迷い出るもののないよう、あちこちと走りまわって羊たちを導きつづける・・・足どりは重く、鉛のようだ、動作も注意力も限界に近く、ほとんど朦朧として、ただ気力ばかりが支えるばかり・・・ ああ、またあのちびが道をそれて向こうの端へ下りやがった。また連れ戻しにいかなくては・・・ これで何度目になるだろう?・・・ 突然、犬は力尽きてへたりこんだ。主人はこれも半ば足を引きずりながら、それでもどんどん先へ進んでゆく、呼びかけようにも、もうその力もない・・・ と、主人が振り向いた。おい、何をしている?・・・ 早く来るんだ。・・・ 非情な言葉は振り下ろされた鞭のようだ。犬は声もなくあえぎ、さいごの力を振り絞って訴える、私にはもうこれ以上、一歩も進めません。・・・ 何だと。・・・巨人の形相が変わる、疲れ果てているのはみんな同じだ。犬のくせに生意気な口をきくな。・・・ 暗闇のなかで羊飼いの杖が投げつけられる、それは的をそれて地に落ち、たちまち石に変わってしまう。・・・ それ、ご覧なさい。犬はしずかに言う。私の言葉が間違っていなかった証拠です。・・・ けれどもいま、私はあなたとあなたの羊たちのために、あとわずかだけ、力を奮い起して働きましょう。・・・ こうして犬は立ち上がり、彼らは再び進んでいった。・・・
しばらくゆくうち、犬はまたもや、力と気力の限界が迫っているのを感じはじめる。・・・ 心臓はどくどくと波打って破れんばかり、びっこをひきひき、せいいっぱい進みつづけるが、どう頑張っても先をゆく主人とのあいだは開いてゆくばかりだ・・・ああ! あのおいぼれ羊め、また姿をくらましやがった。いったいどこへ・・・ 思うまもなく、犬は岩のあいだにくずおれる、きっとこのまま息絶える・・・ 主人は気づかずにどんどん行ってしまい、ずいぶん進んでから群れがついてこないのに気がついて、悪態をつきながら戻ってきた。・・・どういうつもりだ、この無精者めが!・・・ 分かってくださらないのですか、ご主人さま。私も羊たちも、もうこれが限界です。・・・ 返事の代わりにこんどは靴が飛んでくる、革製のどっしりと重い羊飼いの靴だ・・・ そしてこれも犬の傍らに落ちるとすぐさま岩に変わってしまう。それを見て、犬は点を仰いで声をあげた。・・・ あゝ、神々もご照覧あれ!・・・ 私のことばにうそ偽りはありませぬ。・・・ それでこんど、もう片方の靴も投げつけてごらんなさい、どうなるか分かったでしょう・・・ それでもいま、私はあなたとあなたの羊たちのために・・・働きましょう。・・・
こうして彼らは進んでいった。今や巨人は杖も失い、片足ははだしで歩かなければならない。よろめきよろめき、亡霊のような彼らの姿はタリヴァン山の尾根のうえを進んでゆき、やがて闇夜のかなたに見えなくなった。・・・ もしかすると、彼らのもろい肉体はとっくの昔にどこかの岩陰に打ち捨てられてしまっており、ひたすら進みゆくべき運命に定められたその姿はその幽霊であるのかもしれなかった。・・・
・・・それでこの山々のあいだには、これら安息を得ぬ魂がいまでも彷徨っているのだという・・・ たしかに夜中、風にギイギイときしむ石垣の木戸は苦しむ者のうめき声のようだし、暗闇のなかで、急に羊が悪夢にうなされて不気味にしわがれた声をあげるのは、何かに取り憑かれているせいに違いない。・・・ 屋根裏でカリカリとひそやかな音をたてているのはネズミかもしれないが、あるいはまた、雲に吹きちぎられてきれぎれの月あかりのなかで、尾根をいっさんに駆け去ってゆく羊飼いの犬の、四つ足の爪が、剥き出しの岩肌にあたる音とも聞こえるのだった・・・
3. <巨人とその妻>の物語に想う
そうか、やはりアングルシーなのだ・・・
それが二つめの物語にさいしょに目を通したとき、私の抱いた感慨だった。
アイルランドの人々にとってそれがタラの丘であり、湖上の島イニシュフリーであるように、ウェールズの人々にとってはアングルシーなのだ。
彼らのエルサレム、聖なる地。・・・
アーサー王が死んだあと、そのなきがらを魔法使いのマーリンが運んでいったのがかの地であるとも言われているその土地。・・・
彼らもまた追われてきたのだ・・・ 運試ししようと、自ら故郷をあとにしてきたわけではあるまい。
ウェールズにも、アイルランドにも、昔は巨人がたくさんいた。
けれども、これらの物語は彼らの栄華の終わり、彼ら力強い種族がまさに滅びゆかんとする時代に属するのだろう。・・・
幽霊になったらもう、身の重みを引きずることもなかろうに、それでも約束の地にたどりつくことは許されなかった。・・・
何でそれほどまでに、彼らの聖地は彼らを拒むのだろう?・・・ おそらくここにも、この地の人びとの苦い記憶が反映されているのだろう・・・
それゆえに当地では、夜中、嘆き苦しむ者の鋭い叫びが闇を切り裂いて上がり、人をベッドから飛び上がらせることがある・・・ そこにはぞっとするような、それでいてこちらの胸まで痛くさせるような、どうしようもない悲しみが。・・・ 叫び声はしばらくつづいてやみ、すると山のふもとの方で、似たような別の叫びがそれに応える・・・ あれは何かの夜の鳥かもしれなかった。けれども休みなき魂の叫びと考えるほうが、ずっと真に迫っていた。・・・
その晩、私はベッドのなかで寝つかれずに、ごうごうと窓辺にあたる風のひびきに耳を傾けていた。
いつのまにか寝入っていたのだろう、暗やみのなかでふと目を覚まして、なぜ目が覚めたのだろうと思った。
それから、まわりの奇妙なしずけさに気がついた・・・ たえず耳についたあの風が、どうしてかふっつりとやんでいた。
私はベッドから出て、窓のところへ行った。
雲のあいだから月の光がもれて、あたりにやわらかなあかるみを投げかけている。・・・
窓を開けると、ひんやりと冷たい空気だった。
私はしばらく頬を外気にさらし、谷間の夜のすがたを眺めた。
・・・と、そのとき、山の上のほうで何か大きなものの動く気配がした。
はじめは雲のかたまりがやってきたのかと思った。それから二つの大きな、人間に似た姿に気がついた。・・・
彼らは連れだって、堂々と上背をのばし、まっすぐに山を下ってやってきた。
男の方は、山岳地方の羊飼いが着るような長いマントを着て、腰のところに幅広い帯を締め、がっしりとした革長靴を履いていた。
女の方は、長い髪をして、首飾りと青い石の額飾りとをつけていた。・・・
宿の右手を通りすぎるとき、おぼろな月の光をまともに受けて、彼らふたりの顔が見えた。
両方とも、樫の木の彫刻のような、誇り高く気品のある顔だちをしていたが、同時に何かを一心にたずね求める、ものに憑かれたような表情を湛えていた。
それを求める心があまりにも強いので、ほとんど無表情に見えるほどだった。・・・
彼らは私の方へは目もくれずに通り過ぎて、どんどん山を下っていった。
彼らを見ていると、目の感覚がおかしくなったようで奇妙な感じだった。まわりのものの、いつも見慣れている大きさの比率とずれているからだ。
全く音もたてず、地を揺るがすこともなく、彼らはどんどん下っていった。
石垣も木立もこともなげに跨ぎ越えて、やがてせりあがった手前の斜面の向こうに見えなくなった。
寝しずまったロウウェンの村のハイ・ストリイトを抜けて、彼らは海辺の街道へ出たのだろうか。・・・
彼らはアングルシーへ向かったのだと私は思う。・・・いつまでも山の上で嘆いていることをやめて、もういちどやってみようと。・・・
私は彼らが、今度こそはそこへたどり着いたことを願う。とりわけ、今ではメナイ海峡に橋もかけられたことだし。・・・
願はくは彼らがそこに安住の地を得んことを。・・・
4. 再びコンウィイへ

今日は再び、山を下って辻馬車をつかまえて、コンウィイの町まで出た。買い物して、帰ってきたところだ・・・
食糧の蓄えがすっかり尽きてしまったので、買い出しに行かねばならなかったのと、発つ前にもういちどコンウィイの町を見たかったのだ。
うららかに晴れた明るい日だった・・・道ゆく景色はあいもかわらずのどかで美しい。
なだらかに盛り上がったヒースの丘々、しずかな水をたたえた湾のきらめき、ひっそりとした石造りの村々。・・・
コンウィイのあの城壁が見えてくると心が踊る、ふたたび狭い城門をくぐり抜けて、中世の町へ入る。・・・
郵便局で、このあたりの風景を描いた絵葉書を何枚か買い、それからこの町の歴史をまとめた手軽な小冊子も一冊見つけた。・・・
裏通りの見上げる家並も、うらぶれた風情ながらどこか絵のように味わいのある、路地をぶらぶら抜けてゆくと、どっしりと聳える大きな教会にゆきあたる。・・・
ヨットの帆の小さな白い三角形がたくさんうかぶ、湾をのぞむ小さなティールームでひと休みする、陽光のあふれる窓辺、こまかな花柄のティーセット、ここに時間はたゆたいまどろむ。・・・
大通りは陽気な避暑客でにぎわい、こう幾日もしずかな山の上で暮らした後だから、少し疲れてしまった。
そろそろわが隠れ居に引き上げようか。・・・
リュウのコテッジでは、特に滞在のあとの方では、かなり粗末な食事をしていた。
そもそも、いちどきに運べる重量に限りがあるので、はじめからそれほど大量の食糧を運べなかったのだ。
ケーキやビスケットのような嗜好品からまず尽きてゆき、それからパンがなくなり、しまいには前の滞在客が残していったオートミールや、宿で売ってくれる缶詰などで命をつないでいた。・・・
それでも、正直なところ、そう大して苦にはならなかった。
何といってもそれらの日々のあいだ、私は自分がいちばんいたいと望む場所にいたのだ。あの美しい谷をのぞむ、おぞらく世界でもっとも見晴らしのいい場所のひとつに。・・・人はめったにこんな幸運に恵まれるものではない・・・それで私は満足し、ほかには何も望まなかった。・・・
5. 羊たちと、鳥たちと
コテッジのまわりにわんさかいた羊たち。・・・
ウェールズでは、どこへ行っても羊がいる。
「土地がやせているからね。山ばかりだし・・・羊くらいしか養えないんじゃないかね」
子羊が小刻みな足どりで走ってゆくうしろ姿はたしかに愛らしい・・・ 思いのほか長い、もじゃもじゃした尻尾が足のあいだにまとわりつき、所在なげにぷらんぷらんと揺れて、何だか足が5本あるみたいだ。着ぐるみの尻尾みたいでもある。
トットットッとリズムよくゆれる、もこっとしたお尻もまた可愛らしい。・・・ことに旅の始めのほうでは、それは心和む光景である・・・大量の羊に食傷しはじめる前までは。・・・
羊たちはときどき互いに頭突きしてみたり、柵に体をこすりつけたり、柵のあいだからとなりの草地へ顔を突き出してみたり、草のつるを体にくっつけたまま引きずって歩いていたりする。
コテッジの庭にも侵入してきて、あざみの花の頭を食いちぎる。・・・
羊たち、彼らは全くキリスト教徒のようだ・・・
いつでも囲いの外に心惹かれていて、あらゆる機会をうかがってはとなりの牧草地へ味見をしにいきたがっているが、いざ自分の囲いを出てしまうと、外ではいつもびくびくしている・・・
外にいてちょっとでも何かが起こると、とたんに元の囲いへ、どうかして逃げ帰ろうとしてパニックを起こすのだ・・・
性格的には、犬にも似ている気がする。
一頭が鳴きだすと、連鎖反応でみんないっしょにメエメエ返事する、何がいったい問題なのかは、誰にも分かっていないらしい。・・・
一頭が走りだすと、つられてみんないっしょに走りだす。が、どこへ向かって、というのは決して考えない。・・・
子羊たちは四六時中母親にくっついて歩き、母親のすることを何でもその通り真似る。それについて、考えることも意識することもないらしい。・・・
母親が立ち止まれば彼らも立ち止まる。歩き出せばいっしょに歩きだす。
母親が草を食べだすと、彼らも食べだす。食べるのをやめて右を向けば、彼らもそろって右を向く。・・・
足を引きずって歩けば、みんな引きずって歩くし、母親が糞をすれば、みんなそろって糞をする。・・・
夕方になると、山の斜面はさまざまな調子のメエメエ声であふれ返る・・・
なかにひときわ、すっかり枯れた声を絶望的に張り上げて、なおも何かを訴えようとしているのがいる。
何をそんなに嘆くのだろう、私の子がいなくなってしまったの、そう言っているのかもしれない。・・・ほんのさっきまでとなりで草を食んでいたのに。・・・
メエエ、メエエ、だれか私の子を見なかった?・・・
この谷の周辺や丘々のあいだで見た、たくさんの色んな種類の鳥たち。・・・
さんざしの枝のあいだを陽気に飛び交わして歌うヒワやシジュウカラ、ぱっとあざやかなオレンジのチョッキのロビン。・・・
エナガにハトにセキレイ、これはせせらぎが近いからだろう・・・
カササギもカラスもいる。はるかな空にはトビや何かの猛禽類が舞っている・・・
ロウウェンの村の近くの、緑ゆたかな森の小道を歩いていて、拾ったヤマドリの尻尾の羽。
薄茶と焦げ茶のしましまの堂々たる尾羽で、2フィートもあろうか。
私はそれを持って帰り、それは今でも私の手元にある。主のヤマドリも悪くは思うまい。・・・
リュウのコテッジのまわりでとりわけ多いのはつばめだった。
ほとんどつばめしか見なかったような気がする。
軒先であれこれと囀りあい、まっさおな空をすいすいと飛びかすめる、するどい鋭角の、濃紺のシルエット、夏の光あふれるコンウィイ・ヴァリィには、つばめの姿がよく似合う。・・・

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇4 幻の雄鹿
次章 ロウウェン篇6 オズモンド姫の物語
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。
瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) ロウウェン篇5
安らえぬ魂 Those Unrested Souls
2006 by 中島 迂生 Ussay Nakajima

1. 当地の伝説と神話
2. <巨人とその犬>の物語に想う
3. <巨人とその妻>の物語に想う
4. 再びコンウィイへ
5. 羊たちと、鳥たちと
*******************************************
1. 当地の伝説と神話
それでこの山々のあいだには、これら安息を得ぬ魂が、今でも彷徨っているのだという。・・・
黒インキのフロッタージュ。・・・
ただこれらの日々、私がこの山の上にいた間にこの土地が私に聞かせてくれた物語ばかりでなく、ずっと以前からここに住んでいた人々のもとに、とうより語り伝えられてきた物語をも、ここで紹介しておくのはよいことだろう。・・・
次に引用するのは、宿の暖炉のマントルピースの上で見つけた、当地の伝説のいくつかをごくごく簡明にまとめたもので、それを私がざっと訳してみたものだ。
著者名も出典もなし。
それゆえ、ここにも載せようがない。・・・
伝説と神話
当地の風景を彩る変わった風物の由来を説明するために、いくつもの寓話が語り伝えられている。・・・
宿のうしろの丘のうえ、道より20ヤードばかりのところに、地面から60度の角度で突き出ている石があって、これはフォンヌ・ガウル、巨人の杖と呼ばれている。
ひとりの巨人とその犬が、山の上で羊を追っていた。あるとき、犬が、もうこれ以上羊を追うことはできないと言った。すると、巨人は怒って犬を殺そうと、持っていた杖を投げつけた。すると杖は石に変わってしまった。それは記憶と警告のしるしとして、今でもそこに残っている。・・・
もうひとつ岩があって、こちらはエスギッド・ガウル、巨人の靴と呼ばれている。
これは、巨人が怒って犬に自分の靴の片方を投げつけたのが石に変わったのだということである。
巨人とその犬は、暗くなったあと、今でもタリヴァン山の上を彷徨うのだと言われている。
そして星のない晩には、彼らの叫びが今でも聞こえてくるのだと。・・・
タリヴァン山についてはもうひとつの話がある。
ひとりの巨人とその妻が、新しい住みかを求めて南ウェールズの方からやって来た。
彼らは新しい家を建てるための材料をかついできた。
タリヴァン山のてっぺんに着いてひと休みしたとき、彼らは大きな島アングルシーに目を留めて、あれこそ求めていた約束の地だと考えた。
そこで彼らは喜びのあまり、もってきた材料すべてをその場に投げ出して、いっさんに駆けていった。・・・
それで、ドアの柱のための二つの石が<トズズー>と<カーロック>となり、別のいくつかの石は、<スル・プルフィアド>(飛び上がった場所)に落ちて、<バルクロディアドゥ・ガウレス>(巨人たちの、エプロンのひと抱え)となった。
彼らは、メナイ海峡を泳いで渡ろうとしたが、溺れて死んでしまった。
それで、彼らの幽霊はタリヴァン山に戻ってきて、がっかりして再び腰を下ろした。・・・
この宿の各部屋の扉には、彼らの記憶に敬意を表して、彼らの名がひとつずつ刻まれている。
それは、あなたがベッドの中でよく眠れるよう、そして夜の深みのなかで、これら安らえぬ魂があなたを悩ますことがないようにとはかってのことである。・・・
2. <巨人とその犬>の物語に想う
これらの物語は、もちろん前々からざっと目を通してはいたけれども、正直あまりよくできた話だとは思えなかった。
何より楽しくない・・・何でこんな楽しくない、救いのない話をわざわざ語り伝えてきたのか?・・・ それが当初の印象だった。・・・
けれども、少しばかりウェールズの歴史をかじったり、人から聞いたりしてみると、これらもまた、この土地の精霊たちの守り伝えてきた、ウェールズの人々の民俗的記憶なのだ、そのことが実感されてくる・・・
何度ここの人たちは侵略を受け、故郷の土地を追われ、痛めつけられ、追い立てられてきたことか。・・・
彼らは実に追われに追われてきた・・・巨人たちでさえもが。・・・犬が疲れ果て、それ以上働くことができなくなるまでに。・・・それでもなお、休むことは許されなかったのだ。・・・
山の上まで少し足をのばした日の次の日、日が暮れて、青いとばりがすっぽりと谷を覆うころ、老人と私は二人きりの食卓について粗末なスープをすすっていた。
「きのう、あんたが戻ってきたころ、ちょうど今くらい暗くなっていたよ」
窓辺のほうを見やりながら、老人が言った。
「あんた暗くなる前に戻るって言ってただろう。だから少し心配になってね」
ぽつりぽつりと言葉を交わしながら、我々はしずかにさじを運んだ。
ちょうど会話が途切れたとき、闇のなかで急に甲高い叫び声が上がった・・・クウェ~ッ、キェッキェッキェッキェッ!・・・ と、老人は手をとめて、一心に耳をすませた。
「あれ、聞こえるかい?・・・ フクロウだよ。仲間に呼びかけてるんだ」
私は少し驚いた。
「あれがフクロウ?・・・ ホッホーって鳴くんじゃなくて?」
「うん。あれはああいう種類のフクロウなんだ」
私もいっしょになって耳をすませた。何とも異様な響きだった。
そののちも、その奇妙なフクロウの呼び声は何度か聞いた。
夜、ひとりきりで床のなかにいて、真っ暗ななかでその声を聞いていると、当地の伝説の巨人やその犬の息づかいが、昼間日の光のもとにいるときよりもずっと身近に感じられてくるのだった。
星のないまっくらな晩、たぶん風も強くて、うずまく雲の群れが次々と不吉なマーブル模様を描いて低い空を流れ去ってゆく、それまでにもう来る日も来る日も休みなくずっと、彼らは羊を追いつづけてきた、故郷の土地を追いたてられ、そこにも休み場を得られぬままに、ごつごつと不毛なる山々の尾根をずっと。・・・
犬はもう疲れきっている、だらりと舌を垂らし、暗闇のなかで目を凝らしながら、それでも迷い出るもののないよう、あちこちと走りまわって羊たちを導きつづける・・・足どりは重く、鉛のようだ、動作も注意力も限界に近く、ほとんど朦朧として、ただ気力ばかりが支えるばかり・・・ ああ、またあのちびが道をそれて向こうの端へ下りやがった。また連れ戻しにいかなくては・・・ これで何度目になるだろう?・・・ 突然、犬は力尽きてへたりこんだ。主人はこれも半ば足を引きずりながら、それでもどんどん先へ進んでゆく、呼びかけようにも、もうその力もない・・・ と、主人が振り向いた。おい、何をしている?・・・ 早く来るんだ。・・・ 非情な言葉は振り下ろされた鞭のようだ。犬は声もなくあえぎ、さいごの力を振り絞って訴える、私にはもうこれ以上、一歩も進めません。・・・ 何だと。・・・巨人の形相が変わる、疲れ果てているのはみんな同じだ。犬のくせに生意気な口をきくな。・・・ 暗闇のなかで羊飼いの杖が投げつけられる、それは的をそれて地に落ち、たちまち石に変わってしまう。・・・ それ、ご覧なさい。犬はしずかに言う。私の言葉が間違っていなかった証拠です。・・・ けれどもいま、私はあなたとあなたの羊たちのために、あとわずかだけ、力を奮い起して働きましょう。・・・ こうして犬は立ち上がり、彼らは再び進んでいった。・・・
しばらくゆくうち、犬はまたもや、力と気力の限界が迫っているのを感じはじめる。・・・ 心臓はどくどくと波打って破れんばかり、びっこをひきひき、せいいっぱい進みつづけるが、どう頑張っても先をゆく主人とのあいだは開いてゆくばかりだ・・・ああ! あのおいぼれ羊め、また姿をくらましやがった。いったいどこへ・・・ 思うまもなく、犬は岩のあいだにくずおれる、きっとこのまま息絶える・・・ 主人は気づかずにどんどん行ってしまい、ずいぶん進んでから群れがついてこないのに気がついて、悪態をつきながら戻ってきた。・・・どういうつもりだ、この無精者めが!・・・ 分かってくださらないのですか、ご主人さま。私も羊たちも、もうこれが限界です。・・・ 返事の代わりにこんどは靴が飛んでくる、革製のどっしりと重い羊飼いの靴だ・・・ そしてこれも犬の傍らに落ちるとすぐさま岩に変わってしまう。それを見て、犬は点を仰いで声をあげた。・・・ あゝ、神々もご照覧あれ!・・・ 私のことばにうそ偽りはありませぬ。・・・ それでこんど、もう片方の靴も投げつけてごらんなさい、どうなるか分かったでしょう・・・ それでもいま、私はあなたとあなたの羊たちのために・・・働きましょう。・・・
こうして彼らは進んでいった。今や巨人は杖も失い、片足ははだしで歩かなければならない。よろめきよろめき、亡霊のような彼らの姿はタリヴァン山の尾根のうえを進んでゆき、やがて闇夜のかなたに見えなくなった。・・・ もしかすると、彼らのもろい肉体はとっくの昔にどこかの岩陰に打ち捨てられてしまっており、ひたすら進みゆくべき運命に定められたその姿はその幽霊であるのかもしれなかった。・・・
・・・それでこの山々のあいだには、これら安息を得ぬ魂がいまでも彷徨っているのだという・・・ たしかに夜中、風にギイギイときしむ石垣の木戸は苦しむ者のうめき声のようだし、暗闇のなかで、急に羊が悪夢にうなされて不気味にしわがれた声をあげるのは、何かに取り憑かれているせいに違いない。・・・ 屋根裏でカリカリとひそやかな音をたてているのはネズミかもしれないが、あるいはまた、雲に吹きちぎられてきれぎれの月あかりのなかで、尾根をいっさんに駆け去ってゆく羊飼いの犬の、四つ足の爪が、剥き出しの岩肌にあたる音とも聞こえるのだった・・・
3. <巨人とその妻>の物語に想う
そうか、やはりアングルシーなのだ・・・
それが二つめの物語にさいしょに目を通したとき、私の抱いた感慨だった。
アイルランドの人々にとってそれがタラの丘であり、湖上の島イニシュフリーであるように、ウェールズの人々にとってはアングルシーなのだ。
彼らのエルサレム、聖なる地。・・・
アーサー王が死んだあと、そのなきがらを魔法使いのマーリンが運んでいったのがかの地であるとも言われているその土地。・・・
彼らもまた追われてきたのだ・・・ 運試ししようと、自ら故郷をあとにしてきたわけではあるまい。
ウェールズにも、アイルランドにも、昔は巨人がたくさんいた。
けれども、これらの物語は彼らの栄華の終わり、彼ら力強い種族がまさに滅びゆかんとする時代に属するのだろう。・・・
幽霊になったらもう、身の重みを引きずることもなかろうに、それでも約束の地にたどりつくことは許されなかった。・・・
何でそれほどまでに、彼らの聖地は彼らを拒むのだろう?・・・ おそらくここにも、この地の人びとの苦い記憶が反映されているのだろう・・・
それゆえに当地では、夜中、嘆き苦しむ者の鋭い叫びが闇を切り裂いて上がり、人をベッドから飛び上がらせることがある・・・ そこにはぞっとするような、それでいてこちらの胸まで痛くさせるような、どうしようもない悲しみが。・・・ 叫び声はしばらくつづいてやみ、すると山のふもとの方で、似たような別の叫びがそれに応える・・・ あれは何かの夜の鳥かもしれなかった。けれども休みなき魂の叫びと考えるほうが、ずっと真に迫っていた。・・・
その晩、私はベッドのなかで寝つかれずに、ごうごうと窓辺にあたる風のひびきに耳を傾けていた。
いつのまにか寝入っていたのだろう、暗やみのなかでふと目を覚まして、なぜ目が覚めたのだろうと思った。
それから、まわりの奇妙なしずけさに気がついた・・・ たえず耳についたあの風が、どうしてかふっつりとやんでいた。
私はベッドから出て、窓のところへ行った。
雲のあいだから月の光がもれて、あたりにやわらかなあかるみを投げかけている。・・・
窓を開けると、ひんやりと冷たい空気だった。
私はしばらく頬を外気にさらし、谷間の夜のすがたを眺めた。
・・・と、そのとき、山の上のほうで何か大きなものの動く気配がした。
はじめは雲のかたまりがやってきたのかと思った。それから二つの大きな、人間に似た姿に気がついた。・・・
彼らは連れだって、堂々と上背をのばし、まっすぐに山を下ってやってきた。
男の方は、山岳地方の羊飼いが着るような長いマントを着て、腰のところに幅広い帯を締め、がっしりとした革長靴を履いていた。
女の方は、長い髪をして、首飾りと青い石の額飾りとをつけていた。・・・
宿の右手を通りすぎるとき、おぼろな月の光をまともに受けて、彼らふたりの顔が見えた。
両方とも、樫の木の彫刻のような、誇り高く気品のある顔だちをしていたが、同時に何かを一心にたずね求める、ものに憑かれたような表情を湛えていた。
それを求める心があまりにも強いので、ほとんど無表情に見えるほどだった。・・・
彼らは私の方へは目もくれずに通り過ぎて、どんどん山を下っていった。
彼らを見ていると、目の感覚がおかしくなったようで奇妙な感じだった。まわりのものの、いつも見慣れている大きさの比率とずれているからだ。
全く音もたてず、地を揺るがすこともなく、彼らはどんどん下っていった。
石垣も木立もこともなげに跨ぎ越えて、やがてせりあがった手前の斜面の向こうに見えなくなった。
寝しずまったロウウェンの村のハイ・ストリイトを抜けて、彼らは海辺の街道へ出たのだろうか。・・・
彼らはアングルシーへ向かったのだと私は思う。・・・いつまでも山の上で嘆いていることをやめて、もういちどやってみようと。・・・
私は彼らが、今度こそはそこへたどり着いたことを願う。とりわけ、今ではメナイ海峡に橋もかけられたことだし。・・・
願はくは彼らがそこに安住の地を得んことを。・・・
4. 再びコンウィイへ

今日は再び、山を下って辻馬車をつかまえて、コンウィイの町まで出た。買い物して、帰ってきたところだ・・・
食糧の蓄えがすっかり尽きてしまったので、買い出しに行かねばならなかったのと、発つ前にもういちどコンウィイの町を見たかったのだ。
うららかに晴れた明るい日だった・・・道ゆく景色はあいもかわらずのどかで美しい。
なだらかに盛り上がったヒースの丘々、しずかな水をたたえた湾のきらめき、ひっそりとした石造りの村々。・・・
コンウィイのあの城壁が見えてくると心が踊る、ふたたび狭い城門をくぐり抜けて、中世の町へ入る。・・・
郵便局で、このあたりの風景を描いた絵葉書を何枚か買い、それからこの町の歴史をまとめた手軽な小冊子も一冊見つけた。・・・
裏通りの見上げる家並も、うらぶれた風情ながらどこか絵のように味わいのある、路地をぶらぶら抜けてゆくと、どっしりと聳える大きな教会にゆきあたる。・・・
ヨットの帆の小さな白い三角形がたくさんうかぶ、湾をのぞむ小さなティールームでひと休みする、陽光のあふれる窓辺、こまかな花柄のティーセット、ここに時間はたゆたいまどろむ。・・・
大通りは陽気な避暑客でにぎわい、こう幾日もしずかな山の上で暮らした後だから、少し疲れてしまった。
そろそろわが隠れ居に引き上げようか。・・・
リュウのコテッジでは、特に滞在のあとの方では、かなり粗末な食事をしていた。
そもそも、いちどきに運べる重量に限りがあるので、はじめからそれほど大量の食糧を運べなかったのだ。
ケーキやビスケットのような嗜好品からまず尽きてゆき、それからパンがなくなり、しまいには前の滞在客が残していったオートミールや、宿で売ってくれる缶詰などで命をつないでいた。・・・
それでも、正直なところ、そう大して苦にはならなかった。
何といってもそれらの日々のあいだ、私は自分がいちばんいたいと望む場所にいたのだ。あの美しい谷をのぞむ、おぞらく世界でもっとも見晴らしのいい場所のひとつに。・・・人はめったにこんな幸運に恵まれるものではない・・・それで私は満足し、ほかには何も望まなかった。・・・
5. 羊たちと、鳥たちと
コテッジのまわりにわんさかいた羊たち。・・・
ウェールズでは、どこへ行っても羊がいる。
「土地がやせているからね。山ばかりだし・・・羊くらいしか養えないんじゃないかね」
子羊が小刻みな足どりで走ってゆくうしろ姿はたしかに愛らしい・・・ 思いのほか長い、もじゃもじゃした尻尾が足のあいだにまとわりつき、所在なげにぷらんぷらんと揺れて、何だか足が5本あるみたいだ。着ぐるみの尻尾みたいでもある。
トットットッとリズムよくゆれる、もこっとしたお尻もまた可愛らしい。・・・ことに旅の始めのほうでは、それは心和む光景である・・・大量の羊に食傷しはじめる前までは。・・・
羊たちはときどき互いに頭突きしてみたり、柵に体をこすりつけたり、柵のあいだからとなりの草地へ顔を突き出してみたり、草のつるを体にくっつけたまま引きずって歩いていたりする。
コテッジの庭にも侵入してきて、あざみの花の頭を食いちぎる。・・・
羊たち、彼らは全くキリスト教徒のようだ・・・
いつでも囲いの外に心惹かれていて、あらゆる機会をうかがってはとなりの牧草地へ味見をしにいきたがっているが、いざ自分の囲いを出てしまうと、外ではいつもびくびくしている・・・
外にいてちょっとでも何かが起こると、とたんに元の囲いへ、どうかして逃げ帰ろうとしてパニックを起こすのだ・・・
性格的には、犬にも似ている気がする。
一頭が鳴きだすと、連鎖反応でみんないっしょにメエメエ返事する、何がいったい問題なのかは、誰にも分かっていないらしい。・・・
一頭が走りだすと、つられてみんないっしょに走りだす。が、どこへ向かって、というのは決して考えない。・・・
子羊たちは四六時中母親にくっついて歩き、母親のすることを何でもその通り真似る。それについて、考えることも意識することもないらしい。・・・
母親が立ち止まれば彼らも立ち止まる。歩き出せばいっしょに歩きだす。
母親が草を食べだすと、彼らも食べだす。食べるのをやめて右を向けば、彼らもそろって右を向く。・・・
足を引きずって歩けば、みんな引きずって歩くし、母親が糞をすれば、みんなそろって糞をする。・・・
夕方になると、山の斜面はさまざまな調子のメエメエ声であふれ返る・・・
なかにひときわ、すっかり枯れた声を絶望的に張り上げて、なおも何かを訴えようとしているのがいる。
何をそんなに嘆くのだろう、私の子がいなくなってしまったの、そう言っているのかもしれない。・・・ほんのさっきまでとなりで草を食んでいたのに。・・・
メエエ、メエエ、だれか私の子を見なかった?・・・
この谷の周辺や丘々のあいだで見た、たくさんの色んな種類の鳥たち。・・・
さんざしの枝のあいだを陽気に飛び交わして歌うヒワやシジュウカラ、ぱっとあざやかなオレンジのチョッキのロビン。・・・
エナガにハトにセキレイ、これはせせらぎが近いからだろう・・・
カササギもカラスもいる。はるかな空にはトビや何かの猛禽類が舞っている・・・
ロウウェンの村の近くの、緑ゆたかな森の小道を歩いていて、拾ったヤマドリの尻尾の羽。
薄茶と焦げ茶のしましまの堂々たる尾羽で、2フィートもあろうか。
私はそれを持って帰り、それは今でも私の手元にある。主のヤマドリも悪くは思うまい。・・・
リュウのコテッジのまわりでとりわけ多いのはつばめだった。
ほとんどつばめしか見なかったような気がする。
軒先であれこれと囀りあい、まっさおな空をすいすいと飛びかすめる、するどい鋭角の、濃紺のシルエット、夏の光あふれるコンウィイ・ヴァリィには、つばめの姿がよく似合う。・・・

瑛瑠洲物語(うぇーるずものがたり) 目次へ戻る
前章 ロウウェン篇4 幻の雄鹿
次章 ロウウェン篇6 オズモンド姫の物語
瑛瑠洲情景(うぇーるず・じょうけい) コンウィイ谷からの風景スケッチなど。こちらもどうぞ。