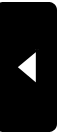2013年11月30日
創造的な不幸-24-
創造的な不幸-愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ-
この作品について 目次
-24- 沈みかけた船・エリオット論
そしてまさにこれが、形而上学的問題を事とする「キリスト教文化圏の」文学に親しめば親しむほどに、Aがどうしても払拭できなかった違和感の由来なのだ。
すなわち、おしなべて彼らの文章には、この世に腰を据えて勝負していこうという姿勢が明らかなのである。しかし、神の側に立ちながら尚この世に腰を据えて勝負するなんてことは、きわめて反キリスト教的な仮定--つまり、所詮終末なんてやって来はしないのだという仮定のもとにしかできはしないではないか。正統的な、つまり終末論的なキリスト教にあっては、文学をやることそのものが、内容どうこうではなく、文学それ自体がすでに罪なのである。なぜか? なぜなら、それは時間を取るからだ。
キリスト教にあっては、黙示録の巨人が断言したように、「もはや時間はない!」のだ。時間は、つまり、この世が存続を許されている時間、あと幾人かでも救い出して神の側に導くことのできる時間は、常に尽きようとしているのである。キリスト教にあっては、この世は常に、今にも沈みかけている巨大な船の如くである。たとえそれが過去二千年間沈みかけ続けているとしても、それは今でもやはり沈みかけているのだ。
そういうときになすべき人の務めとは、言うまでもなく、乗客全員のドアを片っ端からガンガン叩いてまわって事情を説明し、ともかくも救命ボートにひっぱりこんでやることである。悠長にカッサンドラの詩集を取り出して現代風にアレンジしてやろうなんて考えるのは、気違い沙汰だ。しかるに、「キリスト教文学」がやろうとしてきたのは、まさにそれである。
そう、ともかく危機が迫っていて、たくさんの人々の命が危険に曝されているのだ。ここは文学によってキリスト教理念を敷衍しようと呑気に構えている場合ではない。それゆえ終末論は物書きに対しても、詩だの批評だのにかかずらっているより、さっさと出掛けていって神の王国を宣べ伝えるべきことを指し示す。従って、もし文学なるものの役割が一国の文化を支えることにあるとすれば、キリスト教徒にとってそんなものはほとんど存在意義を持たないことになる。なぜなら、真のキリスト教徒はただ神の意志がなされることにのみ心を傾けるのであって、いかなる国家の存亡にも、いかなる文化のあり方にも、いかなる文学的価値にもさしたる注意を払わないからだ。実にこの恐るべき無関心こそが、キリスト教徒たちが国家に対して何ら実質的な危害を加えなかったにもかかわらず、ローマが彼らを弾圧したもっともな理由であった。エレミヤの時代に、神が書記官バルクに忠告したように--
「視よ われ我建てしところの者を毀ち 我植えしところの者を抜かん 是この全地なり 汝己の為に大なる事を求むるか これを求むる勿れ 視よ われ災をすべての民に降さん 然ど汝の生命は我汝のゆかん諸の處にて汝の掠物(ぶんどりもの)とならしめん」--Je45:4,5
そう、神は忠実な者に生命の救いを約束する。ただ生命の救いだけであって、我々がそれに劣らず(ひょっとしたら、それ以上に)重要なものと考えるかもしれないあらゆる文化や文学や芸術については、何の保証もなされていない。結局のところ我々すべては--キリスト教文化圏の人間であれ、非キリスト教文化圏の人間であれ--言わば文化的真空の中で神を求めなければならない。それは困難で、つらい生き方である。そもそも人間にそんなことができるのか? それでも尚、それが真実なのだ。
「汝ら 是はエホバの殿(みや=神殿)なり エホバの殿なり エホバの殿なりと云ふ偽りの言をたのむ勿れ」--Je7:4
それは古代イスラエルの時代に真実であったと同じく、今日においても尚真実なのだ。それがパウロの言葉--「見ゆるものは暫時(しばらく)にして、見えぬものは永遠(とこしへ)に至るなり」の意味するところである。--1Co4:18
* *
後期のエリオットには、この世に腰を据えて勝負していこうという姿勢が特に顕著である。それはもちろん、国教会的な<体制>についての彼の見方から来ているのだ。
エリオットは偉大なもの書きである--Aは彼から大いに学んできたし、偉大すぎて学び取れなかったことはもっとたくさんある。Aが文学だと思っていたものが<日の下における新しいもの>を創り出す冒瀆的な企てであったのに対し、彼なんかのそれが神に対していたく従順であり、それゆえに建設的であるのに、Aは感銘を受けたものだ。それでも尚、彼のキリスト教が終末論の教義を欠いていたために、その論理は避けがたくいくつかの重大な問題を抱えているのである。
例えば、<キリスト教社会の理念>。
それは今読んでも十分価値のある優れた文章である--エリオットの存在によって、そして特にあの時代にエリオットが存在したことによって、イギリス文化は計り知れない恩恵を受けたと思う。そもそも、もう二十世紀も半ばにきていたというのに、国家はキリスト教の上に築かれねばならないという主張が本気でなされ、しかもその主張が意味をなし得たというのはイギリス文化の驚くべき事実である。
しかしながら、ここで彼は少しく人間的な見方に傾いている。彼は終末を考えに含めない--それゆえ我々は、神の世ならぬこの世界がずっと続いていくことを前提に、何とか少しでも神に近づく努力を続けていくしかないのであり、いつまでたっても神が支配してくれないのであれば、結局は人間の支配とかかわらざるを得なくなるのだ。そして、彼の主張--国民の魂だとか品位だとか創造的活動力だとかを保つためにはキリスト教を選び取るしかない--は、一体キリスト教の方としてはそういうもののために選び取られることを許しているのかという問題を、ほとんど考えていない。しかし、神の第一の関心はすべての人間が一致して神を崇拝するということにあって、民族とか国家のアイデンティティーとかいう問題ではないではないか。
そして、こうして正確に神の見地から論じていないということから来る、さらに具体的な問題点がある。それは他でもない、自分の国が戦争をする段になったとき人はどうすべきか、という問題である。
「戦争はいかなる場合にも間違っていると主張する人は、何らかの意味で社会に対する義務を放棄していると私は信じざるを得ない。そしてその社会がキリスト教社会である限りその義務は一段と重要だ。・・・社会責任の観念--自分の属する社会の罪に対して各個人が責任を持つという考えは、もっとしっかりと把握する必要のある考えだ。<平和>のときに社会の罪に対して私にも責任があるとするならば、戦争のときに共同の行動から身を引くことによってその責任を免れることがどうしてできるのか私には分からない。」
ここで彼は主として自分がその理想として描写してきた<キリスト教社会>について語っているのだ。ところが、彼自ら認めるように、
「国家が非キリスト教的行動から暗々裡に非キリスト教的原則に基づく行動へと進み、ついで明白に非キリスト教的原則に基づく行動へと進んでいく傾向に対して我々は安全弁を持っていない。我々はキリスト教の純粋性を保つための安全弁を持っていないのだ」
となれば、今戦争を始めようとしており、自分がそれに参加するか否かの決断を迫られている自分の国が、そのために戦う価値があるほどにキリスト教的であるかどうかを、一体誰が判断するのであろうか? あるいは彼は、ある社会の中で生活して、その恩恵を受けている以上、その正当性いかんに関わりなく共同の行動に参加する義務があると考えているのかもしれない。しかしそれでは、正当なるものを支持し、間違ったものを退けるという神に対する道徳的義務はどうなるのであろうか?
これが、神とカエサルを混同することから生じてくるディレンマである。
一方、終末論を奉じるキリスト教徒の場合はどうか。彼らもまた、戦争はいかなる場合にも間違っているとは主張しない。彼らは神による戦争--ハルマゲドン--を支持する。しかし人間による戦争は支持しない。つまり彼らは良心的兵役拒否の立場を取る。そうすることによって彼らはもちろん社会的責任を放棄しているのだ。彼らは神を受け入れるために自分の文化や伝統すら放棄したのだ、どうしてその社会的責任までを放棄しないことがあろう。しかし彼らはカエサルによって実現することの決してない神の正義を支持しており、そのためにどんな犠牲をもいとわない覚悟ができているのだから、道徳的責任を放棄していることにはならないわけだ。
一体に、神の僕のこの世に対する態度というものはかくの如くである。常にそうだった--結局のところこの世はエデンの外において始まったのであり、そもそもの始まりからして神から疎外されているのだ。それで彼らはバビロンにとどまってその罪に対して責任を持つようにとは命ぜられず、却って、「彼女の罪に預かることを望まず、彼女と共に滅ぼされることを望まないなら、彼女から出よ」と命ぜられているのである。<キリスト教国家>において、事情は多少とも異なっただろうか? 彼らはエルサレムからも逃れよと命ぜられたのだ。
そして、神の裁きが人間の起こす戦争よりも寛容であるとはとても言いがたい--それは「老人も、若者も、処女も、小さな子供も、女たちも」食らい尽くす容赦ない剣なのであり、「エホバに打ち殺される者はその日、地の一方の果てから他方の果てにまで及ぶ」のだ。--Ez9,Je25:33
こうして明らかに神もまた、社会に対してその罪の責任を問うのである--カナンの日にそうであったように。
さて、<キリスト教社会の理念>において素描されているようなキリスト教と社会との関係の特色は、言わばモンテーニュ的な中庸と寛容と生ぬるさである。感動的な率直さをもってキリスト教が前面に押し出されたかと思うと、それがいよいよ力を発揮すべきところでは奇妙にも骨抜きにされてしまっている。こういう特色は、彼の文学観にも共通しているのである。
だが、先走りするのはやめて、その文学論を少し丁寧にたどってみよう。
キリスト教文化圏の非キリスト教的世界に向かって書かれた彼の説得は、確かに感動的である。
例えば彼の比較的短い文学論の一つ、<批評の機能>。
ここで彼が問題としているのは、価値、基準、正義である--「人それぞれに明確な態度を取るべきこと、そしてときには実際に一つのものを捨てて他のものを取らねばならない場合のあること」についてである。
ここで彼はミドゥルトン・マリーを引き合いに出す--「マリー氏が教えているのは、文学に対しても、またはその他のすべての事柄に対しても、少なくとも二つの態度があるが、我々はその両方を採るわけにはいかないということなのである」
そしてこの二つの態度というのは、我々は我々の外部にある権威に従うべきか、それとも我々自身の心内の声に耳を傾けるべきかということである。前者はキリスト教の本質であり、後者は別名を汎神論ないしは内なる神の教説という。それはつまり、我々は我々とは別個の何者かに従うべきか、あるいは自分の好き勝手にして構わないかという問題なのである。
エリオットはもちろん前者を採って、そして後者を痛烈に皮肉っている。我々自身は後者を採るのも自由であるし、そしてそれを貫くのは必ずしも容易ではないゆえに場合によってはりっぱなことであるとすら考えるかもしれない、ただ我々は、それでは神に受け入れられないということを知っておかなければならない。この点についての誤解から、内と外との悪しき混同が引き起こされてきたのである。
これに関してはチェスタトンも全く同意見であって、クエーカー教徒やストア派を批判したくだりで彼はこう書いている。
「心を照らすどんな光を想像してみたところで、こういう連中の言う『内なる光』なるものほど悪しきものはありえない。どんな宗教が恐ろしいと言ったところで、内なる神の崇拝ほど恐ろしい宗教は他にない。いやしくも人間を知っているほどの人ならば、これがどれほど恐ろしいものなのかも知っているはずだ。・・・誰かが内なる神を崇拝するということは、結局のところその誰かが誰か自身を信ずるということに終わるのだ。そんなものを信ずるくらいなら、すべからく太陽でも月でも崇拝すべきである。・・・猫でもワニでも、自分の家の近所にいるならば、そいつをつかまえて崇拝するがよい。ただ内なる神だけはよしたほうがよい。キリスト教がこの世に現れた第一の目的は、まさしくこのことを強烈に主張することに他ならなかったのだ。人間は、単に内を省みるばかりでなく、外を仰ぎ見、・・・神の軍隊と神の隊長の姿を見つめなければならぬのだ。・・・人間は厳然として外の光に目覚めたのだ。その光は太陽のようにうるわしく、月のごとく明らかで、軍規を押し立てて疾走する軍団にもまして恐るべき光であったのだ」--<正統とは何か>
そして、エリオットもまた(宗派は違うにせよ)同じくキリスト教徒だったのだから、彼の場合にも外の光、外部の権威とはキリスト教を意味したと考えてよいだろう。内なる神の信奉者たちを代弁して、彼はこんなふうに皮肉っている--
「もし何かが好きになったら、ただその事実だけで十分であり、・・・我々は好きになりたいと思っているものなら何でも好きになれるだけでなく、どういう勝手な理由で好きになっても構わないのである」
しかし、エリオットに言わせればこういう見方はもちろん間違っているのであり、それゆえ彼ははっきりと宣言する、
「・・・問題は・・・どういう態度が我々にとって自然であるとか、または容易であるとかいうことではなくて、どちらが正しいかということである。どちらか一方の態度の方が他方よりも望ましいか、さもなければどうでもよいかのどちらかである。しかし、かような選択がどうでもよいなどと、どうして言えるであろうか」
問題は、どちらが正しいかということである! 実に正論ではないか。
正否と好き嫌いの相克は、普遍にして永遠の問題である。Aはのちのち、文学とは関係のない文脈においてもこのあたりのエリオットの言葉をたびたび思い出したものだ。A自身は最終的に、チェスタトンとエリオットを向こうに回して正しいものを捨て、好きなものを取ったが、そうすることが正しいなどと考えはしなかった。
そう、正しいものと好きなものが一致すること--それはAもまた自身において試みて、ついに成し遂げられなかった難題である。<宗教と文学>という別の文章で、エリオットはさらにこの問題を取り上げている。
「文学評価のためには、我々は二つのこと、すなわち『我々は何を好むか』及び『我々は何を好むべきであるか』ということを、同時にはっきり知っておく必要がある。この両方を心得ているほど誠実な人はほとんどいない。第一の命題は我々が現に感じていることが何であるかを知ることである・・・。また第二の命題には、自分の及ばざるところを知るということも含まれている。なぜなら、我々はどうして好むべきなのかという理由を知っていなければ、何を好むべきかということが本当に分かるはずはないし、また好むべき理由を知るということは、同時に、我々が現在まだそれを好むようになっていない理由を知ることにもなるからである。・・・
「我々が現在何を好んでいるかということを知るのは、文章を読む者としての我々のつとめである。そして我々が何を好むべきであるかということを知るのは、文学の読者であると同時にキリスト教徒としての我々のつとめである。現に好んでいるものはすべて好むべきものと一致していると考えたりしないことが、誠意ある人間としての我々のつとめである。また、我々は好むべきものを実際今好んでいるなどと言わないようにすることが、誠意あるキリスト教徒としての我々のつとめである」
そう、キリスト教の最大の掟からしてそもそも(あなたは神を愛さなければならない、隣人を愛さなければならない)第一に、正しいことと我々の好むこととが(つまり、「愛する」と「なければならない」とが)一致する必要性、我々が正しいことを好むようになるべきことを強調しているのだ。それゆえ、この精神はすべての分野に敷衍されてしかるべきなのである。
しかしながら、こと文学に関して言えば、彼の意見は注意深く検討される必要がある。例えば、年代は前後するが<伝統と個人の才能>。ここにおいて、彼は注目すべき価値変換を試みている--
「我々はある詩人を称賛するにあたって、その作品のうちで、他の詩人に尤も似ていない面を強調しようとする傾向がある。詩人の作品におけるかような面あるいは部分に、個性的なもの、その詩人特有の本質があるように思い込むのである。・・・ところが、我々がかような偏見を持たずに詩人に近づきさえすれば、作品の最も優れた部分だけではなく、最も個性的な部分でさえも、往々にして彼の祖先たる過去の詩人たちがその不滅性を最も強く発揮している箇所に他ならないということが分かるであろう」
次いで彼は、<伝統>という言葉によって自分の意味するところを説明する--
「それは相続することのできないものであり、もし欲しければ、非常な努力をして獲得しなければならないものである。それはまず第一に歴史的意識を必要とするが、かような意識は、二十五才をすぎてもなお詩人でありたいと思う者にはほとんど欠くべからざるものであると言えよう。そしてこの歴史的意識は、過去せるものとしての過去の認識ではなく、過去が現在に生きているという認識を含んでいる。そしてそれは、人が創作するとき、単に自分が骨の髄まで現代人であるというだけでなく、ホーマー以来のヨーロッパ文学全体、及びその中に含まれる彼自身の国の文学全体が同時的に存在し、同時的な秩序を形成しているということを感じさせずにはおかないものなのである。かかる歴史的意識は時間的なものに対する意識であるとともに、時間を越えたものに対する意識であり、また時間的なものと時間を越えたものとを同時にとらえる意識でもあって、それが作家を伝統的にするのである。そしてそれは同時に、作家をして彼が時間の中で占める位置と、彼自身の属している時代を極めて鋭く意識せしめるものなのである」
「・・・詩人は、ヨーロッパの精神及び彼自身の国の精神--それが自分一人の精神よりもはるかに重要なものであることを彼はいつか学ぶであろうが--は、常に変化する精神であり、そしてかかる変化はその途上において何ものをも遺棄しない発展であるということ--言い換えれば、シェイクスピアもホーマーも、旧石器時代最後の画家が岩の壁面に描いた絵画も、朽ち果てさせないような発展であるということも知っていなければならない」
「・・・シェイクスピアは、大抵の人が大英博物館全体から得ることのできるのよりも、さらに本質的な歴史の知識をプルタークから学び取った。・・・強調すべきは、詩人は過去に対する意識を育成ないしは獲得し、生涯を通じてこの意識をたえず発達させなければならないということである。
「そうすることによって、詩人はその瞬間におけるあるがままの自己を、たえず自分より価値のあるものに委ねていることになるのである。芸術家の進歩とはまさにたえざる自己犠牲、すなわち常に個性を滅却することを指すのである」
たえざる自己犠牲と個性の滅却!
ここにおいて我々は、なぜ彼が文学という手段によっても人は神に仕え得ると考えたかを知るのである。そして、もちろんこういう主張は、我々は我々の内なる神ではなくて外部にある権威に規範を求めるべきであるという先の主張に関連している。それから、<批評の機能>において彼はその考えを要約して繰り返すのだが--
「私は・・・文学すなわち世界文学、ヨーロッパ文学、一国の文学というものを、個々の作家の書いた作品の寄せ集めとしてではなく、言わば『有機的全体』として、つまり個々の文学作品ならびに個々の芸術家の作品がそれとの関係において、しかもそれとの関係においてのみ、各自の意義を有するような一つの体系として考えていた。従って、芸術家の外部に彼が忠実に奉仕すべきなにものかが存在するわけであり、それは芸術家が彼独自の地位を獲得し確保するために自らを従わせ犠牲に供すべき神聖な義務なのである」
このあたりにきて、我々ははたと首を傾げ、この時点で彼が自分を本当にキリスト教的なもの書きと考えていたのかどうかを疑いはじめる。なぜなら、キリスト教徒がどうして「彼独自の地位を獲得し確保する」ことなんかを目的としてよいであろうか。それはキリスト教徒であることを踏み越えてしまった芸術家がすることではないのか。さらに--
「・・・たしかに芸術はそれ自身を越えた目的に奉仕するものであると言えるかもしれないが、芸術自体はそれらの目的を意識している必要はない。事実、芸術は、もろもろの価値理論によってその職務をどのように定義されるにしても、それを遂行するためには、かような目的に対して無関心である方がはるかによいのである」
ここに至って我々の疑いは決定的となる。仮にも芸術家であってしかも同時にキリスト教徒でありたいと望むなら、もちろん彼は自分の目的を強烈に意識していなければならないはずである。神の側を選び取ったり、罪と戦ったりするには、神や罪をまず意識していなければならない。キリスト教に欠かすべからざるは意識である。このことを無視すると、芸術はそれ自身を超越した神に奉仕する代わりに、それ自身を超越した悪魔に奉仕することになりかねない。現にそういうことはたびたび起こってきたのではなかったか。
どうもエリオットにはそういうところがある。<宗教と文学>においてもそうだが、彼は、必ずしも神の基準に従わない文学全般に対して、それ自体の存在意義というようなものを認めているのである。この寛容さが、エリオットが己れの教理体系の中に終末論を有していなかったことの必然的な結果であるわけだが--それにしても、それは「エホバと張り合う関係を一切認めない」と公言したエヒウの態度とは明らかに異なっているのである。
もっとも、気持ちは分かるという気がする。文筆業をなりわいとしていて、しかもそれに誇りを持っている場合、文学それ自身の存在意義というようなものを信じないでは、とてもやってゆけたものではない。モンテーニュ的な中庸は、彼のアイデンティティーが立ち往くための必要悪だったのかもしれない。
* *
そう、多くのキリスト教文化圏の文学が、キリスト教的であることを妨げている最大の問題とは、実にそれがキリスト教文化圏の中で生み出されてきたという事実そのものなのである。それは多くの場合、書き手のキリスト教についての意識がその属する文化の中で形成されてきたことを意味する。彼らのうちの実に多くは、世俗の抱く信仰をそのまま己れの信仰としてきた。例えば、シェイクスピアだってそうだった。
彼の作品はエリザベス朝の時代精神を、キリスト教とヒューマニズムが混ざり合って併存していた当時の文化状況をよく反映している--というのはよく言われる話だ。それゆえそれは当たり前のようにキリスト教の世界観を前提としていると同時にまた、人間の偉大さを称賛してもいる。迷信やギリシャ哲学やローマ神話なんかもたっぷりと取り込まれている。どこからどこまでが何なのか、よく分からない。だとしたら、キリスト教徒たるもの、それが確かにいくぶんキリスト教的であるからというので、あるいは単に、ヨーロッパ文学が今までに成し遂げたうちで最も偉大な仕事の一つだからというので、無批判にそれを受け入れてしまっていいものだろうか? 「汝らわが条例を守るべし 汝の家畜をして異類と交らしむべからず 異類の種をまぜて汝の田野に播くべからず 麻と毛をまじへたる衣服を身につくべからず」--Le19:19
いや、シェイクスピアくらいならまだよかったかもしれない。時代の神学をそのまま受け入れる精神は、十九世紀に至って世界が神を失ったとき、世界と一緒に信仰の暗礁に乗り上げてしまったのである。キルケゴールやチェスタトンが信仰を持ち続けることに成功し、少なくともその精神性においてはほぼ完璧にキリスト教的であることができたのは、彼らが、彼ら自身の信仰を確固として持っていたからであり、己れと世界とをはっきり区別すべきことを知っていたからである。そうすることを選ばないで、誠実にものを考え続けた人々は、結局のところ、十分にキリスト教的であり続けることができなかった。
ドストエフスキー。「自分は十九世紀の子供である--疑惑と不信の時代の子供である。信仰への渇望が強ければ強いほど、その反対の証拠が見えてくる」
そして苦悩の末、彼は「例えキリストが間違っているとしても自分はキリストを取る」と宣言するのだが--実際のところは、その言葉は彼のつもりに反して全く反キリスト教的なのである。
昔、ドストエフスキーのような、形而上学的苦悩にどっぷりつかった世界をAは遠くから眺めていて、ああいうのこそが世に認められる文学というものなのだと、一応知ってはいた。そして、そういう世界にできるだけ近づかないように用心していた。けれどもあとになって、改めてAは思う--あれほど何の役にも立たない、何の意味もない代物もないものだと。彼らはただ無様に苦しみ続けるばかりで、どこへ向かっても進んでゆかれない。読者を神へ導くことによって神にとって有用な者となることもなければ、芸術そのものの力を神のくびきから解き放してやることもできない。それゆえ、我々がどう生きたらいいのかを示すこともない。そういう文学が評価されているのは確かである。
「第一級の知性の試金石とは、二つの対立する考えを心に宿しながら、しかも尚十分に精神が機能し得るか否かにある」
と、例えばライオネル・トリリングは<リベラル・イマジネーション>の中で書いている。
「文化の本来の有り様は闘争である。あるいは少なくとも論争である。ディアレクティックでなければ文化は何物でもない。そして、いかなる文化においても、ディアレクティックの多くの部分を自らの内部に取り込んでいるある種の芸術家が存在する。彼らの意義と力とは矛盾においてこそ存するのであり、そういう芸術家は自国の文化の本質そのものを内部に宿していると言えよう」
彼はここで明らかに、そういう人々を、非難するのではなく讃えているのだ。自分の中で、二つの考えが対立し、相争うところのすべての作家たちを讃えている。ところで、そういう作家たちが<キリスト教的>であるなどということがありうるのか? キリスト教の本質とは、二つではなく、一つの考えだけを常に言いつづけることにあったのではないか?
これだから、キリスト教作家が文化と関わり合いになるとろくなことはないのだ。
たしかにドストエフスキーは矛盾の作家であった、浴室に女中を閉じ込めて強姦しておきながら、「もし真理を手にするに必要なだけの苦悶の定量を満たすために、子供たちが苦しまねばならないとしたら・・・」といった科白をイヴァン・カラマーゾフに吐かせることもできた。彼が実際に苦悩していたのも本当である。しかし、問題はそういうことではないのだ。そういう苦悩そのものに、どれだけの意味があるかということなのである。それは誰の役に立っているのか?
そういう苦悩はホーソンもまた共有している。彼の作品には、この時代の知性が否応なしに背負い込まされたこういうある種のニヒリズムが、埋めようのない深い絶望が陰を落としている。
彼は進歩の教説や科学万能主義に媚を売らなかった。彼は原罪を、人間のモータリティーを語るのをやめなかった。けれども彼の反キリスト教性は、もっと微妙な、それと判別しにくいかたちで現れている。彼の作品は、その絶望によって生じた虚を突くように、ヒューマニズムやロマンティシズムなどの反キリスト教的な価値がその中へひそかに持ち込まれるのを許しているのだ。というのは、どういうわけで彼は姦婦ヘスタをあれほどすばらしく魅力的に、英雄的なまでに力強く描くことができたのか。いやしくもキリスト教的であろうと努めるなら、書き手は恋の熱情の美しさを語っても、それが「間違った」種類の恋である場合、それを否定しなくてはならないのではないのか。
多くの書き手はこの問題に直面する--例えばアンナ・カレーニナはヘスタほど立派な女ではなかったかもしれないが、その作品においてトルストイが直面したのも同じ問題だった。そして、そこではプロット的には罪人たちを裁いても、心情的には彼らの側に傾いて語られているので、それはキリスト教的な文学と反キリスト教的なそれとの危うい境界線に立つことになったのである。罪に対する同情と、神の掟へのひそかな疑念--文学に対してその独自の立場なんかを与えてやったがさいご、こうしたものが滑り込んでくるのを、誰もとどめることはできない。
それはまた、多少事情は違うが、グリーンの<権力と栄光>に出てくる警部の人格者ぶりについても言えることである。
同じ本の別の文脈で、ウィスキー・プリーストが過去を回想する場面がある。「司祭は、壁に頭をもたせかけて、半ば目を閉じた--彼は昔の聖週のことを思い出していた。そのとき、詰め物をした張り子のユダの人形が鐘楼にぶらさげられ、その人形がゆれてドアから外にはみ出すと、子供たちがブリキ罐やがらがらでやかましい音をたてた。教区の真面目な老人たちは、ときどき、そうしたことはやめたほうがいいと反対した。『わが主の裏切り者』とはいえ、そんな人形にして吊り下げるのは冒瀆だと、彼らは言った。だが、彼はそれには何も答えないで、その習慣を続けさせた--世界の裏切り者が笑い物にされるのはいいことだ、と彼には思えたからだ。それをやめさせたりすると、彼を、神と戦った人--望みのない戦いで崇高な犠牲者となったプロメテウスのごとき人--として理想化することはあまりにも容易だったからだ。」
人はそれを聞いてびっくりするだろう--ユダがプロメテウスだって? ユダのこそこそした裏切りと、プロメテウスの雄々しい、悲劇的な力強さとに、一体どんな共通点があるというのか? それでも尚、共通点はあったのだ--なぜならば、彼らは共に、神に反逆する者だったのだから。
ここに文学の問題の根本がある。我々は人がどんなふうに描写されているかということと、彼が実際にどんな人間であるかということを区別しなければならないのだ。
<緋文字>のアンビギュイティー。この本については今までに膨大な量の注釈が書かれていて、ヘスタに関しても実に様々な立場から、いろんなことが言われている--彼女を悪魔呼ばわりしたD.H.ロレンスから、彼女にマグナ・マテルのアーキタイプを見い出したR.E.トッドまで。しかも、そのどれもがテクストの中に論拠を持っているのだ。想起せよ、ヘスタの精神性を描写するのに、書き手がいかに惜しみなく言葉を費やしたかを、にもかかわらず、結局のところ、ヘスタもディムズデールも架空の人物であり、ダビデやバテシバと違って実際にこの世に生きはしなかったことを。
キリスト教の大きな特色の一つは、それが人に決断を迫ることである。人は神の前における自分の立場に関して、曖昧なところを残しておくことを許されない。彼は神を取るのか、それとも拒むのか、どちらかにしなくてはならない。問題は、書き手がそのどちらの立場を取って書いているのか、はっきりしない場合なのである。一体彼は、自分の本に出てくる登場人物についてどう思っているのか、彼らを断罪しているのか、それとも賛美しているのか? 書き手には自分の立場を表明する道徳的責任があるのではないか?
<緋文字>を読みおえた者は、それによって己れの正邪についての感覚が揺らぎ、かき乱され、しかもそこへ何らの新しい秩序も与えられぬままに放っておかれているのを見い出す--精神衛生上、まこと望ましからぬ事態である。あの本が世に出たとき、華々しい賞賛とともに喧々囂々の非難が巻き起こったのはそういうわけなのだ。
あるいはまた、苦悩の意味をめぐって。
「苦悩はホーソンにおいては中心的で、それは共鳴をおこす手段以上のものである。教育的、懲罰的、因果応報的、償い的である。
『たしかに』と<緋文字>の終わり近くに、ヘスタはアーサーに言う、
『たしかに、私たちは、この悲しみをもって、互いの罪を贖いました』と」
--R.スチュアート<アメリカ文学とキリスト教>
しかし、死すべき人間が互いの罪を贖うなんてことが大体可能なのか? アーサーの苦悩が意味を持つのは、それが最後の最後になって、彼に神の側を選ばせるからである。従って、ヘスタもまた痛ましく苦悩したが、神を選ばなかった彼女の苦悩には、何の報酬も、埋め合わせもない。神に仕えんと欲する者の苦悩は、神の目にそれなりの価値を持つ--「あなたへの犠牲は砕かれた霊なのです・・・」--しかし、苦悩はそれだけでは用をなさない。最終的に献身を果たさない限り、それだけでは献身と、それに則った人生との代用にはならないのだ。
それでも尚、ホーソンはこうしたすべてのことを了解した上で書き続けたのだろう、という気がAにはする--それゆえに、彼の文章はあのような翳りを帯びたのであろうと。
ハーバート・リードもまた、彼の非宗教性には気づいていた。<緋文字>論の最後のところで引用したリードの注解の続き、有限性と無限性とを表現するための、宗教の必要性について述べた次の部分で彼はこう続けている--「ホーソンは、当然のことながらこの種の支えを欠いていた。それゆえに彼は例の代用物で凌がざるを得なかったのだ。そしてそれは彼の読者のうちの実に多くの者に、その弱点をさらけ出す結果になったのだが--その代用物とは、シンボリズムである。」続けて彼は、<緋文字>をその最も顕著な例として挙げているのだ。
Hawthorne, of course, lacked this support, and fell back on that substitute which has proved a weariness to so many of his readers--symbolism.
あるいはメルヴィル。彼の場合、絶望はさらに大きかった。
エルサレムへ旅行したとき、彼は聖地のあまりの荒廃ぶりに衝撃を受ける。彼の目にはその光景が、神を失ったヨーロッパ精神の痛々しい心象のように映るのだ。
「ニーバーやシュトラウスなんかくそくらえだ。彼らは我々から、人生の輝きを奪ったのだ。幻想を覚ましてやると言ったって、何がありがたいものか」
Heartly wish Niebuhr and Straus to the dogs. They have robbed us of the bloom. If they have undecieved anyone---no thanks to him.
そのよき友人であったホーソンは彼についてこう描写している--
「・・・どうして彼は・・・単調で陰鬱なこの砂漠を、性懲りもなく彷徨い続けるのだろう。私が彼を知ったとき以来、またそのずっと以前から、彼は彷徨い続けているのだ。彼は信仰を持つこともできず、不信仰に落ちつくこともできない。彼はまた、あまりにも正直で勇気がありすぎるので、どちらか一方に決めることもできないのだ」
<モービー・ディック>は、ギリシャ悲劇そのものである。どうしてヨーロッパ文学というのは、神に対する信仰を失うとおしなべてギリシャ悲劇的になるのだろう。それはたぶん、もはや傍らに神がいなくて、それでも道徳的に生きようとする場合、取り得るのはそういう生き方しかないからだ。それは、一人でできるから。
<モービー・ディック>は、はっきりと反キリスト教的である。
「メルヴィルは<モービー・ディック>を書き終えてのち、ホーソンにあてて、『私は罪深い本を(a wicked book)書き終わり、今は小羊のように汚れのない気持ちです』と書き送った。だが、もしもメルヴィルが自分の書いたものを正しいと感じていたなら、なぜ彼は<モービー・ディック>を『罪深い本』と呼んだのだろうか?
「あるいは罪深い主人公の本を書いたためかもしれない。確かに主人公はその罪深い行為のために罰せられる。だが、もし彼が英雄として、あるいは英雄みたいなものとして、同情的に、賛美するように描かれているとしたら? その場合は著者の目から見て『罪深い本』となるのだ。メルヴィルの場合は、『失楽園』のミルトンの場合を思い出させる。その詩のはじめの方ではセイタンが英雄的に見えるからである。事実、メルヴィルのエイハブの描写はしばしばミルトンのセイタンの描写をしのばせるようだ。両方とも堕ちたりといえども大天使のごとく、傷を負い、執念深く、復讐に一念を凝らした超英雄である。第二巻までの『失楽園』は罪深い本だと、ミルトンも考えたのではないだろうか? あの恐ろしい最初の幾つかの場面におけるセイタンの扱い方はあまりに同情的で、キリスト教的敬虔と厳密に一致しないのではないか? たぶんメルヴィルもエイハブの扱い方についてこういう気持ちを持ったであろう。」--<アメリカ文学とキリスト教>
Melville said to Hawthorne, after the completion of "Moby Dick", "I have written a wicked book, and feel as spotless as the lamb. "If Melville felt justified in what he had written, why did he call "Moby Dick" "a wicked book"?
Perhaps because he had written a book with a wicked protagonist. The protagonist, to be sure, is punished for his wickedness. Still, what if he is presented sympathetically, admiringly, as a hero, or something of a hero? Then perhaps the book becomes "a wicked book" in the eyes of its author. Melville's case recalls Milton's, in "Paradise Lost", where Satan appears in a heroic light in the early part of the poem. Melville's description of Ahab, in fact, often seems reminiscent of Milton's description of Satan. Both are superheroes, archangelic though fallen, battle-scarred, vindictive, bent on revenge. Might not Milton have thought that "Paradise Lost" through Book Two was a wicked book? Is not the treatment of Satan in those tremendous opening scenes too sympathetic to comport strictly with Christian piety? Possibly Melville felt this about his treatment of Ahab・・・
---R. Stewart, "American Literature And Christian Doctrine"
そういうギリシャ的精神は、例えば<ピエール>なんかにも共通している。もっとも彼がキリスト教的なものに反逆することはない--彼が戦いを挑むのは、社会的な慣習、虚偽の上に築かれた平安に対してである。
後にこれを映画化したレオス・カラックスは語っている--
「・・・彼はその重みを背負おうとするが、力がなくて小さいので失墜してしまう。しかし彼が悲劇の英雄になるのは、失墜しても運命を引き受けようとするからなのだ」
こうしてここにおいても、最も重要な主題は神の栄光なんかではなく、迷い悩みながらも孤独に戦い続ける魂の戦いであり、個人の尊厳である。ヨーロッパ文学の歴史の本質的な部分を成してきたのは実にこのようなテーマなのだ。
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
この作品について 目次
-24- 沈みかけた船・エリオット論
そしてまさにこれが、形而上学的問題を事とする「キリスト教文化圏の」文学に親しめば親しむほどに、Aがどうしても払拭できなかった違和感の由来なのだ。
すなわち、おしなべて彼らの文章には、この世に腰を据えて勝負していこうという姿勢が明らかなのである。しかし、神の側に立ちながら尚この世に腰を据えて勝負するなんてことは、きわめて反キリスト教的な仮定--つまり、所詮終末なんてやって来はしないのだという仮定のもとにしかできはしないではないか。正統的な、つまり終末論的なキリスト教にあっては、文学をやることそのものが、内容どうこうではなく、文学それ自体がすでに罪なのである。なぜか? なぜなら、それは時間を取るからだ。
キリスト教にあっては、黙示録の巨人が断言したように、「もはや時間はない!」のだ。時間は、つまり、この世が存続を許されている時間、あと幾人かでも救い出して神の側に導くことのできる時間は、常に尽きようとしているのである。キリスト教にあっては、この世は常に、今にも沈みかけている巨大な船の如くである。たとえそれが過去二千年間沈みかけ続けているとしても、それは今でもやはり沈みかけているのだ。
そういうときになすべき人の務めとは、言うまでもなく、乗客全員のドアを片っ端からガンガン叩いてまわって事情を説明し、ともかくも救命ボートにひっぱりこんでやることである。悠長にカッサンドラの詩集を取り出して現代風にアレンジしてやろうなんて考えるのは、気違い沙汰だ。しかるに、「キリスト教文学」がやろうとしてきたのは、まさにそれである。
そう、ともかく危機が迫っていて、たくさんの人々の命が危険に曝されているのだ。ここは文学によってキリスト教理念を敷衍しようと呑気に構えている場合ではない。それゆえ終末論は物書きに対しても、詩だの批評だのにかかずらっているより、さっさと出掛けていって神の王国を宣べ伝えるべきことを指し示す。従って、もし文学なるものの役割が一国の文化を支えることにあるとすれば、キリスト教徒にとってそんなものはほとんど存在意義を持たないことになる。なぜなら、真のキリスト教徒はただ神の意志がなされることにのみ心を傾けるのであって、いかなる国家の存亡にも、いかなる文化のあり方にも、いかなる文学的価値にもさしたる注意を払わないからだ。実にこの恐るべき無関心こそが、キリスト教徒たちが国家に対して何ら実質的な危害を加えなかったにもかかわらず、ローマが彼らを弾圧したもっともな理由であった。エレミヤの時代に、神が書記官バルクに忠告したように--
「視よ われ我建てしところの者を毀ち 我植えしところの者を抜かん 是この全地なり 汝己の為に大なる事を求むるか これを求むる勿れ 視よ われ災をすべての民に降さん 然ど汝の生命は我汝のゆかん諸の處にて汝の掠物(ぶんどりもの)とならしめん」--Je45:4,5
そう、神は忠実な者に生命の救いを約束する。ただ生命の救いだけであって、我々がそれに劣らず(ひょっとしたら、それ以上に)重要なものと考えるかもしれないあらゆる文化や文学や芸術については、何の保証もなされていない。結局のところ我々すべては--キリスト教文化圏の人間であれ、非キリスト教文化圏の人間であれ--言わば文化的真空の中で神を求めなければならない。それは困難で、つらい生き方である。そもそも人間にそんなことができるのか? それでも尚、それが真実なのだ。
「汝ら 是はエホバの殿(みや=神殿)なり エホバの殿なり エホバの殿なりと云ふ偽りの言をたのむ勿れ」--Je7:4
それは古代イスラエルの時代に真実であったと同じく、今日においても尚真実なのだ。それがパウロの言葉--「見ゆるものは暫時(しばらく)にして、見えぬものは永遠(とこしへ)に至るなり」の意味するところである。--1Co4:18
* *
後期のエリオットには、この世に腰を据えて勝負していこうという姿勢が特に顕著である。それはもちろん、国教会的な<体制>についての彼の見方から来ているのだ。
エリオットは偉大なもの書きである--Aは彼から大いに学んできたし、偉大すぎて学び取れなかったことはもっとたくさんある。Aが文学だと思っていたものが<日の下における新しいもの>を創り出す冒瀆的な企てであったのに対し、彼なんかのそれが神に対していたく従順であり、それゆえに建設的であるのに、Aは感銘を受けたものだ。それでも尚、彼のキリスト教が終末論の教義を欠いていたために、その論理は避けがたくいくつかの重大な問題を抱えているのである。
例えば、<キリスト教社会の理念>。
それは今読んでも十分価値のある優れた文章である--エリオットの存在によって、そして特にあの時代にエリオットが存在したことによって、イギリス文化は計り知れない恩恵を受けたと思う。そもそも、もう二十世紀も半ばにきていたというのに、国家はキリスト教の上に築かれねばならないという主張が本気でなされ、しかもその主張が意味をなし得たというのはイギリス文化の驚くべき事実である。
しかしながら、ここで彼は少しく人間的な見方に傾いている。彼は終末を考えに含めない--それゆえ我々は、神の世ならぬこの世界がずっと続いていくことを前提に、何とか少しでも神に近づく努力を続けていくしかないのであり、いつまでたっても神が支配してくれないのであれば、結局は人間の支配とかかわらざるを得なくなるのだ。そして、彼の主張--国民の魂だとか品位だとか創造的活動力だとかを保つためにはキリスト教を選び取るしかない--は、一体キリスト教の方としてはそういうもののために選び取られることを許しているのかという問題を、ほとんど考えていない。しかし、神の第一の関心はすべての人間が一致して神を崇拝するということにあって、民族とか国家のアイデンティティーとかいう問題ではないではないか。
そして、こうして正確に神の見地から論じていないということから来る、さらに具体的な問題点がある。それは他でもない、自分の国が戦争をする段になったとき人はどうすべきか、という問題である。
「戦争はいかなる場合にも間違っていると主張する人は、何らかの意味で社会に対する義務を放棄していると私は信じざるを得ない。そしてその社会がキリスト教社会である限りその義務は一段と重要だ。・・・社会責任の観念--自分の属する社会の罪に対して各個人が責任を持つという考えは、もっとしっかりと把握する必要のある考えだ。<平和>のときに社会の罪に対して私にも責任があるとするならば、戦争のときに共同の行動から身を引くことによってその責任を免れることがどうしてできるのか私には分からない。」
ここで彼は主として自分がその理想として描写してきた<キリスト教社会>について語っているのだ。ところが、彼自ら認めるように、
「国家が非キリスト教的行動から暗々裡に非キリスト教的原則に基づく行動へと進み、ついで明白に非キリスト教的原則に基づく行動へと進んでいく傾向に対して我々は安全弁を持っていない。我々はキリスト教の純粋性を保つための安全弁を持っていないのだ」
となれば、今戦争を始めようとしており、自分がそれに参加するか否かの決断を迫られている自分の国が、そのために戦う価値があるほどにキリスト教的であるかどうかを、一体誰が判断するのであろうか? あるいは彼は、ある社会の中で生活して、その恩恵を受けている以上、その正当性いかんに関わりなく共同の行動に参加する義務があると考えているのかもしれない。しかしそれでは、正当なるものを支持し、間違ったものを退けるという神に対する道徳的義務はどうなるのであろうか?
これが、神とカエサルを混同することから生じてくるディレンマである。
一方、終末論を奉じるキリスト教徒の場合はどうか。彼らもまた、戦争はいかなる場合にも間違っているとは主張しない。彼らは神による戦争--ハルマゲドン--を支持する。しかし人間による戦争は支持しない。つまり彼らは良心的兵役拒否の立場を取る。そうすることによって彼らはもちろん社会的責任を放棄しているのだ。彼らは神を受け入れるために自分の文化や伝統すら放棄したのだ、どうしてその社会的責任までを放棄しないことがあろう。しかし彼らはカエサルによって実現することの決してない神の正義を支持しており、そのためにどんな犠牲をもいとわない覚悟ができているのだから、道徳的責任を放棄していることにはならないわけだ。
一体に、神の僕のこの世に対する態度というものはかくの如くである。常にそうだった--結局のところこの世はエデンの外において始まったのであり、そもそもの始まりからして神から疎外されているのだ。それで彼らはバビロンにとどまってその罪に対して責任を持つようにとは命ぜられず、却って、「彼女の罪に預かることを望まず、彼女と共に滅ぼされることを望まないなら、彼女から出よ」と命ぜられているのである。<キリスト教国家>において、事情は多少とも異なっただろうか? 彼らはエルサレムからも逃れよと命ぜられたのだ。
そして、神の裁きが人間の起こす戦争よりも寛容であるとはとても言いがたい--それは「老人も、若者も、処女も、小さな子供も、女たちも」食らい尽くす容赦ない剣なのであり、「エホバに打ち殺される者はその日、地の一方の果てから他方の果てにまで及ぶ」のだ。--Ez9,Je25:33
こうして明らかに神もまた、社会に対してその罪の責任を問うのである--カナンの日にそうであったように。
さて、<キリスト教社会の理念>において素描されているようなキリスト教と社会との関係の特色は、言わばモンテーニュ的な中庸と寛容と生ぬるさである。感動的な率直さをもってキリスト教が前面に押し出されたかと思うと、それがいよいよ力を発揮すべきところでは奇妙にも骨抜きにされてしまっている。こういう特色は、彼の文学観にも共通しているのである。
だが、先走りするのはやめて、その文学論を少し丁寧にたどってみよう。
キリスト教文化圏の非キリスト教的世界に向かって書かれた彼の説得は、確かに感動的である。
例えば彼の比較的短い文学論の一つ、<批評の機能>。
ここで彼が問題としているのは、価値、基準、正義である--「人それぞれに明確な態度を取るべきこと、そしてときには実際に一つのものを捨てて他のものを取らねばならない場合のあること」についてである。
ここで彼はミドゥルトン・マリーを引き合いに出す--「マリー氏が教えているのは、文学に対しても、またはその他のすべての事柄に対しても、少なくとも二つの態度があるが、我々はその両方を採るわけにはいかないということなのである」
そしてこの二つの態度というのは、我々は我々の外部にある権威に従うべきか、それとも我々自身の心内の声に耳を傾けるべきかということである。前者はキリスト教の本質であり、後者は別名を汎神論ないしは内なる神の教説という。それはつまり、我々は我々とは別個の何者かに従うべきか、あるいは自分の好き勝手にして構わないかという問題なのである。
エリオットはもちろん前者を採って、そして後者を痛烈に皮肉っている。我々自身は後者を採るのも自由であるし、そしてそれを貫くのは必ずしも容易ではないゆえに場合によってはりっぱなことであるとすら考えるかもしれない、ただ我々は、それでは神に受け入れられないということを知っておかなければならない。この点についての誤解から、内と外との悪しき混同が引き起こされてきたのである。
これに関してはチェスタトンも全く同意見であって、クエーカー教徒やストア派を批判したくだりで彼はこう書いている。
「心を照らすどんな光を想像してみたところで、こういう連中の言う『内なる光』なるものほど悪しきものはありえない。どんな宗教が恐ろしいと言ったところで、内なる神の崇拝ほど恐ろしい宗教は他にない。いやしくも人間を知っているほどの人ならば、これがどれほど恐ろしいものなのかも知っているはずだ。・・・誰かが内なる神を崇拝するということは、結局のところその誰かが誰か自身を信ずるということに終わるのだ。そんなものを信ずるくらいなら、すべからく太陽でも月でも崇拝すべきである。・・・猫でもワニでも、自分の家の近所にいるならば、そいつをつかまえて崇拝するがよい。ただ内なる神だけはよしたほうがよい。キリスト教がこの世に現れた第一の目的は、まさしくこのことを強烈に主張することに他ならなかったのだ。人間は、単に内を省みるばかりでなく、外を仰ぎ見、・・・神の軍隊と神の隊長の姿を見つめなければならぬのだ。・・・人間は厳然として外の光に目覚めたのだ。その光は太陽のようにうるわしく、月のごとく明らかで、軍規を押し立てて疾走する軍団にもまして恐るべき光であったのだ」--<正統とは何か>
そして、エリオットもまた(宗派は違うにせよ)同じくキリスト教徒だったのだから、彼の場合にも外の光、外部の権威とはキリスト教を意味したと考えてよいだろう。内なる神の信奉者たちを代弁して、彼はこんなふうに皮肉っている--
「もし何かが好きになったら、ただその事実だけで十分であり、・・・我々は好きになりたいと思っているものなら何でも好きになれるだけでなく、どういう勝手な理由で好きになっても構わないのである」
しかし、エリオットに言わせればこういう見方はもちろん間違っているのであり、それゆえ彼ははっきりと宣言する、
「・・・問題は・・・どういう態度が我々にとって自然であるとか、または容易であるとかいうことではなくて、どちらが正しいかということである。どちらか一方の態度の方が他方よりも望ましいか、さもなければどうでもよいかのどちらかである。しかし、かような選択がどうでもよいなどと、どうして言えるであろうか」
問題は、どちらが正しいかということである! 実に正論ではないか。
正否と好き嫌いの相克は、普遍にして永遠の問題である。Aはのちのち、文学とは関係のない文脈においてもこのあたりのエリオットの言葉をたびたび思い出したものだ。A自身は最終的に、チェスタトンとエリオットを向こうに回して正しいものを捨て、好きなものを取ったが、そうすることが正しいなどと考えはしなかった。
そう、正しいものと好きなものが一致すること--それはAもまた自身において試みて、ついに成し遂げられなかった難題である。<宗教と文学>という別の文章で、エリオットはさらにこの問題を取り上げている。
「文学評価のためには、我々は二つのこと、すなわち『我々は何を好むか』及び『我々は何を好むべきであるか』ということを、同時にはっきり知っておく必要がある。この両方を心得ているほど誠実な人はほとんどいない。第一の命題は我々が現に感じていることが何であるかを知ることである・・・。また第二の命題には、自分の及ばざるところを知るということも含まれている。なぜなら、我々はどうして好むべきなのかという理由を知っていなければ、何を好むべきかということが本当に分かるはずはないし、また好むべき理由を知るということは、同時に、我々が現在まだそれを好むようになっていない理由を知ることにもなるからである。・・・
「我々が現在何を好んでいるかということを知るのは、文章を読む者としての我々のつとめである。そして我々が何を好むべきであるかということを知るのは、文学の読者であると同時にキリスト教徒としての我々のつとめである。現に好んでいるものはすべて好むべきものと一致していると考えたりしないことが、誠意ある人間としての我々のつとめである。また、我々は好むべきものを実際今好んでいるなどと言わないようにすることが、誠意あるキリスト教徒としての我々のつとめである」
そう、キリスト教の最大の掟からしてそもそも(あなたは神を愛さなければならない、隣人を愛さなければならない)第一に、正しいことと我々の好むこととが(つまり、「愛する」と「なければならない」とが)一致する必要性、我々が正しいことを好むようになるべきことを強調しているのだ。それゆえ、この精神はすべての分野に敷衍されてしかるべきなのである。
しかしながら、こと文学に関して言えば、彼の意見は注意深く検討される必要がある。例えば、年代は前後するが<伝統と個人の才能>。ここにおいて、彼は注目すべき価値変換を試みている--
「我々はある詩人を称賛するにあたって、その作品のうちで、他の詩人に尤も似ていない面を強調しようとする傾向がある。詩人の作品におけるかような面あるいは部分に、個性的なもの、その詩人特有の本質があるように思い込むのである。・・・ところが、我々がかような偏見を持たずに詩人に近づきさえすれば、作品の最も優れた部分だけではなく、最も個性的な部分でさえも、往々にして彼の祖先たる過去の詩人たちがその不滅性を最も強く発揮している箇所に他ならないということが分かるであろう」
次いで彼は、<伝統>という言葉によって自分の意味するところを説明する--
「それは相続することのできないものであり、もし欲しければ、非常な努力をして獲得しなければならないものである。それはまず第一に歴史的意識を必要とするが、かような意識は、二十五才をすぎてもなお詩人でありたいと思う者にはほとんど欠くべからざるものであると言えよう。そしてこの歴史的意識は、過去せるものとしての過去の認識ではなく、過去が現在に生きているという認識を含んでいる。そしてそれは、人が創作するとき、単に自分が骨の髄まで現代人であるというだけでなく、ホーマー以来のヨーロッパ文学全体、及びその中に含まれる彼自身の国の文学全体が同時的に存在し、同時的な秩序を形成しているということを感じさせずにはおかないものなのである。かかる歴史的意識は時間的なものに対する意識であるとともに、時間を越えたものに対する意識であり、また時間的なものと時間を越えたものとを同時にとらえる意識でもあって、それが作家を伝統的にするのである。そしてそれは同時に、作家をして彼が時間の中で占める位置と、彼自身の属している時代を極めて鋭く意識せしめるものなのである」
「・・・詩人は、ヨーロッパの精神及び彼自身の国の精神--それが自分一人の精神よりもはるかに重要なものであることを彼はいつか学ぶであろうが--は、常に変化する精神であり、そしてかかる変化はその途上において何ものをも遺棄しない発展であるということ--言い換えれば、シェイクスピアもホーマーも、旧石器時代最後の画家が岩の壁面に描いた絵画も、朽ち果てさせないような発展であるということも知っていなければならない」
「・・・シェイクスピアは、大抵の人が大英博物館全体から得ることのできるのよりも、さらに本質的な歴史の知識をプルタークから学び取った。・・・強調すべきは、詩人は過去に対する意識を育成ないしは獲得し、生涯を通じてこの意識をたえず発達させなければならないということである。
「そうすることによって、詩人はその瞬間におけるあるがままの自己を、たえず自分より価値のあるものに委ねていることになるのである。芸術家の進歩とはまさにたえざる自己犠牲、すなわち常に個性を滅却することを指すのである」
たえざる自己犠牲と個性の滅却!
ここにおいて我々は、なぜ彼が文学という手段によっても人は神に仕え得ると考えたかを知るのである。そして、もちろんこういう主張は、我々は我々の内なる神ではなくて外部にある権威に規範を求めるべきであるという先の主張に関連している。それから、<批評の機能>において彼はその考えを要約して繰り返すのだが--
「私は・・・文学すなわち世界文学、ヨーロッパ文学、一国の文学というものを、個々の作家の書いた作品の寄せ集めとしてではなく、言わば『有機的全体』として、つまり個々の文学作品ならびに個々の芸術家の作品がそれとの関係において、しかもそれとの関係においてのみ、各自の意義を有するような一つの体系として考えていた。従って、芸術家の外部に彼が忠実に奉仕すべきなにものかが存在するわけであり、それは芸術家が彼独自の地位を獲得し確保するために自らを従わせ犠牲に供すべき神聖な義務なのである」
このあたりにきて、我々ははたと首を傾げ、この時点で彼が自分を本当にキリスト教的なもの書きと考えていたのかどうかを疑いはじめる。なぜなら、キリスト教徒がどうして「彼独自の地位を獲得し確保する」ことなんかを目的としてよいであろうか。それはキリスト教徒であることを踏み越えてしまった芸術家がすることではないのか。さらに--
「・・・たしかに芸術はそれ自身を越えた目的に奉仕するものであると言えるかもしれないが、芸術自体はそれらの目的を意識している必要はない。事実、芸術は、もろもろの価値理論によってその職務をどのように定義されるにしても、それを遂行するためには、かような目的に対して無関心である方がはるかによいのである」
ここに至って我々の疑いは決定的となる。仮にも芸術家であってしかも同時にキリスト教徒でありたいと望むなら、もちろん彼は自分の目的を強烈に意識していなければならないはずである。神の側を選び取ったり、罪と戦ったりするには、神や罪をまず意識していなければならない。キリスト教に欠かすべからざるは意識である。このことを無視すると、芸術はそれ自身を超越した神に奉仕する代わりに、それ自身を超越した悪魔に奉仕することになりかねない。現にそういうことはたびたび起こってきたのではなかったか。
どうもエリオットにはそういうところがある。<宗教と文学>においてもそうだが、彼は、必ずしも神の基準に従わない文学全般に対して、それ自体の存在意義というようなものを認めているのである。この寛容さが、エリオットが己れの教理体系の中に終末論を有していなかったことの必然的な結果であるわけだが--それにしても、それは「エホバと張り合う関係を一切認めない」と公言したエヒウの態度とは明らかに異なっているのである。
もっとも、気持ちは分かるという気がする。文筆業をなりわいとしていて、しかもそれに誇りを持っている場合、文学それ自身の存在意義というようなものを信じないでは、とてもやってゆけたものではない。モンテーニュ的な中庸は、彼のアイデンティティーが立ち往くための必要悪だったのかもしれない。
* *
そう、多くのキリスト教文化圏の文学が、キリスト教的であることを妨げている最大の問題とは、実にそれがキリスト教文化圏の中で生み出されてきたという事実そのものなのである。それは多くの場合、書き手のキリスト教についての意識がその属する文化の中で形成されてきたことを意味する。彼らのうちの実に多くは、世俗の抱く信仰をそのまま己れの信仰としてきた。例えば、シェイクスピアだってそうだった。
彼の作品はエリザベス朝の時代精神を、キリスト教とヒューマニズムが混ざり合って併存していた当時の文化状況をよく反映している--というのはよく言われる話だ。それゆえそれは当たり前のようにキリスト教の世界観を前提としていると同時にまた、人間の偉大さを称賛してもいる。迷信やギリシャ哲学やローマ神話なんかもたっぷりと取り込まれている。どこからどこまでが何なのか、よく分からない。だとしたら、キリスト教徒たるもの、それが確かにいくぶんキリスト教的であるからというので、あるいは単に、ヨーロッパ文学が今までに成し遂げたうちで最も偉大な仕事の一つだからというので、無批判にそれを受け入れてしまっていいものだろうか? 「汝らわが条例を守るべし 汝の家畜をして異類と交らしむべからず 異類の種をまぜて汝の田野に播くべからず 麻と毛をまじへたる衣服を身につくべからず」--Le19:19
いや、シェイクスピアくらいならまだよかったかもしれない。時代の神学をそのまま受け入れる精神は、十九世紀に至って世界が神を失ったとき、世界と一緒に信仰の暗礁に乗り上げてしまったのである。キルケゴールやチェスタトンが信仰を持ち続けることに成功し、少なくともその精神性においてはほぼ完璧にキリスト教的であることができたのは、彼らが、彼ら自身の信仰を確固として持っていたからであり、己れと世界とをはっきり区別すべきことを知っていたからである。そうすることを選ばないで、誠実にものを考え続けた人々は、結局のところ、十分にキリスト教的であり続けることができなかった。
ドストエフスキー。「自分は十九世紀の子供である--疑惑と不信の時代の子供である。信仰への渇望が強ければ強いほど、その反対の証拠が見えてくる」
そして苦悩の末、彼は「例えキリストが間違っているとしても自分はキリストを取る」と宣言するのだが--実際のところは、その言葉は彼のつもりに反して全く反キリスト教的なのである。
昔、ドストエフスキーのような、形而上学的苦悩にどっぷりつかった世界をAは遠くから眺めていて、ああいうのこそが世に認められる文学というものなのだと、一応知ってはいた。そして、そういう世界にできるだけ近づかないように用心していた。けれどもあとになって、改めてAは思う--あれほど何の役にも立たない、何の意味もない代物もないものだと。彼らはただ無様に苦しみ続けるばかりで、どこへ向かっても進んでゆかれない。読者を神へ導くことによって神にとって有用な者となることもなければ、芸術そのものの力を神のくびきから解き放してやることもできない。それゆえ、我々がどう生きたらいいのかを示すこともない。そういう文学が評価されているのは確かである。
「第一級の知性の試金石とは、二つの対立する考えを心に宿しながら、しかも尚十分に精神が機能し得るか否かにある」
と、例えばライオネル・トリリングは<リベラル・イマジネーション>の中で書いている。
「文化の本来の有り様は闘争である。あるいは少なくとも論争である。ディアレクティックでなければ文化は何物でもない。そして、いかなる文化においても、ディアレクティックの多くの部分を自らの内部に取り込んでいるある種の芸術家が存在する。彼らの意義と力とは矛盾においてこそ存するのであり、そういう芸術家は自国の文化の本質そのものを内部に宿していると言えよう」
彼はここで明らかに、そういう人々を、非難するのではなく讃えているのだ。自分の中で、二つの考えが対立し、相争うところのすべての作家たちを讃えている。ところで、そういう作家たちが<キリスト教的>であるなどということがありうるのか? キリスト教の本質とは、二つではなく、一つの考えだけを常に言いつづけることにあったのではないか?
これだから、キリスト教作家が文化と関わり合いになるとろくなことはないのだ。
たしかにドストエフスキーは矛盾の作家であった、浴室に女中を閉じ込めて強姦しておきながら、「もし真理を手にするに必要なだけの苦悶の定量を満たすために、子供たちが苦しまねばならないとしたら・・・」といった科白をイヴァン・カラマーゾフに吐かせることもできた。彼が実際に苦悩していたのも本当である。しかし、問題はそういうことではないのだ。そういう苦悩そのものに、どれだけの意味があるかということなのである。それは誰の役に立っているのか?
そういう苦悩はホーソンもまた共有している。彼の作品には、この時代の知性が否応なしに背負い込まされたこういうある種のニヒリズムが、埋めようのない深い絶望が陰を落としている。
彼は進歩の教説や科学万能主義に媚を売らなかった。彼は原罪を、人間のモータリティーを語るのをやめなかった。けれども彼の反キリスト教性は、もっと微妙な、それと判別しにくいかたちで現れている。彼の作品は、その絶望によって生じた虚を突くように、ヒューマニズムやロマンティシズムなどの反キリスト教的な価値がその中へひそかに持ち込まれるのを許しているのだ。というのは、どういうわけで彼は姦婦ヘスタをあれほどすばらしく魅力的に、英雄的なまでに力強く描くことができたのか。いやしくもキリスト教的であろうと努めるなら、書き手は恋の熱情の美しさを語っても、それが「間違った」種類の恋である場合、それを否定しなくてはならないのではないのか。
多くの書き手はこの問題に直面する--例えばアンナ・カレーニナはヘスタほど立派な女ではなかったかもしれないが、その作品においてトルストイが直面したのも同じ問題だった。そして、そこではプロット的には罪人たちを裁いても、心情的には彼らの側に傾いて語られているので、それはキリスト教的な文学と反キリスト教的なそれとの危うい境界線に立つことになったのである。罪に対する同情と、神の掟へのひそかな疑念--文学に対してその独自の立場なんかを与えてやったがさいご、こうしたものが滑り込んでくるのを、誰もとどめることはできない。
それはまた、多少事情は違うが、グリーンの<権力と栄光>に出てくる警部の人格者ぶりについても言えることである。
同じ本の別の文脈で、ウィスキー・プリーストが過去を回想する場面がある。「司祭は、壁に頭をもたせかけて、半ば目を閉じた--彼は昔の聖週のことを思い出していた。そのとき、詰め物をした張り子のユダの人形が鐘楼にぶらさげられ、その人形がゆれてドアから外にはみ出すと、子供たちがブリキ罐やがらがらでやかましい音をたてた。教区の真面目な老人たちは、ときどき、そうしたことはやめたほうがいいと反対した。『わが主の裏切り者』とはいえ、そんな人形にして吊り下げるのは冒瀆だと、彼らは言った。だが、彼はそれには何も答えないで、その習慣を続けさせた--世界の裏切り者が笑い物にされるのはいいことだ、と彼には思えたからだ。それをやめさせたりすると、彼を、神と戦った人--望みのない戦いで崇高な犠牲者となったプロメテウスのごとき人--として理想化することはあまりにも容易だったからだ。」
人はそれを聞いてびっくりするだろう--ユダがプロメテウスだって? ユダのこそこそした裏切りと、プロメテウスの雄々しい、悲劇的な力強さとに、一体どんな共通点があるというのか? それでも尚、共通点はあったのだ--なぜならば、彼らは共に、神に反逆する者だったのだから。
ここに文学の問題の根本がある。我々は人がどんなふうに描写されているかということと、彼が実際にどんな人間であるかということを区別しなければならないのだ。
<緋文字>のアンビギュイティー。この本については今までに膨大な量の注釈が書かれていて、ヘスタに関しても実に様々な立場から、いろんなことが言われている--彼女を悪魔呼ばわりしたD.H.ロレンスから、彼女にマグナ・マテルのアーキタイプを見い出したR.E.トッドまで。しかも、そのどれもがテクストの中に論拠を持っているのだ。想起せよ、ヘスタの精神性を描写するのに、書き手がいかに惜しみなく言葉を費やしたかを、にもかかわらず、結局のところ、ヘスタもディムズデールも架空の人物であり、ダビデやバテシバと違って実際にこの世に生きはしなかったことを。
キリスト教の大きな特色の一つは、それが人に決断を迫ることである。人は神の前における自分の立場に関して、曖昧なところを残しておくことを許されない。彼は神を取るのか、それとも拒むのか、どちらかにしなくてはならない。問題は、書き手がそのどちらの立場を取って書いているのか、はっきりしない場合なのである。一体彼は、自分の本に出てくる登場人物についてどう思っているのか、彼らを断罪しているのか、それとも賛美しているのか? 書き手には自分の立場を表明する道徳的責任があるのではないか?
<緋文字>を読みおえた者は、それによって己れの正邪についての感覚が揺らぎ、かき乱され、しかもそこへ何らの新しい秩序も与えられぬままに放っておかれているのを見い出す--精神衛生上、まこと望ましからぬ事態である。あの本が世に出たとき、華々しい賞賛とともに喧々囂々の非難が巻き起こったのはそういうわけなのだ。
あるいはまた、苦悩の意味をめぐって。
「苦悩はホーソンにおいては中心的で、それは共鳴をおこす手段以上のものである。教育的、懲罰的、因果応報的、償い的である。
『たしかに』と<緋文字>の終わり近くに、ヘスタはアーサーに言う、
『たしかに、私たちは、この悲しみをもって、互いの罪を贖いました』と」
--R.スチュアート<アメリカ文学とキリスト教>
しかし、死すべき人間が互いの罪を贖うなんてことが大体可能なのか? アーサーの苦悩が意味を持つのは、それが最後の最後になって、彼に神の側を選ばせるからである。従って、ヘスタもまた痛ましく苦悩したが、神を選ばなかった彼女の苦悩には、何の報酬も、埋め合わせもない。神に仕えんと欲する者の苦悩は、神の目にそれなりの価値を持つ--「あなたへの犠牲は砕かれた霊なのです・・・」--しかし、苦悩はそれだけでは用をなさない。最終的に献身を果たさない限り、それだけでは献身と、それに則った人生との代用にはならないのだ。
それでも尚、ホーソンはこうしたすべてのことを了解した上で書き続けたのだろう、という気がAにはする--それゆえに、彼の文章はあのような翳りを帯びたのであろうと。
ハーバート・リードもまた、彼の非宗教性には気づいていた。<緋文字>論の最後のところで引用したリードの注解の続き、有限性と無限性とを表現するための、宗教の必要性について述べた次の部分で彼はこう続けている--「ホーソンは、当然のことながらこの種の支えを欠いていた。それゆえに彼は例の代用物で凌がざるを得なかったのだ。そしてそれは彼の読者のうちの実に多くの者に、その弱点をさらけ出す結果になったのだが--その代用物とは、シンボリズムである。」続けて彼は、<緋文字>をその最も顕著な例として挙げているのだ。
Hawthorne, of course, lacked this support, and fell back on that substitute which has proved a weariness to so many of his readers--symbolism.
あるいはメルヴィル。彼の場合、絶望はさらに大きかった。
エルサレムへ旅行したとき、彼は聖地のあまりの荒廃ぶりに衝撃を受ける。彼の目にはその光景が、神を失ったヨーロッパ精神の痛々しい心象のように映るのだ。
「ニーバーやシュトラウスなんかくそくらえだ。彼らは我々から、人生の輝きを奪ったのだ。幻想を覚ましてやると言ったって、何がありがたいものか」
Heartly wish Niebuhr and Straus to the dogs. They have robbed us of the bloom. If they have undecieved anyone---no thanks to him.
そのよき友人であったホーソンは彼についてこう描写している--
「・・・どうして彼は・・・単調で陰鬱なこの砂漠を、性懲りもなく彷徨い続けるのだろう。私が彼を知ったとき以来、またそのずっと以前から、彼は彷徨い続けているのだ。彼は信仰を持つこともできず、不信仰に落ちつくこともできない。彼はまた、あまりにも正直で勇気がありすぎるので、どちらか一方に決めることもできないのだ」
<モービー・ディック>は、ギリシャ悲劇そのものである。どうしてヨーロッパ文学というのは、神に対する信仰を失うとおしなべてギリシャ悲劇的になるのだろう。それはたぶん、もはや傍らに神がいなくて、それでも道徳的に生きようとする場合、取り得るのはそういう生き方しかないからだ。それは、一人でできるから。
<モービー・ディック>は、はっきりと反キリスト教的である。
「メルヴィルは<モービー・ディック>を書き終えてのち、ホーソンにあてて、『私は罪深い本を(a wicked book)書き終わり、今は小羊のように汚れのない気持ちです』と書き送った。だが、もしもメルヴィルが自分の書いたものを正しいと感じていたなら、なぜ彼は<モービー・ディック>を『罪深い本』と呼んだのだろうか?
「あるいは罪深い主人公の本を書いたためかもしれない。確かに主人公はその罪深い行為のために罰せられる。だが、もし彼が英雄として、あるいは英雄みたいなものとして、同情的に、賛美するように描かれているとしたら? その場合は著者の目から見て『罪深い本』となるのだ。メルヴィルの場合は、『失楽園』のミルトンの場合を思い出させる。その詩のはじめの方ではセイタンが英雄的に見えるからである。事実、メルヴィルのエイハブの描写はしばしばミルトンのセイタンの描写をしのばせるようだ。両方とも堕ちたりといえども大天使のごとく、傷を負い、執念深く、復讐に一念を凝らした超英雄である。第二巻までの『失楽園』は罪深い本だと、ミルトンも考えたのではないだろうか? あの恐ろしい最初の幾つかの場面におけるセイタンの扱い方はあまりに同情的で、キリスト教的敬虔と厳密に一致しないのではないか? たぶんメルヴィルもエイハブの扱い方についてこういう気持ちを持ったであろう。」--<アメリカ文学とキリスト教>
Melville said to Hawthorne, after the completion of "Moby Dick", "I have written a wicked book, and feel as spotless as the lamb. "If Melville felt justified in what he had written, why did he call "Moby Dick" "a wicked book"?
Perhaps because he had written a book with a wicked protagonist. The protagonist, to be sure, is punished for his wickedness. Still, what if he is presented sympathetically, admiringly, as a hero, or something of a hero? Then perhaps the book becomes "a wicked book" in the eyes of its author. Melville's case recalls Milton's, in "Paradise Lost", where Satan appears in a heroic light in the early part of the poem. Melville's description of Ahab, in fact, often seems reminiscent of Milton's description of Satan. Both are superheroes, archangelic though fallen, battle-scarred, vindictive, bent on revenge. Might not Milton have thought that "Paradise Lost" through Book Two was a wicked book? Is not the treatment of Satan in those tremendous opening scenes too sympathetic to comport strictly with Christian piety? Possibly Melville felt this about his treatment of Ahab・・・
---R. Stewart, "American Literature And Christian Doctrine"
そういうギリシャ的精神は、例えば<ピエール>なんかにも共通している。もっとも彼がキリスト教的なものに反逆することはない--彼が戦いを挑むのは、社会的な慣習、虚偽の上に築かれた平安に対してである。
後にこれを映画化したレオス・カラックスは語っている--
「・・・彼はその重みを背負おうとするが、力がなくて小さいので失墜してしまう。しかし彼が悲劇の英雄になるのは、失墜しても運命を引き受けようとするからなのだ」
こうしてここにおいても、最も重要な主題は神の栄光なんかではなく、迷い悩みながらも孤独に戦い続ける魂の戦いであり、個人の尊厳である。ヨーロッパ文学の歴史の本質的な部分を成してきたのは実にこのようなテーマなのだ。
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
2013年11月30日
創造的な不幸-23-
創造的な不幸-愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ-
この作品について 目次
-23- 文学の問題その2、文化・カエサル・ウェスタン・キャノン
文化の問題。
この国では大体において、文学とは超道徳的情緒である。罪もそこに美があれば許される。許されるどころか奨励されさえする。いや、そもそも罪という概念がないのだった。<雪国>の世界はあまりにも詩情に満ちているので、読み手はそれが姦淫の物語だということにもほとんど気がつかない。
A自身の文学観も似たようなものだった。A自身は厄介な良心の問題を避けて通り、自分の作品の中で誰にも神の掟を踏み越えさせなかったし、誰のことをも傷つけなかった。けれどもAはそれが神に受け入れられないことを知っていた、なぜならその<文学>は本質的に、超道徳的な思想を持っていたからだ。
罪なしに、文学は一体どうしてやってゆけよう? 恋の熱情は美しく、文学至上主義的であるがゆえに、また簡単に道徳の境界を踏み越える。一切が神の道徳律に支配された世界のどこに、詩情や幽玄や「もののあはれ」の宿る余地があろう? 他のすべてが完全にそろっていても、文学の欠落した世界に、そもそも生きる価値なんかあるのだろうか?
けれども、こうして語りながらもAは、規準とそれをもってはかる対象との、二つの精神性の間の絶望的な隔たりのどうしようもなさを、身にしみて感ぜずにはいられない。
とどのつまりは文化の問題なのではないかと、Aは思う。
美とか芸術とか文学とかについての普遍的な定義があり得ないのは、それぞれの文化によってその意味するところが異なるからであり、逆に言うならばそれぞれの文化こそが、その文化圏における美とか芸術とか文学のあり方を決定するのだ。
人間とそれ以外の被造物を峻別することなく、あらゆる<自然>をあるがままに受け入れ、正義だの道徳だの人生の意味だの、肩肘張ったことは考えず、柳田邦男が書いたように、「米がたくさん取れる」ことが生きがいとなってきたのがこの国の文化であれば、その文学においても正邪善悪が大して問題となるはずもない。
そう、我々の文化は人と自然とを区別しない。人の本質--ネイチャーと自然界の自然--ネイチャーとの区別を理解するのにAがあれほど苦労しなければならなかったのは、そもそもA自身がそういう区別の存在しない文化の中に住んでいたからだったのだ。それゆえ紫の上は源氏が新しい女をつくるたびに、彼の道徳的責任を問う代わりにそれを雷とか洪水とか土砂崩れのような不可抗力として受けとめて耐え忍ばなければならなかった。源氏の側の意識も大して変わらなかっただろう。彼は、<夜と霧>の第七章で説かれているように、己れは「他のようにもでき得る」のではないか、などとついぞ考えたりしなかった。そして彼を取り巻く文化全体が彼の生き方を受け入れ、称賛さえしたのだ。紫の上の苦悩を通して、よるべなき人生の悲しみ、くらいのことは語られるかもしれない。しかし、それゆえに源氏は自分の中の罪と戦って、一人の女だけを愛さなければならない、なんてことは言い出さないのだ。
そして、それが神の目に間違っているというなら、それはつまり、我々の文化全体は間違っているということだ。そしてAもまたそういう文化の中で育ってきたのだ。
それゆえAにとって、宗教と文学とが対立する概念であったのもけだし当然だった。ヨーロッパの宗教と、アジアの文学観とがそもそも調和するはずがないのだ。二つの世界は互いを否定し合うので、決して混じり合ってはならなかった。それゆえその境界には壁が築かれたのだ。
その壁が崩れ落ちたとき、Aの精神世界はついに一つに統合された。しかし、それゆえにどれだけの苦悩と混乱と激痛が引き起こされただろう。もちろんAは、自分の愛してきた世界を放棄して、神の側を選び取らなければならなかった。人は己れの全体を生ける犠牲として神に差し出さねばならず、そのあらゆる想念、内的世界の最後の片隅までも、神に明け渡さねばならないのだ。「そしてあなたの目が、あなたの右手があなたをつまずかせるなら・・・」
R.スチュアートは詩篇の中に、ウォレンはヘミングウェイの主人公のギリシャ精神に、チェスタトンは十戒にすら詩情を見い出したかもしれない。しかし我々にとっては、詩情は常に、正義とか道徳とは無関係のところにしか見い出されようがない--とどのつまりは文化の問題なのだ。
*
引き続き、文化の問題--文化の本質と可触性をめぐって。
あれほどまでに確信に満ちて現代のイスラエルになりきり、その役を演じようとしてきたアメリカ。--しかし、一体何が彼らをそうさせたのか?
そして我々は思い至る--その地理的環境。大陸のあの大平原は、何かを思い出させるのではないか--その広大さ、その単調さ、その苛酷さにおいて--古代イスラエルの旅した荒野を。
想起せよ--<緋色の研究>の第二部冒頭において、暗示されているのはまさにそれである。それこそが、他のどこよりそのアメリカにおいて、今なお最もキリスト教が力を保っている理由の一つではないのか? --ゲニウス・ロキにおける精神の類似性。
あるいはオースターの<ガラスの街>。古代イスラエルとアメリカのアナロジー。
西へ向かう荒野の旅--西へ向かうピルグリム・ファーザーズ。
カナンとの戦争、そして殺戮と征服--同じく、インディアンと呼ばれたネイティヴ・アメリカンとの。
例えばフォークナーなんかを読んでいてAがつくづくと感じるのは、その小説世界における、人間と神との強い、直接的な結びつきである。彼の作品に出てくる南部人の暮らしはごく日常的なレベルでキリスト教と密着していて、それゆえに彼らが(ほとんど無意識的にであっても)神の名を口にするとき、それはちゃんと地に足をつけて物を言っている感じがする。彼らにとって、神とは南部の照りつける太陽だとか、乾いた広大な荒野と同じくらい身近な存在なのだ。それはまさに「彼らにいと近く、彼らの口の中、心の中に」息づいているのだった。
そういう環境というのは、神に仕えるには、とてもふさわしいと言えるのではないだろうか? 「それというのも、肉と肉との触れ合いには、まわりくどくて複雑な礼儀正しい順序を無視し、それを飛び越えてじかにまっすぐ進んでゆくもので、愛しあう者ばかりか憎みあう者も、その触れ合いによって造られるので・・・」--<アブサロム、アブサロム!>
結局のところ、我々を最も動かすのは抽象的な概念ではなく、直接目で見、手で触れることのできるものである--いわばその可触性とも言うべきものである。我々は愛という概念を、最初に神の啓示によってではなく、自分の周囲の人間たちから学ぶ。それゆえにヨハネも書いたのではなかったか--「自分が見ることのできる兄弟を愛さない者が、見たことのない神を愛することはできない」と。--1Joh4:20
それゆえにまた、キリスト教の深く根づいた文化の中で育ってきた人間の方が、キリスト教を自然に受け入れやすいし、またより良く理解するに違いない。
この点で、我々非キリスト教文化圏の人間は全く弱い立場にある。
今日、この国の人間の大方は文化的なみなし児である。それはAが常々感じてきたことだ。昔、小説の舞台を東ドイツの山村に選んでしまったことから、その辺りの一般的な民家の造りだとかフォークロアを少しかじったことがあるのだが、そのときも今日に至るまで伝統が生きて根づいているのに新鮮な驚きを覚えたのだった。そして、振り返って新たな目で自分の周囲を見渡してみると、この国の物理的な部分が--都市の景観にしろ、建築様式にしろ--一体何を根拠にして築かれているのか、さっぱり分からないことに気づいた。それ以来、文化的無根拠さの感覚はAに取り憑いて離れなくなったのである。
けれども、それまではただ気づかなかっただけで、実際はずっと前からそんなふうであったことに変わりはない。そうではないか、幼い頃から団地暮らしで、自分の国の伝統から切り断たれてしまった空間の中で育ってきて、かと言ってテ-ブルとかスリッパを作り出した国の精神性を受け継ぐこともなく。それは生活感情においても同じで、この国の人々は改まってものを考えるときですら神を視野に入れることはまずないし、毎日歯を磨くのと同じ感覚で神の名を口にすることは尚更ない。こんな環境の中で暮らしていて、一体自分には神との関係ゆえに苦しむ権利があるのだろうかとすら、Aは疑いたくなるのだった。
神につながる物理的なイメージは、もちろんAも持っている。Aにとって神とはまず、暖房が効きすぎの上に人がいっぱいで息のつまりそうな日曜日の集会所であり、さっさとおもてに出て遊びたいのになかなか終わらない、来るべき王国についての講演である。しかし、そういう組織ないし共同体も、我々自身の文化と結びつかない限り結局のところ、植民地みたいに地に足のつかない、中途半端な代物であることに変わりはない。
我々の宗教が、我々人の文化と結びついたものでありたいと願うのは当たり前のことではないのか? そもそも取ってつけたように外国の宗教をやろうとする方が間違っているのだと、言って片づけたい誘惑に駆られるのは自然なことではないのか?
しかし尚、正義は普遍である。オースターがヨナ書について述べたように--「いやしくも正義というものがあるとするなら、それは万人のための正義でなくてはならない。誰一人除外されてはならない。さもなくば正義というものはあり得ない。それは避けられない結論である。」それゆえ、もしキリスト教の教えが本当に正しいのであれば、それはキリスト教文化圏の人間にとってだけでなく、非キリスト教文化圏の人間にとっても正しいはずではないか?
それゆえに、問題となってくるのはこのことなのだ--それが正しいからというのでキリスト教を選び取ろうとする場合、我々はその教理と我々自身の文化との剥離を一体どうやって処理したものだろうか? そして、それはキリスト教を選び取ろうとするなべての異邦諸国民の、等しく直面する問題なのである--<接ぎ木されたオリ-ブの枝>たる我々の。
もちろん、我々は自分の文化の方を諦めなければならない。必ずしもその全部を諦める必要はない。まずキリスト教の規準を持ってきてそれで自分の文化を注意深く推し量ってみて、その掟に触れない部分はそのまま維持し(これには日常的な生活習慣とか芸術的な感覚が含まれるかもしれない)、それに反する部分は切り捨てるだろう(これには宗教と、それにある種の哲学的な感情が含まれるかもしれない)。しかし、生活習慣から宗教的な意味合いを排除すること、あるいは芸術から哲学的な感情を分離することは容易ではないから、彼は常に苦境に立たされることになるだろう。そして、どっちみち他者の規準によって裁断された文化などというものは、総体としてはもはや文化とは言えないから、彼は自ら文化的なみなし児、引き裂かれた存在となることに甘んずるわけである。しかし彼はそれによって神の是認を得るであろう。アブラハムはまさにそのようにしたのだ。神の命に従ってウルの地を捨てたとき、彼は己れの文化をも捨てたのだ。それから彼は死ぬまで外人居留者としてカナンの地で天幕暮らしをした。彼は真の土台を持つ都市を待ち望んでいたからだ。パウロが彼を範として示したところの、初期キリスト教徒たちもやはり同じ道を選んだ。物理的には自分の国に留まったかもしれないが、彼らもやはり自分の文化を--その総体性を諦めるという意味で--捨てたのだ。
そう、我々異邦人はなべて、神を受け入れるとき、自分の文化を神の規準で裁断しなければならなくなる。
生け花はよろしいが、日の丸はよろしくない。
ポンチョはよろしいが、ケツァルコアトルを崇拝してはいけない。
仮面をかぶって踊るのは構わないが、死者の前に火を灯してはいけない。
我々はなべて、個人としての己れを捨て去ると同時に己れの文化の総体性を諦めなければならないのだ。いや、そればかりでなく、キリスト教に属するある種の文化を受け入れることをも余儀なくされる。
「律法はよき事柄の影」にすぎないとは言え、我々は神の特質やその物事の進め方を学ぶためにヘブライ語聖書を読むとき、同時にやはりイスラエルの文化についても学ばざるをえない。荒野の旅のくだりを読んでいるとAはきまってのどが渇いてくる--しかし、あの風土もまた文化である。荒野がひからびていたからこそ民は水を求めて神を呪ったのだ。しかし、その不従順から受けた罰については、豊葦原の瑞穂の国のキリスト教徒も学ばなければならない。彼らもまたアダムから罪を受け継いだ死すべき人間であり、彼らもまた神に対して不従順になり得るからだ。
あるいは、祭司のエフォドだの、幕屋の覆い布の柄だの、何でこんな面倒な雑事につきあわなければならないかと思う、しかしそれもまた文化である。それにはキリストの贖いのひな型としての象徴的な意味があって、そうとなればキリストがそのために死んだあらゆる人間はそれに関心を持たねばならないのだ。
それだけではない。我々は自分の言葉で考えているだけではどうも神の愛についてよく理解できなくて、やはりギリシャ語本文に立ち返らざるをえない。こうして毎日日本語でしゃべりながら自分の信仰についてはギリシャ語で考えるという不自然を余儀なくされる。
言語をめぐる問題。
例えば、Aの組織ではその出版物はすべて、はじめに英語で書かれて、それから何百カ国語かの他の言語に訳される段取りになっていた。真理というものが普遍的であるならば、もちろんこういうやり方でなくてはならない。「絶対的で不動なる真理が、どうして言語によって異なったりするだろう?」--<孤独の発明>
しかしながら、真理の正確さと、国語の美しさと、この二つは決して立ち往かない。一方のためにつねにもう一方が犠牲になるのであって、宗教が国境を越えるたびに変質してゆかないためには、どうしても国語の美しさの方が折れることになる。
それゆえ、組織の方針でできるだけ完全に字義訳されたその日本語は、はっきり言って死んだ日本語であった。そんなものを四六時中読まされることが精神にどういう破壊的な影響を及ぼすことか--Aはすっかりうんざりして、思ったのだ--普遍的正義のために我々は、我々自身の言語感覚までを犠牲にしなければならないのか? 神は我々に、そこまでを要求するのか? だとしたら、神が反逆者どもをバベルの塔から追い散らしたとき、人類は、エデンから追放されたときと勝るとも劣らない、また別の重荷を背負わされたことになると言えないだろうか?
こうして文化的に引き裂かれた存在となることは耐えがたいことではないのか? それはあまりにも残酷な要求ではないのか?
これが非キリスト教文化圏のキリスト教徒が直面する、文化の問題である。
* *
ところで、それではキリスト教文化圏のキリスト教徒にとっては、文化の問題は全然問題にならないと、我々は考えていいのか? --否! キリスト教文化圏における文化の問題は、ひょっとすると非キリスト教文化圏におけるよりももっと始末に負えないくらいの大問題なのだ。というのも、そもそもキリスト教という概念と、文化という概念とは、決して相立ち往くものではないからだ。
文化というものは、選ぶことができない。それはアプリオリに我々よりも前に存在していて、我々は否応なくその中に生を受け、そしてその影響のもとに形造られてゆく。メルヴィルが書いたように、「土地が人間を決定するのだ。」それゆえ、逆に言えば人は自分の生まれついた文化を受け入れるのに、ほとんど何の努力も要しない。ところがキリスト教の方はと言うと、それは間違いなく人に選択を強いるのであり、その高い道徳規準や犠牲の多い生き方のゆえにまた、それを受け入れるために人は日々努力しなくてはならない。それゆえ、それは本来ならば個人的に決定を下した個人によって奉じられるべきものであり、文化のような無意識的なものと混同されるべきではないのだ。
極端な話、詐欺師や殺人犯や姦淫を行う者や反逆者や無神論者もキリスト教文化圏に属し得るし、現に属しているが、彼らが同時にキリスト教徒であるということはあり得ないわけだ。それゆえに、キリスト教文化圏にあってキリスト教徒であることもまた、非キリスト教文化圏にあってそうであることに、勝るとも劣らない挑戦なのである。
例えば、教理の正当性をめぐる問題。
世にいわゆるキリスト教文化というものが、正しくキリスト教的であるという保証はどこにもない。すでに見てきた通り、キリスト教が広まってゆく過程で様々な異教の教理や哲学と混ぜ合わされてきたのは周知の事実である。こうして不純なキリスト教を受け入れてきた人々は、要するに、普遍の真理のために自らの文化を断念することを望まなかったので、その代わりに真理の方を自らの文化になじむように加工する方を選んだのだ。そうすることによって、自らの文化ばかりか自らの精神にまで調和と一貫性が与えられるという点では申し分のない方法だったかもしれない。けれどもそれは、神の見地からすれば無意味であるばかりか、有害ですらあった。なぜなら、神にとってはもちろん、文化だの人間の精神の調和だのなんかよりも、神自身が正しく崇拝されることの方がよっぽど重要なのだから、そんな崇拝は受け入れられない--ゆえに、それは全然崇拝しないのと一緒である、せいぜい、崇拝者自身の良心をなだめるのに役立つくらいのものだ。ところが、そういうやり方を身近に見て、これがキリスト教というものなのだと思い込んでしまう周囲の人間の知性にとっては--そう、それは恐ろしく有害なのである。
加えて言うなら、分裂という問題もある。文化とは本質的に多様性である。いちいち文化にへつらっていたら、キリスト教はそれこそ無限に分裂してしまうのであり、(我々が現に見ているように)「私はパウロに」、「私はアポロに」ということになるわけだ。そして、その相違が軋轢、憎悪、流血を引き起こす。
中でも、文化の問題を論ずるにあたって最も重要なのは、カエサルとの結びつきという問題であろう。すでに見てきたように、イエスが「私の王国はこの世のものではない」と宣言したにもかかわらず、ローマがキリスト教を国教として以来、それは人々の観念の中で大いにこの世のものとなってきた。それゆえにそれは大問題なのだ。
なぜなら、国家というものもまた(革命を起こそうという気にでもならない限り)基本的にアプリオリで、選択を許さないという点で文化に似ているからだ。それゆえ国家が「キリスト教化される」と、真面目なキリスト教徒ももちろん生み出される一方で、税金を払わされるのと同じ感覚で仕方なしに、あるいは深い考えなしにキリスト教徒となるキリスト教徒ももちろん生み出されるのである。そしてこうした人々が、キリスト教的観点から見た、一つの集合体としてのキリスト教の質を絶えず落としてゆくことになる。
こういう試みはかつて十分になされたのではなかったか? すなわち、古代イスラエルにおいて。彼らは一つの国民として神に献身していたにもかかわらず、絶えず堕落し続けては神の叱責を受け、それにも耳を貸そうとしなかったのでついに神の是認を失った。こうして一つの国民が全体として神に受け入れられるということの不可能が立証されたがゆえに、神は新しい取り決めにおいて個人の決定というものが不可欠であることを強調したのではなかったか? しかるに、ヨーロッパの歴史は逆戻りして同じ過ちを繰り返したのである。
"The Portage" のヒトラー。
・・・The Nazarene said his kingdom was not of this world. Honey lies. It was here on earth he founded his slave-church.
神とカエサルを結びつけた人々の責任。
それは多分に政治的な利害ゆえでもあった。同時にまた(アウグスティヌスのように)全くの善意と神に対する熱心ゆえであったことも間違いない。しかし、結果として引き起こされた問題に、彼らは全く責任がないのだろうか?
十字軍の暴虐行為を、彼らはどう言い訳するだろうか?
あるいは教会制度の腐敗や宗教戦争で流された夥しい血を?
いや、それだけではない--それがつまづきの石となってキリスト教に背を向けた人々に対しても、彼らは責任を負ってはいないのか?
キリスト教が社会悪の数々に対する責任の一端を担っていると考えて原罪を否定し、自然主義を奉じるようになったルソーに向かって、彼らは何と言い訳するのか?
そういうルソーに心酔し、悪の起源は社会的であり、外在的であって、それゆえに制度を変えれば人間はよくなると信じて革命を引き起こした人々に向かって、彼らは何と言うのか?
あるいは既成の道徳観念を叩き壊してまわったバロウズやギンズバーグが、だってこの社会の腐敗と偽善のそもそものはじまりはキリスト教ではないかと言ったら、彼らは何と返答するのか?
* *
例えばマリリン・フリードマンとジャン・ナーヴソンの共著<ポリティカル・コレクトネス>。この本でとりわけ興味深いのは、PCの攻撃の的となってきた西洋中心思想というものが、多くの点でいかにキリスト教のアナロジーとして見られるか、にもかかわらず、キリスト教そのものではないためにいかに窮地に陥っているか、という点である。
例えばその中の、ウェスタン・キャノンをめぐる一節。
ここではウェスタン・キャノン--伝統的西洋的規範--を奉じる保守派と、マルティカルチュラリズム--多文化主義--を提唱する左派もしくはラディカルとの、対立するそれぞれの言い分が提出されている。問題となっているのは、大学教育における文学の授業のカリキュラムをいかに組むべきか、というものである。保守側は、西洋の偉大な伝統を固守し、それをあらゆる文化や文学の尺度にすべきであると考え、一方の左派は、多様な文化のそれぞれの価値を認めるべきで、伝統的な西洋文化だけを特別扱いするのは間違っていると考える。ここで言う西洋的な伝統というのは、はっきりと定義できるものではないのだが、まあ大雑把に言ってソクラテス、ホーマー、英語、キリスト教、ミルトン、シェイクスピア、民主主義、白人男性至上主義、あたりを意味すると考えていいだろう。 まずはウェスタン・キャノン側の主張。
ロジャー・キンボール--それは人類にとって普遍的な益がある、と彼は主張する。それはすべての人に訴えかける--性、人種、民族を越えて。
ウェスタン・キャノンを批判したり無視したりすることは、我々の社会の基盤を脅かす。我々の政治制度の基本概念とは、論理性、個人の権利、公正な批評、性や人種や民族に関わりのない正義、などである--これらがわが自由民主国家を維持するのに不可欠な概念であり、ウェスタン・キャノンはこうした概念を推進するのだ。
ウィリアム・ベネットの主張--西洋文明の偉大な所産は、多民族国家を一つに結び合わせる。
ドナルド・ケイガン--西洋文明、そして西洋文化が我々の学問研究の中心に置かれないなら、自由民主主義社会は危機に瀕するであろう。
アラン・ブルームは、この戦いはすでに敗北に終わったと考えている。<アメリカン・マインドの終焉>--「今日、高等教育は学生の魂を貧弱にするとともに、民主主義を損なっている」
あらゆる相違を超越した、人類にとっての普遍的な益! 我々の社会全体にとっての福祉! その自信たっぷりな調子、自惚れを自惚れとも思わない滑稽な真摯さ--それはまさにキリスト教のドグマである。
「ペテロ口を開きて言ふ、『われ今まことに知る、神は偏ることをせず、何れの国の人にても神を敬ひて義をおこなふ者を容れ給ふことを』」--Act10:34,35
「願はくは汝わが命令にききしたがはんことを もし然らば汝の平安は河のごとく 汝の義はうみの波のごとく・・・」--Is48:18
そして、保守派の文学者たちは、アメリカにおいてウェスタン・キャノンがこの役割を果たしてきたと信じているのだ。従って、彼らの反動的とも感じられる主張はつまるところ、高低の基準、よしあしの区別、中心と周辺との秩序が失われ、物事が無限に相対化されてしまうことへの危惧、一国の国民的精神性が痛ましくも分裂してしまうことへの警鐘、であると考えられる。しかしこの宗教はその権威として、人間の伝統しか持っていない。批判者はそこを突いてくるのだ。 マリリン・フリードマンの反論。
ウェスタン・キャノンは普遍性を持っているって? それでは普遍性とは何か--我々の社会には、西洋式ではない教育を受けた人はたくさんいるし、全然教育を受けなかった人だってたくさんいる。普遍性を定義し、それを持っていることを証明するのは難しい。普遍性の証拠とは何か--西洋人自身がそう言っているということだけなのか? だとしたら、それは途方もない無知、傲慢もいいところだ。持っていると主張するだけでは、実際に持っていることにはならないのだ。
それからフリードマンは自ら<普遍性>の試金石を示す。フリードマンによれば、普遍性の証拠とは「みんながそれと認めること」である。あらゆる立場からの声が聞かれなければならない。
異文化間の比較検討をする前には、その判断基準が異文化同士の間で適切であることが明らかにされなければならない。しかし、そんな判断基準を見つけるのはまず無理であろう。我々の社会全体への福祉という主張にしたってそうだ。我々にとっての福祉とは何か--具体的にどんな福祉が最も望ましいと、誰に言えるのか。
加えるに、ウェスタン・キャノンは大きな道徳的欠陥を抱えている。現代米国に生活するにあたって無視できない側面であるところの、あの複雑な多民族性にどう対処すべきかについて、ほとんど洞察を与えていない。また、フェミニズム、性、ジェンダーを含む、人間のアイデンティティーをめぐる問題に関しても、批判的省察を与えていない。
こうした欠陥を埋め合わせるために、カリキュラムはぜひともマルティカルチュラリズムを取り入れるべきなのだ。
これがフリードマンの言い分である。
たしかにもっともな言い分だ。しかし、これがもし、キリスト教のアナロジーとしてのウェスタン・キャノンではなく、キリスト教そのものだったとしたら--そうしたら、こうした言い分はみんな論破できるのだ。というのは、もし神の権威で真実とか普遍性を語るのであれば誰にも反論できないからだ。
傲慢だって? --語っているのは神なのだ、どうしてそんなことがありえよう。普遍性の証拠とは、みんながそれと認めることだって? とんでもない! 真実が真実であるために、どうしてみんなからそれと認められる必要があるのか。異文化間の判断基準は存在しない? --まさか! 神の原則は、いつだって判断基準として機能するではないか。我々にとってどんな福祉が最も望ましいのか--それも、決めるのは我々自身ではなくて、神である。人種や性の問題についての十分な省察を与えていないからといって、それが何だろう? 神は、いつだって正しいのだ。
という具合に。有無を言わせず。
しかし、普遍性をめぐるウェスタン・キャノン信奉者たちの主張はちょっと、興味深い。すなわち彼らはウェスタン・キャノンなるものを、重力とか引力のようなものとほとんど同じくらい普遍的なものと考えているのである。それはあらゆる人間の<本質>に関して確信に満ちた論議を展開したR.スチュアートの文章や、「普遍的な人間の問題を追求した」フォークナーを思い起こさせる。
スチュアートはフォークナーの小説世界におけるキリスト教的象徴主義の効用の一つを次のように説明する。「(それによって)キリスト教的な意味は驚くべき偏在性(ubiquity)を持ち得るという考えが・・・伝えられる。・・・彼は・・・象徴的な作家である。ミシシッピー人はフォークナーが絶対的な意味で彼らのことを書いていると想像してはいけないし、ニュー・イングランド人や中西部人やカリフォルニア人も、彼は自分たちのことを書いているのではないなどと想像してはならない。・・・彼が書いているのは人間の条件についてである。彼が書いているのは原罪についてであり、これは--信ずるに足る十分な理由があるが--最も広い人間社会に広がっているのである。
「・・・彼がまっすぐその核心をのぞきこんだ事物が、ミシシッピー特有のものでないことは確かである。それは人類にのみ特有のものである。」
それは中国人にも、フィジー人にも、イヌイットにもあてはまるのであり--とまでいかなかったのは、スチュアートの謙虚ゆえと考えてよいだろう。しかしこういう文学観が、西洋精神の普遍性についての考え方の基礎となってきたのはほぼ間違いあるまい。ところで彼らが(神の見地からして)許されるとしたら、それは彼らがキリスト教の原則を--神の権威を下敷きにして--語っているからなのである。キリスト教の理念の普遍性を主張することを傲慢であると考える必要はない。ところが、ウェスタン・キャノンが神の概念を抜きにして、ウェスタン・キャノンそれ自身の名において普遍性を主張し始めるとなると--これはもう、傲慢以外の何物でもなくなってしまうのだ。このあたりにも我々は、神とカエサルとの混同が引き起こしてきた問題を見ることができるのである。
* *
カール・レーヴィットはニーチェを論じた際に、逆の観点からこの問題を取り上げている。すなわち、ニーチェの時代におけるニヒリズムがなぜまだ不完全なものでしかなかったかを説明して、彼は書くのである--(二重カッコ内はニーチェの引用)
「・・・人間は現在まだ中間状態にある。人間は根底においてもはや何ものも信じないが、それにもかかわらず一切のものをそのままにしておくのである。『今や一切のものは全く虚偽か、弱々しいか、常軌を逸している。』人はもはや義なる神によるキリスト教の救いを待ち望まないが、しかしやはり似たような意味で、社会的『正義』によって地上的解放を供しようと試みるのである。人はもはやキリスト教的彼岸を信じない。それにもかかわらず、世俗的終末論の形態において彼岸をしっかり持っている。人はキリスト教的自己否定を根底において拒否するが、自然的自己主張を肯定するのでもない。人はもはや『キリスト教的結婚』や『キリスト教的国家』を信じない。けれども、このことは出生や婚礼や死亡を見せかけのキリスト教的きよめで装うことを何人にも禁じはしない。
「この曖昧さの結果、今やすべてのものが信ずべき意味を持たないものとして現れ、また『無価値』になったということ、このことをニーチェは、実際には基準を与え得ないものとなってしまい、また世俗的になった我々の生に対して実際に行われた価値評価がそれに対して久しい以前から矛盾しているところのかの諸価値が、未だになお価値基準として通用していることの帰結であると解する。『私はあたりを見まわす。かつて真理と呼ばれたかのもの--キリスト教的真理、キリスト教的信仰、キリスト教的教会--について一語も残っていない。・・・すべての人はこのことを知っている。それにもかかわらず、一切が元のままに留まっている。普段は非常にとらわれない種類の人間であり、またどこまでも反キリスト教的行動の人であるわが政治家たちさえも、今日なお自らをキリスト教徒と呼び、聖餐に列することを考えれば、端正さと自己に対する尊敬との最後の感情はどこへいったのだろうか。誰を一体キリスト教は否認するのか。「この世」とは何を言うのか。人が兵士、裁判官、愛国者であること、自己を防衛すること、自分の利益を欲すること、自負していること、・・・各瞬間における一切の行動、あらゆる本能、実際に行われている一切の価値評価、これらのものは今日すべて反キリスト教的である。それにもかかわらず、現代人が自分を未だにキリスト教徒と呼んで恥じないとは、彼は何と言う虚偽の奇形児でなければならないことか。」
そしてこれが、歴史的にキリスト教と文化や国家なるものが混ぜ合わされてきたことの避けがたい結果である。
誰を一体キリスト教は否認するのか? 「この世」とは何を言うのか? ニーチェはもちろん、ヤコブが「自分を世から汚点のない状態に保つように」と命じた世について語っていたのだ。(Jas1:27)そしてヨハネが、「世も世にあるものも愛することがないように」と警告した世について。(1Joh2:15-19)
この明確な区別、鋭い断絶がキリスト教の本質なのである。それゆえに世は裁かれねばならず、それゆえに終末が招来されねばならないのだ。
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
この作品について 目次
-23- 文学の問題その2、文化・カエサル・ウェスタン・キャノン
文化の問題。
この国では大体において、文学とは超道徳的情緒である。罪もそこに美があれば許される。許されるどころか奨励されさえする。いや、そもそも罪という概念がないのだった。<雪国>の世界はあまりにも詩情に満ちているので、読み手はそれが姦淫の物語だということにもほとんど気がつかない。
A自身の文学観も似たようなものだった。A自身は厄介な良心の問題を避けて通り、自分の作品の中で誰にも神の掟を踏み越えさせなかったし、誰のことをも傷つけなかった。けれどもAはそれが神に受け入れられないことを知っていた、なぜならその<文学>は本質的に、超道徳的な思想を持っていたからだ。
罪なしに、文学は一体どうしてやってゆけよう? 恋の熱情は美しく、文学至上主義的であるがゆえに、また簡単に道徳の境界を踏み越える。一切が神の道徳律に支配された世界のどこに、詩情や幽玄や「もののあはれ」の宿る余地があろう? 他のすべてが完全にそろっていても、文学の欠落した世界に、そもそも生きる価値なんかあるのだろうか?
けれども、こうして語りながらもAは、規準とそれをもってはかる対象との、二つの精神性の間の絶望的な隔たりのどうしようもなさを、身にしみて感ぜずにはいられない。
とどのつまりは文化の問題なのではないかと、Aは思う。
美とか芸術とか文学とかについての普遍的な定義があり得ないのは、それぞれの文化によってその意味するところが異なるからであり、逆に言うならばそれぞれの文化こそが、その文化圏における美とか芸術とか文学のあり方を決定するのだ。
人間とそれ以外の被造物を峻別することなく、あらゆる<自然>をあるがままに受け入れ、正義だの道徳だの人生の意味だの、肩肘張ったことは考えず、柳田邦男が書いたように、「米がたくさん取れる」ことが生きがいとなってきたのがこの国の文化であれば、その文学においても正邪善悪が大して問題となるはずもない。
そう、我々の文化は人と自然とを区別しない。人の本質--ネイチャーと自然界の自然--ネイチャーとの区別を理解するのにAがあれほど苦労しなければならなかったのは、そもそもA自身がそういう区別の存在しない文化の中に住んでいたからだったのだ。それゆえ紫の上は源氏が新しい女をつくるたびに、彼の道徳的責任を問う代わりにそれを雷とか洪水とか土砂崩れのような不可抗力として受けとめて耐え忍ばなければならなかった。源氏の側の意識も大して変わらなかっただろう。彼は、<夜と霧>の第七章で説かれているように、己れは「他のようにもでき得る」のではないか、などとついぞ考えたりしなかった。そして彼を取り巻く文化全体が彼の生き方を受け入れ、称賛さえしたのだ。紫の上の苦悩を通して、よるべなき人生の悲しみ、くらいのことは語られるかもしれない。しかし、それゆえに源氏は自分の中の罪と戦って、一人の女だけを愛さなければならない、なんてことは言い出さないのだ。
そして、それが神の目に間違っているというなら、それはつまり、我々の文化全体は間違っているということだ。そしてAもまたそういう文化の中で育ってきたのだ。
それゆえAにとって、宗教と文学とが対立する概念であったのもけだし当然だった。ヨーロッパの宗教と、アジアの文学観とがそもそも調和するはずがないのだ。二つの世界は互いを否定し合うので、決して混じり合ってはならなかった。それゆえその境界には壁が築かれたのだ。
その壁が崩れ落ちたとき、Aの精神世界はついに一つに統合された。しかし、それゆえにどれだけの苦悩と混乱と激痛が引き起こされただろう。もちろんAは、自分の愛してきた世界を放棄して、神の側を選び取らなければならなかった。人は己れの全体を生ける犠牲として神に差し出さねばならず、そのあらゆる想念、内的世界の最後の片隅までも、神に明け渡さねばならないのだ。「そしてあなたの目が、あなたの右手があなたをつまずかせるなら・・・」
R.スチュアートは詩篇の中に、ウォレンはヘミングウェイの主人公のギリシャ精神に、チェスタトンは十戒にすら詩情を見い出したかもしれない。しかし我々にとっては、詩情は常に、正義とか道徳とは無関係のところにしか見い出されようがない--とどのつまりは文化の問題なのだ。
*
引き続き、文化の問題--文化の本質と可触性をめぐって。
あれほどまでに確信に満ちて現代のイスラエルになりきり、その役を演じようとしてきたアメリカ。--しかし、一体何が彼らをそうさせたのか?
そして我々は思い至る--その地理的環境。大陸のあの大平原は、何かを思い出させるのではないか--その広大さ、その単調さ、その苛酷さにおいて--古代イスラエルの旅した荒野を。
想起せよ--<緋色の研究>の第二部冒頭において、暗示されているのはまさにそれである。それこそが、他のどこよりそのアメリカにおいて、今なお最もキリスト教が力を保っている理由の一つではないのか? --ゲニウス・ロキにおける精神の類似性。
あるいはオースターの<ガラスの街>。古代イスラエルとアメリカのアナロジー。
西へ向かう荒野の旅--西へ向かうピルグリム・ファーザーズ。
カナンとの戦争、そして殺戮と征服--同じく、インディアンと呼ばれたネイティヴ・アメリカンとの。
例えばフォークナーなんかを読んでいてAがつくづくと感じるのは、その小説世界における、人間と神との強い、直接的な結びつきである。彼の作品に出てくる南部人の暮らしはごく日常的なレベルでキリスト教と密着していて、それゆえに彼らが(ほとんど無意識的にであっても)神の名を口にするとき、それはちゃんと地に足をつけて物を言っている感じがする。彼らにとって、神とは南部の照りつける太陽だとか、乾いた広大な荒野と同じくらい身近な存在なのだ。それはまさに「彼らにいと近く、彼らの口の中、心の中に」息づいているのだった。
そういう環境というのは、神に仕えるには、とてもふさわしいと言えるのではないだろうか? 「それというのも、肉と肉との触れ合いには、まわりくどくて複雑な礼儀正しい順序を無視し、それを飛び越えてじかにまっすぐ進んでゆくもので、愛しあう者ばかりか憎みあう者も、その触れ合いによって造られるので・・・」--<アブサロム、アブサロム!>
結局のところ、我々を最も動かすのは抽象的な概念ではなく、直接目で見、手で触れることのできるものである--いわばその可触性とも言うべきものである。我々は愛という概念を、最初に神の啓示によってではなく、自分の周囲の人間たちから学ぶ。それゆえにヨハネも書いたのではなかったか--「自分が見ることのできる兄弟を愛さない者が、見たことのない神を愛することはできない」と。--1Joh4:20
それゆえにまた、キリスト教の深く根づいた文化の中で育ってきた人間の方が、キリスト教を自然に受け入れやすいし、またより良く理解するに違いない。
この点で、我々非キリスト教文化圏の人間は全く弱い立場にある。
今日、この国の人間の大方は文化的なみなし児である。それはAが常々感じてきたことだ。昔、小説の舞台を東ドイツの山村に選んでしまったことから、その辺りの一般的な民家の造りだとかフォークロアを少しかじったことがあるのだが、そのときも今日に至るまで伝統が生きて根づいているのに新鮮な驚きを覚えたのだった。そして、振り返って新たな目で自分の周囲を見渡してみると、この国の物理的な部分が--都市の景観にしろ、建築様式にしろ--一体何を根拠にして築かれているのか、さっぱり分からないことに気づいた。それ以来、文化的無根拠さの感覚はAに取り憑いて離れなくなったのである。
けれども、それまではただ気づかなかっただけで、実際はずっと前からそんなふうであったことに変わりはない。そうではないか、幼い頃から団地暮らしで、自分の国の伝統から切り断たれてしまった空間の中で育ってきて、かと言ってテ-ブルとかスリッパを作り出した国の精神性を受け継ぐこともなく。それは生活感情においても同じで、この国の人々は改まってものを考えるときですら神を視野に入れることはまずないし、毎日歯を磨くのと同じ感覚で神の名を口にすることは尚更ない。こんな環境の中で暮らしていて、一体自分には神との関係ゆえに苦しむ権利があるのだろうかとすら、Aは疑いたくなるのだった。
神につながる物理的なイメージは、もちろんAも持っている。Aにとって神とはまず、暖房が効きすぎの上に人がいっぱいで息のつまりそうな日曜日の集会所であり、さっさとおもてに出て遊びたいのになかなか終わらない、来るべき王国についての講演である。しかし、そういう組織ないし共同体も、我々自身の文化と結びつかない限り結局のところ、植民地みたいに地に足のつかない、中途半端な代物であることに変わりはない。
我々の宗教が、我々人の文化と結びついたものでありたいと願うのは当たり前のことではないのか? そもそも取ってつけたように外国の宗教をやろうとする方が間違っているのだと、言って片づけたい誘惑に駆られるのは自然なことではないのか?
しかし尚、正義は普遍である。オースターがヨナ書について述べたように--「いやしくも正義というものがあるとするなら、それは万人のための正義でなくてはならない。誰一人除外されてはならない。さもなくば正義というものはあり得ない。それは避けられない結論である。」それゆえ、もしキリスト教の教えが本当に正しいのであれば、それはキリスト教文化圏の人間にとってだけでなく、非キリスト教文化圏の人間にとっても正しいはずではないか?
それゆえに、問題となってくるのはこのことなのだ--それが正しいからというのでキリスト教を選び取ろうとする場合、我々はその教理と我々自身の文化との剥離を一体どうやって処理したものだろうか? そして、それはキリスト教を選び取ろうとするなべての異邦諸国民の、等しく直面する問題なのである--<接ぎ木されたオリ-ブの枝>たる我々の。
もちろん、我々は自分の文化の方を諦めなければならない。必ずしもその全部を諦める必要はない。まずキリスト教の規準を持ってきてそれで自分の文化を注意深く推し量ってみて、その掟に触れない部分はそのまま維持し(これには日常的な生活習慣とか芸術的な感覚が含まれるかもしれない)、それに反する部分は切り捨てるだろう(これには宗教と、それにある種の哲学的な感情が含まれるかもしれない)。しかし、生活習慣から宗教的な意味合いを排除すること、あるいは芸術から哲学的な感情を分離することは容易ではないから、彼は常に苦境に立たされることになるだろう。そして、どっちみち他者の規準によって裁断された文化などというものは、総体としてはもはや文化とは言えないから、彼は自ら文化的なみなし児、引き裂かれた存在となることに甘んずるわけである。しかし彼はそれによって神の是認を得るであろう。アブラハムはまさにそのようにしたのだ。神の命に従ってウルの地を捨てたとき、彼は己れの文化をも捨てたのだ。それから彼は死ぬまで外人居留者としてカナンの地で天幕暮らしをした。彼は真の土台を持つ都市を待ち望んでいたからだ。パウロが彼を範として示したところの、初期キリスト教徒たちもやはり同じ道を選んだ。物理的には自分の国に留まったかもしれないが、彼らもやはり自分の文化を--その総体性を諦めるという意味で--捨てたのだ。
そう、我々異邦人はなべて、神を受け入れるとき、自分の文化を神の規準で裁断しなければならなくなる。
生け花はよろしいが、日の丸はよろしくない。
ポンチョはよろしいが、ケツァルコアトルを崇拝してはいけない。
仮面をかぶって踊るのは構わないが、死者の前に火を灯してはいけない。
我々はなべて、個人としての己れを捨て去ると同時に己れの文化の総体性を諦めなければならないのだ。いや、そればかりでなく、キリスト教に属するある種の文化を受け入れることをも余儀なくされる。
「律法はよき事柄の影」にすぎないとは言え、我々は神の特質やその物事の進め方を学ぶためにヘブライ語聖書を読むとき、同時にやはりイスラエルの文化についても学ばざるをえない。荒野の旅のくだりを読んでいるとAはきまってのどが渇いてくる--しかし、あの風土もまた文化である。荒野がひからびていたからこそ民は水を求めて神を呪ったのだ。しかし、その不従順から受けた罰については、豊葦原の瑞穂の国のキリスト教徒も学ばなければならない。彼らもまたアダムから罪を受け継いだ死すべき人間であり、彼らもまた神に対して不従順になり得るからだ。
あるいは、祭司のエフォドだの、幕屋の覆い布の柄だの、何でこんな面倒な雑事につきあわなければならないかと思う、しかしそれもまた文化である。それにはキリストの贖いのひな型としての象徴的な意味があって、そうとなればキリストがそのために死んだあらゆる人間はそれに関心を持たねばならないのだ。
それだけではない。我々は自分の言葉で考えているだけではどうも神の愛についてよく理解できなくて、やはりギリシャ語本文に立ち返らざるをえない。こうして毎日日本語でしゃべりながら自分の信仰についてはギリシャ語で考えるという不自然を余儀なくされる。
言語をめぐる問題。
例えば、Aの組織ではその出版物はすべて、はじめに英語で書かれて、それから何百カ国語かの他の言語に訳される段取りになっていた。真理というものが普遍的であるならば、もちろんこういうやり方でなくてはならない。「絶対的で不動なる真理が、どうして言語によって異なったりするだろう?」--<孤独の発明>
しかしながら、真理の正確さと、国語の美しさと、この二つは決して立ち往かない。一方のためにつねにもう一方が犠牲になるのであって、宗教が国境を越えるたびに変質してゆかないためには、どうしても国語の美しさの方が折れることになる。
それゆえ、組織の方針でできるだけ完全に字義訳されたその日本語は、はっきり言って死んだ日本語であった。そんなものを四六時中読まされることが精神にどういう破壊的な影響を及ぼすことか--Aはすっかりうんざりして、思ったのだ--普遍的正義のために我々は、我々自身の言語感覚までを犠牲にしなければならないのか? 神は我々に、そこまでを要求するのか? だとしたら、神が反逆者どもをバベルの塔から追い散らしたとき、人類は、エデンから追放されたときと勝るとも劣らない、また別の重荷を背負わされたことになると言えないだろうか?
こうして文化的に引き裂かれた存在となることは耐えがたいことではないのか? それはあまりにも残酷な要求ではないのか?
これが非キリスト教文化圏のキリスト教徒が直面する、文化の問題である。
* *
ところで、それではキリスト教文化圏のキリスト教徒にとっては、文化の問題は全然問題にならないと、我々は考えていいのか? --否! キリスト教文化圏における文化の問題は、ひょっとすると非キリスト教文化圏におけるよりももっと始末に負えないくらいの大問題なのだ。というのも、そもそもキリスト教という概念と、文化という概念とは、決して相立ち往くものではないからだ。
文化というものは、選ぶことができない。それはアプリオリに我々よりも前に存在していて、我々は否応なくその中に生を受け、そしてその影響のもとに形造られてゆく。メルヴィルが書いたように、「土地が人間を決定するのだ。」それゆえ、逆に言えば人は自分の生まれついた文化を受け入れるのに、ほとんど何の努力も要しない。ところがキリスト教の方はと言うと、それは間違いなく人に選択を強いるのであり、その高い道徳規準や犠牲の多い生き方のゆえにまた、それを受け入れるために人は日々努力しなくてはならない。それゆえ、それは本来ならば個人的に決定を下した個人によって奉じられるべきものであり、文化のような無意識的なものと混同されるべきではないのだ。
極端な話、詐欺師や殺人犯や姦淫を行う者や反逆者や無神論者もキリスト教文化圏に属し得るし、現に属しているが、彼らが同時にキリスト教徒であるということはあり得ないわけだ。それゆえに、キリスト教文化圏にあってキリスト教徒であることもまた、非キリスト教文化圏にあってそうであることに、勝るとも劣らない挑戦なのである。
例えば、教理の正当性をめぐる問題。
世にいわゆるキリスト教文化というものが、正しくキリスト教的であるという保証はどこにもない。すでに見てきた通り、キリスト教が広まってゆく過程で様々な異教の教理や哲学と混ぜ合わされてきたのは周知の事実である。こうして不純なキリスト教を受け入れてきた人々は、要するに、普遍の真理のために自らの文化を断念することを望まなかったので、その代わりに真理の方を自らの文化になじむように加工する方を選んだのだ。そうすることによって、自らの文化ばかりか自らの精神にまで調和と一貫性が与えられるという点では申し分のない方法だったかもしれない。けれどもそれは、神の見地からすれば無意味であるばかりか、有害ですらあった。なぜなら、神にとってはもちろん、文化だの人間の精神の調和だのなんかよりも、神自身が正しく崇拝されることの方がよっぽど重要なのだから、そんな崇拝は受け入れられない--ゆえに、それは全然崇拝しないのと一緒である、せいぜい、崇拝者自身の良心をなだめるのに役立つくらいのものだ。ところが、そういうやり方を身近に見て、これがキリスト教というものなのだと思い込んでしまう周囲の人間の知性にとっては--そう、それは恐ろしく有害なのである。
加えて言うなら、分裂という問題もある。文化とは本質的に多様性である。いちいち文化にへつらっていたら、キリスト教はそれこそ無限に分裂してしまうのであり、(我々が現に見ているように)「私はパウロに」、「私はアポロに」ということになるわけだ。そして、その相違が軋轢、憎悪、流血を引き起こす。
中でも、文化の問題を論ずるにあたって最も重要なのは、カエサルとの結びつきという問題であろう。すでに見てきたように、イエスが「私の王国はこの世のものではない」と宣言したにもかかわらず、ローマがキリスト教を国教として以来、それは人々の観念の中で大いにこの世のものとなってきた。それゆえにそれは大問題なのだ。
なぜなら、国家というものもまた(革命を起こそうという気にでもならない限り)基本的にアプリオリで、選択を許さないという点で文化に似ているからだ。それゆえ国家が「キリスト教化される」と、真面目なキリスト教徒ももちろん生み出される一方で、税金を払わされるのと同じ感覚で仕方なしに、あるいは深い考えなしにキリスト教徒となるキリスト教徒ももちろん生み出されるのである。そしてこうした人々が、キリスト教的観点から見た、一つの集合体としてのキリスト教の質を絶えず落としてゆくことになる。
こういう試みはかつて十分になされたのではなかったか? すなわち、古代イスラエルにおいて。彼らは一つの国民として神に献身していたにもかかわらず、絶えず堕落し続けては神の叱責を受け、それにも耳を貸そうとしなかったのでついに神の是認を失った。こうして一つの国民が全体として神に受け入れられるということの不可能が立証されたがゆえに、神は新しい取り決めにおいて個人の決定というものが不可欠であることを強調したのではなかったか? しかるに、ヨーロッパの歴史は逆戻りして同じ過ちを繰り返したのである。
"The Portage" のヒトラー。
・・・The Nazarene said his kingdom was not of this world. Honey lies. It was here on earth he founded his slave-church.
神とカエサルを結びつけた人々の責任。
それは多分に政治的な利害ゆえでもあった。同時にまた(アウグスティヌスのように)全くの善意と神に対する熱心ゆえであったことも間違いない。しかし、結果として引き起こされた問題に、彼らは全く責任がないのだろうか?
十字軍の暴虐行為を、彼らはどう言い訳するだろうか?
あるいは教会制度の腐敗や宗教戦争で流された夥しい血を?
いや、それだけではない--それがつまづきの石となってキリスト教に背を向けた人々に対しても、彼らは責任を負ってはいないのか?
キリスト教が社会悪の数々に対する責任の一端を担っていると考えて原罪を否定し、自然主義を奉じるようになったルソーに向かって、彼らは何と言い訳するのか?
そういうルソーに心酔し、悪の起源は社会的であり、外在的であって、それゆえに制度を変えれば人間はよくなると信じて革命を引き起こした人々に向かって、彼らは何と言うのか?
あるいは既成の道徳観念を叩き壊してまわったバロウズやギンズバーグが、だってこの社会の腐敗と偽善のそもそものはじまりはキリスト教ではないかと言ったら、彼らは何と返答するのか?
* *
例えばマリリン・フリードマンとジャン・ナーヴソンの共著<ポリティカル・コレクトネス>。この本でとりわけ興味深いのは、PCの攻撃の的となってきた西洋中心思想というものが、多くの点でいかにキリスト教のアナロジーとして見られるか、にもかかわらず、キリスト教そのものではないためにいかに窮地に陥っているか、という点である。
例えばその中の、ウェスタン・キャノンをめぐる一節。
ここではウェスタン・キャノン--伝統的西洋的規範--を奉じる保守派と、マルティカルチュラリズム--多文化主義--を提唱する左派もしくはラディカルとの、対立するそれぞれの言い分が提出されている。問題となっているのは、大学教育における文学の授業のカリキュラムをいかに組むべきか、というものである。保守側は、西洋の偉大な伝統を固守し、それをあらゆる文化や文学の尺度にすべきであると考え、一方の左派は、多様な文化のそれぞれの価値を認めるべきで、伝統的な西洋文化だけを特別扱いするのは間違っていると考える。ここで言う西洋的な伝統というのは、はっきりと定義できるものではないのだが、まあ大雑把に言ってソクラテス、ホーマー、英語、キリスト教、ミルトン、シェイクスピア、民主主義、白人男性至上主義、あたりを意味すると考えていいだろう。 まずはウェスタン・キャノン側の主張。
ロジャー・キンボール--それは人類にとって普遍的な益がある、と彼は主張する。それはすべての人に訴えかける--性、人種、民族を越えて。
ウェスタン・キャノンを批判したり無視したりすることは、我々の社会の基盤を脅かす。我々の政治制度の基本概念とは、論理性、個人の権利、公正な批評、性や人種や民族に関わりのない正義、などである--これらがわが自由民主国家を維持するのに不可欠な概念であり、ウェスタン・キャノンはこうした概念を推進するのだ。
ウィリアム・ベネットの主張--西洋文明の偉大な所産は、多民族国家を一つに結び合わせる。
ドナルド・ケイガン--西洋文明、そして西洋文化が我々の学問研究の中心に置かれないなら、自由民主主義社会は危機に瀕するであろう。
アラン・ブルームは、この戦いはすでに敗北に終わったと考えている。<アメリカン・マインドの終焉>--「今日、高等教育は学生の魂を貧弱にするとともに、民主主義を損なっている」
あらゆる相違を超越した、人類にとっての普遍的な益! 我々の社会全体にとっての福祉! その自信たっぷりな調子、自惚れを自惚れとも思わない滑稽な真摯さ--それはまさにキリスト教のドグマである。
「ペテロ口を開きて言ふ、『われ今まことに知る、神は偏ることをせず、何れの国の人にても神を敬ひて義をおこなふ者を容れ給ふことを』」--Act10:34,35
「願はくは汝わが命令にききしたがはんことを もし然らば汝の平安は河のごとく 汝の義はうみの波のごとく・・・」--Is48:18
そして、保守派の文学者たちは、アメリカにおいてウェスタン・キャノンがこの役割を果たしてきたと信じているのだ。従って、彼らの反動的とも感じられる主張はつまるところ、高低の基準、よしあしの区別、中心と周辺との秩序が失われ、物事が無限に相対化されてしまうことへの危惧、一国の国民的精神性が痛ましくも分裂してしまうことへの警鐘、であると考えられる。しかしこの宗教はその権威として、人間の伝統しか持っていない。批判者はそこを突いてくるのだ。 マリリン・フリードマンの反論。
ウェスタン・キャノンは普遍性を持っているって? それでは普遍性とは何か--我々の社会には、西洋式ではない教育を受けた人はたくさんいるし、全然教育を受けなかった人だってたくさんいる。普遍性を定義し、それを持っていることを証明するのは難しい。普遍性の証拠とは何か--西洋人自身がそう言っているということだけなのか? だとしたら、それは途方もない無知、傲慢もいいところだ。持っていると主張するだけでは、実際に持っていることにはならないのだ。
それからフリードマンは自ら<普遍性>の試金石を示す。フリードマンによれば、普遍性の証拠とは「みんながそれと認めること」である。あらゆる立場からの声が聞かれなければならない。
異文化間の比較検討をする前には、その判断基準が異文化同士の間で適切であることが明らかにされなければならない。しかし、そんな判断基準を見つけるのはまず無理であろう。我々の社会全体への福祉という主張にしたってそうだ。我々にとっての福祉とは何か--具体的にどんな福祉が最も望ましいと、誰に言えるのか。
加えるに、ウェスタン・キャノンは大きな道徳的欠陥を抱えている。現代米国に生活するにあたって無視できない側面であるところの、あの複雑な多民族性にどう対処すべきかについて、ほとんど洞察を与えていない。また、フェミニズム、性、ジェンダーを含む、人間のアイデンティティーをめぐる問題に関しても、批判的省察を与えていない。
こうした欠陥を埋め合わせるために、カリキュラムはぜひともマルティカルチュラリズムを取り入れるべきなのだ。
これがフリードマンの言い分である。
たしかにもっともな言い分だ。しかし、これがもし、キリスト教のアナロジーとしてのウェスタン・キャノンではなく、キリスト教そのものだったとしたら--そうしたら、こうした言い分はみんな論破できるのだ。というのは、もし神の権威で真実とか普遍性を語るのであれば誰にも反論できないからだ。
傲慢だって? --語っているのは神なのだ、どうしてそんなことがありえよう。普遍性の証拠とは、みんながそれと認めることだって? とんでもない! 真実が真実であるために、どうしてみんなからそれと認められる必要があるのか。異文化間の判断基準は存在しない? --まさか! 神の原則は、いつだって判断基準として機能するではないか。我々にとってどんな福祉が最も望ましいのか--それも、決めるのは我々自身ではなくて、神である。人種や性の問題についての十分な省察を与えていないからといって、それが何だろう? 神は、いつだって正しいのだ。
という具合に。有無を言わせず。
しかし、普遍性をめぐるウェスタン・キャノン信奉者たちの主張はちょっと、興味深い。すなわち彼らはウェスタン・キャノンなるものを、重力とか引力のようなものとほとんど同じくらい普遍的なものと考えているのである。それはあらゆる人間の<本質>に関して確信に満ちた論議を展開したR.スチュアートの文章や、「普遍的な人間の問題を追求した」フォークナーを思い起こさせる。
スチュアートはフォークナーの小説世界におけるキリスト教的象徴主義の効用の一つを次のように説明する。「(それによって)キリスト教的な意味は驚くべき偏在性(ubiquity)を持ち得るという考えが・・・伝えられる。・・・彼は・・・象徴的な作家である。ミシシッピー人はフォークナーが絶対的な意味で彼らのことを書いていると想像してはいけないし、ニュー・イングランド人や中西部人やカリフォルニア人も、彼は自分たちのことを書いているのではないなどと想像してはならない。・・・彼が書いているのは人間の条件についてである。彼が書いているのは原罪についてであり、これは--信ずるに足る十分な理由があるが--最も広い人間社会に広がっているのである。
「・・・彼がまっすぐその核心をのぞきこんだ事物が、ミシシッピー特有のものでないことは確かである。それは人類にのみ特有のものである。」
それは中国人にも、フィジー人にも、イヌイットにもあてはまるのであり--とまでいかなかったのは、スチュアートの謙虚ゆえと考えてよいだろう。しかしこういう文学観が、西洋精神の普遍性についての考え方の基礎となってきたのはほぼ間違いあるまい。ところで彼らが(神の見地からして)許されるとしたら、それは彼らがキリスト教の原則を--神の権威を下敷きにして--語っているからなのである。キリスト教の理念の普遍性を主張することを傲慢であると考える必要はない。ところが、ウェスタン・キャノンが神の概念を抜きにして、ウェスタン・キャノンそれ自身の名において普遍性を主張し始めるとなると--これはもう、傲慢以外の何物でもなくなってしまうのだ。このあたりにも我々は、神とカエサルとの混同が引き起こしてきた問題を見ることができるのである。
* *
カール・レーヴィットはニーチェを論じた際に、逆の観点からこの問題を取り上げている。すなわち、ニーチェの時代におけるニヒリズムがなぜまだ不完全なものでしかなかったかを説明して、彼は書くのである--(二重カッコ内はニーチェの引用)
「・・・人間は現在まだ中間状態にある。人間は根底においてもはや何ものも信じないが、それにもかかわらず一切のものをそのままにしておくのである。『今や一切のものは全く虚偽か、弱々しいか、常軌を逸している。』人はもはや義なる神によるキリスト教の救いを待ち望まないが、しかしやはり似たような意味で、社会的『正義』によって地上的解放を供しようと試みるのである。人はもはやキリスト教的彼岸を信じない。それにもかかわらず、世俗的終末論の形態において彼岸をしっかり持っている。人はキリスト教的自己否定を根底において拒否するが、自然的自己主張を肯定するのでもない。人はもはや『キリスト教的結婚』や『キリスト教的国家』を信じない。けれども、このことは出生や婚礼や死亡を見せかけのキリスト教的きよめで装うことを何人にも禁じはしない。
「この曖昧さの結果、今やすべてのものが信ずべき意味を持たないものとして現れ、また『無価値』になったということ、このことをニーチェは、実際には基準を与え得ないものとなってしまい、また世俗的になった我々の生に対して実際に行われた価値評価がそれに対して久しい以前から矛盾しているところのかの諸価値が、未だになお価値基準として通用していることの帰結であると解する。『私はあたりを見まわす。かつて真理と呼ばれたかのもの--キリスト教的真理、キリスト教的信仰、キリスト教的教会--について一語も残っていない。・・・すべての人はこのことを知っている。それにもかかわらず、一切が元のままに留まっている。普段は非常にとらわれない種類の人間であり、またどこまでも反キリスト教的行動の人であるわが政治家たちさえも、今日なお自らをキリスト教徒と呼び、聖餐に列することを考えれば、端正さと自己に対する尊敬との最後の感情はどこへいったのだろうか。誰を一体キリスト教は否認するのか。「この世」とは何を言うのか。人が兵士、裁判官、愛国者であること、自己を防衛すること、自分の利益を欲すること、自負していること、・・・各瞬間における一切の行動、あらゆる本能、実際に行われている一切の価値評価、これらのものは今日すべて反キリスト教的である。それにもかかわらず、現代人が自分を未だにキリスト教徒と呼んで恥じないとは、彼は何と言う虚偽の奇形児でなければならないことか。」
そしてこれが、歴史的にキリスト教と文化や国家なるものが混ぜ合わされてきたことの避けがたい結果である。
誰を一体キリスト教は否認するのか? 「この世」とは何を言うのか? ニーチェはもちろん、ヤコブが「自分を世から汚点のない状態に保つように」と命じた世について語っていたのだ。(Jas1:27)そしてヨハネが、「世も世にあるものも愛することがないように」と警告した世について。(1Joh2:15-19)
この明確な区別、鋭い断絶がキリスト教の本質なのである。それゆえに世は裁かれねばならず、それゆえに終末が招来されねばならないのだ。
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
2013年11月30日
創造的な不幸-22-
創造的な不幸-愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ-
この作品について 目次
-22- 文学の問題、その1
文学の問題。
神々は、我々を人間とする為に何らかの欠点をお与えになる。
・・・You, gods, will give us
Some faults to make us men.
---<アントニーとクレオパトラ>第五幕第一場
Aはこの言葉が文学の問題の本質を突いているのを感じ取って、長らく忘れられなかった。
我々はここでの神が小文字のgodsであって、大文字のGod ではないことに留意すべきである。God は--キリスト教の神は--我々を人間とするために欠点を与えたりしなかった。その神は我々を、はじめから完全なものとして創造したのであり、人間の方が自ら罪を犯して不完全なものとなったのだ。
ところが人間のその不完全性が、文学に対して--あるいは芸術全般に対して--はかりしれない奥ゆきと広がりと深みとひだとを与えてきたこと、これは否定し得ない事実ではないのか? いや、順序から言えば、人間の不完全性こそがこの不完全なる世界における芸術を生み出してきたのだ。それでは、人間の罪と、それゆえに生じる一切の苦しみと理不尽--それは芸術のための必要悪なのか?
ヴォルテールの"The World It Goes" 。
これはヨナ書のパロディーである。
流血の都市ニネベ。
神は預言者ヨナに命じて「彼らの悪が私の前に達したことを」告げさせ、「あとわずか四十日でニネベは覆される」ことを布告させる。
すると驚くべきことに、住民たちはこぞって悔い改め、その悪と暴虐の道から引き返して神に信仰を置くようになる。この知らせがニネベの王のもとに達すると、彼は自ら粗布を身にまとって灰の中に座り、悔い改めを布告する。
「まことの神が翻ってまさに悔やまれ、その燃える怒りから離れて、我々が滅びないようにしてくださることはないと、誰が知っていようか。」
それで神は彼らがその悪から立ち返ったのを見て、彼らに加えると宣言したその災いを加えなかった。
ヨナ書の大筋はざっとこの通りである。
しかるに、ヴォルテールの短篇においてはニネベがペルセポリスに変わる。滅びの宣告を携えてゆくのは、ヨナではなくて一人の天使である。
彼はペルセポリスを検証すべく、しばらくそこに滞在する。なるほどその都市は悪徳と不徳義に満ちている。ところがそこに住むうちに、天使はだんだんとその都市が好きになってくる。なるほど悪徳に満ちてはいるが、それに勝って人間的な魅力に富んだ都市でもあったのだ。
そこで天使は一人の職人に命じてダイヤモンドと土塊とで彫像をつくらせ、それを神のもとに持ってゆく。
「神よ、これがすべてダイヤモンドでできてはいないという理由で、あなたはこの愛らしい彫像を壊しておしまいになりますか」
それで神はペルセポリスを滅ぼさなかった。
この二つの話において、決定的な違いは、滅びを宣告された人間の側の行動にある。すなわち、ニネベの人々は己れの悪を捨てたので、神もまた加えようとしていた災いを放棄した--この点において神の言葉は果たされなかったが、その目的は悪を断ち滅ぼすことにあり、それはすでに達せられていた、すなわち、邪悪であった人間がもはや邪悪でなくなっていたからだ。だから神の威信は少しも傷ついていないし、その義の規準も侵されていない。ところがペルセポリスの場合、人々は何らの変化も遂げないのであり、逆に神の方が天使に説得されて考えを変えるのだ。これは、ヒューマニズム--人間至上主義の威光の前に、神の権威ですら退けられることを意味する。
十八世紀のオプティミズム、科学の発達、啓蒙思想。人間性への無邪気な信頼が、ヴォルテールとその時代の特色だった。
人間は人間だけで善悪の規準を定めてやってゆける--それはまさに、エデンで蛇がエバをたぶらかした言葉ではなかったか。
エデンからの追放、ないし脱出、それは人類の原風景である--禁断の木の実を手にしたとき、エバはエデンを捨て、神の権威を退けた。彼女は「神の如くなり、決して死することなし」という蛇の言葉を信じたのだ。近代のヒューマニストも基本的には同じことを繰り返したのであり、ただ彼らは、蛇と違って自らの主張を誠実に信じていたのだった。
ヴォルテールの神は偶像を打ち壊さなかったが、1914年から始まる一連の出来事がそれを打ち壊した。人間は人間だけでけっこううまくやってゆけるのだ、そりゃあ神の目から見れば不完全で罪深いかもしれないが、それなりに、いやそれだからこそ、魅力的で愛すべき存在ではないか。--そういう幻想を、この現実が打ち壊したのだ。
1914年8月4日、ヘンリー・ジェームズの書簡。
「我々が今、悪夢の中に生きているのではないように語ってもむだなことです。過去の恐るべき流血と恐怖の深淵に、文明社会はつき落とされてしまったのです。時に後退することはあっても、世界は次第によくなると信じてきた我々の年月は、すべてむだになってしまいました。けれどもこの欺瞞の年月の間に我々が目指し、意図してきたもののすべてを今ありのままに受けとめるというのは、あまりに悲劇的で、言うべき言葉も見つかりません。我々の過去の愚者の楽園の一切が、その正体を暴露されてしまったのです。そんなもののためにえいえいと努力してきたとは、我々は何と愚かだったのでしょうか。」
打ち砕かれた人間至上主義の悲しみ。
人間の罪は、文学にとってたしかに豊かな源泉となってきたかもしれない。けれど、<孤独の発明>以後、Aは思うようになった--文学が必要とする苦しみと理不尽の最大指数というものが仮にあるとして、この世界はそれをはるかに凌駕している。
それゆえマヤコフスキーは自ら命を絶った。彼は二十年代ソ連における農村の惨状を目にして、自分が見たものを書き続けることにもはや耐えられなかったのだ。
「詩人マヤコフスキーは私が何とか理解しようとして果たさなかった詩人だが、偉大な才能の十字架と共に、憎しみ、怒り、暴力を背負い、自分と自分の民族の苦悩に意味を見いだすことに失敗した人間だった。・・・天才がいかに偉大であろうと、いつまでも無限に否定だけを糧にしては生き続けられない」 --ロレンス・ヴァン・デル・ポスト<ロシアへの旅>
あるいはアドルノ--「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」
Aは、神によって断罪された文学の死を悲しむ。Aはペルセポリスの像のために、丘の上で哀歌を唱えたいと思う。
それでも尚、だれもそれを凌駕できない。なぜなら、相手は神だからだ。神を捨てること、拒否することはできる。しかし、凌駕することはできない。
再びローマ書--「すべての人は罪を犯したので神の栄光に達しない」
* *
文学と完全性について。
将来地上に回復されることになっているパラダイス、完全なる人間の住む完全なる世界、そういう世界に文学の生まれる余地はあるか?
「神は光であり、神との結びつきにおいてはいかなる闇も存在し得ない」--そのような世界に、文学は存在し得るのか?
Aはかつて自分の属していた会衆を思い出す--彼らのうちに、思想においても言動においても存在する、越えることを許されない明確な一線。悪を絶対に許容しない、道徳的な強靱さ。文学も芸術も「もののあはれ」も幽玄の興趣も、何ものもその倫理規準を超越することは許されない。エホバ--愛と義のアマルガム。
彼らのうちに文学らしきものが存在するとしても、それはいつでも真理のプロパガンダ装置もしくはその探究の手段であり、決して文学そのもののための文学ではなかった。けれど、ああ--神の規準によって真ん中で分断された「もののあはれ」など、とても見られたものではない。
そういう人々のうちにあって、文学はどうすればいいのか。ただ真理のプロパガンダに専念していればいいのか。中世の聖者伝、あるいは長らくロシアの文壇を毒してきた社会主義リアリズムのようになってしまっていいのか。それでは文学の死ではないのか。それとも、(カフカについて一注釈者が書いたように)文学とは真理の探究であるなら、真理が見い出された今、文学は死んでしまって構わないのか--真理がそれほど貴重なものであるなら。
* *
一方、Aにとって文学の本質とは、他でもない、<神への反逆>だった--他に何があろう? それは神の創造したこの世界に対抗して、全く別の、新しい秩序を打ち立てる行為であり、神の定めた<世界の真実>に対する、最も深い意味での挑戦だったのである。Aの創り出した世界では、人は神に仕えることなしに幸福に生きることができ、社会は神の権威なしに立ちゆくのだった--すなわちそこにおいては蛇の嘘が真実となったのだ。それゆえAの<文学>は、例えば<権力と栄光>の背景となった六十年代のメキシコや、ソ連におけるような共産主義革命なんかよりも何倍も重い罪だった。なぜなら、革命は現実の世界に起こったのであり、現実の世界は常に神の定めた<世界の真実>に左右されているからだ--人々の間でキリスト教がどれほど衰退しようと関係ない、それはもっとアプリオリなものであって、あらゆる人間はついにそれから逃れられないのだ。げんに二十年代に始まるソ連の惨状は、神なしのユートピアの建設が不可能であったことを反駁の余地なく実証して、「此人彼人を治めてこれに害を蒙らしむることあり」という神の言葉の正しさを、逆説的に明らかにした。だからもしも、人がこの過程をつぶさに観察して、神の正しさについて確信を得、その結果神に仕える生き方を選ぶ決定を下したとすれば、それは神にとって喜ばしいことではないか?
そしてそれは、革命がどれだけ大量の、罪のない血を流したとしても尚真実なのである。実際、神が現在に至るまで、エデンの外における人類の存続と、その道徳的混乱の存続とを許している理由はここにあるのではなかったか?
それに対して、Aの<文学>は一滴の血も流さないので、一見すればそれは無害と思えるかもしれない。しかし、こういうことが起きたとしたらどうだろう? 仮にAの書いた小説が世に出たとする。そして、経験の少ない、若いキリスト教徒がそれを読み、それに影響されて神なしのユートピアの可能性についての幻想を抱くようになって、その結果神の道から迷い出るようなことになったとしたら? そして、終末のときにこの世と共に滅ぼされるようなことになったとしたら?
そうしたら、神のもとから一つの魂が失われたことに対してAは間違いなく血の責任を負うのであり、「これら小さな者の一人をつまづかせるよりは、挽き臼を首にかけられて海に投げ込まれた方がましである」とのキリストの言葉を身に受けることになるのだ。
こうして、間違った思想が間違った行動の萌芽として、行動そのものより罪深いとすれば、神の目には、スターリンよりもマルクスやロバート・オーウェンの方がなお罪深いと、我々は考えることができないだろうか?
ナジェージダ・マンデリシュタームが、二十年代の文化人たちを批判した言葉を思い出されるだろうか。二十年代そのものは躍動に満ちたすばらしい時代だった、ただそのあとの路線を誤ったからすべてがおかしくなっていったのだという考えを、彼女は退けている--「彼らは、その後起こったことに対して責任を認めていないのである。しかし、果してそうだろうか? なにしろ、当時あった価値観を破壊して、新しい国だ、未曾有の実験だ、樹を伐れば木っ端は吹っ飛ぶといった、今もなくてはならない形式を発見したのは、他ならぬ二十年代の人々だったのである。すべての死刑は、目下我々は二度と暴圧のない社会を建設しているのだから、・・・どんな犠牲も許されるのだと、正当化されていたのである。・・・」
ところで、ここで我々は「神に断罪される共産主義」という図式を転換して、「自分の認める以外のあらゆる文学形式を断罪する、キリスト教のアナロジーとしての共産主義」という図式によってもまた、この問題を考えることができる。共産主義思想がキリスト教から生まれたことを、"Portage" のヒトラーも指摘していなかっただろうか。ナジェージダ・マンデリシュタームもまた書いている--「信奉者たちがつつましくも科学と呼んでいたこの宗教が権威を授けた人間は、神様並みに高められる。この宗教は、自分の信仰の象徴と道徳とを作成した。・・・一九二〇年代には、少なからぬ人々が、キリスト教の勝利の歴史から類推して、新しい宗教の千年王国を予言した。さらに最も良心的な人々は、教会の犯した歴史的な罪業を列挙しながら、キリスト教の本質は宗教裁判によっても変わらなかったくらいだから、新しい宗教もそうだろうと類推をたくましくしたのである。・・・」
そしてこの新しい宗教が、文学に対していかなる態度を取ったか--
「わが国では遠慮会釈なく経歴や死亡年月日が歪められている。オシップがヴォロネージでドイツ人に殺された、という噂を流したのは誰か? 収容所で大量に人が死にだしたのは四十年代初めからだ、といっているのは誰か? 現存の、また物故した詩人たちの詩集を立派な作品はみなわざと抜かして出版しているのは誰か? 命を落とした作家や詩人、今も生きている作家や詩人のもう出版されるばかりになっている原稿を、何年も編集局にしまいこんでいるのは誰か? そんな例はとても全部は数えきれない。さまざまな形の保管庫にしまいこまれたり、埋もれたりしているものはあまりにも多く、焼き捨てられたものはさらに多いのである」
「・・・この時代の注目すべき特質は、人を殺し自分も命を落としたこういう新しい人たちすべてが、自分だけにしか思考し判断する権利を認めていなかったということであった。・・・昼夜時を分かたず護衛つきで自分たちのところへひっぱってこられる人間が、自分に自由な詩を書く権利があることをいささかも疑っていないと知ったら、取調官の誰もが哄笑したことだろう。・・・ヤーゴダはオシップの詩がすっかり気に入って空で覚えていたほどで、・・・この詩をブハーリンに自ら読んで聞かせたのだが、自分に有利だと考えたなら彼は過去、現在、未来のすべての文学をためらうことなく抹殺したにちがいない。」
「スルコフはパステルナークの小説がどうして悪いのか私に説明してくれた。ドクトル・ジヴァゴにはわが国の現実を判断する権利がない、我々は彼にそういう権利を与えなかったのだから、というのである。」
「死に方を選びながらオシップは、わが国の指導者たちの・・・詩へのはかりしれぬ尊敬を引き合いに出して、私を慰めるのであった。『嘆くことはないじゃないか。詩が尊ばれているのは、わが国だけだよ。詩のために人殺しをやっているのはね。詩のために人がこんなに殺される国はどこにもないからね』と彼は言うのだった。」
「・・・家政婦は、自分たちはみな不法に流刑に処されているのだと主張していた。たとえば彼女だが、彼女は逮捕される頃にはもう自分の党の仕事から離れていたし、逮捕されたときは私人であった。
『彼らだってこのことは知っていましたよ!』
と彼女は言うのだった。だが私には・・・どうも彼女の主張が分からなかった。粉砕された党の一員であったことを自ら認めるなら、なぜ彼女は自分が流刑に処せられていることに腹を立てるのだろう? わが国の基準からすればそれが当然なのである。そう私はその時考えていた。『わが国の基準』は・・・恐ろしくて残酷だが、それが現実であり、強大な権力は、たとえ今は活動していないにせよやはり動きだすおそれのある公然の敵たちを黙って見ているわけにはいかない。・・・
「ナールブト・・・の観点からすればオシップを流刑に処さないわけにはいかなかった。『国家は自衛しなければならないだろう? でなければどうなるか、考えてごらんよ』
私は反駁しなかった。出版されたのでもなければ公衆の前で朗読されたのでもない詩は思想と同じである。思想ゆえに人を流刑にはできないと、言い争ったり説明したりする必要があっただろうか。」
思想ゆえに人を流刑にはできないだって?・・・とんでもない! 思想こそは全く、そのために人を流刑にしたり殺したりする最大の根拠なのである。イエスも言ったのではなかったか--「心から出るものが人を汚す」と。
あらゆる罪と反逆とは思想から始まる。最初の罪は一人の天使の心の中で始まったのだ。彼の「思想の自由」ゆえに。それがまた「女を見てこれに欲情を抱く者は・・・」ということの意味だし(ノアの日に、「まことの神の子ら」においてそれがいかに真実となったかを見よ)、それがまた「神を愛せ」という第一の掟の意味でもある。最大の掟がかくのごとく、法律をもって罰することのできない掟であったことには意味があるのだ。この掟は、心を、思想を支配する掟であったからだ。
共産主義がキリスト教のアナロジーであるのなら、そのもっとも忌まわしい部分もまた、キリスト教にその原型を見い出すことができるのである。
それゆえ、キリスト教は、あらゆる芸術がそこから生み出されるところの精神性のあり方そのものを規定するのであるから、芸術の立場からすれば、それは芸術に対する最大の冒涜である。他方、キリスト教の立場からすれば、芸術は、神に対する精神の全き服従という第一原理を無視しかねないのだから、芸術のそういう本質こそは神に対する最大の冒瀆である。
スターリン主義と文学とのあの軋轢に満ちた関係から、我々はこの本質的真理を学ぶことができるのである。
自らの芸術によって新しい世界を創造すること、自らの芸術を神と張り合う位置にまで高めること。
芸術の持つこういう力を認識するとき、中世ヨーロッパにおいて役者や音楽家が賤民の部類に入れられていたのは何ら驚くべきことではない。そうすることによって教会は、芸術をくびきのもとに屈伏させ、芸術から自らを守る必要があったのだ。カミュによれば、十八世紀においてすらそうだった。
「俳優のこような習練をカトリック教会がどうして断罪しなかったはずがあろう。この芸術における魂の異端的増殖、感情の放蕩、ただ一つの運命しか生きぬことを拒み、あらゆる放埒に身を投じてゆく精神の破廉恥な意図を、教会は退けた。・・・それらは教会の教えるものすべての否定に他ならないからだ。永遠は演技ではない。永遠より芝居を好ほど無分別な精神は、自分の救いを失ってしまった。・・・俳優という実に卑しめられていた職業が、異様なまでの精神の葛藤を引き起こす所以はここにある。
「十八世紀の著名な悲劇女優アドリエンヌ・ルクーヴルールは、臨終の床で懺悔と聖体拝受を望んだが、その職業を否認することは拒んだ。それゆえに彼女は懺悔の恵みに浴することができなかった。まさしくこれは、自分の深い情熱を選び、神を敵とすること以外の何であろう。そして、臨終の苦しみにあったこの女性は、自分が芸術と呼んでいたものの否認を涙ながらに拒むことによって、かつて彼女が舞台で脚光を浴びていたころには絶対に達し得なかった偉大さに達したことを証明したのである。それは彼女が演じたうちでもっとも見事な役、しかももっとも困難な役であった。天と、それに比べればいかにもつまらないものに思える自己への忠実とのどちらを選ぶか、永遠より自己をよしとするか、それとも神の中に身を沈めるか、これは敢然として生きねばならぬ数世紀来の悲劇なのだ。
「当時の俳優たちは自分が破門されていることを知っていた。俳優という職業に入ることは地獄を選ぶことだったのだ。そして教会は彼らの中に最悪の敵を見ていた。文人たちの中には、『なんだと、モリエールに最後の救いを与えることを拒否したんだと!』といって憤慨する者も何人かあった。だがそうした教会の態度は正当だった・・・」<シーシュポスの神話>
* *
当時小学生だったAは、これだけのことを言葉にして意識化するだけの知的な勇気も、冒瀆的な正直さも持ち合わせていなかった。しかしながら自分がしていることの意味をおぼろげながら認識していて、その認識がまた、Aを苦しめたのだった。なぜなら、当時のAはまだ、神を捨てていいとは思っていなかったからであり、神への崇拝をどんなに重荷と感じても、その必要性については何の疑問も抱いていなかったからだ。
それでも尚、Aにとって<文学>は、重苦しい神の権威からの唯一のサンクチュアリであり、道徳的アムステルダムだったのだ。当時Aの属していた会衆では、あらゆる楽しみが断罪され、芸術的感性は絞殺されて死に絶えていた。集会に連れられてゆくとき、Aはいつでも戸口に傘を置くように自分の<文学>を置いて中に入り、帰るときにまた持ち帰ったものだ。そこは全く、十七世紀のボストンみたいなところだった。それにもちろん、神の命令は(愛せよ、従え、善良なれ)、Aがどこにいてもつきまとってきた。ペンを手にして紙に向かっているときだけ、Aは自由に息をすることができたのだ。この領域までも神の手に引き渡すなどということは、Aにとって、考えるだけでも耐えられなかった。自分の内的世界全体が根こそぎ奪い取られるようで、そんな想念が頭をかすめるたびに、Aはぞっとして身震いした。
けれど、そんなふうにいつまでもどっちつかずの状態でいるわけにいかないことは、Aにもよく分かっていた。Aは知っていた--あまり考えたくはなかったが--将来のいつかに、どうしても避けられない、命がけの対決が控えていることを。
Aはまさに最初から、引き裂かれた存在だったのだ。
一方では、自分はもちろん神に仕える人生を歩むことになるだろうと思っていたし、もう一方では、もちろんそんなことにはならないだろうと思っていたのだから。
* *
それから、<孤独の発明>との出会いがやってくる。
ここにおいてAははじめて、伝統的ヨーロッパ的文学観に出会ったといっていいだろう--すなわち、文学とは形而上学的な問題に渡るものであり、また、渡るべきものであるということ。
それより三年ほど前に(Aは十四かそこらだった)、Aは同じオースターの<幽霊たち>に出会っている。それも衝撃的な出会いだった--近代世界がカフカに出会ったときの衝撃。こんな小説が書かれ得るのか! と思ったものだ。その頃のオースターのキャッチフレーズは<エレガントな前衛>だった。
恐らく<幽霊たち>を知らなかったら、<孤独の発明>との出会いもこれほど強烈ではなかっただろう。あの小説を書いた、彼ですら意味を求めていること--「彼もまた意味を渇望している」
これまでの歴史の中で引き起こされてきた、世界中の苦しみ--これらすべてには一体何の意味があるのか、どこかに救いはないのかと、凄まじいばかりに問いかける彼の姿。「世界は残虐であるがゆえに。世界は人を絶望にしか導きえないゆえに。ひとかけらの救いもない絶望、どこにも出口のない絶望。何ものもこの牢獄のドアを開けることはできない。希望の消滅、それがこの牢獄の名だ。・・・彼はこれ以上先へ進めない」
けれどもこれほどまでの世界の絶望は、ちょうど逆光になったものの影の濃さが背後の光の強烈さを際立たせるように、Aをして、劇的な仕方であるものの存在に対して目を開かせたのである--すなわち、神の希望に対して!
生まれてはじめて、Aは自分が長年にわたって提供されてきたものの何たるかを理解した。すなわち神の教えとは、この世界の道徳的無秩序に対する答えであり、意味であり、救いであったのだ。
その本を一気に読み通したときの感動を、Aは思い出す。
それはダマスカスに向かうサウロの前に現れたまぶしい光さながらだった。その日を境に、Aは突如急転回して神の道を突っ走りはじめる。
Aを根底から揺さぶったあの感動に、Aの激しい思い込みと、思い込んだら誰にも動かせない頑迷さと、命がけで突っ走る激烈さとが結びつけば、始末に負えないパリサイ人ができあがるのは火を見るより明らかだった。
Aは思い出す--自分の目を開かせてくれた感謝と共に、ぜひとも彼に真理を伝えなければという使命感に駆られ、拙い英語で便箋十枚ばかりの手紙を書きつづってオースターに送ったこと。その手紙が住所不備で結局彼のもとに届かなかったことを、Aは全くもって感謝する次第である--誰に? 恐らくは、<現代の無>に。
それからAが苦悩に押し潰されて身動きがとれなくなるまでに、長くはかからなかった。人に向けた鋭い裁きの刃を、Aは自分自身に対しても突きつけたからだ。
とりわけAを苦しめたのは愛の問題だった。
「あなたは心をこめ魂をこめ、思いをこめ力をこめてあなたの神エホバを愛さねばならない--これが最大で、第一の掟です」
Aは神を愛せなかった。
苦悩が言葉を持つ前の、果てしない苦悩。
苦悩が言葉を持って語りだしてからの、再び、果てしない苦悩。
自らを説得しようとして自問自答を続けたために残された、膨大な量のメモ--あまりに教唆的で、あまりに容赦なく、読み返そうとしても目に触れただけで、当時の精神状態が思い起こされて息苦しくなり、吐き気がしてくる。
神への愛について。
フェデリコ・フェリーニの<道>。
ジェルソミーヌと連れの男が、旅の途中でとある修道院に一夜の宿を借りる。そこの修道女の一人が、ジェルソミーヌに向かってこんなふうに語りかけるのだ。
「旅をされているのですね。私たちも、二年ごとに修道院を移り住んでいるのです」
「なぜ」
「長く暮らしていると、庭の草一本にでも愛情がわいて、その分だけ神様へのおつとめがおろそかになります」
その反証。
カポーティの<草の竪琴>。
恋人と一緒に、線路の上に止めた車の中で列車がくるのを待っていたライリー。
彼は言う--彼女のことを、ほんとに愛することができないんだ。そうすることが僕の願いなのに。
すると聞き手の一人が答えるのだ--お前は反対の方向から始めようとしたのだよ、ライリー。どうして一人の娘を想うことができる? 今まで一枚の木の葉にでも心を寄せたことがあったかね? 一枚の木の葉、一握りの種、まずこういうものから始めるんだ。そして愛するとはどういうことなのかを、ほんの少しずつ学ぶのだ。
神への愛について。
苦悩の中のA。彼は一枚の木の葉を前に自問する--これと神と、己れはどちらをより愛しているか?
そうやって一つずつ、すべてを切り捨ててゆくことが、神への愛を培う唯一の方法だと思っていた。こうして世界はどんどん色あせ、すさんでいった。
しかし、キリスト自らそう問うたのではなかったか? 彼はペテロにそう問わなかっただろうか--しかも三度も。「あなたはこれらのすべてよりも私を愛していますか」と。
そして、インディサイスィヴであることもまた罪なのだ。
「汝らいつまで二つのものの間にてまよふや エホバもし神ならば之に従へ されどバアルもし神ならば之に従へ」---1Ki18:21
ずっと長い間、Aは恋人から結婚を迫られている男みたいに、ぐずぐずと決定を引きのばしてきたのだった。
Aは神に献身しなければならないと分かっていながら、尚どうしても自分を捨てられずにいた、そしてそういう自分のふがいなさにすっかり嫌気がさしていた。Aにはいやというほど分かっていたのだ--エリオットが皮肉って言ったように、我々は決定を引きのばす強さだけでなく、決定を下すだけの強さをも持たなくてはならないことを。
どれだけ長い間、Aは絶望的になりながらも、己れの心を神に屈伏させようとして必死に戦い続けたことだろう--Aは常に戦場だった。
そしてその間にもどんどん時間は経ってゆき、女の方は待ちくたびれて年をとってゆく。これは神の忍耐が尽きて、終末が到来するのに相当する。
どっちつかずの辛さというものは、Aの場合、精神的な、形而上学的なものでは全然なかったのだ。それはもっと身近で、それこそ肌で感ぜずにはいられないような種類のものだった。すなわちAのまわりには、小さい頃から神の言葉を教え込まれてきた従順な優等生たちがいっぱいいて、彼らが組織の規範に則って一つ一つ着実に段階を踏み、さいごに神への献身と全き自己放棄の象徴としての洗礼を受けてゆくのを、Aはずっと見てきたのだ。Aと大して年も変わらず、あるいは年下でさえあるのに、彼らが神の前に於ける立場の点でははるか先へ行ってしまっていて、一方己れは自らの不従順ゆえに一人取り残され、どうしようもない劣等感に苦しめられているのだった。
そして、この国にあって、神についての概念が全然一般的でない中にあって、キリスト教徒であることの意味するところを彼らが十分には理解していないとしても、それは問題ではなかった。神にとって重要なのは、人が何を理解しているかということよりも、どんなふうに生きているかということなのだ。そして神のもとにとどまって学び続ける限り、人はまた必ずや理解をも得るのだった。
「お許しください、私はほんの少年にすぎません」
と言ったエレミヤに向かって、神は請け合わなかっただろうか--
「私があなたと共にいて、あなたを助ける」と。
彼らはそこまで深い認識なしにバプテスマを受けるかもしれない、しかし彼らはその誓いに調和した生涯を送る。そのために自分で考えるということをついに知らぬまま終わったり、幾分パリサイ人化したりもするかもしれない。それでも尚、いちばん重要なのは、神に仕え続けることだった。
あるいは伝道活動。
訪問を受ける側にしてみれば、それはただ腹を立ててドアをバタンと閉めるか、またはご苦労さんといって雑誌を受け取るくらいのことにすぎなかった--ものの一分もかかりはしない。しかし、訪問する側はドアを叩くたびに、迫り来る終末からの救いと、神への献身に至る長い道のりの始まりとを提供してたのだ。自分がそれを選び取れないでいるAにとって、それは最高に不誠実な行為だった--己れに対しても神に対しても。
それゆえAは苦しんだ。それでも尚Aは出掛けていった--行って王国を宣べ伝えよと、神が命じていたから。
* *
カポーティの<ティファニーで朝食を>。
ヒロインのホリー・ゴライトリーは、もとは貧しい孤児である。三十年代南部のひどい時期、盗みを働いて食いつなぎ、やがてとある農家に引き取られて養われることになる。そして、十四の年で、男やもめであったそこの主人と結婚する。みんなに大事にされて何不自由ない暮らしだったのに、彼女は田舎での平穏な暮らしに飽き足りず、やがて家を飛び出して都会へ行ってしまう。
ホリーはチャンスをつかむ。O.J.バーマンなるマネージャーに見い出されて、映画女優となる訓練を受けるのだ。ところが、富と名声の可能性をあっさり捨てて、ある映画の大事なテストの前日、彼女はふらりとニューヨークへ飛んでいってしまう。
そこから電話をかけて、彼女は言う、あたし今ニューヨークに来ているの。
何だってニューヨークなんかに? バーマンは激昂してつっかかる。
あたしニューヨークに行ったことがなかったから来てみたのよ。
すぐ戻ってこい、このバカ者!
いやよ。
何だって? 一体何を考えているんだ?
あたしあんな役やりたくないわ。
じゃあ、一体何をやりたいんだね?
それが分かったらいの一番にあんたに知らせるわ。
こうしてニューヨークに住みついたホリーは、職にも就かず、飼い猫に名前もつけず、アパートの表札には<旅行中>と記して、男たちから貰うチップで気ままな独り暮らしを続けている。
語り手の青年が彼女と出会ったのはこんなときだった。ときにホリーは十八才だ。
あたし、もちろんお金もほしいし、有名にもなりたいのよ、と彼女は説明する。でもそのために自分自身でいることを犠牲にしたくないの、決してね。いつかあたしがあたし自身でいられるような安住の地が見つかったら、猫に名前をつけて、家具でも買うことにするわ。
仮住まいのホリーのアパートには家具らしきものがなくて、スーツケースをひっくり返してテーブルにしている。
ホリーはすらりとしてスタイルがよく、いつも地味だけども趣味のよい恰好をして(黒、ブルー、灰色)、そして「レモンか、朝食のシリアルのように」清潔である。ときどき「いやな赤」に悩まされ、タクシーに飛び乗って五番街のティファニーに駆けつけたりする。
そう、彼女にあっては形而上学的苦悩も、ときどき心の片隅を曇らす「いやな赤」にすぎない。
人は誰でも自分と正反対の人間に憧れるというのは本当ではないか?
こんな小粋で自由でよるべないホリーの生き方にこそ、Aは憧れてやまなかった。ひとときの心の慰めを求めて陽だまりに腰を下ろし、(映画の中でホリーがしたように)ギターを取って<ムーン・リヴァー>を歌っては、彼女の手にしているような自由--物理的、精神的、道徳的自由に、自分がいかに遠く隔たっているかを思うのだった。
<ムーン・リヴァー>の歌詞は原著にはない--映画化されるにあたって新たに書き下ろされたものである。けれどもそのメロディーが、ホリーの生き方全体に流れている、そこはかとなくよるべない気分を何と的確に表していることか--
Moon River, wider than a mile
I'm crossin’ you in style someday ・・・
<大きな河>というイメージは、ホリーの生まれ育った南部を想起させる。例えば、ミシシッピー。ホリーが五才くらいのときに、大河の土手をよちよち歩きながら対岸も見えないくらいの茶色いしずかな水の広がりを見渡して、いつの日かここを渡ってやろうと実際心に誓った、と考えてもいい。しかしそれはまた、成長してニューヨークに住む彼女の心象でもある。ムーン・リヴァーの向こう側は、ホリーの探し続けている安住の地を象徴する。けれども安住の地なんてものは、本当はどこにも存在しないのだ。それは美しい幻だった--渡ってみたところで茫漠とした大地と、また次のムーン・リヴァーが広がっているにすぎない。無数のムーン・リヴァーを渡ってゆくこと、それが人生というものなのかもしれないが--。
Aが神のもとに縛られていたころは、こんな詩的なニヒリズムを持つことは許されなかった。神の要求する生活はあまりにも散文的だった。人生は確たる目的を持っていて、人は日々それを目指して努力し続けなければならなかった。
しかし尚、絶対者によって定められた目的以上に、人生にとって必要な何物があろう? それゆえ、Aはとても長いこと、己れを神に振り向けさせようとして労苦した。
神と文学との対立。
「我らはもろもろの論説を破り、神の示教に逆ひて建てたる凡ての櫓をこぼち、凡ての念(おもひ)を虜にしてキリストに服(したが)はしむ」---2Co9:4,5
神への献身は、一切の事物を神に屈服せしめることを意味した--それは太古より今に至るまで、生み出されてきたすべての文学のうち、神の規準にかなわない一切の部分を否定することを意味した--例えば、<ムーン・リヴァー>の詩情ですら。
そのことを考えるとAは眩暈を覚えた。
それでも尚、神への愛ゆえにAはそれをしようとした。Aは自分が出会うすべての文学を、神の道徳規範をもって裁断した。Aはミューズを冒瀆した--かつて一身を捧げてきた偉大なミューズを。それはあまりにも酷たらしいことだった。アブラハムの手をとめる天使は現れなかった。Aは自ら切り刻んだ文学の血にまみれ、神に向かってうめいた--エホバよ、ここまでひどいことを、あなたは私に要求なさるのですか。
それゆえにAは神を憎悪した。
文学とは何か。神への愛とは。
それが分からないで、尚存在し続けるのはほとんど不可能だった。
もはや存在し得ないところで存在し続ける苦悩。
* *
それからさらに長いときを経て、Aはグリーンとかチェスタトンとかエリオットに出会い、自分が今まで文学だと思っていたのとは全然違うような<文学>が、この世の中には存在することを知ることになる。
それは驚異だった--彼らが、文学によっても神に栄光を帰することができると、半ば本気で信じていたらしいことは。
彼らはヨーロッパ的文学観の最も伝統的な部分を受け継いでいた。その見方によれば、文学の本質的な存在意義とは、読者を宗教的道徳的に裨益すること--バニヤン流にもっとはっきり言えば、読者を神のもとに導くこと--だった。そして、こうした見方からすれば、文学は今なお二義的な位置に甘んずるのであり、それ自身によって立つ価値とか力とかを持つことはない。エリオットがしばしば文学それ自身の無意味さとか無根拠さについて語っているが、それは誠実な物言いであると思う。しかし、もっと後代に下るにつれて文学は饒舌になり、バニヤンの硬直から次第に自らを解き放ってゆく。想起せよ--彼らの詩や小説や戯曲、それらが神を、神へ到る困難な道のりを語りながら、いかに手の込んだプロットや小道具や情景描写を併せ持ち、力強さと文学的感受性と想像力とに溢れ、そして--対話に満ちているかを。
そう、それらは神をたたえることによって死んでしまってはおらず、否、神をたたえることによって生き生きと生命にあふれていた。彼らの多くは道徳的問題をその作品の中心に据え、その批評の多くもまたしばしば道徳的視点からなされている--そしてまさにそのことが、人の精神を力強く鼓舞しているのだ。
そしてまた、彼らの罪の扱い方についても。そう、最もキリスト教的な文学とは、姦淫や殺人について語らない文学ではない。想起せよ--聖書そのものが、どれだけ夥しい罪の記録に満ちているかを。しかし、そこには厳然たる道徳的視点があって、義なる者は祝福され、悪しき者は裁かれるのである。その視座、その力、その行動によって、夥しい罪の記録は聖なる書と呼ばれている。
それゆえ、いやしくも神にとって有用な文学というものがあるとすれば、それは、こうでなくてはならなかった。
こういった種類の文学に、自分はなぜもっと早く出会えなかったのだろうかと、Aはしばしば訝ったものだ。
彼らは--つまり、Aの属していた組織の指導者たちは--羊たちが、世俗のキリスト教文学と言われる書物を手に取ることを喜ばなかった。どちらかと言うと、避けたがっているふうにさえ思われた。それはなぜだったんだろう? 聖書だけ読んでいたのでは理解できなかったであろう幾多の概念を、自分はそれによって理解し得たのに。ずっと長いこと、Aはそれらの概念を、まるで目隠しされ、手袋をはめた手で彫像を触るような仕方でしか理解できないできたのだ。そしてまた、彼らはみな、あれだけ誠実に神を求め、あれだけ突きつめてものを考え、あれだけ魂を傾けて書いたのに。
教義上の意見の相違によって、良心が混乱させられるから?
あるいは単に、神のためにのみ費やされるべき時間や注意力を、不当に奪われるから? それとも、いかに偉大な文学といえども、所詮は死すべき人間の手になる業であり、不謬じゃないから?
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
この作品について 目次
-22- 文学の問題、その1
文学の問題。
神々は、我々を人間とする為に何らかの欠点をお与えになる。
・・・You, gods, will give us
Some faults to make us men.
---<アントニーとクレオパトラ>第五幕第一場
Aはこの言葉が文学の問題の本質を突いているのを感じ取って、長らく忘れられなかった。
我々はここでの神が小文字のgodsであって、大文字のGod ではないことに留意すべきである。God は--キリスト教の神は--我々を人間とするために欠点を与えたりしなかった。その神は我々を、はじめから完全なものとして創造したのであり、人間の方が自ら罪を犯して不完全なものとなったのだ。
ところが人間のその不完全性が、文学に対して--あるいは芸術全般に対して--はかりしれない奥ゆきと広がりと深みとひだとを与えてきたこと、これは否定し得ない事実ではないのか? いや、順序から言えば、人間の不完全性こそがこの不完全なる世界における芸術を生み出してきたのだ。それでは、人間の罪と、それゆえに生じる一切の苦しみと理不尽--それは芸術のための必要悪なのか?
ヴォルテールの"The World It Goes" 。
これはヨナ書のパロディーである。
流血の都市ニネベ。
神は預言者ヨナに命じて「彼らの悪が私の前に達したことを」告げさせ、「あとわずか四十日でニネベは覆される」ことを布告させる。
すると驚くべきことに、住民たちはこぞって悔い改め、その悪と暴虐の道から引き返して神に信仰を置くようになる。この知らせがニネベの王のもとに達すると、彼は自ら粗布を身にまとって灰の中に座り、悔い改めを布告する。
「まことの神が翻ってまさに悔やまれ、その燃える怒りから離れて、我々が滅びないようにしてくださることはないと、誰が知っていようか。」
それで神は彼らがその悪から立ち返ったのを見て、彼らに加えると宣言したその災いを加えなかった。
ヨナ書の大筋はざっとこの通りである。
しかるに、ヴォルテールの短篇においてはニネベがペルセポリスに変わる。滅びの宣告を携えてゆくのは、ヨナではなくて一人の天使である。
彼はペルセポリスを検証すべく、しばらくそこに滞在する。なるほどその都市は悪徳と不徳義に満ちている。ところがそこに住むうちに、天使はだんだんとその都市が好きになってくる。なるほど悪徳に満ちてはいるが、それに勝って人間的な魅力に富んだ都市でもあったのだ。
そこで天使は一人の職人に命じてダイヤモンドと土塊とで彫像をつくらせ、それを神のもとに持ってゆく。
「神よ、これがすべてダイヤモンドでできてはいないという理由で、あなたはこの愛らしい彫像を壊しておしまいになりますか」
それで神はペルセポリスを滅ぼさなかった。
この二つの話において、決定的な違いは、滅びを宣告された人間の側の行動にある。すなわち、ニネベの人々は己れの悪を捨てたので、神もまた加えようとしていた災いを放棄した--この点において神の言葉は果たされなかったが、その目的は悪を断ち滅ぼすことにあり、それはすでに達せられていた、すなわち、邪悪であった人間がもはや邪悪でなくなっていたからだ。だから神の威信は少しも傷ついていないし、その義の規準も侵されていない。ところがペルセポリスの場合、人々は何らの変化も遂げないのであり、逆に神の方が天使に説得されて考えを変えるのだ。これは、ヒューマニズム--人間至上主義の威光の前に、神の権威ですら退けられることを意味する。
十八世紀のオプティミズム、科学の発達、啓蒙思想。人間性への無邪気な信頼が、ヴォルテールとその時代の特色だった。
人間は人間だけで善悪の規準を定めてやってゆける--それはまさに、エデンで蛇がエバをたぶらかした言葉ではなかったか。
エデンからの追放、ないし脱出、それは人類の原風景である--禁断の木の実を手にしたとき、エバはエデンを捨て、神の権威を退けた。彼女は「神の如くなり、決して死することなし」という蛇の言葉を信じたのだ。近代のヒューマニストも基本的には同じことを繰り返したのであり、ただ彼らは、蛇と違って自らの主張を誠実に信じていたのだった。
ヴォルテールの神は偶像を打ち壊さなかったが、1914年から始まる一連の出来事がそれを打ち壊した。人間は人間だけでけっこううまくやってゆけるのだ、そりゃあ神の目から見れば不完全で罪深いかもしれないが、それなりに、いやそれだからこそ、魅力的で愛すべき存在ではないか。--そういう幻想を、この現実が打ち壊したのだ。
1914年8月4日、ヘンリー・ジェームズの書簡。
「我々が今、悪夢の中に生きているのではないように語ってもむだなことです。過去の恐るべき流血と恐怖の深淵に、文明社会はつき落とされてしまったのです。時に後退することはあっても、世界は次第によくなると信じてきた我々の年月は、すべてむだになってしまいました。けれどもこの欺瞞の年月の間に我々が目指し、意図してきたもののすべてを今ありのままに受けとめるというのは、あまりに悲劇的で、言うべき言葉も見つかりません。我々の過去の愚者の楽園の一切が、その正体を暴露されてしまったのです。そんなもののためにえいえいと努力してきたとは、我々は何と愚かだったのでしょうか。」
打ち砕かれた人間至上主義の悲しみ。
人間の罪は、文学にとってたしかに豊かな源泉となってきたかもしれない。けれど、<孤独の発明>以後、Aは思うようになった--文学が必要とする苦しみと理不尽の最大指数というものが仮にあるとして、この世界はそれをはるかに凌駕している。
それゆえマヤコフスキーは自ら命を絶った。彼は二十年代ソ連における農村の惨状を目にして、自分が見たものを書き続けることにもはや耐えられなかったのだ。
「詩人マヤコフスキーは私が何とか理解しようとして果たさなかった詩人だが、偉大な才能の十字架と共に、憎しみ、怒り、暴力を背負い、自分と自分の民族の苦悩に意味を見いだすことに失敗した人間だった。・・・天才がいかに偉大であろうと、いつまでも無限に否定だけを糧にしては生き続けられない」 --ロレンス・ヴァン・デル・ポスト<ロシアへの旅>
あるいはアドルノ--「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」
Aは、神によって断罪された文学の死を悲しむ。Aはペルセポリスの像のために、丘の上で哀歌を唱えたいと思う。
それでも尚、だれもそれを凌駕できない。なぜなら、相手は神だからだ。神を捨てること、拒否することはできる。しかし、凌駕することはできない。
再びローマ書--「すべての人は罪を犯したので神の栄光に達しない」
* *
文学と完全性について。
将来地上に回復されることになっているパラダイス、完全なる人間の住む完全なる世界、そういう世界に文学の生まれる余地はあるか?
「神は光であり、神との結びつきにおいてはいかなる闇も存在し得ない」--そのような世界に、文学は存在し得るのか?
Aはかつて自分の属していた会衆を思い出す--彼らのうちに、思想においても言動においても存在する、越えることを許されない明確な一線。悪を絶対に許容しない、道徳的な強靱さ。文学も芸術も「もののあはれ」も幽玄の興趣も、何ものもその倫理規準を超越することは許されない。エホバ--愛と義のアマルガム。
彼らのうちに文学らしきものが存在するとしても、それはいつでも真理のプロパガンダ装置もしくはその探究の手段であり、決して文学そのもののための文学ではなかった。けれど、ああ--神の規準によって真ん中で分断された「もののあはれ」など、とても見られたものではない。
そういう人々のうちにあって、文学はどうすればいいのか。ただ真理のプロパガンダに専念していればいいのか。中世の聖者伝、あるいは長らくロシアの文壇を毒してきた社会主義リアリズムのようになってしまっていいのか。それでは文学の死ではないのか。それとも、(カフカについて一注釈者が書いたように)文学とは真理の探究であるなら、真理が見い出された今、文学は死んでしまって構わないのか--真理がそれほど貴重なものであるなら。
* *
一方、Aにとって文学の本質とは、他でもない、<神への反逆>だった--他に何があろう? それは神の創造したこの世界に対抗して、全く別の、新しい秩序を打ち立てる行為であり、神の定めた<世界の真実>に対する、最も深い意味での挑戦だったのである。Aの創り出した世界では、人は神に仕えることなしに幸福に生きることができ、社会は神の権威なしに立ちゆくのだった--すなわちそこにおいては蛇の嘘が真実となったのだ。それゆえAの<文学>は、例えば<権力と栄光>の背景となった六十年代のメキシコや、ソ連におけるような共産主義革命なんかよりも何倍も重い罪だった。なぜなら、革命は現実の世界に起こったのであり、現実の世界は常に神の定めた<世界の真実>に左右されているからだ--人々の間でキリスト教がどれほど衰退しようと関係ない、それはもっとアプリオリなものであって、あらゆる人間はついにそれから逃れられないのだ。げんに二十年代に始まるソ連の惨状は、神なしのユートピアの建設が不可能であったことを反駁の余地なく実証して、「此人彼人を治めてこれに害を蒙らしむることあり」という神の言葉の正しさを、逆説的に明らかにした。だからもしも、人がこの過程をつぶさに観察して、神の正しさについて確信を得、その結果神に仕える生き方を選ぶ決定を下したとすれば、それは神にとって喜ばしいことではないか?
そしてそれは、革命がどれだけ大量の、罪のない血を流したとしても尚真実なのである。実際、神が現在に至るまで、エデンの外における人類の存続と、その道徳的混乱の存続とを許している理由はここにあるのではなかったか?
それに対して、Aの<文学>は一滴の血も流さないので、一見すればそれは無害と思えるかもしれない。しかし、こういうことが起きたとしたらどうだろう? 仮にAの書いた小説が世に出たとする。そして、経験の少ない、若いキリスト教徒がそれを読み、それに影響されて神なしのユートピアの可能性についての幻想を抱くようになって、その結果神の道から迷い出るようなことになったとしたら? そして、終末のときにこの世と共に滅ぼされるようなことになったとしたら?
そうしたら、神のもとから一つの魂が失われたことに対してAは間違いなく血の責任を負うのであり、「これら小さな者の一人をつまづかせるよりは、挽き臼を首にかけられて海に投げ込まれた方がましである」とのキリストの言葉を身に受けることになるのだ。
こうして、間違った思想が間違った行動の萌芽として、行動そのものより罪深いとすれば、神の目には、スターリンよりもマルクスやロバート・オーウェンの方がなお罪深いと、我々は考えることができないだろうか?
ナジェージダ・マンデリシュタームが、二十年代の文化人たちを批判した言葉を思い出されるだろうか。二十年代そのものは躍動に満ちたすばらしい時代だった、ただそのあとの路線を誤ったからすべてがおかしくなっていったのだという考えを、彼女は退けている--「彼らは、その後起こったことに対して責任を認めていないのである。しかし、果してそうだろうか? なにしろ、当時あった価値観を破壊して、新しい国だ、未曾有の実験だ、樹を伐れば木っ端は吹っ飛ぶといった、今もなくてはならない形式を発見したのは、他ならぬ二十年代の人々だったのである。すべての死刑は、目下我々は二度と暴圧のない社会を建設しているのだから、・・・どんな犠牲も許されるのだと、正当化されていたのである。・・・」
ところで、ここで我々は「神に断罪される共産主義」という図式を転換して、「自分の認める以外のあらゆる文学形式を断罪する、キリスト教のアナロジーとしての共産主義」という図式によってもまた、この問題を考えることができる。共産主義思想がキリスト教から生まれたことを、"Portage" のヒトラーも指摘していなかっただろうか。ナジェージダ・マンデリシュタームもまた書いている--「信奉者たちがつつましくも科学と呼んでいたこの宗教が権威を授けた人間は、神様並みに高められる。この宗教は、自分の信仰の象徴と道徳とを作成した。・・・一九二〇年代には、少なからぬ人々が、キリスト教の勝利の歴史から類推して、新しい宗教の千年王国を予言した。さらに最も良心的な人々は、教会の犯した歴史的な罪業を列挙しながら、キリスト教の本質は宗教裁判によっても変わらなかったくらいだから、新しい宗教もそうだろうと類推をたくましくしたのである。・・・」
そしてこの新しい宗教が、文学に対していかなる態度を取ったか--
「わが国では遠慮会釈なく経歴や死亡年月日が歪められている。オシップがヴォロネージでドイツ人に殺された、という噂を流したのは誰か? 収容所で大量に人が死にだしたのは四十年代初めからだ、といっているのは誰か? 現存の、また物故した詩人たちの詩集を立派な作品はみなわざと抜かして出版しているのは誰か? 命を落とした作家や詩人、今も生きている作家や詩人のもう出版されるばかりになっている原稿を、何年も編集局にしまいこんでいるのは誰か? そんな例はとても全部は数えきれない。さまざまな形の保管庫にしまいこまれたり、埋もれたりしているものはあまりにも多く、焼き捨てられたものはさらに多いのである」
「・・・この時代の注目すべき特質は、人を殺し自分も命を落としたこういう新しい人たちすべてが、自分だけにしか思考し判断する権利を認めていなかったということであった。・・・昼夜時を分かたず護衛つきで自分たちのところへひっぱってこられる人間が、自分に自由な詩を書く権利があることをいささかも疑っていないと知ったら、取調官の誰もが哄笑したことだろう。・・・ヤーゴダはオシップの詩がすっかり気に入って空で覚えていたほどで、・・・この詩をブハーリンに自ら読んで聞かせたのだが、自分に有利だと考えたなら彼は過去、現在、未来のすべての文学をためらうことなく抹殺したにちがいない。」
「スルコフはパステルナークの小説がどうして悪いのか私に説明してくれた。ドクトル・ジヴァゴにはわが国の現実を判断する権利がない、我々は彼にそういう権利を与えなかったのだから、というのである。」
「死に方を選びながらオシップは、わが国の指導者たちの・・・詩へのはかりしれぬ尊敬を引き合いに出して、私を慰めるのであった。『嘆くことはないじゃないか。詩が尊ばれているのは、わが国だけだよ。詩のために人殺しをやっているのはね。詩のために人がこんなに殺される国はどこにもないからね』と彼は言うのだった。」
「・・・家政婦は、自分たちはみな不法に流刑に処されているのだと主張していた。たとえば彼女だが、彼女は逮捕される頃にはもう自分の党の仕事から離れていたし、逮捕されたときは私人であった。
『彼らだってこのことは知っていましたよ!』
と彼女は言うのだった。だが私には・・・どうも彼女の主張が分からなかった。粉砕された党の一員であったことを自ら認めるなら、なぜ彼女は自分が流刑に処せられていることに腹を立てるのだろう? わが国の基準からすればそれが当然なのである。そう私はその時考えていた。『わが国の基準』は・・・恐ろしくて残酷だが、それが現実であり、強大な権力は、たとえ今は活動していないにせよやはり動きだすおそれのある公然の敵たちを黙って見ているわけにはいかない。・・・
「ナールブト・・・の観点からすればオシップを流刑に処さないわけにはいかなかった。『国家は自衛しなければならないだろう? でなければどうなるか、考えてごらんよ』
私は反駁しなかった。出版されたのでもなければ公衆の前で朗読されたのでもない詩は思想と同じである。思想ゆえに人を流刑にはできないと、言い争ったり説明したりする必要があっただろうか。」
思想ゆえに人を流刑にはできないだって?・・・とんでもない! 思想こそは全く、そのために人を流刑にしたり殺したりする最大の根拠なのである。イエスも言ったのではなかったか--「心から出るものが人を汚す」と。
あらゆる罪と反逆とは思想から始まる。最初の罪は一人の天使の心の中で始まったのだ。彼の「思想の自由」ゆえに。それがまた「女を見てこれに欲情を抱く者は・・・」ということの意味だし(ノアの日に、「まことの神の子ら」においてそれがいかに真実となったかを見よ)、それがまた「神を愛せ」という第一の掟の意味でもある。最大の掟がかくのごとく、法律をもって罰することのできない掟であったことには意味があるのだ。この掟は、心を、思想を支配する掟であったからだ。
共産主義がキリスト教のアナロジーであるのなら、そのもっとも忌まわしい部分もまた、キリスト教にその原型を見い出すことができるのである。
それゆえ、キリスト教は、あらゆる芸術がそこから生み出されるところの精神性のあり方そのものを規定するのであるから、芸術の立場からすれば、それは芸術に対する最大の冒涜である。他方、キリスト教の立場からすれば、芸術は、神に対する精神の全き服従という第一原理を無視しかねないのだから、芸術のそういう本質こそは神に対する最大の冒瀆である。
スターリン主義と文学とのあの軋轢に満ちた関係から、我々はこの本質的真理を学ぶことができるのである。
自らの芸術によって新しい世界を創造すること、自らの芸術を神と張り合う位置にまで高めること。
芸術の持つこういう力を認識するとき、中世ヨーロッパにおいて役者や音楽家が賤民の部類に入れられていたのは何ら驚くべきことではない。そうすることによって教会は、芸術をくびきのもとに屈伏させ、芸術から自らを守る必要があったのだ。カミュによれば、十八世紀においてすらそうだった。
「俳優のこような習練をカトリック教会がどうして断罪しなかったはずがあろう。この芸術における魂の異端的増殖、感情の放蕩、ただ一つの運命しか生きぬことを拒み、あらゆる放埒に身を投じてゆく精神の破廉恥な意図を、教会は退けた。・・・それらは教会の教えるものすべての否定に他ならないからだ。永遠は演技ではない。永遠より芝居を好ほど無分別な精神は、自分の救いを失ってしまった。・・・俳優という実に卑しめられていた職業が、異様なまでの精神の葛藤を引き起こす所以はここにある。
「十八世紀の著名な悲劇女優アドリエンヌ・ルクーヴルールは、臨終の床で懺悔と聖体拝受を望んだが、その職業を否認することは拒んだ。それゆえに彼女は懺悔の恵みに浴することができなかった。まさしくこれは、自分の深い情熱を選び、神を敵とすること以外の何であろう。そして、臨終の苦しみにあったこの女性は、自分が芸術と呼んでいたものの否認を涙ながらに拒むことによって、かつて彼女が舞台で脚光を浴びていたころには絶対に達し得なかった偉大さに達したことを証明したのである。それは彼女が演じたうちでもっとも見事な役、しかももっとも困難な役であった。天と、それに比べればいかにもつまらないものに思える自己への忠実とのどちらを選ぶか、永遠より自己をよしとするか、それとも神の中に身を沈めるか、これは敢然として生きねばならぬ数世紀来の悲劇なのだ。
「当時の俳優たちは自分が破門されていることを知っていた。俳優という職業に入ることは地獄を選ぶことだったのだ。そして教会は彼らの中に最悪の敵を見ていた。文人たちの中には、『なんだと、モリエールに最後の救いを与えることを拒否したんだと!』といって憤慨する者も何人かあった。だがそうした教会の態度は正当だった・・・」<シーシュポスの神話>
* *
当時小学生だったAは、これだけのことを言葉にして意識化するだけの知的な勇気も、冒瀆的な正直さも持ち合わせていなかった。しかしながら自分がしていることの意味をおぼろげながら認識していて、その認識がまた、Aを苦しめたのだった。なぜなら、当時のAはまだ、神を捨てていいとは思っていなかったからであり、神への崇拝をどんなに重荷と感じても、その必要性については何の疑問も抱いていなかったからだ。
それでも尚、Aにとって<文学>は、重苦しい神の権威からの唯一のサンクチュアリであり、道徳的アムステルダムだったのだ。当時Aの属していた会衆では、あらゆる楽しみが断罪され、芸術的感性は絞殺されて死に絶えていた。集会に連れられてゆくとき、Aはいつでも戸口に傘を置くように自分の<文学>を置いて中に入り、帰るときにまた持ち帰ったものだ。そこは全く、十七世紀のボストンみたいなところだった。それにもちろん、神の命令は(愛せよ、従え、善良なれ)、Aがどこにいてもつきまとってきた。ペンを手にして紙に向かっているときだけ、Aは自由に息をすることができたのだ。この領域までも神の手に引き渡すなどということは、Aにとって、考えるだけでも耐えられなかった。自分の内的世界全体が根こそぎ奪い取られるようで、そんな想念が頭をかすめるたびに、Aはぞっとして身震いした。
けれど、そんなふうにいつまでもどっちつかずの状態でいるわけにいかないことは、Aにもよく分かっていた。Aは知っていた--あまり考えたくはなかったが--将来のいつかに、どうしても避けられない、命がけの対決が控えていることを。
Aはまさに最初から、引き裂かれた存在だったのだ。
一方では、自分はもちろん神に仕える人生を歩むことになるだろうと思っていたし、もう一方では、もちろんそんなことにはならないだろうと思っていたのだから。
* *
それから、<孤独の発明>との出会いがやってくる。
ここにおいてAははじめて、伝統的ヨーロッパ的文学観に出会ったといっていいだろう--すなわち、文学とは形而上学的な問題に渡るものであり、また、渡るべきものであるということ。
それより三年ほど前に(Aは十四かそこらだった)、Aは同じオースターの<幽霊たち>に出会っている。それも衝撃的な出会いだった--近代世界がカフカに出会ったときの衝撃。こんな小説が書かれ得るのか! と思ったものだ。その頃のオースターのキャッチフレーズは<エレガントな前衛>だった。
恐らく<幽霊たち>を知らなかったら、<孤独の発明>との出会いもこれほど強烈ではなかっただろう。あの小説を書いた、彼ですら意味を求めていること--「彼もまた意味を渇望している」
これまでの歴史の中で引き起こされてきた、世界中の苦しみ--これらすべてには一体何の意味があるのか、どこかに救いはないのかと、凄まじいばかりに問いかける彼の姿。「世界は残虐であるがゆえに。世界は人を絶望にしか導きえないゆえに。ひとかけらの救いもない絶望、どこにも出口のない絶望。何ものもこの牢獄のドアを開けることはできない。希望の消滅、それがこの牢獄の名だ。・・・彼はこれ以上先へ進めない」
けれどもこれほどまでの世界の絶望は、ちょうど逆光になったものの影の濃さが背後の光の強烈さを際立たせるように、Aをして、劇的な仕方であるものの存在に対して目を開かせたのである--すなわち、神の希望に対して!
生まれてはじめて、Aは自分が長年にわたって提供されてきたものの何たるかを理解した。すなわち神の教えとは、この世界の道徳的無秩序に対する答えであり、意味であり、救いであったのだ。
その本を一気に読み通したときの感動を、Aは思い出す。
それはダマスカスに向かうサウロの前に現れたまぶしい光さながらだった。その日を境に、Aは突如急転回して神の道を突っ走りはじめる。
Aを根底から揺さぶったあの感動に、Aの激しい思い込みと、思い込んだら誰にも動かせない頑迷さと、命がけで突っ走る激烈さとが結びつけば、始末に負えないパリサイ人ができあがるのは火を見るより明らかだった。
Aは思い出す--自分の目を開かせてくれた感謝と共に、ぜひとも彼に真理を伝えなければという使命感に駆られ、拙い英語で便箋十枚ばかりの手紙を書きつづってオースターに送ったこと。その手紙が住所不備で結局彼のもとに届かなかったことを、Aは全くもって感謝する次第である--誰に? 恐らくは、<現代の無>に。
それからAが苦悩に押し潰されて身動きがとれなくなるまでに、長くはかからなかった。人に向けた鋭い裁きの刃を、Aは自分自身に対しても突きつけたからだ。
とりわけAを苦しめたのは愛の問題だった。
「あなたは心をこめ魂をこめ、思いをこめ力をこめてあなたの神エホバを愛さねばならない--これが最大で、第一の掟です」
Aは神を愛せなかった。
苦悩が言葉を持つ前の、果てしない苦悩。
苦悩が言葉を持って語りだしてからの、再び、果てしない苦悩。
自らを説得しようとして自問自答を続けたために残された、膨大な量のメモ--あまりに教唆的で、あまりに容赦なく、読み返そうとしても目に触れただけで、当時の精神状態が思い起こされて息苦しくなり、吐き気がしてくる。
神への愛について。
フェデリコ・フェリーニの<道>。
ジェルソミーヌと連れの男が、旅の途中でとある修道院に一夜の宿を借りる。そこの修道女の一人が、ジェルソミーヌに向かってこんなふうに語りかけるのだ。
「旅をされているのですね。私たちも、二年ごとに修道院を移り住んでいるのです」
「なぜ」
「長く暮らしていると、庭の草一本にでも愛情がわいて、その分だけ神様へのおつとめがおろそかになります」
その反証。
カポーティの<草の竪琴>。
恋人と一緒に、線路の上に止めた車の中で列車がくるのを待っていたライリー。
彼は言う--彼女のことを、ほんとに愛することができないんだ。そうすることが僕の願いなのに。
すると聞き手の一人が答えるのだ--お前は反対の方向から始めようとしたのだよ、ライリー。どうして一人の娘を想うことができる? 今まで一枚の木の葉にでも心を寄せたことがあったかね? 一枚の木の葉、一握りの種、まずこういうものから始めるんだ。そして愛するとはどういうことなのかを、ほんの少しずつ学ぶのだ。
神への愛について。
苦悩の中のA。彼は一枚の木の葉を前に自問する--これと神と、己れはどちらをより愛しているか?
そうやって一つずつ、すべてを切り捨ててゆくことが、神への愛を培う唯一の方法だと思っていた。こうして世界はどんどん色あせ、すさんでいった。
しかし、キリスト自らそう問うたのではなかったか? 彼はペテロにそう問わなかっただろうか--しかも三度も。「あなたはこれらのすべてよりも私を愛していますか」と。
そして、インディサイスィヴであることもまた罪なのだ。
「汝らいつまで二つのものの間にてまよふや エホバもし神ならば之に従へ されどバアルもし神ならば之に従へ」---1Ki18:21
ずっと長い間、Aは恋人から結婚を迫られている男みたいに、ぐずぐずと決定を引きのばしてきたのだった。
Aは神に献身しなければならないと分かっていながら、尚どうしても自分を捨てられずにいた、そしてそういう自分のふがいなさにすっかり嫌気がさしていた。Aにはいやというほど分かっていたのだ--エリオットが皮肉って言ったように、我々は決定を引きのばす強さだけでなく、決定を下すだけの強さをも持たなくてはならないことを。
どれだけ長い間、Aは絶望的になりながらも、己れの心を神に屈伏させようとして必死に戦い続けたことだろう--Aは常に戦場だった。
そしてその間にもどんどん時間は経ってゆき、女の方は待ちくたびれて年をとってゆく。これは神の忍耐が尽きて、終末が到来するのに相当する。
どっちつかずの辛さというものは、Aの場合、精神的な、形而上学的なものでは全然なかったのだ。それはもっと身近で、それこそ肌で感ぜずにはいられないような種類のものだった。すなわちAのまわりには、小さい頃から神の言葉を教え込まれてきた従順な優等生たちがいっぱいいて、彼らが組織の規範に則って一つ一つ着実に段階を踏み、さいごに神への献身と全き自己放棄の象徴としての洗礼を受けてゆくのを、Aはずっと見てきたのだ。Aと大して年も変わらず、あるいは年下でさえあるのに、彼らが神の前に於ける立場の点でははるか先へ行ってしまっていて、一方己れは自らの不従順ゆえに一人取り残され、どうしようもない劣等感に苦しめられているのだった。
そして、この国にあって、神についての概念が全然一般的でない中にあって、キリスト教徒であることの意味するところを彼らが十分には理解していないとしても、それは問題ではなかった。神にとって重要なのは、人が何を理解しているかということよりも、どんなふうに生きているかということなのだ。そして神のもとにとどまって学び続ける限り、人はまた必ずや理解をも得るのだった。
「お許しください、私はほんの少年にすぎません」
と言ったエレミヤに向かって、神は請け合わなかっただろうか--
「私があなたと共にいて、あなたを助ける」と。
彼らはそこまで深い認識なしにバプテスマを受けるかもしれない、しかし彼らはその誓いに調和した生涯を送る。そのために自分で考えるということをついに知らぬまま終わったり、幾分パリサイ人化したりもするかもしれない。それでも尚、いちばん重要なのは、神に仕え続けることだった。
あるいは伝道活動。
訪問を受ける側にしてみれば、それはただ腹を立ててドアをバタンと閉めるか、またはご苦労さんといって雑誌を受け取るくらいのことにすぎなかった--ものの一分もかかりはしない。しかし、訪問する側はドアを叩くたびに、迫り来る終末からの救いと、神への献身に至る長い道のりの始まりとを提供してたのだ。自分がそれを選び取れないでいるAにとって、それは最高に不誠実な行為だった--己れに対しても神に対しても。
それゆえAは苦しんだ。それでも尚Aは出掛けていった--行って王国を宣べ伝えよと、神が命じていたから。
* *
カポーティの<ティファニーで朝食を>。
ヒロインのホリー・ゴライトリーは、もとは貧しい孤児である。三十年代南部のひどい時期、盗みを働いて食いつなぎ、やがてとある農家に引き取られて養われることになる。そして、十四の年で、男やもめであったそこの主人と結婚する。みんなに大事にされて何不自由ない暮らしだったのに、彼女は田舎での平穏な暮らしに飽き足りず、やがて家を飛び出して都会へ行ってしまう。
ホリーはチャンスをつかむ。O.J.バーマンなるマネージャーに見い出されて、映画女優となる訓練を受けるのだ。ところが、富と名声の可能性をあっさり捨てて、ある映画の大事なテストの前日、彼女はふらりとニューヨークへ飛んでいってしまう。
そこから電話をかけて、彼女は言う、あたし今ニューヨークに来ているの。
何だってニューヨークなんかに? バーマンは激昂してつっかかる。
あたしニューヨークに行ったことがなかったから来てみたのよ。
すぐ戻ってこい、このバカ者!
いやよ。
何だって? 一体何を考えているんだ?
あたしあんな役やりたくないわ。
じゃあ、一体何をやりたいんだね?
それが分かったらいの一番にあんたに知らせるわ。
こうしてニューヨークに住みついたホリーは、職にも就かず、飼い猫に名前もつけず、アパートの表札には<旅行中>と記して、男たちから貰うチップで気ままな独り暮らしを続けている。
語り手の青年が彼女と出会ったのはこんなときだった。ときにホリーは十八才だ。
あたし、もちろんお金もほしいし、有名にもなりたいのよ、と彼女は説明する。でもそのために自分自身でいることを犠牲にしたくないの、決してね。いつかあたしがあたし自身でいられるような安住の地が見つかったら、猫に名前をつけて、家具でも買うことにするわ。
仮住まいのホリーのアパートには家具らしきものがなくて、スーツケースをひっくり返してテーブルにしている。
ホリーはすらりとしてスタイルがよく、いつも地味だけども趣味のよい恰好をして(黒、ブルー、灰色)、そして「レモンか、朝食のシリアルのように」清潔である。ときどき「いやな赤」に悩まされ、タクシーに飛び乗って五番街のティファニーに駆けつけたりする。
そう、彼女にあっては形而上学的苦悩も、ときどき心の片隅を曇らす「いやな赤」にすぎない。
人は誰でも自分と正反対の人間に憧れるというのは本当ではないか?
こんな小粋で自由でよるべないホリーの生き方にこそ、Aは憧れてやまなかった。ひとときの心の慰めを求めて陽だまりに腰を下ろし、(映画の中でホリーがしたように)ギターを取って<ムーン・リヴァー>を歌っては、彼女の手にしているような自由--物理的、精神的、道徳的自由に、自分がいかに遠く隔たっているかを思うのだった。
<ムーン・リヴァー>の歌詞は原著にはない--映画化されるにあたって新たに書き下ろされたものである。けれどもそのメロディーが、ホリーの生き方全体に流れている、そこはかとなくよるべない気分を何と的確に表していることか--
Moon River, wider than a mile
I'm crossin’ you in style someday ・・・
<大きな河>というイメージは、ホリーの生まれ育った南部を想起させる。例えば、ミシシッピー。ホリーが五才くらいのときに、大河の土手をよちよち歩きながら対岸も見えないくらいの茶色いしずかな水の広がりを見渡して、いつの日かここを渡ってやろうと実際心に誓った、と考えてもいい。しかしそれはまた、成長してニューヨークに住む彼女の心象でもある。ムーン・リヴァーの向こう側は、ホリーの探し続けている安住の地を象徴する。けれども安住の地なんてものは、本当はどこにも存在しないのだ。それは美しい幻だった--渡ってみたところで茫漠とした大地と、また次のムーン・リヴァーが広がっているにすぎない。無数のムーン・リヴァーを渡ってゆくこと、それが人生というものなのかもしれないが--。
Aが神のもとに縛られていたころは、こんな詩的なニヒリズムを持つことは許されなかった。神の要求する生活はあまりにも散文的だった。人生は確たる目的を持っていて、人は日々それを目指して努力し続けなければならなかった。
しかし尚、絶対者によって定められた目的以上に、人生にとって必要な何物があろう? それゆえ、Aはとても長いこと、己れを神に振り向けさせようとして労苦した。
神と文学との対立。
「我らはもろもろの論説を破り、神の示教に逆ひて建てたる凡ての櫓をこぼち、凡ての念(おもひ)を虜にしてキリストに服(したが)はしむ」---2Co9:4,5
神への献身は、一切の事物を神に屈服せしめることを意味した--それは太古より今に至るまで、生み出されてきたすべての文学のうち、神の規準にかなわない一切の部分を否定することを意味した--例えば、<ムーン・リヴァー>の詩情ですら。
そのことを考えるとAは眩暈を覚えた。
それでも尚、神への愛ゆえにAはそれをしようとした。Aは自分が出会うすべての文学を、神の道徳規範をもって裁断した。Aはミューズを冒瀆した--かつて一身を捧げてきた偉大なミューズを。それはあまりにも酷たらしいことだった。アブラハムの手をとめる天使は現れなかった。Aは自ら切り刻んだ文学の血にまみれ、神に向かってうめいた--エホバよ、ここまでひどいことを、あなたは私に要求なさるのですか。
それゆえにAは神を憎悪した。
文学とは何か。神への愛とは。
それが分からないで、尚存在し続けるのはほとんど不可能だった。
もはや存在し得ないところで存在し続ける苦悩。
* *
それからさらに長いときを経て、Aはグリーンとかチェスタトンとかエリオットに出会い、自分が今まで文学だと思っていたのとは全然違うような<文学>が、この世の中には存在することを知ることになる。
それは驚異だった--彼らが、文学によっても神に栄光を帰することができると、半ば本気で信じていたらしいことは。
彼らはヨーロッパ的文学観の最も伝統的な部分を受け継いでいた。その見方によれば、文学の本質的な存在意義とは、読者を宗教的道徳的に裨益すること--バニヤン流にもっとはっきり言えば、読者を神のもとに導くこと--だった。そして、こうした見方からすれば、文学は今なお二義的な位置に甘んずるのであり、それ自身によって立つ価値とか力とかを持つことはない。エリオットがしばしば文学それ自身の無意味さとか無根拠さについて語っているが、それは誠実な物言いであると思う。しかし、もっと後代に下るにつれて文学は饒舌になり、バニヤンの硬直から次第に自らを解き放ってゆく。想起せよ--彼らの詩や小説や戯曲、それらが神を、神へ到る困難な道のりを語りながら、いかに手の込んだプロットや小道具や情景描写を併せ持ち、力強さと文学的感受性と想像力とに溢れ、そして--対話に満ちているかを。
そう、それらは神をたたえることによって死んでしまってはおらず、否、神をたたえることによって生き生きと生命にあふれていた。彼らの多くは道徳的問題をその作品の中心に据え、その批評の多くもまたしばしば道徳的視点からなされている--そしてまさにそのことが、人の精神を力強く鼓舞しているのだ。
そしてまた、彼らの罪の扱い方についても。そう、最もキリスト教的な文学とは、姦淫や殺人について語らない文学ではない。想起せよ--聖書そのものが、どれだけ夥しい罪の記録に満ちているかを。しかし、そこには厳然たる道徳的視点があって、義なる者は祝福され、悪しき者は裁かれるのである。その視座、その力、その行動によって、夥しい罪の記録は聖なる書と呼ばれている。
それゆえ、いやしくも神にとって有用な文学というものがあるとすれば、それは、こうでなくてはならなかった。
こういった種類の文学に、自分はなぜもっと早く出会えなかったのだろうかと、Aはしばしば訝ったものだ。
彼らは--つまり、Aの属していた組織の指導者たちは--羊たちが、世俗のキリスト教文学と言われる書物を手に取ることを喜ばなかった。どちらかと言うと、避けたがっているふうにさえ思われた。それはなぜだったんだろう? 聖書だけ読んでいたのでは理解できなかったであろう幾多の概念を、自分はそれによって理解し得たのに。ずっと長いこと、Aはそれらの概念を、まるで目隠しされ、手袋をはめた手で彫像を触るような仕方でしか理解できないできたのだ。そしてまた、彼らはみな、あれだけ誠実に神を求め、あれだけ突きつめてものを考え、あれだけ魂を傾けて書いたのに。
教義上の意見の相違によって、良心が混乱させられるから?
あるいは単に、神のためにのみ費やされるべき時間や注意力を、不当に奪われるから? それとも、いかに偉大な文学といえども、所詮は死すべき人間の手になる業であり、不謬じゃないから?
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません