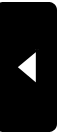2013年11月30日
創造的な不幸-2-
創造的な不幸-愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ-
この作品について 目次
-2- 愛について、その2
愛について、語源的アプローチ。
愛について語られるとき、しばしば持ち出されるのはアガペーとエロースとの対比であり、エロースが誘因をもつ愛であるのに対し、アガペーは誘因をもたない、無償の愛である、という説明である。たとえばニーグレンの<アガペーとエロース>---
「アガペーは主権をもち、対象から独立していて、『悪しき者にも善き者にも』注がれる。従ってそれは自発的で、『誘因のないもの』で、受けるに価しない人々に自らを贈与するのである。アガペーは惜しみなく与え消費する。なぜならそれは神ご自身の豊かさと充足に基づいているからである」
これは分かりやすい図式である。しかしながらやや正確さに欠ける。誘因を持つ愛がおしなべてエロースなのではないし、アガペーが誘因を持つということが絶対にないわけでもないのだ。
ギリシャ語で愛を表す言葉はこの二つだけではなくて、もっとたくさんある---ストルゲー、フィラデルフィア、フィリアストロゲス。しかしこの場合を考えるのにいちばんふさわしいのはフィリアという語によって表される概念である。
フィリアは、相手のよき内面的特質によって、自然と己れの中に育まれるところの愛である。ヴァインの新旧約聖書用語解説辞典の定義---tender affection.
あるいはジェイムズ・ストロングの注解---personal attachment, as a matter of feeling or sentiment.
要するにそれは誘因を持つ愛である。しかし、それはソクラテスがエロースを定義したように自分に欠けているものを求めるわけでは必ずしもないし、またエロースが主に知的あるいは肉体的な側面に重きを置くのに対し、フィリアはむしろ特質とか感情と結びついている。
それに対し、アガペーと結びついているのは原則とか正義という概念である。アガペーはもともとはキリスト教の神の愛を説明するためにできた言葉ではない。しかしそれがキリスト教用語として転用される場合、それは神の義と密接な関わりを持っているのだ。
というのは、神が人に愛することを命ずる場合、愛とは何を意味するのか、我々はいかにして愛すべきなのかをも規定する必要があるからだ。愛とは常に他者にとっての最善の益を求めることなのか? だとしたら、最善の益とは一体どういう基準で決まるのか? もし、複数の他者の益が相矛盾するとしたら?
その基準を与えるのが神の義なのである。それゆえここにおいて、愛の問題とはまた正義の問題なのだ。
アガペーについてのヴァインの注解。
・・・It was not drawn out by any excellency in its objects.Rom5:8. It was an exercise of the Divine Will in deliberate choice, made without assignable cause ・・・cp.Deut.7:7,8.
同じく、ストロングの注解。
(It) is wider, embracing espec, the judgement and the deliberate assent of the will as a matter of principle, duty, and propriety ・・・
それゆえアガペーは原則に、principle に導かれ規定される愛である。あくまで神の義の原則に従い、感情に支配されることはないが、しかし没感情的な特質ではなくて、フィリア的要素も包含し得る。
たとえばJoh3:35に、キリストに対する神の愛について述べられているが、(「父は御子を愛し、萬物をその手に委ね給へり」)ここでの「愛」はアガペーである。しかるに5:30において同じ内容が繰り返されるが、こちらではフィリアになっている。神がキリストに対してtender affectionを抱いていると考えるのは妥当なことである。さらにMr12:31では「おのれの如く汝の隣を愛すべし」と命じられていて、ここでの「愛」はアガペーだが、隣人にも色々ある。よき隣人に対してはフィリア的アガペーを抱き得るだろうし、そうでもない隣人に対してはフィリア的要素のより少ないアガペーになるだろう。そしてそれは同情とか誠実な関心といった形を取り得るだろう。
では「汝の敵を愛せ」はどうか? アガペーは義の原則を絶対に侵さないのだから相手の行う悪を容認するということではないし、相手に対してtender affectionを持つということでもない。( ゆえに例えばグレアム・グリーンの< ブライトン・ロック> の中でローズがピンキーに対して抱く愛情は、厳密には神の命ずる種類のアガペーではない。ローズにしてみれば愛するピンキーに自分が殺されてもかまわないのかもしれないが、神にとってはかまわないことではないのだ。そして、ローズがだんだんに、自分が足を踏み入れてしまった悪を認識し、やがてはっきりと共犯者の立場を取るのを見よ---彼女はむしろ「緋文字」のヘスタに似ている。彼女は自分の愛ゆえに神の愛を退けたのだ。)そうではなく、それは義の原則の許容範囲内において相手に親切に振る舞うということである。律法には「汝もし汝の敵の牛あるいは驢馬の迷ひ去るに遭はばかならずこれを牽きてその人に歸すべし 汝もし汝を惡む者の驢馬のその負の下に仆れ臥すを見ば慎みてこれを遺てさるべからず必ずこれを助けてその負を釋くべし」(Ex23:4,5)とあるし、箴言には「汝の仇もし飢えなば之に糧をくらはせ もし渇かば之に水を飲ませよ 汝斯するは火をこれが首に積むなり エホバ汝に報ひ給ふべし」とある。かくして人は「惡に勝たるることなく、善をもて惡に勝」ってゆくのである。(Rom12:21)因みに「なんぢの仇を憎むべし」は実際には律法の言葉ではなく、後世のユダヤ人がつけ加えたものだという。
ウィリアム・バークレーは注解している。
「アガペーは知性と関係している。それは(フィリアの場合とは異なり)おのずと自分の心の中に生ずる単なる感情ではない。それは一つの規範であって、我々はその規範に従って慎重に生活する。アガペーは意志と非常に深い関係にある。それは一つの征服であり、勝利であり、達成である。自然に自分の敵を愛せる人はいない。自分の敵を愛することは、我々の自然の傾向と感情全体に対する征服である。実際このアガペー・・・は愛せない人を愛し、好きではない人を愛する力である」---<新約聖書の用語>
そして、この強い意志の力の出自となっているもの、それこそが神とキリストの愛なのである。「主は我らの為に生命を捨てたまへり、之によりて愛ということを知りたり」(1Joh3:16)
それでは、神に対する人間の愛とはいかなるものか? Mr12:29,30には「主なる汝の神を愛すべし(アガペー)」とあって、これが最大で第一のおきてである。具体的には、「神の誡命を守るは即ち神を愛するなり」(1Joh5:3)というわけだ。この愛とはいかなる愛か?
「神に対する人間の義務は、完全な絶対的な自己献身である。しかし、神に対する人間のアガペーについて語ることは、人間が神に関して独立の立場を持っていることを示唆するかもしれないし、神だけが本質上愛なのであるから、神に対する人間の自己献身は応答にすぎない、という本質的真理を、曖昧にするかもしれないのである。・・・
「人間は神を愛すべきである。それは彼が他のいかなる欲求の対象よりも神に欲求の一層充分な完全な満足を見いだすからではなく、神の『誘因のない』愛が彼を圧倒し、強制して、そのため神を愛するほか何もできないからである」---<アガペーとエロース>
しかし、神の前に人間はそんなにひ弱な存在でなくてはならないのか?
神とキリストがまず人間を愛したのだから、この愛はフィリア的要素を、つまり誘因を持つ。しかも人間の抱くであろう愛それ自体よりもはるかに強い誘因である。この時点において人は容易にtender affectionを抱き得るであろう。しかるにパウロがRom7.に書いている通り、罪人たる人間の自然の傾向が神のおきてと対立するとき、周囲の世が何らの道徳基準も持たないとき、あるいは信仰のゆえにすべてを失って艱苦の極みにあるとき(たとえばヨブ、あるいはアウシュヴィッツ)、そういうときに貫くことのできる愛は、もはや受動的被誘発的な愛ではあり得ない。それは意志の愛、規範の愛である。アガペーとはそういうものではなかったか?
しかし結局のところ、それだけでは完全ではない。
パウロは書いている---「われ確く信ず、死も生命も、御使も、権威ある者も、今ある者も後あらん者も、力ある者も、高きも深きも、此の他の造られたるものも、我らの主キリスト・イエスにある神の愛より、我らを離れしむるを得ざることを」(Rom8:38,39)
ここで問題とされているのは神に対する人の愛ではなく、人に対する神の愛である。そう、神からの愛に支えられて人は神への愛を貫くのだ。そしてAは、まさにこの種の愛が、自分のうちに決定的に欠落していることを知ったのだった。
* *
Aはかつてディムズデールだった---それゆえ<緋文字>はAにとって意味を持つ。神への献身を果たせない苦悩。
機械的な服従だけならまだいい。ところが神を愛すべしとは!
全き従順と献身、そんなとてつもないことを要求する神を、一体どうやって愛したらいいのだろう?
神を愛するとは一体どういうことなのか?
神の、人に対する愛---アガペー---は、ゼロに対する百の愛だということになっている。人類は自ら堕落したのであって、神が独り子イエスを贖いとして与える義務は全然なかった。ところが彼は人類への愛ゆえにそれを与え、誰でもそれに信仰を働かせる者に永遠の命を約束する(Joh3:16)---そこまではまあ分かる。
ところが神は己れの愛に応ずる者に何を求めたか?
献身を---しかも愛の動機による献身をだ!
「人もし我に從ひ來らんと思はば、己をすて、日々おのが十字架を負ひて我に從へ」
これはまた、恐るべき思想的自由の剥奪、身体的自由の束縛ではないか。
自由にものを考えたり、好き勝手に生きたりできないのなら、永遠の命なんか貰ったところで一体何になるだろう?
或いは、己れを捨てて神に仕えることで神に何らかの利益を与えることができるのならまだいい。他者を益しているという自覚によって、我々は自尊心を持つことができるからだ。ところが神は、我々を必要としているわけでもない---「神汝の手より何をか受け給はん」(Job35:7)---ただ、己れの愛に対する感謝の表明としてのみそれを求めているにすぎない。
これでは百対ゼロどころか、その反対にゼロ対百と言った方がいいくらい、不均衡な関係ではないか。我々はただ神への感謝を表明する為だけに、我々の全生涯を費やさなければならないのだ。なんということだろう。
神殿建設のために夥しい宝物を捧げるダビデ。
「萬の物は汝より出づ我らは只汝の手より受けて汝に獻げたるなり」(Cro29:14)
すべてのものは神から出ている---我々は与えるべき何ものも持たず、もともと神のものであったものを、神に返すにすぎないのだ。
しかし、それでは与えられた意味がないのではないか? 一方的に与えておいて、後から返されることを期待するとは、神とは何者なのか?
神は常に人に対して、その生涯の中で神への奉仕が第一となることを求めてきた。片手間であってはならなくて、いつでもそれが第一であり、中心でなくてはならなかった。
イスラエルに於いては例の七面倒な律法に則って、しじゅう牛や羊を捧げたり、聖会に集まったり、敵と戦ったり、水を浴びたりしなくてはならなかった。最良の物は常に神に捧げられなければならなかった---穀物の初物とか、動物の脂肪とか。
彼らのすべてが、生きるために神に仕えるのではなく、神に仕えるために生きなければならなかった。
アブラハムもそうだった、ヨブもそうだった。
絶対者に対して絶対的な立場に立つということ、まさにそれが、神への愛における逆説なのだ。
神は何の見返りも求めずに人を愛するというのは真実か?
否、神の愛は人に対し、人の立場にありながら神の如く、神を愛することを要求する。何の見返りも求めずに神を愛することを要求するのだ。神の前に己れの持つ最善のもの、己れの持つすべてのものを差し出すことを要求するのだ。
「キリストの愛われらに迫れり。我ら思ふに、一人すべての人に代りて死にたれば、凡ての人すでに死にたるなり。その凡ての人に代はりて死に給ひしは、生ける人の最早おのれの為に生きず、己に代り死にて甦へり給ひし者のために、生きん為なり」(2Co5:14,15)
そう、キリストの愛は圧倒的である。それは決断を強要する。即ち、その愛に応じて己れを捨てることによって、道徳的に正しい人間であることを示すか、あるいは、その愛に応えないことによって、道徳的にどうしようもないろくでなしであることを示すかの決断を。
我々は、この圧倒的な愛を前にして尚踏みとどまり、私はお前に贖いとして死んでくれと頼んだ覚えはない、お前が勝手に死んだのではないか、勝手に死んでおいて、後から同じだけの愛と献身を要求するとは一体どういう愛なのかと、口に出して言うだけの神経を持ち合わせているだろうか?
* *
mortality がimmortality に出会ったときの恐怖。
シナイで神に出会ったイスラエル。
「汝らの近づきたるは、火の燃ゆる觸り得べき山・黒雲・黒闇・嵐、ラッパの音、言の聲にあらず、この聲を聞きし者は此の上に言の加へられざらんことを願へり。これ『獣すら山に觸れなば、石にて撃るべし』と命ぜられしを、彼らは忍ぶこと能はざりし故なり。その現れしところ極めて怖しかりしかば、モーセは『われ甚く怖れ戰けり』と云へり」(He12:18-20)
恒久性の概念。
常にそして永久に。
ラテン語のsemperには「常に」と「永久に」と言う二つの意味がある。この二つの概念は同じではない。同じでない二つの概念が一つの言葉で表されているのはなぜか?
この言葉を考え出した精神性のうちには、「これまでずっとそうであったことは、これからもずっとそうである、あるいはあるべきである」という信念が働いていたのだ。
この考え方でいくと、現在という一点に何ら特別な意味はなく、それは無限から無限へ流れる時間の流れの中の一点にすぎない。
そしてもちろんそういう精神性は神に由来するのだ。
私はアルファでありオメガであり---
神に仕えつづけること。今日も、明日も、ずっと、常に、永遠に。
その考えはAを怖れさせた。
永続性という牢獄の中で、Aは自分がほとんど死にそうに、窒息しそうになっているのを見いだす。
Aの祈り。
どうぞ飛び立つ勇気を与えて下さい、そして一生飛び続ける強さを---
いや、そうではなく。
もっともっと高く、飛んでゆきたいという願いを。
神に仕えることができないのなら、一切の事柄は無駄であった。
本当に、心から、献身すら果たせれば他には何もいらないと思っていた。
実際その頃は、神の僕の名に恥じない生活を送っていた。自転車を一時間こいで高校から帰ってくると、疲れた足をひきずって集会へ、あるいは伝道へ出掛ける---日々聖書を研究し、その規範に従って生活して---実存主義者やニヒリストと付き合ったりすることもなく。
それでもやはり、献身とは、最終的には内面の問題だった。
外面の行動によって内面を変えることはできないのだった。
Aは最終的に、己れを捨てて神にすべてを差し出したいと、本当に、心の底から思うことができなかった。そう思うことができなかったので、どれほどAは苦しんだだろう。
Penance, that's enough! Penitence, none!
真摯なる自己欺瞞を、ついにAは貫けなかった。
* *
この章を結ぶにあたって、ずっと後年になってからAが出会い、神への愛の告白として最も感動的なものの一つであると感じた書物について、少し語ろう。
G.K.チェスタトンの<正統とは何か>。
著者はカトリックで、この書物は要するに護教論なのだが、それがちっとも人をうんざりさせないのは、その文章の調子に、彼が自分のことを抑圧したりあるいは棚に上げたりしているところが全くないからである。むしろ不自然に思えるくらい、全くない。その反対に、この不信心な世にあって無視されたりひどく誤解されたりしている、愛する神と教会を弁護するために、彼は自分の持つ豊かなウィットと才能を縦横無尽に駆使している、そしてそうすることを、心から楽しんでいるのである。
もちろん我々は、教理面における彼の言い分をすべて受け入れるわけにはいかない。チェスタトンほどの優れた知性が、三位一体や永劫の地獄などの存在を平気で信じていられるというのには、全く首を傾げざるを得ない。それは全く、知性の従順が誤用された結果であるとしか、考えようがない。
それでも尚、それは非常に感動的な書物なのである。
特に感動的なのは、<おとぎの国の倫理学>という題の付された第四章で、ここで彼はおとぎ話の論理に則って愛や感謝や道徳の問題を解きあかしてみせる。というのは、おとぎ話こそは彼の「最初にして最後の哲学、一点の曇りもなく信じて疑わぬ哲学」だからである。
「私が経験したもっとも強大な感情は何かと言えば、人生は驚異であると同時に貴重だという感情だったのだ。それは一つの恍惚であった。なぜならそれは冒険だったからである。そしてそれが冒険であったのは、それが一つの偶然であったからだった。おとぎ話には、お姫様より怪獣ののほうがたくさん出てくるからといって、それでおとぎ話の楽しさが少しでも少なくなることはまるでなかった。とにかくおとぎの国にいることが楽しかったのである。あらゆる幸福の源は感謝である。・・・サンタクロースが靴下に玩具やお菓子の贈り物を入れてくれると、子供たちはただすなおに感謝する。それならサンタクロースが、私の靴下にこの二本の奇跡的な脚という贈り物を入れてくれた時、私はどうしてすなおに感謝していけない理由があったろう。誕生日のプレゼントに葉巻やスリッパを貰ったら、我々は贈ってくれた人に感謝する。それなら誕生日のプレゼントに誕生そのものを貰った時、誰にも感謝してはいけない理由がどこにあろうか」
それから彼は「もし」という言葉の効用について語る。
「あらゆる美徳はこの『もし』の中にある。・・・妖精はいつもこういう言いかたをする---『もし《牛》という言葉さえ言わなければ、あなたは金とサファイアの宮殿にお住みになれます。』あるいは、『もし王女様にタマネギさえ見せなければ、いつまでも王女様と一緒に幸せな暮らしができるのです。』魔法の力はいつでもたった一つ、してはならない条件にかかっている。たった一つの小さなことだけが禁じられていて、その条件さえ破らなければ、目も眩むような壮大なことがみな与えられるのだ。・・・
「この国の本当の住人たちは、自分にはぜんぜん理解できないものにいとも従順に従うのである。おとぎの国では、不可解な幸福が不可解な条件に支配されている。箱を開けるとあらゆる災厄が一度に飛び出す。たった一つの言葉を忘れたばっかりに、数々の都市が姿を消す。ランプに火をつけると、恋が飛んで逃げて行く。花を摘んだとたん、何人もの人の命が失われてしまう。リンゴを食べると、神の希望が消え失せる。
「おとぎ話はいつもこんな調子である。・・・
「シンデレラは、降って湧いたように馬車と馭者とを貰ったが、しかし同じようにどこからともなく命令も受けたのである---十二時までにはかならず帰って来るように。それに彼女にはガラスの靴もあった。そして実際、このガラスという物質が、おとぎ話であれほどたびたび出てくるということは、どう考えても単なる偶然とは思えない。ガラスのお城に住む王女様もあれば、ガラスの山に住んでいる王女様もある。・・・このガラスのか細い輝きは、実は、幸福がいかにもキラキラしてしかし同時にいかに壊れやすいものか、その事実を表しているからにほかならない。たしかに幸福はガラスに似ている。・・・そしておとぎ話のこの感覚もまた私の心の奥底に深くしみこんで、世界全体にたいする私の感受性を決めてしまったのである。人生はダイアモンドのように輝くが、同時に窓ガラスのように壊れやすい---私はそう感じ、そして今もそう感じている」
「だが、誤解しないでいただきたい。壊れやすいということは、壊滅しやすいというのと同じではないのだ。ガラスを打てば、ひとたまりもなく壊れてしまう。だから要するに打たなければよろしい。そうすればガラスは何千年も元のままである。人間の喜びとは、まさにこれだと私には思えたのだ。妖精の国であろうと地上であろうと変わりはない。幸福は、われわれが何かをしないことにかかっている。ところがそれは、われわれがいつ何時でもやりかねないことであって、しかも、なぜそれをしてはならぬのか、その理由はよくわからないことが多いのだ。ところで、私がここで特に強調しておきたいのは、少なくとも私には、これがぜんぜん不当だとは思えなかったという点である。たとえば、粉屋の三番目の息子が妖精に向かってこう聞くとする---『何だって妖精の宮殿で逆立ちしてはいけないのですか。その理由を説明して下さい。』すると妖精はこの要請に答えて、まこと正当にこう言うだろう。『ふむ。そんなことを言うんなら、そもそもなぜ妖精の宮殿がここにあるのか、その理由をまず説明して貰おう。』あるいはシンデレラが聞いたとする---『どうして私は舞踏会を十二時に出なければならないのですか。』魔法使いは答えるはずだ---『どうしてお前は十二時までそこにいるんだい。』もしかりに私が遺言をして、物を言う象を十匹と、天馬を百頭、ある男に残してやるとする。遺言の条件が、この贈り物と同様、少々奇妙であったとしても、その男は文句を言えた義理ではあるまい。天馬がいくらで売れるだろうなどと、下らぬ穿鑿なんかしないのが礼儀というものだ。そして私にとっては、現に生きているということ、現に世界がそこにあるということ自体が、実に途方もなく奇妙な遺産に思われて、だから、たとえ私には何から何までわからぬことだらけだとしても、その理由がわからぬと言って文句をつけるなどということは思いもよらなかったのだ。・・・『してはならない』ことは『してもよろしい』ことと同様に異様であった。太陽と同じく驚くべきことであり、水と同じくとらえがたく、そびえたつ大樹と同じく幻想的で恐るべきものだったのである」
そしてこれが、神の要求に対する彼の態度であった。それはいかにAのそれと違っていたことか!
神のすべての要求は彼にとって「たった一つの小さなこと」であったのだ。
それはたまたま彼の属していた組織がAのそれよりも人に対して少なく要求したということによるものではない。例えば性と結婚に関する神の要求について彼は書いている、「一人の女を守るということは、一人の女に本当に出会うという大事に比べては、まことに小さな代償というべきだ。一度しか結婚できぬと不平を言うのは、一度しか生まれられぬと不平を言うのと同じことだった」
こんなふうに言ってのける人間が世の中に存在するなんて、Aにはほとんど信じられなかった。Aにとって、一人の女に生涯忠実であるなんてことは、とても相手にできないくらい法外な要求と思われたのだ。
しかし、それ以上に我慢できなかったのは、例によって、神への愛ゆえにそうしなければならないという事実だった。
そしてまさにこれが、チェスタトンにとって神のすべての要求が「小さなこと」でしかなかった理由である。
彼の驚くべき従順と畏敬とを生み出しているもの、それは実に、愛である。彼の文章には、神に対する愛が、いとしい恋人に対するような心からの愛情がにじみ出ている。
そして、彼はもともとこうなるべき人だったのだ。彼はAと違って、神の会衆の中に生まれ落ちはしなかった。けれども彼は、神に出会うずっと前から神を探し求め、まだ見ぬ神を愛していたのだ。だからついに神に出会ったとき、そのあらゆる要求をことごとく受け入れ、己れをすっかり明け渡すのは、彼にとって容易なことだった。それから彼は、事実上生涯を神のために捧げた---すなわち彼の場合は、文筆活動によって神を宣伝するというかたちを取ったわけだ。
神と人との関係は、男と女の関係によく似ている。女にとって、愛する男に自分の体を明け渡すと共に、生涯をその男のために生きるのは至福の喜びである。彼女はすでにその男に心を明け渡しているからだ。ところが彼女がその相手を愛していない場合、それは悪夢以外の何ものでもない。神を愛する者と愛さない者との相違もかくのごとくである。
「幸福は、われわれが何かをしないことにかかっている。ところがそれは、われわれがいつ何時でもやりかねないことであって、しかも、なぜそれをしてはならぬのか、その理由はよくわからないことが多いのだ」
エデンにおけるアダムとエバについての、実に適格な描写ではないか。
Aが子供の頃、人々がしばしばアダムとエバを非難するのを聞いたものだが、彼らがどうしてそんなふうに非難するのか、Aにはさっぱり理解できなかった。 彼らは禁断の木の実を食べた---当然のことではないか。
Aがエバだったとしても、やっぱり食べたことだろう。食べないなんてことは、考えられもしなかった。そのために人類全体に対して死の宣告が下されようと、それが何だというのか?
それゆえ、Aは自分がエバでなかったことを、たまたまエバに生まれたばっかりに、自分の不従順のせいで人類全体が責任を取らされるようなはめにならないですんだことを、全くもって感謝したのである。そしてこんなふうな感謝の仕方をするということ自体、実にあってしかるべき感謝の欠如を示しているのに他ならなかった。
「あらゆる幸福の源は感謝である」! けだしこれは名言である。
しかし、感謝とは一つの才能ではあるまいか? これほど素直に、これほど自分自身との何の葛藤もなしに感謝できる人をAは知らない。この章の末尾のところで彼はまた書いている---「われわれは、何がわれわれを創ったにしても、その創り主にたいして従順であらねばならぬ。それは創られたものの当然の義務というものだ」
Aには、ごく自然にこんなふうに考えるなんて、とてもではないができなかった。
その反対に、Aはごく自然にこんなふうに考えた---せっかく命をもらったからには、それを好きなように使えるのでなければ意味がないではないか? そうでなければ感謝することもできないではないか---それを命じられた通りに使わなければならないとしたら。
そういうわけで、Aは今だ、十二時までに帰らなくてはならないのなら舞踏会なんかに連れていってもらわなくていいと、駄々をこねるシンデレラだった。
* *
しかし、どうやっても叩きつぶすことのできないAの不従順は、しだいにAの立場をのっぴきならぬものにしていった。
Aは伝道なんか好きではなかった---伝道なんかに一生を捧げたくなかった。しかし、だとしたら一体どういう生きかたをしたらいいのか?
神の側をとらないということはつまり神に敵する側をとるということだが(「我と偕ならぬ者は我にそむき、我とともに集めぬ者は散すなり」)、これまでずっとAのことを忍んでくれた神とその全会衆とを敵にまわしてまでする価値のある、どんな仕事がこの世の中に存在するというのか?
もう一度ものを書くのか---形而上学的な問題にわたらない限り無意味だと、分かってしまった文学をやるのか? 子供の頃思い描いたように山の中の一軒家にこもって、来る日も来る日もひたすら何の役にも立たない小説を書いて、そして静かに死んでゆくのか?
そんな強さが今のAにあるのか---ミューズへの信仰は失われてしまったというのに?
* *
神に従え。神に従え。
しかし、我々はなぜ神に従わなければならないのか?
チェスタトンにとって、それは全く明白なことだった。「それは創られた者の当然の義務である」と彼は言う。
こういう感謝の念が、Aには欠けていた。Aの心は「信仰の種子がまかれるべき土壌」なんかではなかった。
最終的にこの問題に関してAの目を開かせたのは、パスカルが書いたような、人間性についての真実、あるいは罪という概念の理解だったであろう。
人間は道徳的に生きるために、何ものかに従わなくてはならないということ。「もし罪なしと言はば、是みづから欺けるにて真理われらのうちになし」--1Joh1:8
罪、あるいは不完全性という概念を、Aは長いこと理解できなかった。他の人間は不完全かもしれないが、自分は完全だと思っていたのだから。
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
この作品について 目次
-2- 愛について、その2
愛について、語源的アプローチ。
愛について語られるとき、しばしば持ち出されるのはアガペーとエロースとの対比であり、エロースが誘因をもつ愛であるのに対し、アガペーは誘因をもたない、無償の愛である、という説明である。たとえばニーグレンの<アガペーとエロース>---
「アガペーは主権をもち、対象から独立していて、『悪しき者にも善き者にも』注がれる。従ってそれは自発的で、『誘因のないもの』で、受けるに価しない人々に自らを贈与するのである。アガペーは惜しみなく与え消費する。なぜならそれは神ご自身の豊かさと充足に基づいているからである」
これは分かりやすい図式である。しかしながらやや正確さに欠ける。誘因を持つ愛がおしなべてエロースなのではないし、アガペーが誘因を持つということが絶対にないわけでもないのだ。
ギリシャ語で愛を表す言葉はこの二つだけではなくて、もっとたくさんある---ストルゲー、フィラデルフィア、フィリアストロゲス。しかしこの場合を考えるのにいちばんふさわしいのはフィリアという語によって表される概念である。
フィリアは、相手のよき内面的特質によって、自然と己れの中に育まれるところの愛である。ヴァインの新旧約聖書用語解説辞典の定義---tender affection.
あるいはジェイムズ・ストロングの注解---personal attachment, as a matter of feeling or sentiment.
要するにそれは誘因を持つ愛である。しかし、それはソクラテスがエロースを定義したように自分に欠けているものを求めるわけでは必ずしもないし、またエロースが主に知的あるいは肉体的な側面に重きを置くのに対し、フィリアはむしろ特質とか感情と結びついている。
それに対し、アガペーと結びついているのは原則とか正義という概念である。アガペーはもともとはキリスト教の神の愛を説明するためにできた言葉ではない。しかしそれがキリスト教用語として転用される場合、それは神の義と密接な関わりを持っているのだ。
というのは、神が人に愛することを命ずる場合、愛とは何を意味するのか、我々はいかにして愛すべきなのかをも規定する必要があるからだ。愛とは常に他者にとっての最善の益を求めることなのか? だとしたら、最善の益とは一体どういう基準で決まるのか? もし、複数の他者の益が相矛盾するとしたら?
その基準を与えるのが神の義なのである。それゆえここにおいて、愛の問題とはまた正義の問題なのだ。
アガペーについてのヴァインの注解。
・・・It was not drawn out by any excellency in its objects.Rom5:8. It was an exercise of the Divine Will in deliberate choice, made without assignable cause ・・・cp.Deut.7:7,8.
同じく、ストロングの注解。
(It) is wider, embracing espec, the judgement and the deliberate assent of the will as a matter of principle, duty, and propriety ・・・
それゆえアガペーは原則に、principle に導かれ規定される愛である。あくまで神の義の原則に従い、感情に支配されることはないが、しかし没感情的な特質ではなくて、フィリア的要素も包含し得る。
たとえばJoh3:35に、キリストに対する神の愛について述べられているが、(「父は御子を愛し、萬物をその手に委ね給へり」)ここでの「愛」はアガペーである。しかるに5:30において同じ内容が繰り返されるが、こちらではフィリアになっている。神がキリストに対してtender affectionを抱いていると考えるのは妥当なことである。さらにMr12:31では「おのれの如く汝の隣を愛すべし」と命じられていて、ここでの「愛」はアガペーだが、隣人にも色々ある。よき隣人に対してはフィリア的アガペーを抱き得るだろうし、そうでもない隣人に対してはフィリア的要素のより少ないアガペーになるだろう。そしてそれは同情とか誠実な関心といった形を取り得るだろう。
では「汝の敵を愛せ」はどうか? アガペーは義の原則を絶対に侵さないのだから相手の行う悪を容認するということではないし、相手に対してtender affectionを持つということでもない。( ゆえに例えばグレアム・グリーンの< ブライトン・ロック> の中でローズがピンキーに対して抱く愛情は、厳密には神の命ずる種類のアガペーではない。ローズにしてみれば愛するピンキーに自分が殺されてもかまわないのかもしれないが、神にとってはかまわないことではないのだ。そして、ローズがだんだんに、自分が足を踏み入れてしまった悪を認識し、やがてはっきりと共犯者の立場を取るのを見よ---彼女はむしろ「緋文字」のヘスタに似ている。彼女は自分の愛ゆえに神の愛を退けたのだ。)そうではなく、それは義の原則の許容範囲内において相手に親切に振る舞うということである。律法には「汝もし汝の敵の牛あるいは驢馬の迷ひ去るに遭はばかならずこれを牽きてその人に歸すべし 汝もし汝を惡む者の驢馬のその負の下に仆れ臥すを見ば慎みてこれを遺てさるべからず必ずこれを助けてその負を釋くべし」(Ex23:4,5)とあるし、箴言には「汝の仇もし飢えなば之に糧をくらはせ もし渇かば之に水を飲ませよ 汝斯するは火をこれが首に積むなり エホバ汝に報ひ給ふべし」とある。かくして人は「惡に勝たるることなく、善をもて惡に勝」ってゆくのである。(Rom12:21)因みに「なんぢの仇を憎むべし」は実際には律法の言葉ではなく、後世のユダヤ人がつけ加えたものだという。
ウィリアム・バークレーは注解している。
「アガペーは知性と関係している。それは(フィリアの場合とは異なり)おのずと自分の心の中に生ずる単なる感情ではない。それは一つの規範であって、我々はその規範に従って慎重に生活する。アガペーは意志と非常に深い関係にある。それは一つの征服であり、勝利であり、達成である。自然に自分の敵を愛せる人はいない。自分の敵を愛することは、我々の自然の傾向と感情全体に対する征服である。実際このアガペー・・・は愛せない人を愛し、好きではない人を愛する力である」---<新約聖書の用語>
そして、この強い意志の力の出自となっているもの、それこそが神とキリストの愛なのである。「主は我らの為に生命を捨てたまへり、之によりて愛ということを知りたり」(1Joh3:16)
それでは、神に対する人間の愛とはいかなるものか? Mr12:29,30には「主なる汝の神を愛すべし(アガペー)」とあって、これが最大で第一のおきてである。具体的には、「神の誡命を守るは即ち神を愛するなり」(1Joh5:3)というわけだ。この愛とはいかなる愛か?
「神に対する人間の義務は、完全な絶対的な自己献身である。しかし、神に対する人間のアガペーについて語ることは、人間が神に関して独立の立場を持っていることを示唆するかもしれないし、神だけが本質上愛なのであるから、神に対する人間の自己献身は応答にすぎない、という本質的真理を、曖昧にするかもしれないのである。・・・
「人間は神を愛すべきである。それは彼が他のいかなる欲求の対象よりも神に欲求の一層充分な完全な満足を見いだすからではなく、神の『誘因のない』愛が彼を圧倒し、強制して、そのため神を愛するほか何もできないからである」---<アガペーとエロース>
しかし、神の前に人間はそんなにひ弱な存在でなくてはならないのか?
神とキリストがまず人間を愛したのだから、この愛はフィリア的要素を、つまり誘因を持つ。しかも人間の抱くであろう愛それ自体よりもはるかに強い誘因である。この時点において人は容易にtender affectionを抱き得るであろう。しかるにパウロがRom7.に書いている通り、罪人たる人間の自然の傾向が神のおきてと対立するとき、周囲の世が何らの道徳基準も持たないとき、あるいは信仰のゆえにすべてを失って艱苦の極みにあるとき(たとえばヨブ、あるいはアウシュヴィッツ)、そういうときに貫くことのできる愛は、もはや受動的被誘発的な愛ではあり得ない。それは意志の愛、規範の愛である。アガペーとはそういうものではなかったか?
しかし結局のところ、それだけでは完全ではない。
パウロは書いている---「われ確く信ず、死も生命も、御使も、権威ある者も、今ある者も後あらん者も、力ある者も、高きも深きも、此の他の造られたるものも、我らの主キリスト・イエスにある神の愛より、我らを離れしむるを得ざることを」(Rom8:38,39)
ここで問題とされているのは神に対する人の愛ではなく、人に対する神の愛である。そう、神からの愛に支えられて人は神への愛を貫くのだ。そしてAは、まさにこの種の愛が、自分のうちに決定的に欠落していることを知ったのだった。
* *
Aはかつてディムズデールだった---それゆえ<緋文字>はAにとって意味を持つ。神への献身を果たせない苦悩。
機械的な服従だけならまだいい。ところが神を愛すべしとは!
全き従順と献身、そんなとてつもないことを要求する神を、一体どうやって愛したらいいのだろう?
神を愛するとは一体どういうことなのか?
神の、人に対する愛---アガペー---は、ゼロに対する百の愛だということになっている。人類は自ら堕落したのであって、神が独り子イエスを贖いとして与える義務は全然なかった。ところが彼は人類への愛ゆえにそれを与え、誰でもそれに信仰を働かせる者に永遠の命を約束する(Joh3:16)---そこまではまあ分かる。
ところが神は己れの愛に応ずる者に何を求めたか?
献身を---しかも愛の動機による献身をだ!
「人もし我に從ひ來らんと思はば、己をすて、日々おのが十字架を負ひて我に從へ」
これはまた、恐るべき思想的自由の剥奪、身体的自由の束縛ではないか。
自由にものを考えたり、好き勝手に生きたりできないのなら、永遠の命なんか貰ったところで一体何になるだろう?
或いは、己れを捨てて神に仕えることで神に何らかの利益を与えることができるのならまだいい。他者を益しているという自覚によって、我々は自尊心を持つことができるからだ。ところが神は、我々を必要としているわけでもない---「神汝の手より何をか受け給はん」(Job35:7)---ただ、己れの愛に対する感謝の表明としてのみそれを求めているにすぎない。
これでは百対ゼロどころか、その反対にゼロ対百と言った方がいいくらい、不均衡な関係ではないか。我々はただ神への感謝を表明する為だけに、我々の全生涯を費やさなければならないのだ。なんということだろう。
神殿建設のために夥しい宝物を捧げるダビデ。
「萬の物は汝より出づ我らは只汝の手より受けて汝に獻げたるなり」(Cro29:14)
すべてのものは神から出ている---我々は与えるべき何ものも持たず、もともと神のものであったものを、神に返すにすぎないのだ。
しかし、それでは与えられた意味がないのではないか? 一方的に与えておいて、後から返されることを期待するとは、神とは何者なのか?
神は常に人に対して、その生涯の中で神への奉仕が第一となることを求めてきた。片手間であってはならなくて、いつでもそれが第一であり、中心でなくてはならなかった。
イスラエルに於いては例の七面倒な律法に則って、しじゅう牛や羊を捧げたり、聖会に集まったり、敵と戦ったり、水を浴びたりしなくてはならなかった。最良の物は常に神に捧げられなければならなかった---穀物の初物とか、動物の脂肪とか。
彼らのすべてが、生きるために神に仕えるのではなく、神に仕えるために生きなければならなかった。
アブラハムもそうだった、ヨブもそうだった。
絶対者に対して絶対的な立場に立つということ、まさにそれが、神への愛における逆説なのだ。
神は何の見返りも求めずに人を愛するというのは真実か?
否、神の愛は人に対し、人の立場にありながら神の如く、神を愛することを要求する。何の見返りも求めずに神を愛することを要求するのだ。神の前に己れの持つ最善のもの、己れの持つすべてのものを差し出すことを要求するのだ。
「キリストの愛われらに迫れり。我ら思ふに、一人すべての人に代りて死にたれば、凡ての人すでに死にたるなり。その凡ての人に代はりて死に給ひしは、生ける人の最早おのれの為に生きず、己に代り死にて甦へり給ひし者のために、生きん為なり」(2Co5:14,15)
そう、キリストの愛は圧倒的である。それは決断を強要する。即ち、その愛に応じて己れを捨てることによって、道徳的に正しい人間であることを示すか、あるいは、その愛に応えないことによって、道徳的にどうしようもないろくでなしであることを示すかの決断を。
我々は、この圧倒的な愛を前にして尚踏みとどまり、私はお前に贖いとして死んでくれと頼んだ覚えはない、お前が勝手に死んだのではないか、勝手に死んでおいて、後から同じだけの愛と献身を要求するとは一体どういう愛なのかと、口に出して言うだけの神経を持ち合わせているだろうか?
* *
mortality がimmortality に出会ったときの恐怖。
シナイで神に出会ったイスラエル。
「汝らの近づきたるは、火の燃ゆる觸り得べき山・黒雲・黒闇・嵐、ラッパの音、言の聲にあらず、この聲を聞きし者は此の上に言の加へられざらんことを願へり。これ『獣すら山に觸れなば、石にて撃るべし』と命ぜられしを、彼らは忍ぶこと能はざりし故なり。その現れしところ極めて怖しかりしかば、モーセは『われ甚く怖れ戰けり』と云へり」(He12:18-20)
恒久性の概念。
常にそして永久に。
ラテン語のsemperには「常に」と「永久に」と言う二つの意味がある。この二つの概念は同じではない。同じでない二つの概念が一つの言葉で表されているのはなぜか?
この言葉を考え出した精神性のうちには、「これまでずっとそうであったことは、これからもずっとそうである、あるいはあるべきである」という信念が働いていたのだ。
この考え方でいくと、現在という一点に何ら特別な意味はなく、それは無限から無限へ流れる時間の流れの中の一点にすぎない。
そしてもちろんそういう精神性は神に由来するのだ。
私はアルファでありオメガであり---
神に仕えつづけること。今日も、明日も、ずっと、常に、永遠に。
その考えはAを怖れさせた。
永続性という牢獄の中で、Aは自分がほとんど死にそうに、窒息しそうになっているのを見いだす。
Aの祈り。
どうぞ飛び立つ勇気を与えて下さい、そして一生飛び続ける強さを---
いや、そうではなく。
もっともっと高く、飛んでゆきたいという願いを。
神に仕えることができないのなら、一切の事柄は無駄であった。
本当に、心から、献身すら果たせれば他には何もいらないと思っていた。
実際その頃は、神の僕の名に恥じない生活を送っていた。自転車を一時間こいで高校から帰ってくると、疲れた足をひきずって集会へ、あるいは伝道へ出掛ける---日々聖書を研究し、その規範に従って生活して---実存主義者やニヒリストと付き合ったりすることもなく。
それでもやはり、献身とは、最終的には内面の問題だった。
外面の行動によって内面を変えることはできないのだった。
Aは最終的に、己れを捨てて神にすべてを差し出したいと、本当に、心の底から思うことができなかった。そう思うことができなかったので、どれほどAは苦しんだだろう。
Penance, that's enough! Penitence, none!
真摯なる自己欺瞞を、ついにAは貫けなかった。
* *
この章を結ぶにあたって、ずっと後年になってからAが出会い、神への愛の告白として最も感動的なものの一つであると感じた書物について、少し語ろう。
G.K.チェスタトンの<正統とは何か>。
著者はカトリックで、この書物は要するに護教論なのだが、それがちっとも人をうんざりさせないのは、その文章の調子に、彼が自分のことを抑圧したりあるいは棚に上げたりしているところが全くないからである。むしろ不自然に思えるくらい、全くない。その反対に、この不信心な世にあって無視されたりひどく誤解されたりしている、愛する神と教会を弁護するために、彼は自分の持つ豊かなウィットと才能を縦横無尽に駆使している、そしてそうすることを、心から楽しんでいるのである。
もちろん我々は、教理面における彼の言い分をすべて受け入れるわけにはいかない。チェスタトンほどの優れた知性が、三位一体や永劫の地獄などの存在を平気で信じていられるというのには、全く首を傾げざるを得ない。それは全く、知性の従順が誤用された結果であるとしか、考えようがない。
それでも尚、それは非常に感動的な書物なのである。
特に感動的なのは、<おとぎの国の倫理学>という題の付された第四章で、ここで彼はおとぎ話の論理に則って愛や感謝や道徳の問題を解きあかしてみせる。というのは、おとぎ話こそは彼の「最初にして最後の哲学、一点の曇りもなく信じて疑わぬ哲学」だからである。
「私が経験したもっとも強大な感情は何かと言えば、人生は驚異であると同時に貴重だという感情だったのだ。それは一つの恍惚であった。なぜならそれは冒険だったからである。そしてそれが冒険であったのは、それが一つの偶然であったからだった。おとぎ話には、お姫様より怪獣ののほうがたくさん出てくるからといって、それでおとぎ話の楽しさが少しでも少なくなることはまるでなかった。とにかくおとぎの国にいることが楽しかったのである。あらゆる幸福の源は感謝である。・・・サンタクロースが靴下に玩具やお菓子の贈り物を入れてくれると、子供たちはただすなおに感謝する。それならサンタクロースが、私の靴下にこの二本の奇跡的な脚という贈り物を入れてくれた時、私はどうしてすなおに感謝していけない理由があったろう。誕生日のプレゼントに葉巻やスリッパを貰ったら、我々は贈ってくれた人に感謝する。それなら誕生日のプレゼントに誕生そのものを貰った時、誰にも感謝してはいけない理由がどこにあろうか」
それから彼は「もし」という言葉の効用について語る。
「あらゆる美徳はこの『もし』の中にある。・・・妖精はいつもこういう言いかたをする---『もし《牛》という言葉さえ言わなければ、あなたは金とサファイアの宮殿にお住みになれます。』あるいは、『もし王女様にタマネギさえ見せなければ、いつまでも王女様と一緒に幸せな暮らしができるのです。』魔法の力はいつでもたった一つ、してはならない条件にかかっている。たった一つの小さなことだけが禁じられていて、その条件さえ破らなければ、目も眩むような壮大なことがみな与えられるのだ。・・・
「この国の本当の住人たちは、自分にはぜんぜん理解できないものにいとも従順に従うのである。おとぎの国では、不可解な幸福が不可解な条件に支配されている。箱を開けるとあらゆる災厄が一度に飛び出す。たった一つの言葉を忘れたばっかりに、数々の都市が姿を消す。ランプに火をつけると、恋が飛んで逃げて行く。花を摘んだとたん、何人もの人の命が失われてしまう。リンゴを食べると、神の希望が消え失せる。
「おとぎ話はいつもこんな調子である。・・・
「シンデレラは、降って湧いたように馬車と馭者とを貰ったが、しかし同じようにどこからともなく命令も受けたのである---十二時までにはかならず帰って来るように。それに彼女にはガラスの靴もあった。そして実際、このガラスという物質が、おとぎ話であれほどたびたび出てくるということは、どう考えても単なる偶然とは思えない。ガラスのお城に住む王女様もあれば、ガラスの山に住んでいる王女様もある。・・・このガラスのか細い輝きは、実は、幸福がいかにもキラキラしてしかし同時にいかに壊れやすいものか、その事実を表しているからにほかならない。たしかに幸福はガラスに似ている。・・・そしておとぎ話のこの感覚もまた私の心の奥底に深くしみこんで、世界全体にたいする私の感受性を決めてしまったのである。人生はダイアモンドのように輝くが、同時に窓ガラスのように壊れやすい---私はそう感じ、そして今もそう感じている」
「だが、誤解しないでいただきたい。壊れやすいということは、壊滅しやすいというのと同じではないのだ。ガラスを打てば、ひとたまりもなく壊れてしまう。だから要するに打たなければよろしい。そうすればガラスは何千年も元のままである。人間の喜びとは、まさにこれだと私には思えたのだ。妖精の国であろうと地上であろうと変わりはない。幸福は、われわれが何かをしないことにかかっている。ところがそれは、われわれがいつ何時でもやりかねないことであって、しかも、なぜそれをしてはならぬのか、その理由はよくわからないことが多いのだ。ところで、私がここで特に強調しておきたいのは、少なくとも私には、これがぜんぜん不当だとは思えなかったという点である。たとえば、粉屋の三番目の息子が妖精に向かってこう聞くとする---『何だって妖精の宮殿で逆立ちしてはいけないのですか。その理由を説明して下さい。』すると妖精はこの要請に答えて、まこと正当にこう言うだろう。『ふむ。そんなことを言うんなら、そもそもなぜ妖精の宮殿がここにあるのか、その理由をまず説明して貰おう。』あるいはシンデレラが聞いたとする---『どうして私は舞踏会を十二時に出なければならないのですか。』魔法使いは答えるはずだ---『どうしてお前は十二時までそこにいるんだい。』もしかりに私が遺言をして、物を言う象を十匹と、天馬を百頭、ある男に残してやるとする。遺言の条件が、この贈り物と同様、少々奇妙であったとしても、その男は文句を言えた義理ではあるまい。天馬がいくらで売れるだろうなどと、下らぬ穿鑿なんかしないのが礼儀というものだ。そして私にとっては、現に生きているということ、現に世界がそこにあるということ自体が、実に途方もなく奇妙な遺産に思われて、だから、たとえ私には何から何までわからぬことだらけだとしても、その理由がわからぬと言って文句をつけるなどということは思いもよらなかったのだ。・・・『してはならない』ことは『してもよろしい』ことと同様に異様であった。太陽と同じく驚くべきことであり、水と同じくとらえがたく、そびえたつ大樹と同じく幻想的で恐るべきものだったのである」
そしてこれが、神の要求に対する彼の態度であった。それはいかにAのそれと違っていたことか!
神のすべての要求は彼にとって「たった一つの小さなこと」であったのだ。
それはたまたま彼の属していた組織がAのそれよりも人に対して少なく要求したということによるものではない。例えば性と結婚に関する神の要求について彼は書いている、「一人の女を守るということは、一人の女に本当に出会うという大事に比べては、まことに小さな代償というべきだ。一度しか結婚できぬと不平を言うのは、一度しか生まれられぬと不平を言うのと同じことだった」
こんなふうに言ってのける人間が世の中に存在するなんて、Aにはほとんど信じられなかった。Aにとって、一人の女に生涯忠実であるなんてことは、とても相手にできないくらい法外な要求と思われたのだ。
しかし、それ以上に我慢できなかったのは、例によって、神への愛ゆえにそうしなければならないという事実だった。
そしてまさにこれが、チェスタトンにとって神のすべての要求が「小さなこと」でしかなかった理由である。
彼の驚くべき従順と畏敬とを生み出しているもの、それは実に、愛である。彼の文章には、神に対する愛が、いとしい恋人に対するような心からの愛情がにじみ出ている。
そして、彼はもともとこうなるべき人だったのだ。彼はAと違って、神の会衆の中に生まれ落ちはしなかった。けれども彼は、神に出会うずっと前から神を探し求め、まだ見ぬ神を愛していたのだ。だからついに神に出会ったとき、そのあらゆる要求をことごとく受け入れ、己れをすっかり明け渡すのは、彼にとって容易なことだった。それから彼は、事実上生涯を神のために捧げた---すなわち彼の場合は、文筆活動によって神を宣伝するというかたちを取ったわけだ。
神と人との関係は、男と女の関係によく似ている。女にとって、愛する男に自分の体を明け渡すと共に、生涯をその男のために生きるのは至福の喜びである。彼女はすでにその男に心を明け渡しているからだ。ところが彼女がその相手を愛していない場合、それは悪夢以外の何ものでもない。神を愛する者と愛さない者との相違もかくのごとくである。
「幸福は、われわれが何かをしないことにかかっている。ところがそれは、われわれがいつ何時でもやりかねないことであって、しかも、なぜそれをしてはならぬのか、その理由はよくわからないことが多いのだ」
エデンにおけるアダムとエバについての、実に適格な描写ではないか。
Aが子供の頃、人々がしばしばアダムとエバを非難するのを聞いたものだが、彼らがどうしてそんなふうに非難するのか、Aにはさっぱり理解できなかった。 彼らは禁断の木の実を食べた---当然のことではないか。
Aがエバだったとしても、やっぱり食べたことだろう。食べないなんてことは、考えられもしなかった。そのために人類全体に対して死の宣告が下されようと、それが何だというのか?
それゆえ、Aは自分がエバでなかったことを、たまたまエバに生まれたばっかりに、自分の不従順のせいで人類全体が責任を取らされるようなはめにならないですんだことを、全くもって感謝したのである。そしてこんなふうな感謝の仕方をするということ自体、実にあってしかるべき感謝の欠如を示しているのに他ならなかった。
「あらゆる幸福の源は感謝である」! けだしこれは名言である。
しかし、感謝とは一つの才能ではあるまいか? これほど素直に、これほど自分自身との何の葛藤もなしに感謝できる人をAは知らない。この章の末尾のところで彼はまた書いている---「われわれは、何がわれわれを創ったにしても、その創り主にたいして従順であらねばならぬ。それは創られたものの当然の義務というものだ」
Aには、ごく自然にこんなふうに考えるなんて、とてもではないができなかった。
その反対に、Aはごく自然にこんなふうに考えた---せっかく命をもらったからには、それを好きなように使えるのでなければ意味がないではないか? そうでなければ感謝することもできないではないか---それを命じられた通りに使わなければならないとしたら。
そういうわけで、Aは今だ、十二時までに帰らなくてはならないのなら舞踏会なんかに連れていってもらわなくていいと、駄々をこねるシンデレラだった。
* *
しかし、どうやっても叩きつぶすことのできないAの不従順は、しだいにAの立場をのっぴきならぬものにしていった。
Aは伝道なんか好きではなかった---伝道なんかに一生を捧げたくなかった。しかし、だとしたら一体どういう生きかたをしたらいいのか?
神の側をとらないということはつまり神に敵する側をとるということだが(「我と偕ならぬ者は我にそむき、我とともに集めぬ者は散すなり」)、これまでずっとAのことを忍んでくれた神とその全会衆とを敵にまわしてまでする価値のある、どんな仕事がこの世の中に存在するというのか?
もう一度ものを書くのか---形而上学的な問題にわたらない限り無意味だと、分かってしまった文学をやるのか? 子供の頃思い描いたように山の中の一軒家にこもって、来る日も来る日もひたすら何の役にも立たない小説を書いて、そして静かに死んでゆくのか?
そんな強さが今のAにあるのか---ミューズへの信仰は失われてしまったというのに?
* *
神に従え。神に従え。
しかし、我々はなぜ神に従わなければならないのか?
チェスタトンにとって、それは全く明白なことだった。「それは創られた者の当然の義務である」と彼は言う。
こういう感謝の念が、Aには欠けていた。Aの心は「信仰の種子がまかれるべき土壌」なんかではなかった。
最終的にこの問題に関してAの目を開かせたのは、パスカルが書いたような、人間性についての真実、あるいは罪という概念の理解だったであろう。
人間は道徳的に生きるために、何ものかに従わなくてはならないということ。「もし罪なしと言はば、是みづから欺けるにて真理われらのうちになし」--1Joh1:8
罪、あるいは不完全性という概念を、Aは長いこと理解できなかった。他の人間は不完全かもしれないが、自分は完全だと思っていたのだから。
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
2013年11月30日
創造的な不幸-3-
創造的な不幸-愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ-
この作品について 目次
-3- 罪・自然
1986年、チェルノブイリ。
世界はもはや、かつての世界ではない---Aに対してこの事件が意味したのは、ヨーロッパに対して1914年が意味した如くであった。
それは秩序の崩壊であり、幻想の倒壊だったのである。
世界はもはや安全な場所ではなくなった---我々は今や、暗黒の混沌と狂気の力に剥き出しの状態で曝されるようになったのである。
もっとも、実際のところ世界は常にそんなふうだったのであり、ただAがそれまで気づかなかっただけのことにすぎない。
Aは確かに気づき、また知るようになった。自分がその中で育ち、それゆえに無邪気に信頼してきた文明が、どんな牙を隠し持っていたかを。
Aにおいて、最初の衝撃は放射能ノイローゼというかたちで現れ(目に見えない危険に対する病的な恐怖---例えば、雨にぬれることや、髪を梳くことを恐がる)、後には、もっと厄介な、抜きがたい悪影響が残って、後々まで尾をひいた。
というのは、問題は放射能汚染だけにとどまらなかったからだ。この二十世紀における自然破壊の末路を見るうちに(沈黙の春、風が吹くとき、オゾン、アマゾンの森林伐採)、Aは次第に極端な自然主義者になってゆき、しまいには、あらゆる自然は無条件に善であり、あらゆる不自然は絶対的に悪であると考えるようになった。それゆえ人間は決して自然の力を無視したり、これに逆らったりしてはならず、却って徹底的にこれに服従し、自らを適応させていかなくてはならない。それゆえより重要なのは、人類の存続よりも地球の存続の方である。
けれども、現実の世界がそういう哲学からいかにかけ離れたところで廻っているかを見るにつけ、Aはただ己れの非力に絶望するしかなかった。
Aはあらゆる不自然なものをいとい憎んだ---車、テレビ、現代建築。雑草を抜くこと、プラスチック製品、食品添加物、ヴェルサイユの中庭。果てはヨーロッパの長い歴史が生み出した現代文明そのものを。
このあたりから、自分の思想が神の目から見て危険な領域にさしかかったのを感じて、Aはそこで考えるのをやめる。少なくとも、意識の上では。
何といってもその頃Aはまだ子供だったのだし、その頃はまだ神を恐れていたのだ。だから、己れの心に神の教えに対する疑いが芽生えるのを許さなかった。
しかし、いったん動き始めた考えというものは、例え考えるのをやめても意識下では否応なく進んでいくものなのだ。Aが己れの考えと認めなかった、そこから先のAの考えを言葉にするとこういうふうになる---そのヨーロッパの長い歴史の、精神的な支柱となってきたものは何か---それは他ならぬキリスト教ではないか。考えてもみよ、ヨーロッパ人が原始の森と戦い、これを打ち倒し、征服していったイメージ、それはキリスト教徒が己れの罪と戦い、これを打ち倒し、征服していったイメージと重なりはしないか。
当然の成り行きだった、彼らにとって、自然性---ナチュラリティーは悪であり、罪であったのだから。キリスト教国から最初に森が消え、こうして彼らが環境問題に悩まされるようになったのは偶然ではない。
自然に反することは、いつでも必ず問題を引き起こした。
それでAは、キリスト教の教えが果して絶対的な意味で正しいのか---つまり、光合成が正しいとか、水の循環は正しいとかいうのと同じ意味において正しいのかという問題に、密かに悩まされ続けたのである。
* *
神は本当に正しいか。
それはまさにサタンがエデンにおいて提起した問題であり、ヨブが苦悩のうちに発しないではいられなかった疑問である。これに対して然りと答えるために、世界中のキリスト教徒は日夜戦ってきたのである。
それでもAは考えないわけにいかなかった---すなわち、水の循環はそのままにあるのが正しいのであって、これに反したり、これを束縛したりするのは正しくなかった。川底をコンクリートで固めたり、ダムやら人造湖やらを造ってせき止めたりするのは正しくなかった。必ずやどこかにひずみが生じ、何かが損害を受け、どこかが耐えきれなくなって溢れだした。それで、神の掟によって人間を縛るのが、これと同じ結果になりはしないかと恐れたのだ。
自然界は、ありのままにあるのが正しい。
人間もそうではないのか?
ホイットマンの言い分(「私はあるがままにある。それで十分だ」--I exist as I am. That is enough)は正しいのではないか?
一体どうして掟や道徳というものが必要なのか?
* *
神についての知識はそこらじゅうに溢れていた。Aは聖書を読み、自然界を眺め、周りの人間たちを観察した。けれども、そうして得た知識はどうも相矛盾するように思われた。あの千変万化する、生き生きとした、汲めども尽きせぬ深みと広がりを持った、すばらしい自然界を創り出したのと、あの人を抑圧する重苦しい道徳律を考案したのが同じ神だとは、(少なくとも感覚的には)とても思えなかったのだ。
Aはいつでも、自然界の示す豊かな表情に心打たれたものだ。
Aはしばしば雑草の群れを観察してスケッチしたり、雲の重なり具合を長いことじっと見つめたりして、考えた。万華鏡のように移ろいゆくこの二度とはない瞬間の、一つ一つが厳密な意味において神の創造と呼べるのだろうか? それともかくの如く世界を設計し、各々の機能を配置して、最初の一押しをしてやったのが神であるというだけで、あとはただ偶然の所産にすぎないのか?
その頃Aのいた会衆---それはずいぶん昔のことなのに、今だ思い出すだに喉を締めつけられるような息苦しさと嫌悪感がよみがえる。
それはまさに十七世紀のボストンそのものだった。
がちがちの道徳律と、偽善と、お仕着せの愛。
愛せよ、従え、べきである。
キリストは勝手に死んだのではなかったか?
我々は別に、頼みもしなかったのではないか?
勝手に死んでおいて愛と献身を要求するなんて、いったいどういう愛なのだろうか?
グリーンの<権力と栄光>の中に出てくる警部が、教会に対して抱いている生理的な嫌悪感が、Aにはよく理解できた。
「警部のはらわたには、犬と犬との間に生じるような生理的な憎悪の念が騒ぎだした。
『こいつらときたら、みんな同じように見えるんだから』
と、警部は言った。その白いモスリンのドレスを見たとき、恐怖と言えるようなものが彼を襲った。彼は少年時代の、教会の香のかおり、蝋燭、レース編み、うぬぼれ、犠牲の意味なんか分かりもしない連中が祭壇の上から突きつける、法外な要求などを思い出した。」
・・・A natural hatred as between dog and dog stirred in the lieutenant's bowels. ・・・
"They all look alike to me," the liutenant said. Something you could almost have called horror moved him when he looked at the white muslin dresses---he remembered the smell of incense in the churches of his boyhood, the candles and the laciness and the self-esteem, the immense demands made from the alter steps by men who didn't know the meaning of sacrifice.
あの、敬虔で純粋で重苦しい雰囲気。
Aは見てきたのだ---彼らがイエスのように、たえず己れの欲するところではなく神の命ずるところに従って生き、自分の理性や感情ではなく、神の言葉によって自分を律してゆく、そういう姿を。それはまっすぐな幾何学模様に刈り込まれた樹木のように、不自然な姿に思えた。Aは訝った---あれで彼らの人間存在全体としての収支は釣り合うのだろうか?
彼らはまるでヴェルサイユの中庭のようだった、そしてヴェルサイユの中庭こそは、Aがこの世で最も嫌ったものの一つだったのだ。
そして、自然主義者にとって特に耐えがたいのは、かの最大にして第一の掟であった---なんぢ心を盡し、精神を盡し、思いを盡し、力を盡して、主なる汝の神を愛すべし。自然主義者は自然であることを神聖であることの不可欠な条件として考える、だから彼らは、愛が命令され得るなんていう考えに耐えられないのだ。
自然主義者は、愛は天然資源---ナチュラル・リソースだと思っている。(「よいものはみんな、野性的で、自由だ」--All good things are wild and free --ヘンリー・デイヴィッド・ソロ-<ウォーキング>)
それゆえ、それを人工的に培おうとするのは自然---ネイチャーに対する冒瀆だった。
造花や模造真珠と同じように。
それゆえ、Aは否が応でも耳を傾けざるを得ない、心の底で密やかに、けれどしつっこく繰り返されるその囁きに。
要するに、キリスト教とエコロジー的発想とは両立しないのではないか? そして、エコロジー的発想が早急に敷衍される必要が誰の目にも明らかなこの二十世紀末に、エコロジー的発想と両立しないということは、つまりこの二十世紀末にあってキリスト教は立ち往かない、ということではないか?
この種の危惧は、キリスト教の存続をまじめに考えるすべての聖職者の間にもあってしかるべきなのだ。
Aはあるとき、キリスト教をエコロジーと結びつけようとする一人の牧師の努力について、新聞で読んだことがある。彼はキリスト教が反自然主義的でないことを証明しようとして、「キリストの」言葉を引き合いに出していた---「木の中にも石の中にも私はいる。」
Aが知る限り、キリストはこんな、八百万の神々みたいなことを言いはしなかった。よくよく見ると、それは外典からの引用だったのだ。
Aはむしろ失望した、と言っていい---キリスト教とエコロジーとを調和させるには、こんなこじつけに訴えるしかないのか?
こういう問題について、一体神はどう考えているのか?
神と人との無限の隔たりが生み出す異質さの感覚。
Aは見てきた---始終「べきである、べきである」と言われて、思いきりくつろぐことを決して許されない彼らの生き方。彼らが、人の救いに心を砕くあまり胃潰瘍になったり、己れの非力に絶望して鬱病になったり、己れの罪に思い悩んで神経症になったり、日曜日に寝坊する権利を放棄したり、神に捧げるべき時間が奪われるというので、それ自体は無害な楽しみや、場合によっては好きな仕事をすら断念したりするのを見てきて、Aは正直なところ、腹を立てた。
こんなのは不健全ではないか? 神は何だってわざわざ、身体と精神を痛めつけるような生き方を要求するのか? それは人間の本質と相入れないのではないか?
あるいは、完全な神を不完全な人間が代表することの不可能さ。
「さらば汝らの天の父の全きが如く、汝らも全かれ」(Mt5:48)
それは要するにプロパガンダである---人はそれを敏感に感じ取る。彼らがそれを完全に伝えようとして肩肘を張り、どんな偏りもないように注意するあまり臆病になり、あらゆる異議や疑念に対してただちに神を弁護できるように身構えているのを。
人はそんなものに心を動かされはしない。それでも尚、それは正しいやり方なのである。というのは、受け入れやすいように神の言葉を糖衣にくるんだり水増ししたりし、あるいはあまりに人間的なレベルに引き下げて語るのは、神に対する侮辱だからだ。
あまりに抽象的な論議は人を動かさず、自分の経験から直接生まれた実感の方が人を動かす。しかし、自分の経験しなかったことについても語らなければならないとしたら?
A自身も常々感じたのではなかったか---自分でも理解できないことを人に言っている無責任さ、信仰もないのに業だけが先走っている奇妙さを。というのは、誰がキリストを与え給うた神の愛なんかを「実感」できるだろうか?
Aは思い出す---演壇から講演したあと、自分の言葉に自分の行動が追いついていないのを感じて良心に苦しめられ、気分が悪くなって帰ってしまった講演者のことを。
Aは別に彼のことを哀れんだり批判したりする気はない---Aの組織にだってパリサイ人はいくらでもいたから、彼がそこまで発達した良心を持ち合わせていたことにAは感動したものだ。しかも彼自身は非の打ち所もなく善良な僕だったのだから。彼はまさに「わが體を打ちたたきて之を服従せしめ」たのだ。「恐らくは他人に宣傳へて自ら棄てらるる事あらん」。
そう、己れの中の悪を自覚しているというのは大切なことだ。そうでなければ己れの悪と戦うべきことを、ほんとうに他人に教えることはできない。
しかしその一方で、罪の自覚に圧倒されてしまってもならないのだ。我々は他人を教えなくてはならないし、それには己れの人格に関してある程度の自尊心を持つ必要があるからだ。絶望に屈してしまうことは許されない---キルケゴールによれば、まさにそれが最大の堕落なのだ。
人間が神を代表しようとする限り、常にこの種のディレンマがついてまわる---両極端の間で危うい均衡を保ち続ける努力が求められるのだ。人は鋭敏な良心を保って己れの中の悪を見つめながら、尚かつ他人を教えなければならない。
不完全な人間に対して、神は何という困難なことを求めるのか?
想起せよ---アウグスティヌスやルターやカルヴィンや、ジョナサン・エドワーズやデイヴィッド・ブレイナードや、神に仕えた他の幾多の偉大な人々が、同じ問題でどれほど苦しんだかを。
あるいは、この堕落した世にあって、とんでもなく高い道徳基準。
Aは知っている、世界がどんなに堕落しようと、苟も神の基準がそれに迎合するわけにいかないことを。
しかし、我々はどう考えたものだろうか、この世の堕落から抜け出せないながら、尚神の世界の清浄さに憧れる者たちのことを。
もちろんそういう者たちを、神は親切に助けようとするだろう、己れに仕えるにふさわしい者とするために。
しかし、そのままでは、そんな生き方を是認しはしない。彼らは自分の生活から、神の目に悪とみなされる習慣をきっぱりと断ち切るか、あるいは神の要求に応えんとする道徳的努力の方をきっぱりと断ち切るか、いづれにせよどちらかを選ばなければならない。
実際、決断は必要である---全く分断された二つの行動の基準の間を振り子運動し続けるだけでは、どこへ向かっても進んでゆかれない。そして、そのうちに良心がだんだんに鈍らされないとすれば、やめることのできない悪習に対して良心がこれを糾弾し続けるとすれば---そのうち精神分裂症になってしまうのがおちだろう。幸いにしてその良心が鈍感である場合でも、彼は自分の生き方に対して、決して誇りも自尊心も持つことがないだろう。あるいは、よしきっぱりと神を捨てることができたとしても、神の要求に応えきれなかった彼は、この世のあまりの堕落ぶりに対してもまた不慣れで、免疫を持っていないので、またしても適応異常に苦しめられることになるだろう。
いったい神は、これほど弱小な人間に対して、こんなに苛烈な決断を迫っていいものだろうか? 神の威光は、その達しがたい高さは、ここまで人間をおとしめ、弱くさせ、その力を奪っていいものだろうか?
そして、これこそがニーチェをしてキリスト教を痛烈に弾劾せしめたゆえんではなかったか? あるいはシュタイナー---「最悪の神をお前たちは造り出した。それはお前たちに良心を持つことを教えた。」
"The Portage To San Cristobal Of A.H." の中で登場人物のヒトラーは、なぜ「最終的解決」が必要であったかについて、劇的な説明をやってのける。それはキリスト教における罪あるいは良心についてのドグマが、この世界にいかなる精神的害悪をもたらしてきたかに関する、極めて的確な、おそろしいほどに真実な言説である。
・・・There must be a solution, a final solution. For what is the Jew if he is not a long cancer of unrest? I beg your attention, gentleman, I demand it. Was there ever a crueler invention, a contrivance more calculated to harrow human existence, than that of an omnipotent, all-seeing, yet invisible, impalpable, inconceivable God? ・・・ The Jew emptied the world by setting his God apart, immeasurably apart from man's senses. No images. No imagining even. A blank emptier than desert. Yet with a terrible nearness. Spying on our every misdeed, searching out the heart of our heart for motive. ・・・
我々は思い出すのではないだろうか、ニーチェのシニシズムを。小さな女の子が尋ねる、「神様は、いつでもどこでも私たちのことを見てらっしゃるってほんと?」母親が答える、「そうよ」すると女の子は言う、「まあ、何て失礼なんでしょう!」
・・・His God is purer than any other. And because we are his creatures, we must be better than ourselves, love our neighbour, be continent, give of what we have to the beggar. We must obey every jot of the law. We must bottle up our rages and desires, chastise the flesh and walk bent in the rain. You call me a tyrant, an enslaver. What tyranny and what enslavement have been more oppressive than the sick fantasies of the Jew? You are not Godkillers, but Godmakers. And that is infinitely worse. The Jew invented conscience.
But that was only the first piece of the blackmail. There was worse to come. The white-faced Nazarene. Gentlemen, I find it difficult to contain myself. ・・・ What did that epileptic rabbi ask of man? That he renounce the world, that he leave father and mother behind, that he offer the other cheek, that he render good for evil, that he love his neighbour as himself, no, better, for self-love is an evil. Oh, grand castration! Note the cunning of it. Demand of human beings more than they can give, and you will make them cripples, hypocrites, mendicants for salvation. ・・・ What could be than the Jew's addiction to the ideal?
読者は神への愛をめぐるくだりでもこの部分の一節が引用されたことを思い出されるだろう。そう、愛の問題と罪の問題とはつながっている。愛の問題は、いかにして己れの心を規範に服従させるかという問題であったが、罪の問題とは、そもそも己れの心を規範に服従させることが正しいのかどうかという問題だからである。
そして、どちらの問題が先に来るかは、それらを問題とする個人の、キリスト教的な概念との関係いかんによって決まるのである。
すなわち、キリスト教的な概念が彼にとって非常に身近で、それがほとんど〈前提〉とも言えるような個人にとっては、「汝愛すべし」という掟がまず最初にあるので、それゆえ愛の問題の方が先に来る。しかるに、それが彼にとって見慣れない、異質なものであるような個人にとっては、「愛すべし」という命令の正当性をまず納得しないことには愛することの困難に悩みようがないのであるから、当然罪の問題の方が先に来るわけだ。
そしてそれを敷衍して考えるならば、前者がキリスト教文化圏の精神性のあり方であり、後者が非キリスト教文化圏のそれである、と言う事ができる。そしてまたそれが、ヒトラーの論説においてその論法を、各々の論点の配列のされ方を決定している要素でもあるのだ。なぜなら、彼の論法の独特で劇的な点は、きわめてキリスト教的な問題を、全くの異教徒の立場から分析し考察している点にあるからである。実際、自分の目的を遂行するために教会と手を結んだという歴史的事実とは裏腹に、ヒトラーは正真正銘の異教徒だった。彼は側近にこう語っていたという。
「ローマ・カトリックであろうが福音主義教会であろうが、どれもみな同じである。そこには未来はない。ファシズムは神の名にかけて教会と和を結ぶことがあるかもしれない。私もそうするだろう。何故それでいけないのか。そうしたからといってドイツのキリスト教を徹底的に根絶する妨げにはならない。・・・もし私が欲するなら、二、三年のうちに教会を抹殺することもできるのだ」
それゆえ戯曲中のヒトラーがキリスト教についてこんなふうに語るのは歴史的事実にも適っているのである。
・・・To slaughter a city because of an idea, because of a vexation over words. That was a high invention, a device to alter the human soul. Your invention. One Israel, one Volk, one leader. ・・・
彼は神を知らない全異邦人を代表して、神の存在が空気と同じほど自明でない、すべての人間の視点から語っているのである。
こうしてこの戯曲において、シュタイナーは、キリスト教的な世界観と非キリスト教的なそれとの間の決して埋められない深い断絶を、その鋭い亀裂を、忘れられない仕方で鮮やかに描き出しているのである。
* *
あるいは彼らが後生大事に守る、肩が凝りそうに厳格な性道徳。
「凡ての人、婚姻のことを貴べ、また寝床を汚すな。神は淫行のもの、姦淫の者を審き給ふべければなり」(He13:4)
神の規準に適った唯一のセックスとは、ただ結婚関係内のセックスのみであった。それ以外はすべからく排斥の対象となった。
まちがったセックスをしないだけでは十分でなかった。それを心の中で欲することもまた罪だった。それは人を、まちがいなく行動へ駆り立てるからだ。
「すべて色情を懐きて女を見るものは、既に心のうち姦淫したるなり」(Mt5:28) しかし、それでもまだ十分ではなかった。
欲したり考えたりしないためには欲したり考えたりしないような精神性を培う必要があって、そのためには何で自分を養うかということに十分注意しなければならなかった。それゆえ、不道徳を容認あるいは称揚するようなあらゆるメディアはことごとく避けられた---小説、雑誌、映画、テレビ、果ては街頭のポスターや電車の吊り革広告に至るまで。彼らはダビデに倣って祈ったのだ---「わが眼をほかにむけて虚しきことを見ざらしめ 我をなんぢの途にて活かし給へ」(Ps119:37)
さらに彼らは、同じ規準を持たない一般の人々の、悪意のない会話やジョークによっても堕落させられることがないよう、極端につきあいを制限していた。彼らが古代ローマにおける原始キリスト教のように、孤立した共同体を形成せざるを得なかったのも無理はない。時代はもはやヴィクトリア朝ではなく、罪は洪水のように、そこらじゅうに溢れていたからだ。
彼らが結婚を考えて誰かとつき会おうという時には、まちがいがないように細心の注意が払われた---礼儀に適った振る舞い、付き添いつきのデート。部屋や車の中で二人きりになる状況は避けられなくてはならなかった。
これらすべてのことに加えて尚必要とされることがあった---
「エホバを愛しむものよ惡をにくめ」(Ps97:10)
人は悪を避けるだけでなく、悪を憎まなければならなかったのだ。言うまでもなく、そうしなければ本当に悪を避けることはできないからだ。人は、その生き方だけでなく、心そのものが神と調和していなければならなかった。
こういう徳高い人々を見ていてAは、こういう人たちを見てフロイトは抑圧理論を思いついたのだろうなと思ったものだ。
性欲はそれ自体、満たされようとするアプリオリな方向性を持っているのではないか? それを外的要素によって制約しようとする方がまちがっているのではないか? それは反自然的ではないのか?
互いを永続的に縛りつける結婚関係! 考えただけで、息がつまって死にそうだった。Aが子供のときから既に恋愛にも結婚にも興味をなくしてしまったのは、要するにそういう束縛を嫌ったからだった。
Aは一つの規準しか知らなかったし、それによれば、結婚はほとんど神への献身のアナロジーだった。
神から逃れることはできない。しかし、ありがたいことに結婚から逃げ出すことはできたのだ。
* *
行って動物たちと共に住むことができたら。
彼らはあんなにも落ち着き払って、満たされている。
私は立って彼らを眺める、長い長い間。
彼らは自分の境遇にやきもきしたり、泣き言を言ったりしない。
彼らは暗闇の中に目を覚ましたまま横たわって、
自分の罪を嘆いたりしない。
彼らは神への義務だとか言い出して、人をうんざりさせたりしない。
--ウォルト・ホイットマン<ソング・オヴ・マイセルフ>
I think I could turn and live with animals, they're so placid and
self-contained,
I stand and look at them long and long.
They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sin,
They do not make me sick discussing their duty to God.
---W. Whitman, "Song of Myself"
人が自然界と同じように振る舞うのを妨げているもの、そしてAがキリスト教を自分の生き方とするつもりならばまず理解しなければならない、にも拘らず理解できずにいるもの---それは要するに、罪という概念であるように思われた。それゆえ人は現在に留まってはならず、尚一層神の規準にかなう者となるべくたえず努力していかなければならない。
「わが體を打ちたたきて之を服従せしむ。恐らくは他人に宣傳へて自ら棄てらるる事あらん」(1Co9:27)
それはこのような厳しい自己鍛練を必要とする。
戦われ、乗り越えられるべきものは、まず意識されなければならない。ところがAはどうしても神の前に己れの罪を意識することができなかったし、また意識することを欲しなかったのだ。
アダムから受け継いだ罪という概念---それは要するに、一つのイデオロギーなのではないか? しかも何というイデーだろう、ただ存在しているだけで罪を負っているだなんて。人間の尊厳に対する、何という侮辱だろう。どうしてそんなふうに、神の前に人をおとしめようとするのか? なぜそれほど卑屈な人生観を、自虐的な人間観を持たなければならないのか? すべての人は罪を犯しただって? 私がどんな悪いことをしたというのか?
債務の例え。キリスト教における罪という概念について、Aにつくづく考えさせた話の一つ。
「この故に、天國はその家來どもと計算をなさんとする王のごとし。計算を始めしとき、一萬タラントの負債ある家來つれ來られしが、償ひ方なかりしかば、其の主人、この者とその妻子と凡ての所有とを賣りて償ふことを命じたるに、その家來ひれ伏し拝して言ふ 『寛くし給へ、さらば悉く償はん』その家來の主人あはれみて之を解き、その負債を免したり。然るに其の家來いでて、己より百デナリを負ひたる一人の同僚にあひ、之をとらへ、喉を締めて言ふ『負債を償へ』その同僚ひれ伏し、願ひて『寛くし給へ、さらば償はん』と言へど、肯はずして往き、その負債を償ふまで之を獄に入れたり。同僚ども有りし事を見て甚く悲しみ、往きて有りし凡ての事をその主人に告ぐ。ここに主人かれを呼び出して言ふ『惡しき家來よ、なんぢ願ひしによりて、かの負債をことごとく免せり。わが汝を憫みしごとく、汝もまた同僚を憫むべきにあらずや』斯くその主人、怒りて、負債をことごとく償ふまで彼を獄卒に付せり。もし汝等おのおの心より兄弟を赦さずば、我が天の父も亦なんぢらに斯くのごとく爲し給ふべし」
一万タラントは60,000,000デナリである。つまりこの差異は、我々が神に対して負っている罪の大きさと、我々の仲間の人間が我々に対して負っている罪の大きさとの、桁違いな差異を表しているのである。
Aが教えられてきたところによれば、この寓話は神の愛の偉大さを実によく表しているということになっているのだが、Aにはどうもそうではなくて、神に対して人間が余儀なくされている、ひどく不公平で弱い立場を、実によく表しているように思えた。なるほど我々は神に対して一万タラントを負っているかもしれない。しかしそれは我々自身が使い込んだ一万タラントではないのだ。アダムが罪を犯して以来、我々は自らの意志に関係なく、否応なしに罪を負って生まれてくるのであり、言わば我々はみんな、一万タラントの負債と共に生まれてくるのだ。それに対して我々は責任を負っていない。だのにどうして我々はそのためにひれ伏して懇願したり、そのことを許されたりしなくてはならないのか?
あるいは、一タラント与えられてそのまま返した僕。
「また或人とほく旅立せんとして、其の僕どもを呼び、之に己が所有を預くるが如し。各人の能力に應じて、或者には五タラント、或者には二タラント、或者には一タラントを興へ置きて旅立せり。五タラントを受けし者は、直ちに往き、之をはたらかせて他に五タラントを儲け、二タラントを受けし者も同じく他に二タラントを儲く。然るに一タラントを受けし者は、往きて地を堀り、その主人の銀をかくし置けり。久しうして後この僕どもの主人きたりて彼らと計算したるに、五タラントを受けし者は他に五タラントを持ちきたりて言ふ『主よ、なんぢ我に五タラントを預けたりしが、視よ、他に五タラントを儲けたり』主人言ふ『宜いかな、善かつ忠なる僕、なんぢは僅かなる物に忠なりき。我なんぢに多くの物を掌どらせん、汝の主人の歓喜に入れ』二タラントを受けし者も來たりて言ふ『主よ、なんぢ我に二タラントを預けたりしが、視よ、他に二タラントを儲けたり』主人言ふ『宜いかな、善かつ忠なる僕、なんぢは僅かなる物に忠なりき。我なんぢに多くの物を掌どらせん、汝の主人の歓喜に入れ』また一タラントを受けし者もきたりて言ふ『主よ、我はなんぢの嚴しき人にして、播かぬ處より刈り、散さぬ處より斂むることを知るゆえに、懼れてゆき、汝のタラントを地に藏しおけり。視よ、汝はなんぢの物を得たり』主人こたへて言ふ『惡しくかつ惰れる僕、わが播かぬ處より刈り、散さぬ處より斂むることを知るか。さらば我が銀を銀行にあづけ置くべかりしなり、我きたりて利子とともに我が物をうけ取りしものを。されば彼のタラントを取りて十タラントを有てる人に興へよ。すべて有てる人は、興へられて愈々豊ならん。されど有たぬ者は、その有てる物をも取らるべし。而して此の無益なる僕を外の暗黒に逐ひいだせ、其處にて哀哭・切歯することあらん』」---(Mt25:14-30)
彼は託されたものを失ったわけでもないし、主人に仕えるのをやめてしまったわけでもない。それでも叱責され、退けられたのである。
神の前に、生まれてくるすべての人間はこれらの僕のようである---すべての人間は是認を得るために積極的に善をなさねばならず、何もしないことは悪なのである。
あるいは---
「汝等のうち誰か或は耕し、或は牧する僕を有たんに、その僕畑より歸りきたる時、これに對ひて『直ちに來り食に就け』と言ふ者あらんや。反つて『わが夕餐の備をなし、わが飲食するあひだ、帯して給仕せよ、然る後に、なんぢ飲食すべし』と言ふにあらずや。僕、命ぜられし事を為したればとて、主人これに謝すべきか。かくのごとく汝らも命ぜられし事をことごとく為したる時『われらは無益なる僕なり、為すべき事を為したるのみ』と言へ」---(Lu17:7-10)
神の前に、すべての人間はかくのごとく身を持さなければならないのである。 己れを捨て、献身の歩みを全うして尚、我々はこのように言い切れるだろうか?
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
この作品について 目次
-3- 罪・自然
1986年、チェルノブイリ。
世界はもはや、かつての世界ではない---Aに対してこの事件が意味したのは、ヨーロッパに対して1914年が意味した如くであった。
それは秩序の崩壊であり、幻想の倒壊だったのである。
世界はもはや安全な場所ではなくなった---我々は今や、暗黒の混沌と狂気の力に剥き出しの状態で曝されるようになったのである。
もっとも、実際のところ世界は常にそんなふうだったのであり、ただAがそれまで気づかなかっただけのことにすぎない。
Aは確かに気づき、また知るようになった。自分がその中で育ち、それゆえに無邪気に信頼してきた文明が、どんな牙を隠し持っていたかを。
Aにおいて、最初の衝撃は放射能ノイローゼというかたちで現れ(目に見えない危険に対する病的な恐怖---例えば、雨にぬれることや、髪を梳くことを恐がる)、後には、もっと厄介な、抜きがたい悪影響が残って、後々まで尾をひいた。
というのは、問題は放射能汚染だけにとどまらなかったからだ。この二十世紀における自然破壊の末路を見るうちに(沈黙の春、風が吹くとき、オゾン、アマゾンの森林伐採)、Aは次第に極端な自然主義者になってゆき、しまいには、あらゆる自然は無条件に善であり、あらゆる不自然は絶対的に悪であると考えるようになった。それゆえ人間は決して自然の力を無視したり、これに逆らったりしてはならず、却って徹底的にこれに服従し、自らを適応させていかなくてはならない。それゆえより重要なのは、人類の存続よりも地球の存続の方である。
けれども、現実の世界がそういう哲学からいかにかけ離れたところで廻っているかを見るにつけ、Aはただ己れの非力に絶望するしかなかった。
Aはあらゆる不自然なものをいとい憎んだ---車、テレビ、現代建築。雑草を抜くこと、プラスチック製品、食品添加物、ヴェルサイユの中庭。果てはヨーロッパの長い歴史が生み出した現代文明そのものを。
このあたりから、自分の思想が神の目から見て危険な領域にさしかかったのを感じて、Aはそこで考えるのをやめる。少なくとも、意識の上では。
何といってもその頃Aはまだ子供だったのだし、その頃はまだ神を恐れていたのだ。だから、己れの心に神の教えに対する疑いが芽生えるのを許さなかった。
しかし、いったん動き始めた考えというものは、例え考えるのをやめても意識下では否応なく進んでいくものなのだ。Aが己れの考えと認めなかった、そこから先のAの考えを言葉にするとこういうふうになる---そのヨーロッパの長い歴史の、精神的な支柱となってきたものは何か---それは他ならぬキリスト教ではないか。考えてもみよ、ヨーロッパ人が原始の森と戦い、これを打ち倒し、征服していったイメージ、それはキリスト教徒が己れの罪と戦い、これを打ち倒し、征服していったイメージと重なりはしないか。
当然の成り行きだった、彼らにとって、自然性---ナチュラリティーは悪であり、罪であったのだから。キリスト教国から最初に森が消え、こうして彼らが環境問題に悩まされるようになったのは偶然ではない。
自然に反することは、いつでも必ず問題を引き起こした。
それでAは、キリスト教の教えが果して絶対的な意味で正しいのか---つまり、光合成が正しいとか、水の循環は正しいとかいうのと同じ意味において正しいのかという問題に、密かに悩まされ続けたのである。
* *
神は本当に正しいか。
それはまさにサタンがエデンにおいて提起した問題であり、ヨブが苦悩のうちに発しないではいられなかった疑問である。これに対して然りと答えるために、世界中のキリスト教徒は日夜戦ってきたのである。
それでもAは考えないわけにいかなかった---すなわち、水の循環はそのままにあるのが正しいのであって、これに反したり、これを束縛したりするのは正しくなかった。川底をコンクリートで固めたり、ダムやら人造湖やらを造ってせき止めたりするのは正しくなかった。必ずやどこかにひずみが生じ、何かが損害を受け、どこかが耐えきれなくなって溢れだした。それで、神の掟によって人間を縛るのが、これと同じ結果になりはしないかと恐れたのだ。
自然界は、ありのままにあるのが正しい。
人間もそうではないのか?
ホイットマンの言い分(「私はあるがままにある。それで十分だ」--I exist as I am. That is enough)は正しいのではないか?
一体どうして掟や道徳というものが必要なのか?
* *
神についての知識はそこらじゅうに溢れていた。Aは聖書を読み、自然界を眺め、周りの人間たちを観察した。けれども、そうして得た知識はどうも相矛盾するように思われた。あの千変万化する、生き生きとした、汲めども尽きせぬ深みと広がりを持った、すばらしい自然界を創り出したのと、あの人を抑圧する重苦しい道徳律を考案したのが同じ神だとは、(少なくとも感覚的には)とても思えなかったのだ。
Aはいつでも、自然界の示す豊かな表情に心打たれたものだ。
Aはしばしば雑草の群れを観察してスケッチしたり、雲の重なり具合を長いことじっと見つめたりして、考えた。万華鏡のように移ろいゆくこの二度とはない瞬間の、一つ一つが厳密な意味において神の創造と呼べるのだろうか? それともかくの如く世界を設計し、各々の機能を配置して、最初の一押しをしてやったのが神であるというだけで、あとはただ偶然の所産にすぎないのか?
その頃Aのいた会衆---それはずいぶん昔のことなのに、今だ思い出すだに喉を締めつけられるような息苦しさと嫌悪感がよみがえる。
それはまさに十七世紀のボストンそのものだった。
がちがちの道徳律と、偽善と、お仕着せの愛。
愛せよ、従え、べきである。
キリストは勝手に死んだのではなかったか?
我々は別に、頼みもしなかったのではないか?
勝手に死んでおいて愛と献身を要求するなんて、いったいどういう愛なのだろうか?
グリーンの<権力と栄光>の中に出てくる警部が、教会に対して抱いている生理的な嫌悪感が、Aにはよく理解できた。
「警部のはらわたには、犬と犬との間に生じるような生理的な憎悪の念が騒ぎだした。
『こいつらときたら、みんな同じように見えるんだから』
と、警部は言った。その白いモスリンのドレスを見たとき、恐怖と言えるようなものが彼を襲った。彼は少年時代の、教会の香のかおり、蝋燭、レース編み、うぬぼれ、犠牲の意味なんか分かりもしない連中が祭壇の上から突きつける、法外な要求などを思い出した。」
・・・A natural hatred as between dog and dog stirred in the lieutenant's bowels. ・・・
"They all look alike to me," the liutenant said. Something you could almost have called horror moved him when he looked at the white muslin dresses---he remembered the smell of incense in the churches of his boyhood, the candles and the laciness and the self-esteem, the immense demands made from the alter steps by men who didn't know the meaning of sacrifice.
あの、敬虔で純粋で重苦しい雰囲気。
Aは見てきたのだ---彼らがイエスのように、たえず己れの欲するところではなく神の命ずるところに従って生き、自分の理性や感情ではなく、神の言葉によって自分を律してゆく、そういう姿を。それはまっすぐな幾何学模様に刈り込まれた樹木のように、不自然な姿に思えた。Aは訝った---あれで彼らの人間存在全体としての収支は釣り合うのだろうか?
彼らはまるでヴェルサイユの中庭のようだった、そしてヴェルサイユの中庭こそは、Aがこの世で最も嫌ったものの一つだったのだ。
そして、自然主義者にとって特に耐えがたいのは、かの最大にして第一の掟であった---なんぢ心を盡し、精神を盡し、思いを盡し、力を盡して、主なる汝の神を愛すべし。自然主義者は自然であることを神聖であることの不可欠な条件として考える、だから彼らは、愛が命令され得るなんていう考えに耐えられないのだ。
自然主義者は、愛は天然資源---ナチュラル・リソースだと思っている。(「よいものはみんな、野性的で、自由だ」--All good things are wild and free --ヘンリー・デイヴィッド・ソロ-<ウォーキング>)
それゆえ、それを人工的に培おうとするのは自然---ネイチャーに対する冒瀆だった。
造花や模造真珠と同じように。
それゆえ、Aは否が応でも耳を傾けざるを得ない、心の底で密やかに、けれどしつっこく繰り返されるその囁きに。
要するに、キリスト教とエコロジー的発想とは両立しないのではないか? そして、エコロジー的発想が早急に敷衍される必要が誰の目にも明らかなこの二十世紀末に、エコロジー的発想と両立しないということは、つまりこの二十世紀末にあってキリスト教は立ち往かない、ということではないか?
この種の危惧は、キリスト教の存続をまじめに考えるすべての聖職者の間にもあってしかるべきなのだ。
Aはあるとき、キリスト教をエコロジーと結びつけようとする一人の牧師の努力について、新聞で読んだことがある。彼はキリスト教が反自然主義的でないことを証明しようとして、「キリストの」言葉を引き合いに出していた---「木の中にも石の中にも私はいる。」
Aが知る限り、キリストはこんな、八百万の神々みたいなことを言いはしなかった。よくよく見ると、それは外典からの引用だったのだ。
Aはむしろ失望した、と言っていい---キリスト教とエコロジーとを調和させるには、こんなこじつけに訴えるしかないのか?
こういう問題について、一体神はどう考えているのか?
神と人との無限の隔たりが生み出す異質さの感覚。
Aは見てきた---始終「べきである、べきである」と言われて、思いきりくつろぐことを決して許されない彼らの生き方。彼らが、人の救いに心を砕くあまり胃潰瘍になったり、己れの非力に絶望して鬱病になったり、己れの罪に思い悩んで神経症になったり、日曜日に寝坊する権利を放棄したり、神に捧げるべき時間が奪われるというので、それ自体は無害な楽しみや、場合によっては好きな仕事をすら断念したりするのを見てきて、Aは正直なところ、腹を立てた。
こんなのは不健全ではないか? 神は何だってわざわざ、身体と精神を痛めつけるような生き方を要求するのか? それは人間の本質と相入れないのではないか?
あるいは、完全な神を不完全な人間が代表することの不可能さ。
「さらば汝らの天の父の全きが如く、汝らも全かれ」(Mt5:48)
それは要するにプロパガンダである---人はそれを敏感に感じ取る。彼らがそれを完全に伝えようとして肩肘を張り、どんな偏りもないように注意するあまり臆病になり、あらゆる異議や疑念に対してただちに神を弁護できるように身構えているのを。
人はそんなものに心を動かされはしない。それでも尚、それは正しいやり方なのである。というのは、受け入れやすいように神の言葉を糖衣にくるんだり水増ししたりし、あるいはあまりに人間的なレベルに引き下げて語るのは、神に対する侮辱だからだ。
あまりに抽象的な論議は人を動かさず、自分の経験から直接生まれた実感の方が人を動かす。しかし、自分の経験しなかったことについても語らなければならないとしたら?
A自身も常々感じたのではなかったか---自分でも理解できないことを人に言っている無責任さ、信仰もないのに業だけが先走っている奇妙さを。というのは、誰がキリストを与え給うた神の愛なんかを「実感」できるだろうか?
Aは思い出す---演壇から講演したあと、自分の言葉に自分の行動が追いついていないのを感じて良心に苦しめられ、気分が悪くなって帰ってしまった講演者のことを。
Aは別に彼のことを哀れんだり批判したりする気はない---Aの組織にだってパリサイ人はいくらでもいたから、彼がそこまで発達した良心を持ち合わせていたことにAは感動したものだ。しかも彼自身は非の打ち所もなく善良な僕だったのだから。彼はまさに「わが體を打ちたたきて之を服従せしめ」たのだ。「恐らくは他人に宣傳へて自ら棄てらるる事あらん」。
そう、己れの中の悪を自覚しているというのは大切なことだ。そうでなければ己れの悪と戦うべきことを、ほんとうに他人に教えることはできない。
しかしその一方で、罪の自覚に圧倒されてしまってもならないのだ。我々は他人を教えなくてはならないし、それには己れの人格に関してある程度の自尊心を持つ必要があるからだ。絶望に屈してしまうことは許されない---キルケゴールによれば、まさにそれが最大の堕落なのだ。
人間が神を代表しようとする限り、常にこの種のディレンマがついてまわる---両極端の間で危うい均衡を保ち続ける努力が求められるのだ。人は鋭敏な良心を保って己れの中の悪を見つめながら、尚かつ他人を教えなければならない。
不完全な人間に対して、神は何という困難なことを求めるのか?
想起せよ---アウグスティヌスやルターやカルヴィンや、ジョナサン・エドワーズやデイヴィッド・ブレイナードや、神に仕えた他の幾多の偉大な人々が、同じ問題でどれほど苦しんだかを。
あるいは、この堕落した世にあって、とんでもなく高い道徳基準。
Aは知っている、世界がどんなに堕落しようと、苟も神の基準がそれに迎合するわけにいかないことを。
しかし、我々はどう考えたものだろうか、この世の堕落から抜け出せないながら、尚神の世界の清浄さに憧れる者たちのことを。
もちろんそういう者たちを、神は親切に助けようとするだろう、己れに仕えるにふさわしい者とするために。
しかし、そのままでは、そんな生き方を是認しはしない。彼らは自分の生活から、神の目に悪とみなされる習慣をきっぱりと断ち切るか、あるいは神の要求に応えんとする道徳的努力の方をきっぱりと断ち切るか、いづれにせよどちらかを選ばなければならない。
実際、決断は必要である---全く分断された二つの行動の基準の間を振り子運動し続けるだけでは、どこへ向かっても進んでゆかれない。そして、そのうちに良心がだんだんに鈍らされないとすれば、やめることのできない悪習に対して良心がこれを糾弾し続けるとすれば---そのうち精神分裂症になってしまうのがおちだろう。幸いにしてその良心が鈍感である場合でも、彼は自分の生き方に対して、決して誇りも自尊心も持つことがないだろう。あるいは、よしきっぱりと神を捨てることができたとしても、神の要求に応えきれなかった彼は、この世のあまりの堕落ぶりに対してもまた不慣れで、免疫を持っていないので、またしても適応異常に苦しめられることになるだろう。
いったい神は、これほど弱小な人間に対して、こんなに苛烈な決断を迫っていいものだろうか? 神の威光は、その達しがたい高さは、ここまで人間をおとしめ、弱くさせ、その力を奪っていいものだろうか?
そして、これこそがニーチェをしてキリスト教を痛烈に弾劾せしめたゆえんではなかったか? あるいはシュタイナー---「最悪の神をお前たちは造り出した。それはお前たちに良心を持つことを教えた。」
"The Portage To San Cristobal Of A.H." の中で登場人物のヒトラーは、なぜ「最終的解決」が必要であったかについて、劇的な説明をやってのける。それはキリスト教における罪あるいは良心についてのドグマが、この世界にいかなる精神的害悪をもたらしてきたかに関する、極めて的確な、おそろしいほどに真実な言説である。
・・・There must be a solution, a final solution. For what is the Jew if he is not a long cancer of unrest? I beg your attention, gentleman, I demand it. Was there ever a crueler invention, a contrivance more calculated to harrow human existence, than that of an omnipotent, all-seeing, yet invisible, impalpable, inconceivable God? ・・・ The Jew emptied the world by setting his God apart, immeasurably apart from man's senses. No images. No imagining even. A blank emptier than desert. Yet with a terrible nearness. Spying on our every misdeed, searching out the heart of our heart for motive. ・・・
我々は思い出すのではないだろうか、ニーチェのシニシズムを。小さな女の子が尋ねる、「神様は、いつでもどこでも私たちのことを見てらっしゃるってほんと?」母親が答える、「そうよ」すると女の子は言う、「まあ、何て失礼なんでしょう!」
・・・His God is purer than any other. And because we are his creatures, we must be better than ourselves, love our neighbour, be continent, give of what we have to the beggar. We must obey every jot of the law. We must bottle up our rages and desires, chastise the flesh and walk bent in the rain. You call me a tyrant, an enslaver. What tyranny and what enslavement have been more oppressive than the sick fantasies of the Jew? You are not Godkillers, but Godmakers. And that is infinitely worse. The Jew invented conscience.
But that was only the first piece of the blackmail. There was worse to come. The white-faced Nazarene. Gentlemen, I find it difficult to contain myself. ・・・ What did that epileptic rabbi ask of man? That he renounce the world, that he leave father and mother behind, that he offer the other cheek, that he render good for evil, that he love his neighbour as himself, no, better, for self-love is an evil. Oh, grand castration! Note the cunning of it. Demand of human beings more than they can give, and you will make them cripples, hypocrites, mendicants for salvation. ・・・ What could be than the Jew's addiction to the ideal?
読者は神への愛をめぐるくだりでもこの部分の一節が引用されたことを思い出されるだろう。そう、愛の問題と罪の問題とはつながっている。愛の問題は、いかにして己れの心を規範に服従させるかという問題であったが、罪の問題とは、そもそも己れの心を規範に服従させることが正しいのかどうかという問題だからである。
そして、どちらの問題が先に来るかは、それらを問題とする個人の、キリスト教的な概念との関係いかんによって決まるのである。
すなわち、キリスト教的な概念が彼にとって非常に身近で、それがほとんど〈前提〉とも言えるような個人にとっては、「汝愛すべし」という掟がまず最初にあるので、それゆえ愛の問題の方が先に来る。しかるに、それが彼にとって見慣れない、異質なものであるような個人にとっては、「愛すべし」という命令の正当性をまず納得しないことには愛することの困難に悩みようがないのであるから、当然罪の問題の方が先に来るわけだ。
そしてそれを敷衍して考えるならば、前者がキリスト教文化圏の精神性のあり方であり、後者が非キリスト教文化圏のそれである、と言う事ができる。そしてまたそれが、ヒトラーの論説においてその論法を、各々の論点の配列のされ方を決定している要素でもあるのだ。なぜなら、彼の論法の独特で劇的な点は、きわめてキリスト教的な問題を、全くの異教徒の立場から分析し考察している点にあるからである。実際、自分の目的を遂行するために教会と手を結んだという歴史的事実とは裏腹に、ヒトラーは正真正銘の異教徒だった。彼は側近にこう語っていたという。
「ローマ・カトリックであろうが福音主義教会であろうが、どれもみな同じである。そこには未来はない。ファシズムは神の名にかけて教会と和を結ぶことがあるかもしれない。私もそうするだろう。何故それでいけないのか。そうしたからといってドイツのキリスト教を徹底的に根絶する妨げにはならない。・・・もし私が欲するなら、二、三年のうちに教会を抹殺することもできるのだ」
それゆえ戯曲中のヒトラーがキリスト教についてこんなふうに語るのは歴史的事実にも適っているのである。
・・・To slaughter a city because of an idea, because of a vexation over words. That was a high invention, a device to alter the human soul. Your invention. One Israel, one Volk, one leader. ・・・
彼は神を知らない全異邦人を代表して、神の存在が空気と同じほど自明でない、すべての人間の視点から語っているのである。
こうしてこの戯曲において、シュタイナーは、キリスト教的な世界観と非キリスト教的なそれとの間の決して埋められない深い断絶を、その鋭い亀裂を、忘れられない仕方で鮮やかに描き出しているのである。
* *
あるいは彼らが後生大事に守る、肩が凝りそうに厳格な性道徳。
「凡ての人、婚姻のことを貴べ、また寝床を汚すな。神は淫行のもの、姦淫の者を審き給ふべければなり」(He13:4)
神の規準に適った唯一のセックスとは、ただ結婚関係内のセックスのみであった。それ以外はすべからく排斥の対象となった。
まちがったセックスをしないだけでは十分でなかった。それを心の中で欲することもまた罪だった。それは人を、まちがいなく行動へ駆り立てるからだ。
「すべて色情を懐きて女を見るものは、既に心のうち姦淫したるなり」(Mt5:28) しかし、それでもまだ十分ではなかった。
欲したり考えたりしないためには欲したり考えたりしないような精神性を培う必要があって、そのためには何で自分を養うかということに十分注意しなければならなかった。それゆえ、不道徳を容認あるいは称揚するようなあらゆるメディアはことごとく避けられた---小説、雑誌、映画、テレビ、果ては街頭のポスターや電車の吊り革広告に至るまで。彼らはダビデに倣って祈ったのだ---「わが眼をほかにむけて虚しきことを見ざらしめ 我をなんぢの途にて活かし給へ」(Ps119:37)
さらに彼らは、同じ規準を持たない一般の人々の、悪意のない会話やジョークによっても堕落させられることがないよう、極端につきあいを制限していた。彼らが古代ローマにおける原始キリスト教のように、孤立した共同体を形成せざるを得なかったのも無理はない。時代はもはやヴィクトリア朝ではなく、罪は洪水のように、そこらじゅうに溢れていたからだ。
彼らが結婚を考えて誰かとつき会おうという時には、まちがいがないように細心の注意が払われた---礼儀に適った振る舞い、付き添いつきのデート。部屋や車の中で二人きりになる状況は避けられなくてはならなかった。
これらすべてのことに加えて尚必要とされることがあった---
「エホバを愛しむものよ惡をにくめ」(Ps97:10)
人は悪を避けるだけでなく、悪を憎まなければならなかったのだ。言うまでもなく、そうしなければ本当に悪を避けることはできないからだ。人は、その生き方だけでなく、心そのものが神と調和していなければならなかった。
こういう徳高い人々を見ていてAは、こういう人たちを見てフロイトは抑圧理論を思いついたのだろうなと思ったものだ。
性欲はそれ自体、満たされようとするアプリオリな方向性を持っているのではないか? それを外的要素によって制約しようとする方がまちがっているのではないか? それは反自然的ではないのか?
互いを永続的に縛りつける結婚関係! 考えただけで、息がつまって死にそうだった。Aが子供のときから既に恋愛にも結婚にも興味をなくしてしまったのは、要するにそういう束縛を嫌ったからだった。
Aは一つの規準しか知らなかったし、それによれば、結婚はほとんど神への献身のアナロジーだった。
神から逃れることはできない。しかし、ありがたいことに結婚から逃げ出すことはできたのだ。
* *
行って動物たちと共に住むことができたら。
彼らはあんなにも落ち着き払って、満たされている。
私は立って彼らを眺める、長い長い間。
彼らは自分の境遇にやきもきしたり、泣き言を言ったりしない。
彼らは暗闇の中に目を覚ましたまま横たわって、
自分の罪を嘆いたりしない。
彼らは神への義務だとか言い出して、人をうんざりさせたりしない。
--ウォルト・ホイットマン<ソング・オヴ・マイセルフ>
I think I could turn and live with animals, they're so placid and
self-contained,
I stand and look at them long and long.
They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sin,
They do not make me sick discussing their duty to God.
---W. Whitman, "Song of Myself"
人が自然界と同じように振る舞うのを妨げているもの、そしてAがキリスト教を自分の生き方とするつもりならばまず理解しなければならない、にも拘らず理解できずにいるもの---それは要するに、罪という概念であるように思われた。それゆえ人は現在に留まってはならず、尚一層神の規準にかなう者となるべくたえず努力していかなければならない。
「わが體を打ちたたきて之を服従せしむ。恐らくは他人に宣傳へて自ら棄てらるる事あらん」(1Co9:27)
それはこのような厳しい自己鍛練を必要とする。
戦われ、乗り越えられるべきものは、まず意識されなければならない。ところがAはどうしても神の前に己れの罪を意識することができなかったし、また意識することを欲しなかったのだ。
アダムから受け継いだ罪という概念---それは要するに、一つのイデオロギーなのではないか? しかも何というイデーだろう、ただ存在しているだけで罪を負っているだなんて。人間の尊厳に対する、何という侮辱だろう。どうしてそんなふうに、神の前に人をおとしめようとするのか? なぜそれほど卑屈な人生観を、自虐的な人間観を持たなければならないのか? すべての人は罪を犯しただって? 私がどんな悪いことをしたというのか?
債務の例え。キリスト教における罪という概念について、Aにつくづく考えさせた話の一つ。
「この故に、天國はその家來どもと計算をなさんとする王のごとし。計算を始めしとき、一萬タラントの負債ある家來つれ來られしが、償ひ方なかりしかば、其の主人、この者とその妻子と凡ての所有とを賣りて償ふことを命じたるに、その家來ひれ伏し拝して言ふ 『寛くし給へ、さらば悉く償はん』その家來の主人あはれみて之を解き、その負債を免したり。然るに其の家來いでて、己より百デナリを負ひたる一人の同僚にあひ、之をとらへ、喉を締めて言ふ『負債を償へ』その同僚ひれ伏し、願ひて『寛くし給へ、さらば償はん』と言へど、肯はずして往き、その負債を償ふまで之を獄に入れたり。同僚ども有りし事を見て甚く悲しみ、往きて有りし凡ての事をその主人に告ぐ。ここに主人かれを呼び出して言ふ『惡しき家來よ、なんぢ願ひしによりて、かの負債をことごとく免せり。わが汝を憫みしごとく、汝もまた同僚を憫むべきにあらずや』斯くその主人、怒りて、負債をことごとく償ふまで彼を獄卒に付せり。もし汝等おのおの心より兄弟を赦さずば、我が天の父も亦なんぢらに斯くのごとく爲し給ふべし」
一万タラントは60,000,000デナリである。つまりこの差異は、我々が神に対して負っている罪の大きさと、我々の仲間の人間が我々に対して負っている罪の大きさとの、桁違いな差異を表しているのである。
Aが教えられてきたところによれば、この寓話は神の愛の偉大さを実によく表しているということになっているのだが、Aにはどうもそうではなくて、神に対して人間が余儀なくされている、ひどく不公平で弱い立場を、実によく表しているように思えた。なるほど我々は神に対して一万タラントを負っているかもしれない。しかしそれは我々自身が使い込んだ一万タラントではないのだ。アダムが罪を犯して以来、我々は自らの意志に関係なく、否応なしに罪を負って生まれてくるのであり、言わば我々はみんな、一万タラントの負債と共に生まれてくるのだ。それに対して我々は責任を負っていない。だのにどうして我々はそのためにひれ伏して懇願したり、そのことを許されたりしなくてはならないのか?
あるいは、一タラント与えられてそのまま返した僕。
「また或人とほく旅立せんとして、其の僕どもを呼び、之に己が所有を預くるが如し。各人の能力に應じて、或者には五タラント、或者には二タラント、或者には一タラントを興へ置きて旅立せり。五タラントを受けし者は、直ちに往き、之をはたらかせて他に五タラントを儲け、二タラントを受けし者も同じく他に二タラントを儲く。然るに一タラントを受けし者は、往きて地を堀り、その主人の銀をかくし置けり。久しうして後この僕どもの主人きたりて彼らと計算したるに、五タラントを受けし者は他に五タラントを持ちきたりて言ふ『主よ、なんぢ我に五タラントを預けたりしが、視よ、他に五タラントを儲けたり』主人言ふ『宜いかな、善かつ忠なる僕、なんぢは僅かなる物に忠なりき。我なんぢに多くの物を掌どらせん、汝の主人の歓喜に入れ』二タラントを受けし者も來たりて言ふ『主よ、なんぢ我に二タラントを預けたりしが、視よ、他に二タラントを儲けたり』主人言ふ『宜いかな、善かつ忠なる僕、なんぢは僅かなる物に忠なりき。我なんぢに多くの物を掌どらせん、汝の主人の歓喜に入れ』また一タラントを受けし者もきたりて言ふ『主よ、我はなんぢの嚴しき人にして、播かぬ處より刈り、散さぬ處より斂むることを知るゆえに、懼れてゆき、汝のタラントを地に藏しおけり。視よ、汝はなんぢの物を得たり』主人こたへて言ふ『惡しくかつ惰れる僕、わが播かぬ處より刈り、散さぬ處より斂むることを知るか。さらば我が銀を銀行にあづけ置くべかりしなり、我きたりて利子とともに我が物をうけ取りしものを。されば彼のタラントを取りて十タラントを有てる人に興へよ。すべて有てる人は、興へられて愈々豊ならん。されど有たぬ者は、その有てる物をも取らるべし。而して此の無益なる僕を外の暗黒に逐ひいだせ、其處にて哀哭・切歯することあらん』」---(Mt25:14-30)
彼は託されたものを失ったわけでもないし、主人に仕えるのをやめてしまったわけでもない。それでも叱責され、退けられたのである。
神の前に、生まれてくるすべての人間はこれらの僕のようである---すべての人間は是認を得るために積極的に善をなさねばならず、何もしないことは悪なのである。
あるいは---
「汝等のうち誰か或は耕し、或は牧する僕を有たんに、その僕畑より歸りきたる時、これに對ひて『直ちに來り食に就け』と言ふ者あらんや。反つて『わが夕餐の備をなし、わが飲食するあひだ、帯して給仕せよ、然る後に、なんぢ飲食すべし』と言ふにあらずや。僕、命ぜられし事を為したればとて、主人これに謝すべきか。かくのごとく汝らも命ぜられし事をことごとく為したる時『われらは無益なる僕なり、為すべき事を為したるのみ』と言へ」---(Lu17:7-10)
神の前に、すべての人間はかくのごとく身を持さなければならないのである。 己れを捨て、献身の歩みを全うして尚、我々はこのように言い切れるだろうか?
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
2013年11月30日
創造的な不幸-4-
創造的な不幸-愛・罪・自然、および芸術・宗教・政治についての極論的エッセイ-
この作品について 目次
-4- カナン人について
ついに約束の地に入るイスラエル。
「汝の神エホバ汝が往きて獲べきところの地に汝を導きいり多くの國々の民ヘテ人ギルガシ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人エブス人など汝よりも數多くして力ある七つの民を汝の前より逐ひはらひ給はん時 すなはち汝の神エホバかれらを汝に付して汝にこれを撃たせ給はん時は汝かれらをことごとく滅ぼすべし彼らと何の契約をもなすべからず彼らを憫れむべからず」
「汝心に言ふなかれ云く我の義きがためにエホバ我をこの地に導きいりてこれを獲させ給へりと そはこの國々の民の惡しきがためにエホバ之を汝の前より逐ひはらひ給ふなり 汝の往きてその地を獲るは汝の義しきによるにあらず又汝の心の直きによるに非ず この國々の民の惡しきが故にエホバ之を汝の前より逐ひはらひ給ふなり」---De7:1,2,9:4
かくして大殺戮が始まり、血が流され、火が放たれ、死体の山はうずたかく積み上げられるのである。
「邑にある者は男女少きもの老いたるものの區別なく盡くこれを刃にかけて滅ぼし且牛羊驢馬にまで及ぼせり」
「ヨシュアかの日マッケダを取り刃をもて之とその王とを撃ち之とその中なる一切の人をことごとく滅ぼして一人をも遺さず」
「かれとその民とを撃ちころして終に一人をも遺さざりき」
「刃をもてその中なる一切の人を撃ちてことごとく之を滅ぼし氣息する者は一人だに遺さざりき」・・・ ---Jos6-11
こうした記述を前に、人は嫌悪の念をもって立ちどまらずにはいられない。彼らはなぜこれほどまでに殺されなければならなかったのか。彼らが生き延びる手だては本当になかったのか?
これが単なる人間による虐殺だったら、そのために我々はわざわざ立ちどまったりしない。結局のところ我々の歴史はその種のおぞましい記録で満ちているからだ。
カナンの虐殺が特別に問題となるのは、それが全能の神の命令によって遂行されたという事実、まさにその事実によるのである。
そしてこの疑問から、いまや永久に失われてしまった彼らの生活、彼らの文化、彼らの精神性を知ろうとする、切実な探究が始まるのである。
* *
考古学的考察。
「カナン人は自分たちの神々の前で宗教儀式としての不道徳な行為にふけることにより、またその後、自分たちの長子をそれら同じ神々への犠牲として殺害することにより礼拝を行った。カナンの地は大方、国家的規模でソドムやゴモラのようになっていたようである。・・・そのような忌まわしい汚れや残虐行為を事とする文明に、それ以上存続する権利があったであろうか。・・・カナン人の諸都市の遺跡を発掘する考古学者は、神がなぜもっと早く彼らを滅ぼさなかったのだろうかと不思議に思うほどである」---「ハーレイの聖書ハンドブック」1964
しかし、レヴィ・ストロース以後の我々は、あらゆる文化をその文化自身の視点から眺めることを学んだのではなかったか?
例えば、石の祭壇の上で生贄の心臓をえぐりだし、まだぴくぴく動いているそれを太陽に捧げる古代アステカ人。我々はそれを見て考えるかもしれない、彼らは理性のない、残虐で野蛮な民であった、と。しかし、彼らの哲学からすれば、自分たちが偉大な自然のサイクルの中で生き、そこからすべてを与えられて生活している以上、自分たちの方でも何らかの犠牲を払うのは当然のことであり、それどころか、それはサイクルが円滑に回ってゆくために必要不可欠な要素だったのである。したがって問題となってくるのは文化の違いであり、視点の違いである。
彼らの精神性のあり方をたどるのは容易なことではない。大体文書としての記録が残っていないからだ。それは鉄のカーテンの向こう側の全体像をつかむのと同じくらい困難である---そして、それは実際には不可能だろう。我々にできるのはただ、探究し、類推し、想像することのみである。
イスラエルがカナンに入ってきたときの彼らのようすは、イスラエル側の記録によって次のように描写されている。
「ヨルダンの彼方に居るアモリびとの諸の王および海邊に居るカナン人の諸の王はエホバ、ヨルダンの水をイスラエルの人々の前に乾し涸らして我らを濟ひしと聞きイスラエルの人々の事によりて神魂消え心も心ならざりき」Jos5:1
征服が大方完了した時点での結論としては次のように記されている。
「そもそも彼らが心を剛愎にしてイスラエルに攻めよせしはエホバの然らしめ給ひし者なり 彼らは詛はれし者となり憐憫を乞うことをせず滅ぼされんがためなりき 是全くエホバのモーセに命じ給ひしが如し」---Jos11:20
しかしこの二つの言葉は、遺憾ながら矛盾すると言わなくてはならない。もしも本当に失意のどん底にあったのなら、そもそも強情を張る気力もなかったはずだし、もしも彼らが強情だったなら、そこには彼らの強情さを支える何らかの矜持が存在したはずだからでる。
彼らのうち、イスラエルの斥候をかくまって命の保証をとりつけたエリコのラハブと、イスラエルに取り入って契約を結んだギベオンのヒビ人以外は、誰もイスラエルと和を結ぼうとしなかった。彼らは一致団結してイスラエルを迎え撃ちに出た。
「ここにヨルダンの彼方において山地平地レバノンの對へる大海の浜辺に居る諸の王すなはちヘテ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人エブス人たる者どもこれを聞きて 心を同じうし相集まりてヨシュアおよびイスラエルと戦わんとす」---Jos9:1
なんと愚かだったのだろうか彼らは、相手には何せ神の後ろ楯があるのだからどうあがいたって勝てるはずがないではないか、なぜ彼らは降伏して生き延びようとしなかったのかと、我々は考えるだろうか?
実際のところ、彼らには彼らの生活があり、文化があり、歴史的必然性があったはずだ。今の今まで人生はかくのごとく続いてきたのだし、これからだってかくのごとく続いていくはずだった。それが突然、お前たちの土地は四百年前に神がアブラハムに与えると約束したものだから明け渡さなければならないと告げられて、いったい誰がおとなしく引き下がるだろうか。
彼らの大部分が最後の最後まで現実を見ようとせず、無駄な抵抗を続けたのは全く当然のことと言わなければならない。彼らにしてみれば、イスラエルの理屈のほうが明らかに間違っていたのだ。そして彼らには、自分たちの慣れ親しんだ思想や生きかたを捨てる気は全然なかった。ラハブやギベオン人は希有な例外であった。あれだけの謙遜さを示すのはそうそう容易なことではない。大方のカナン人の目には、彼らはむしろ卑屈と映ったことであろう。彼らは全く国賊であると考えられたに違いない。実際、エルサレムの王はギベオンの裏切りを知ると他の四つの都市と連合してこれに対して陣営を敷く。そして、結局は助太刀に来たイスラエルに敗れ、屈辱的な仕方で処刑されるのである。
ここで考えなくてはならないのは、全く当然のことながら、彼らがかくの如き歴史的、文化的、民族的背景のもとに生まれ落ちたのは彼ら自身の責任ではない、という点である。それは彼らにとって、アプリオリに存在した外的状況であった。それでも尚、この外的状況は、彼らが神から裁かれるにあたって、その裁きを左右したほどの、極めて大きな要素となったのである。
このことから次の問題が生じてくるのである。すなわち---個人は外的状況によってどの程度決定されるのか? そしてそれはまた、言い換えればこういうことである---個人は自分の思想・人格・生き方に関してどの程度責任を負うのか?
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません
この作品について 目次
-4- カナン人について
ついに約束の地に入るイスラエル。
「汝の神エホバ汝が往きて獲べきところの地に汝を導きいり多くの國々の民ヘテ人ギルガシ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人エブス人など汝よりも數多くして力ある七つの民を汝の前より逐ひはらひ給はん時 すなはち汝の神エホバかれらを汝に付して汝にこれを撃たせ給はん時は汝かれらをことごとく滅ぼすべし彼らと何の契約をもなすべからず彼らを憫れむべからず」
「汝心に言ふなかれ云く我の義きがためにエホバ我をこの地に導きいりてこれを獲させ給へりと そはこの國々の民の惡しきがためにエホバ之を汝の前より逐ひはらひ給ふなり 汝の往きてその地を獲るは汝の義しきによるにあらず又汝の心の直きによるに非ず この國々の民の惡しきが故にエホバ之を汝の前より逐ひはらひ給ふなり」---De7:1,2,9:4
かくして大殺戮が始まり、血が流され、火が放たれ、死体の山はうずたかく積み上げられるのである。
「邑にある者は男女少きもの老いたるものの區別なく盡くこれを刃にかけて滅ぼし且牛羊驢馬にまで及ぼせり」
「ヨシュアかの日マッケダを取り刃をもて之とその王とを撃ち之とその中なる一切の人をことごとく滅ぼして一人をも遺さず」
「かれとその民とを撃ちころして終に一人をも遺さざりき」
「刃をもてその中なる一切の人を撃ちてことごとく之を滅ぼし氣息する者は一人だに遺さざりき」・・・ ---Jos6-11
こうした記述を前に、人は嫌悪の念をもって立ちどまらずにはいられない。彼らはなぜこれほどまでに殺されなければならなかったのか。彼らが生き延びる手だては本当になかったのか?
これが単なる人間による虐殺だったら、そのために我々はわざわざ立ちどまったりしない。結局のところ我々の歴史はその種のおぞましい記録で満ちているからだ。
カナンの虐殺が特別に問題となるのは、それが全能の神の命令によって遂行されたという事実、まさにその事実によるのである。
そしてこの疑問から、いまや永久に失われてしまった彼らの生活、彼らの文化、彼らの精神性を知ろうとする、切実な探究が始まるのである。
* *
考古学的考察。
「カナン人は自分たちの神々の前で宗教儀式としての不道徳な行為にふけることにより、またその後、自分たちの長子をそれら同じ神々への犠牲として殺害することにより礼拝を行った。カナンの地は大方、国家的規模でソドムやゴモラのようになっていたようである。・・・そのような忌まわしい汚れや残虐行為を事とする文明に、それ以上存続する権利があったであろうか。・・・カナン人の諸都市の遺跡を発掘する考古学者は、神がなぜもっと早く彼らを滅ぼさなかったのだろうかと不思議に思うほどである」---「ハーレイの聖書ハンドブック」1964
しかし、レヴィ・ストロース以後の我々は、あらゆる文化をその文化自身の視点から眺めることを学んだのではなかったか?
例えば、石の祭壇の上で生贄の心臓をえぐりだし、まだぴくぴく動いているそれを太陽に捧げる古代アステカ人。我々はそれを見て考えるかもしれない、彼らは理性のない、残虐で野蛮な民であった、と。しかし、彼らの哲学からすれば、自分たちが偉大な自然のサイクルの中で生き、そこからすべてを与えられて生活している以上、自分たちの方でも何らかの犠牲を払うのは当然のことであり、それどころか、それはサイクルが円滑に回ってゆくために必要不可欠な要素だったのである。したがって問題となってくるのは文化の違いであり、視点の違いである。
彼らの精神性のあり方をたどるのは容易なことではない。大体文書としての記録が残っていないからだ。それは鉄のカーテンの向こう側の全体像をつかむのと同じくらい困難である---そして、それは実際には不可能だろう。我々にできるのはただ、探究し、類推し、想像することのみである。
イスラエルがカナンに入ってきたときの彼らのようすは、イスラエル側の記録によって次のように描写されている。
「ヨルダンの彼方に居るアモリびとの諸の王および海邊に居るカナン人の諸の王はエホバ、ヨルダンの水をイスラエルの人々の前に乾し涸らして我らを濟ひしと聞きイスラエルの人々の事によりて神魂消え心も心ならざりき」Jos5:1
征服が大方完了した時点での結論としては次のように記されている。
「そもそも彼らが心を剛愎にしてイスラエルに攻めよせしはエホバの然らしめ給ひし者なり 彼らは詛はれし者となり憐憫を乞うことをせず滅ぼされんがためなりき 是全くエホバのモーセに命じ給ひしが如し」---Jos11:20
しかしこの二つの言葉は、遺憾ながら矛盾すると言わなくてはならない。もしも本当に失意のどん底にあったのなら、そもそも強情を張る気力もなかったはずだし、もしも彼らが強情だったなら、そこには彼らの強情さを支える何らかの矜持が存在したはずだからでる。
彼らのうち、イスラエルの斥候をかくまって命の保証をとりつけたエリコのラハブと、イスラエルに取り入って契約を結んだギベオンのヒビ人以外は、誰もイスラエルと和を結ぼうとしなかった。彼らは一致団結してイスラエルを迎え撃ちに出た。
「ここにヨルダンの彼方において山地平地レバノンの對へる大海の浜辺に居る諸の王すなはちヘテ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人エブス人たる者どもこれを聞きて 心を同じうし相集まりてヨシュアおよびイスラエルと戦わんとす」---Jos9:1
なんと愚かだったのだろうか彼らは、相手には何せ神の後ろ楯があるのだからどうあがいたって勝てるはずがないではないか、なぜ彼らは降伏して生き延びようとしなかったのかと、我々は考えるだろうか?
実際のところ、彼らには彼らの生活があり、文化があり、歴史的必然性があったはずだ。今の今まで人生はかくのごとく続いてきたのだし、これからだってかくのごとく続いていくはずだった。それが突然、お前たちの土地は四百年前に神がアブラハムに与えると約束したものだから明け渡さなければならないと告げられて、いったい誰がおとなしく引き下がるだろうか。
彼らの大部分が最後の最後まで現実を見ようとせず、無駄な抵抗を続けたのは全く当然のことと言わなければならない。彼らにしてみれば、イスラエルの理屈のほうが明らかに間違っていたのだ。そして彼らには、自分たちの慣れ親しんだ思想や生きかたを捨てる気は全然なかった。ラハブやギベオン人は希有な例外であった。あれだけの謙遜さを示すのはそうそう容易なことではない。大方のカナン人の目には、彼らはむしろ卑屈と映ったことであろう。彼らは全く国賊であると考えられたに違いない。実際、エルサレムの王はギベオンの裏切りを知ると他の四つの都市と連合してこれに対して陣営を敷く。そして、結局は助太刀に来たイスラエルに敗れ、屈辱的な仕方で処刑されるのである。
ここで考えなくてはならないのは、全く当然のことながら、彼らがかくの如き歴史的、文化的、民族的背景のもとに生まれ落ちたのは彼ら自身の責任ではない、という点である。それは彼らにとって、アプリオリに存在した外的状況であった。それでも尚、この外的状況は、彼らが神から裁かれるにあたって、その裁きを左右したほどの、極めて大きな要素となったのである。
このことから次の問題が生じてくるのである。すなわち---個人は外的状況によってどの程度決定されるのか? そしてそれはまた、言い換えればこういうことである---個人は自分の思想・人格・生き方に関してどの程度責任を負うのか?
次章へ
目次へ戻る
下の広告はブログ運営サイドによるもので、中島迂生とは関係ありません