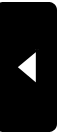2008年10月29日
季節は過ぎて
昨日こそ早苗とりしかいつのまに稲穂そよぎて秋風の吹く
うわっ、和歌をヨコ書きにすると気持ち悪いものですなぁ。
って、もうとっくに稲刈り終わってるし。
それはいいとして、先々週くらいに、東北のご実家に行ってらしたという団員の方。
今頃は景色きれいだったでしょうね、と言うと、「ええ、それはもう。新幹線の窓から見ると、色づいた田んぼが一面のまっ黄色で、ぴかぴか光って、まるで菜の花畑みたい。・・・稲ってこんなにきれいなものかと思ったわ。こちらに戻ってきたら・・・なんか、現実に引き戻されたという感じでね。」
いいなぁ、東北。実はまだ行ったことありません。
そのうち花巻とか、そっちの方、行きたいなぁ。
とくに今年は春あたりから忙しく飛び回りすぎて、あまり季節感を感じてない・・・目には入るのだけれど、立ちどまってゆっくり向きあっていない。
すごく忙しい人でも、短い時間を有効に使って小旅行など楽しんでいる人もいるのだから、自分の場合、それは時間の使い方がへたなせいも大いにあるけど。
たぶんおもに、自分のいま入ってるモードの問題。
劇団を立ち上げてからというもの、ひたすら人集めと脚本書きと、その周辺のことだけに打ちこみつづけて、気がついたら、うわっ、もう秋だったのか!という感じ。
まさに、昨日こそ早苗とりしか・・・。
最近、歩くと落ち葉の独特な匂いがして、ようやく、あー、秋も深まったなぁ、と身にしみて感じます。
さいしょに何かの作品にとりかかるときには、その背景となる自然を身近にしっかり観察して書きこむということがぜったいに必要なのだけれど、じっさいつくる方にかかりきってディテールをつくりこむ作業に入ると、もうまわりは目に入らなくなる。
というか、季節の方が先にどんどん行ってしまう。
季節の移り変わりは緩慢なようでいて、実はものすごく速い。ほとんど一日ごとにたえず表情を変えてゆく。だから、逆に、外を歩き回っていちいち観察しているともうそれだけで終わってしまい、自分で何か書いているひまも、つくり出しているひまもほとんどない。
ミレーの<オフィーリア>には、はじめ水仙の花が描きこんであった。
それを、「その季節には水仙はもう終わってるだろっ」と誰かに突っこまれて・・・ラスキンだったかな、それで、写実主義を重んじるミレーは水仙を消した、という話を聞いたことがあります。
あのものすごく細かくて写実的な背景ゆえ、植物学の先生が学生を連れて来てこの絵の前で講義をした、という話があるくらいだ。
リアリズムの極致。
けれど、じっさいは、あの背景というのは野外にイーゼルを立てて、7月から11月にわたって描かれたため、それでもほんとだったらぜったい同じ季節には咲かないような花どうしが平気で描きこまれたりしているらしい。
描くのには、時間がかかるものね。
描いてるうち、当の花たちは待ちくたびれて枯れていってしまい、また別の種類の花が咲き出す。
すると、そっちの美しさも捨てておけず、また描きこむことになる、するとまたそこで時間を食って・・・。
そういうところ、観察することと表現することの永遠のパラドックスがよくあらわれていて何だか親しみを覚えます。
写実に忠実なようでいてどこかマヌケというか、写実主義などけっとばすくらいの、植物に対する愚直でひたむきな愛着が感じられて。
とりあえず不器用な自分は。
初演までは野外に触れることは疎かにしても、とにかく走りつづけるしかないのでしょう。
うわっ、和歌をヨコ書きにすると気持ち悪いものですなぁ。
って、もうとっくに稲刈り終わってるし。
それはいいとして、先々週くらいに、東北のご実家に行ってらしたという団員の方。
今頃は景色きれいだったでしょうね、と言うと、「ええ、それはもう。新幹線の窓から見ると、色づいた田んぼが一面のまっ黄色で、ぴかぴか光って、まるで菜の花畑みたい。・・・稲ってこんなにきれいなものかと思ったわ。こちらに戻ってきたら・・・なんか、現実に引き戻されたという感じでね。」
いいなぁ、東北。実はまだ行ったことありません。
そのうち花巻とか、そっちの方、行きたいなぁ。
とくに今年は春あたりから忙しく飛び回りすぎて、あまり季節感を感じてない・・・目には入るのだけれど、立ちどまってゆっくり向きあっていない。
すごく忙しい人でも、短い時間を有効に使って小旅行など楽しんでいる人もいるのだから、自分の場合、それは時間の使い方がへたなせいも大いにあるけど。
たぶんおもに、自分のいま入ってるモードの問題。
劇団を立ち上げてからというもの、ひたすら人集めと脚本書きと、その周辺のことだけに打ちこみつづけて、気がついたら、うわっ、もう秋だったのか!という感じ。
まさに、昨日こそ早苗とりしか・・・。
最近、歩くと落ち葉の独特な匂いがして、ようやく、あー、秋も深まったなぁ、と身にしみて感じます。
さいしょに何かの作品にとりかかるときには、その背景となる自然を身近にしっかり観察して書きこむということがぜったいに必要なのだけれど、じっさいつくる方にかかりきってディテールをつくりこむ作業に入ると、もうまわりは目に入らなくなる。
というか、季節の方が先にどんどん行ってしまう。
季節の移り変わりは緩慢なようでいて、実はものすごく速い。ほとんど一日ごとにたえず表情を変えてゆく。だから、逆に、外を歩き回っていちいち観察しているともうそれだけで終わってしまい、自分で何か書いているひまも、つくり出しているひまもほとんどない。
ミレーの<オフィーリア>には、はじめ水仙の花が描きこんであった。
それを、「その季節には水仙はもう終わってるだろっ」と誰かに突っこまれて・・・ラスキンだったかな、それで、写実主義を重んじるミレーは水仙を消した、という話を聞いたことがあります。
あのものすごく細かくて写実的な背景ゆえ、植物学の先生が学生を連れて来てこの絵の前で講義をした、という話があるくらいだ。
リアリズムの極致。
けれど、じっさいは、あの背景というのは野外にイーゼルを立てて、7月から11月にわたって描かれたため、それでもほんとだったらぜったい同じ季節には咲かないような花どうしが平気で描きこまれたりしているらしい。
描くのには、時間がかかるものね。
描いてるうち、当の花たちは待ちくたびれて枯れていってしまい、また別の種類の花が咲き出す。
すると、そっちの美しさも捨てておけず、また描きこむことになる、するとまたそこで時間を食って・・・。
そういうところ、観察することと表現することの永遠のパラドックスがよくあらわれていて何だか親しみを覚えます。
写実に忠実なようでいてどこかマヌケというか、写実主義などけっとばすくらいの、植物に対する愚直でひたむきな愛着が感じられて。
とりあえず不器用な自分は。
初演までは野外に触れることは疎かにしても、とにかく走りつづけるしかないのでしょう。
2008年10月06日
オフィーリア随想
ジョン・エヴァレット・ミレーの<オフィーリア>。
劇団を立ち上げて<視覚的な美>を追求してゆこうと思い至ったとき、ラファエル前派は私にとって大きな存在だった。とくにこの<オフィーリア>は。昔から、美の極致、美の具現だと思っていた。
この絵のことを「こわっ」とか「ぞっとする」とか言う人がいるけれど(漱石も「不愉快だ」と書いている)、そういうのが私にはよく分からない。というか、そういう要素が・・・ある種の凄み、底知れなさというものが、美しいということのなかには当然含まれるものだし、まったく毒気がなかったら、それはほんとうには美とはいえないだろう。
でも一方で、それはすごく分かりやすい美しさでもあり、万人にアピールするところをもっている。
とらえがたい底知れなさと、人口に膾炙する分かりやすさと、その両方を兼ね備えているもの。時代を超えて生き残っていくのは、常にそういうものだ。
ダ・ヴィンチの絵にしてもそう。ショパンやベートーベンにしてもそう。
そういうものを生み出せるのが、真の偉大さなのだと思う。
*
絵は実物を見なきゃダメだというひとがいる。私は必ずしもそうは思わない。
ひとりで、しかも自分のペースで静かに対するということが、作品を味わううえでは大切だと思う。
画集やカタログの写真だってけっこうイデーは伝わってくるものだし、人がわさわさいるなかで遠くから慌ただしく本物を見るより、ひとりしずかに画集ででも眺める方が、ゆっくりその絵と対話できるのではないだろうか。
同じ理由で、私はどちらをとるかと言われたら、映画だったら大画面で映画館で見るより、家でビデオかDVDを、場面によっては一時停止して少し考え事をしたり、いくどか巻き戻したりしながら見る方が好きだし、音楽だったらコンサートに行って豆粒みたいな実物を見るより、ライヴ映像を何度も繰り返し反芻しながら見る方が好きだ。
そう、本を読むように、味わうのが好き。
*
そういったこともあって、東京に来ていると知っても、すぐに見に行こうとは思わなかった。
作品を味わうには、どういう状況で味わうかというのも大切。環境、背景というものはどんな場合にも重要だ。
いちばん最高の味わい方は、それが生み出されたその土地で味わうということ。
芸術だって地産地消なのだ。
子供のころから愛してやまない、Philippa Pearce の Minnow on the Say を、それが書かれた、ケンブリッジにほど近い小さな村にひと夏過ごして読んだことがある。
あれは最高の経験だった。ほんとに・・・自分の内側と外側、心のなかに抱く世界と、じっさい目に触れる景色、吸いこむ空気、頬にふれる風がつながっている感じ・・・すべてがしっくりとひとつに調和している感覚、夢のように幸福な日々だった。
エセックスの、中世に建てられた、木ずりと漆喰の古い建物に滞在していたことがある。その町全体が、古い建物の多い、中世の香りを濃厚に残した町だった。
寝室の壁に、緑色を基調とした、水車小屋を描いた美しい絵がかかっていて、その部屋の雰囲気に、また窓から見える外の景色などにも実によくあっていた。誰の絵だろう、ずっと気になって、ほかに誰もいないとき、こっそり絵を裏返して見てみた。そうしたら、なんとびっくり、コンスタブルだった。私が知らなかっただけで、すごく有名な絵のようだった。びっくりしたのは、自分のその前の滞在先が、コンスタブルがずっと住んでいたところで、その関係の書物なども買い求めていたからだ。
そのときつくづくと感じられたのは、・・・ここがこんな建物だからこそ、こんな町だからこそ、壁に掛けられたコンスタブルの絵がこんなにも映えるのだ、ということだった。それが描かれたのと同じ世界のつづきなのだ。だから、絵が生きている・・・まわりの空気を吸って、呼吸している。・・・そしてまた、それを見る私もまたその空気を吸って、呼吸して、その同じ世界のなかでこの絵を見ている・・・
極言すれば、こんなふうな状態でなければ、我々はほんとうには見ることもできないし、味わうこともできないだろう。
*
だから・・・オフィーリアだってそうだろう、東京の人ごみのなかでは所在なかろう。じっさいそれを見るまでに、どんな景色の中を通っていくか、ということだって大切なのだ。
やはり野に置け、せめてそれが描かれた国で、見るべきなのではないかな。
だから見るならこんどイギリスに行ったとき、テートまで足を延ばして・・・と、そんなふうに考えていたのだった。
けれど、一方ではまた分かっていた・・・じっさいイギリスに行ったら、ミュージアムになんか行かないだろう。雲の流れゆくにつれ、風の吹きすぎるにつれて刻々と表情の変わる生きた絵を見に、さっさと田舎へ逃げ出してしまうだろう。
せっかく東京まで、来てくれたことだし。これはやっぱり、見に行かないと悪いかも。
そんなわけで、見に行った。
*
じっさい行ってみると、さいしょの印象は、「あんがい小さいな」と。
そういうことって、よくあることなのだけれど。
自分のなかですごく大きな存在となってきたから、実物ももっと大きいものだと思いこんでいた。
でも、ここで大切なのは、忘れないこと・・・じっさいの大きさより、自分の心のなかの大きさの方がほんとうなのだと。
そういうことって、よくあった。
グリーン・ノウだって、トムズ・ミッドナイト・ガーデンのお屋敷だって、じっさいのモデルより、それが描かれた本の中のすがたの方がぜんぜん大きい。
じっさい行ってみると拍子抜けする。
それをさいしょに読んだ時の自分がとても小さかった、というのは確かだけれど、それだけの問題ではない。
それをモデルに書いた作者自身が、自分の大切にする色んなものをそこにありったけ詰めこんで膨らませて描いているから、物語作品になった時点ですでに実物よりはるかに大きいのだ。そして、世界中が愛し、讃えてきたのはそちらの方なのだ。
作者の心のなかに映ったそのイマージュこそが、私を含め、世界中の読者の心のなかで真実となってきたのであり、それこそが尽きせぬ夢とゆたかな滋養を与えてくれてきた。
だから、じっさいの大きさなんてそう大した問題ではない。重要なのはいつだって、それが私の心のなかで、どれだけの大きさであるか。
*
ただ、今回の展示は・・・照明がかなり暗いし、絵と手前の柵との幅を、ほかの絵の場合の3倍くらい広くとってある。だからあんまり細部までつくづくと見えないのだ。
以前にテレビ番組でこの絵を、明るい光の下で細部まで拡大して見せてくれたことがあるのだけれど、正直、そっちの方がありがたかったな、と思ってしまった。
それでも改めて、その緻密な背景描写には感じ入ったし、右端にパープル・ルースストライフが、左端にロビンが描かれているのにもはじめて気がついた。(けど、それももっともなことだった・・・世に出回っている大方のプリントでは、こんな端の方まで印刷されていないのだもの。)
*
すごく興味深かったのは、下絵のデッサン。完成された油絵の方とはかなり違う。
モデルの顔はもっと悲劇的な表情をして、髪はぐねぐねと波打って顔のまわりに広がっているし、たっぷりとしたドレスには小花が散っている。
このイメージは、明らかにボッティチェルリだ。
ところが、完成した絵の方では、人物は異様に緻密な背景のみどりの中に溶けこんで、その表情はほとんど無表情なまでにぐっと抑えられ、髪のうねりも影をひそめて、一様に静謐な表現に変わっている。
それは、イタリア・ルネッサンスの明るく開放的な動的なイメージ、あの降り注ぐ光の世界を、内気で控えめなイングランドに持ちこむ過程でのしぜんな変化でもあったのだろう。たぶん感情的な部分をあえてそうやって抑えたことで、なおいっそう心に訴えかける作品となっている。
*
会場内で、この絵を説明する短い番組が流されていたが、そのなかでテートの学芸員の女性がこんなふうなことを語っていた。
この絵のオフィーリアの、両腕を広げた格好は、伝統的な殉教のポーズであるとともに、その顔の表情は性的でもある。だからここには、死とセックスという相反する要素が同時に表現されているのだ、と。
まあ、分かりやすい説明だし、それも一理あるだろう。でも、そのふたつってそんなに相反する要素だろうか? 感情の極みという点では似たようなものだろう。
私の見る限り、それは両義的というよりはむしろ無表情だ・・・というか中間表情なのだ。
じっと見つめているうちに、私ははっと思いあたる。
これは<泥眼>の表情だ。
<泥眼>(でいがん)は、能の小面のヴァリエーションで、白眼の部分に金泥を塗ったもの、狂女物などに用いられる。
静かなる狂気。
激しい感情の極みにあっては、かえって感情表現は消えてしまい、表情は失われる。世阿弥はそのことを知っていたから、面をつけて舞う能に<狂物>(くるいもの)というジャンルを切り拓いたのだ。
ミレーも下絵をカンヴァスにうつしてゆく過程で、あるいはそのことに気づいていったのではあるまいか。
もしかしたら、モデルのエリザベス・シダルから何か示唆を受けるところもあったのかもしれない。
レオス・カラックスの<ポーラX>。
これはハーマン・メルヴィルの<ピエール、もしくは曖昧性>を映画化したものなのだけれど、そのなかで、主人公の姉役を演じているカテリーナ・ゴルベワという女優がこんなことを言っていた。
映画の終盤で、交通事故にあった主人公のもとへ駆けつけ、警官たちの制止を押し切って狂ったようにそばへ近づこうとする場面、彼女は意図的に無表情に演じたのだという。
悲しみの感情がとても強いので、かえって顔には表れない。彼女はそういう演技をするうえで、日本の能を参考にしたと語っていた。
再び、静かなる狂気。
あの映画は、それほど成功はしなかったのかもしれないが、カラックスの復帰作ということで話題になっていたし、私自身ちょうどメルヴィルのことを論文で書いてたときだったからなかなか感慨深いものがあった。
それにしても国際色豊かだなぁ。メルヴィルは19世紀のアメリカ人だし、カラックスはフランス、ゴルベワはたぶんロシア人。
時代も国境も関係ない。ひとの感情は普遍だし、価値あるものを、評価する人はしているのだ。
オフィーリアの顔をじっと見ていると、私の心には<花筐>(はながたみ)の舞姿が浮かんでくる。<花筐>のシテの照日の前(てるひのまえ)も同じような物語を生きている。このシテにはたぶん、泥眼はつかわないのだろうけど。
日本画の上村松園が、能のこの演目を題材にして描いた絵は有名だ。片手に花籠をもち、狂乱の態で都へ向かおうとする照日の前。
絵のなかの彼女は素面だが、やはり取り憑かれたような異様な無表情。松園もまた、意図的にもともとの能面の感じを投影して描いているのだ。
ミレーと並び称されるラファエロ前派の名匠に、ジョン・ウォーターハウスがいて、彼もまた彼のオフィーリアを描いている。
その構図がまた、松園の花筐の絵にそっくりなのだ。
狂乱の態、立ち姿、手に花をもっているところまで似ている。彼のオフィーリアは川に落ちる直前の姿だ。
私はこの絵を、絵はがきで知っているだけだ。
ハムステッド・ヒースに程近いゴルダーズ・グリーンの駅のそば、フランス人の女性アーティストがやっているとてもおしゃれで居心地のいいカフェがあって、この町に滞在していたとき何度か行っていた。絵から、食器から、アンティーク家具から、この女性の目に適ったものがインテリアを兼ねていろいろ売られていた。
そのなかで、一枚のポストカードが目を引いたのだった。映画の一場面のような美しい絵。川岸に、手に花を持ち、青いドレスを着て佇む若い女。だが、その目だけが異様だった。その目は狂気の目だった。
買い求めてからはじめて裏返して見て、それがウォーターハウスの<オフィーリア>だったことを知った。それで、あんな眼をしていることにも合点がいったのだった。
かくて<静かなる狂気>の系譜は、あちらこちらでしずかにつながっている。・・・
*
ミレーの<オフィーリア>の濃密なドラマ性は、背景の息詰まるようなこまかい自然描写によるところが大きい。実はこの絵は、背景を先に描いたのだという。
「忠実な自然描写を心がけていたミレイは、<オフィーリア>の背景にふさわしい風景を求め、1851年7月から11月にかけて、ロンドンの南西、サリー州のユーウェルという町に滞在し、ホッグズミル川沿いで朝から日没まで絵筆をとって緻密に写生した。写生時期は数ヶ月にも及んだため、画面の中には異なる季節の花も混在している。」
(Bukamura ザ・ミュージアム ジョン・エヴァレット・ミレイ展作品リスト裏の解説文より。)
そのあとで人物を描きこんだために、人物の方がその背景に調和するように調整された、という部分ももちろんあるだろう。
はじめて実物を、つくづくと見たとき、なんかこの人の絵の描き方って、自分の文章の書き方に似てるな、と思った。
背景の方を先に描いたというこの逸話を知り、ますます親しみがわく。
私も文章を書くとき、背景の自然描写のディテールをすごく大切にする。物語のプロットに入る前に、舞台となるその土地の描写をながながと書き連ねる。それで飽きたりうんざりする人も多いだろうと分かってはいるけれど、自分としてはどうしてもここに持ってくる必要があるのだ。その土地からこそその物語は生まれてきたのだし、だからその土地で私が見聞きしたものを記しておきたい、読者とも共有したい。
その土地、その風土、背景というものは、それだけでひとつの世界だ。
そこに人物とか物語がなくても。
無限のドラマを、あらたにいくらでも生み出せる宇宙スープのようなもの。
人物のほうが、「ついでにあるもの」なのだ。別になくてもいい。
だから、ほんとは<背景>って名前が悪い。
ほんとは<背景>なんかじゃなく、<母胎>とか<源>とか呼ぶべきものなのだ。
パリ近郊に出かけて、「印象派の絵そのままの風景、光」とか形容する人がよくいるけど・・・逆だろうそれは。そういう風景が、光があったから、それで印象派の絵が生まれてきたのだ。
絵でも文学作品でも何でも、それを生み出した土地のなかに身をおいてはじめて分かることがある。そういうすばらしいものがなぜ生まれえたのか、それを生み出すのにどういうものが必要だったのか。
人がアートを生み出すのじゃない。人は、与えられるのでなければ何ひとつ生み出せはしない。
メルヴィル。「土地が人間をつくるのだ」<マーディ>。
ゆえに、我々はそれを敷衍してこのように言えるはずだと思う。
「土地がアートを生み出すのだ」と。・・・
劇団を立ち上げて<視覚的な美>を追求してゆこうと思い至ったとき、ラファエル前派は私にとって大きな存在だった。とくにこの<オフィーリア>は。昔から、美の極致、美の具現だと思っていた。
この絵のことを「こわっ」とか「ぞっとする」とか言う人がいるけれど(漱石も「不愉快だ」と書いている)、そういうのが私にはよく分からない。というか、そういう要素が・・・ある種の凄み、底知れなさというものが、美しいということのなかには当然含まれるものだし、まったく毒気がなかったら、それはほんとうには美とはいえないだろう。
でも一方で、それはすごく分かりやすい美しさでもあり、万人にアピールするところをもっている。
とらえがたい底知れなさと、人口に膾炙する分かりやすさと、その両方を兼ね備えているもの。時代を超えて生き残っていくのは、常にそういうものだ。
ダ・ヴィンチの絵にしてもそう。ショパンやベートーベンにしてもそう。
そういうものを生み出せるのが、真の偉大さなのだと思う。
*
絵は実物を見なきゃダメだというひとがいる。私は必ずしもそうは思わない。
ひとりで、しかも自分のペースで静かに対するということが、作品を味わううえでは大切だと思う。
画集やカタログの写真だってけっこうイデーは伝わってくるものだし、人がわさわさいるなかで遠くから慌ただしく本物を見るより、ひとりしずかに画集ででも眺める方が、ゆっくりその絵と対話できるのではないだろうか。
同じ理由で、私はどちらをとるかと言われたら、映画だったら大画面で映画館で見るより、家でビデオかDVDを、場面によっては一時停止して少し考え事をしたり、いくどか巻き戻したりしながら見る方が好きだし、音楽だったらコンサートに行って豆粒みたいな実物を見るより、ライヴ映像を何度も繰り返し反芻しながら見る方が好きだ。
そう、本を読むように、味わうのが好き。
*
そういったこともあって、東京に来ていると知っても、すぐに見に行こうとは思わなかった。
作品を味わうには、どういう状況で味わうかというのも大切。環境、背景というものはどんな場合にも重要だ。
いちばん最高の味わい方は、それが生み出されたその土地で味わうということ。
芸術だって地産地消なのだ。
子供のころから愛してやまない、Philippa Pearce の Minnow on the Say を、それが書かれた、ケンブリッジにほど近い小さな村にひと夏過ごして読んだことがある。
あれは最高の経験だった。ほんとに・・・自分の内側と外側、心のなかに抱く世界と、じっさい目に触れる景色、吸いこむ空気、頬にふれる風がつながっている感じ・・・すべてがしっくりとひとつに調和している感覚、夢のように幸福な日々だった。
エセックスの、中世に建てられた、木ずりと漆喰の古い建物に滞在していたことがある。その町全体が、古い建物の多い、中世の香りを濃厚に残した町だった。
寝室の壁に、緑色を基調とした、水車小屋を描いた美しい絵がかかっていて、その部屋の雰囲気に、また窓から見える外の景色などにも実によくあっていた。誰の絵だろう、ずっと気になって、ほかに誰もいないとき、こっそり絵を裏返して見てみた。そうしたら、なんとびっくり、コンスタブルだった。私が知らなかっただけで、すごく有名な絵のようだった。びっくりしたのは、自分のその前の滞在先が、コンスタブルがずっと住んでいたところで、その関係の書物なども買い求めていたからだ。
そのときつくづくと感じられたのは、・・・ここがこんな建物だからこそ、こんな町だからこそ、壁に掛けられたコンスタブルの絵がこんなにも映えるのだ、ということだった。それが描かれたのと同じ世界のつづきなのだ。だから、絵が生きている・・・まわりの空気を吸って、呼吸している。・・・そしてまた、それを見る私もまたその空気を吸って、呼吸して、その同じ世界のなかでこの絵を見ている・・・
極言すれば、こんなふうな状態でなければ、我々はほんとうには見ることもできないし、味わうこともできないだろう。
*
だから・・・オフィーリアだってそうだろう、東京の人ごみのなかでは所在なかろう。じっさいそれを見るまでに、どんな景色の中を通っていくか、ということだって大切なのだ。
やはり野に置け、せめてそれが描かれた国で、見るべきなのではないかな。
だから見るならこんどイギリスに行ったとき、テートまで足を延ばして・・・と、そんなふうに考えていたのだった。
けれど、一方ではまた分かっていた・・・じっさいイギリスに行ったら、ミュージアムになんか行かないだろう。雲の流れゆくにつれ、風の吹きすぎるにつれて刻々と表情の変わる生きた絵を見に、さっさと田舎へ逃げ出してしまうだろう。
せっかく東京まで、来てくれたことだし。これはやっぱり、見に行かないと悪いかも。
そんなわけで、見に行った。
*
じっさい行ってみると、さいしょの印象は、「あんがい小さいな」と。
そういうことって、よくあることなのだけれど。
自分のなかですごく大きな存在となってきたから、実物ももっと大きいものだと思いこんでいた。
でも、ここで大切なのは、忘れないこと・・・じっさいの大きさより、自分の心のなかの大きさの方がほんとうなのだと。
そういうことって、よくあった。
グリーン・ノウだって、トムズ・ミッドナイト・ガーデンのお屋敷だって、じっさいのモデルより、それが描かれた本の中のすがたの方がぜんぜん大きい。
じっさい行ってみると拍子抜けする。
それをさいしょに読んだ時の自分がとても小さかった、というのは確かだけれど、それだけの問題ではない。
それをモデルに書いた作者自身が、自分の大切にする色んなものをそこにありったけ詰めこんで膨らませて描いているから、物語作品になった時点ですでに実物よりはるかに大きいのだ。そして、世界中が愛し、讃えてきたのはそちらの方なのだ。
作者の心のなかに映ったそのイマージュこそが、私を含め、世界中の読者の心のなかで真実となってきたのであり、それこそが尽きせぬ夢とゆたかな滋養を与えてくれてきた。
だから、じっさいの大きさなんてそう大した問題ではない。重要なのはいつだって、それが私の心のなかで、どれだけの大きさであるか。
*
ただ、今回の展示は・・・照明がかなり暗いし、絵と手前の柵との幅を、ほかの絵の場合の3倍くらい広くとってある。だからあんまり細部までつくづくと見えないのだ。
以前にテレビ番組でこの絵を、明るい光の下で細部まで拡大して見せてくれたことがあるのだけれど、正直、そっちの方がありがたかったな、と思ってしまった。
それでも改めて、その緻密な背景描写には感じ入ったし、右端にパープル・ルースストライフが、左端にロビンが描かれているのにもはじめて気がついた。(けど、それももっともなことだった・・・世に出回っている大方のプリントでは、こんな端の方まで印刷されていないのだもの。)
*
すごく興味深かったのは、下絵のデッサン。完成された油絵の方とはかなり違う。
モデルの顔はもっと悲劇的な表情をして、髪はぐねぐねと波打って顔のまわりに広がっているし、たっぷりとしたドレスには小花が散っている。
このイメージは、明らかにボッティチェルリだ。
ところが、完成した絵の方では、人物は異様に緻密な背景のみどりの中に溶けこんで、その表情はほとんど無表情なまでにぐっと抑えられ、髪のうねりも影をひそめて、一様に静謐な表現に変わっている。
それは、イタリア・ルネッサンスの明るく開放的な動的なイメージ、あの降り注ぐ光の世界を、内気で控えめなイングランドに持ちこむ過程でのしぜんな変化でもあったのだろう。たぶん感情的な部分をあえてそうやって抑えたことで、なおいっそう心に訴えかける作品となっている。
*
会場内で、この絵を説明する短い番組が流されていたが、そのなかでテートの学芸員の女性がこんなふうなことを語っていた。
この絵のオフィーリアの、両腕を広げた格好は、伝統的な殉教のポーズであるとともに、その顔の表情は性的でもある。だからここには、死とセックスという相反する要素が同時に表現されているのだ、と。
まあ、分かりやすい説明だし、それも一理あるだろう。でも、そのふたつってそんなに相反する要素だろうか? 感情の極みという点では似たようなものだろう。
私の見る限り、それは両義的というよりはむしろ無表情だ・・・というか中間表情なのだ。
じっと見つめているうちに、私ははっと思いあたる。
これは<泥眼>の表情だ。
<泥眼>(でいがん)は、能の小面のヴァリエーションで、白眼の部分に金泥を塗ったもの、狂女物などに用いられる。
静かなる狂気。
激しい感情の極みにあっては、かえって感情表現は消えてしまい、表情は失われる。世阿弥はそのことを知っていたから、面をつけて舞う能に<狂物>(くるいもの)というジャンルを切り拓いたのだ。
ミレーも下絵をカンヴァスにうつしてゆく過程で、あるいはそのことに気づいていったのではあるまいか。
もしかしたら、モデルのエリザベス・シダルから何か示唆を受けるところもあったのかもしれない。
レオス・カラックスの<ポーラX>。
これはハーマン・メルヴィルの<ピエール、もしくは曖昧性>を映画化したものなのだけれど、そのなかで、主人公の姉役を演じているカテリーナ・ゴルベワという女優がこんなことを言っていた。
映画の終盤で、交通事故にあった主人公のもとへ駆けつけ、警官たちの制止を押し切って狂ったようにそばへ近づこうとする場面、彼女は意図的に無表情に演じたのだという。
悲しみの感情がとても強いので、かえって顔には表れない。彼女はそういう演技をするうえで、日本の能を参考にしたと語っていた。
再び、静かなる狂気。
あの映画は、それほど成功はしなかったのかもしれないが、カラックスの復帰作ということで話題になっていたし、私自身ちょうどメルヴィルのことを論文で書いてたときだったからなかなか感慨深いものがあった。
それにしても国際色豊かだなぁ。メルヴィルは19世紀のアメリカ人だし、カラックスはフランス、ゴルベワはたぶんロシア人。
時代も国境も関係ない。ひとの感情は普遍だし、価値あるものを、評価する人はしているのだ。
オフィーリアの顔をじっと見ていると、私の心には<花筐>(はながたみ)の舞姿が浮かんでくる。<花筐>のシテの照日の前(てるひのまえ)も同じような物語を生きている。このシテにはたぶん、泥眼はつかわないのだろうけど。
日本画の上村松園が、能のこの演目を題材にして描いた絵は有名だ。片手に花籠をもち、狂乱の態で都へ向かおうとする照日の前。
絵のなかの彼女は素面だが、やはり取り憑かれたような異様な無表情。松園もまた、意図的にもともとの能面の感じを投影して描いているのだ。
ミレーと並び称されるラファエロ前派の名匠に、ジョン・ウォーターハウスがいて、彼もまた彼のオフィーリアを描いている。
その構図がまた、松園の花筐の絵にそっくりなのだ。
狂乱の態、立ち姿、手に花をもっているところまで似ている。彼のオフィーリアは川に落ちる直前の姿だ。
私はこの絵を、絵はがきで知っているだけだ。
ハムステッド・ヒースに程近いゴルダーズ・グリーンの駅のそば、フランス人の女性アーティストがやっているとてもおしゃれで居心地のいいカフェがあって、この町に滞在していたとき何度か行っていた。絵から、食器から、アンティーク家具から、この女性の目に適ったものがインテリアを兼ねていろいろ売られていた。
そのなかで、一枚のポストカードが目を引いたのだった。映画の一場面のような美しい絵。川岸に、手に花を持ち、青いドレスを着て佇む若い女。だが、その目だけが異様だった。その目は狂気の目だった。
買い求めてからはじめて裏返して見て、それがウォーターハウスの<オフィーリア>だったことを知った。それで、あんな眼をしていることにも合点がいったのだった。
かくて<静かなる狂気>の系譜は、あちらこちらでしずかにつながっている。・・・
*
ミレーの<オフィーリア>の濃密なドラマ性は、背景の息詰まるようなこまかい自然描写によるところが大きい。実はこの絵は、背景を先に描いたのだという。
「忠実な自然描写を心がけていたミレイは、<オフィーリア>の背景にふさわしい風景を求め、1851年7月から11月にかけて、ロンドンの南西、サリー州のユーウェルという町に滞在し、ホッグズミル川沿いで朝から日没まで絵筆をとって緻密に写生した。写生時期は数ヶ月にも及んだため、画面の中には異なる季節の花も混在している。」
(Bukamura ザ・ミュージアム ジョン・エヴァレット・ミレイ展作品リスト裏の解説文より。)
そのあとで人物を描きこんだために、人物の方がその背景に調和するように調整された、という部分ももちろんあるだろう。
はじめて実物を、つくづくと見たとき、なんかこの人の絵の描き方って、自分の文章の書き方に似てるな、と思った。
背景の方を先に描いたというこの逸話を知り、ますます親しみがわく。
私も文章を書くとき、背景の自然描写のディテールをすごく大切にする。物語のプロットに入る前に、舞台となるその土地の描写をながながと書き連ねる。それで飽きたりうんざりする人も多いだろうと分かってはいるけれど、自分としてはどうしてもここに持ってくる必要があるのだ。その土地からこそその物語は生まれてきたのだし、だからその土地で私が見聞きしたものを記しておきたい、読者とも共有したい。
その土地、その風土、背景というものは、それだけでひとつの世界だ。
そこに人物とか物語がなくても。
無限のドラマを、あらたにいくらでも生み出せる宇宙スープのようなもの。
人物のほうが、「ついでにあるもの」なのだ。別になくてもいい。
だから、ほんとは<背景>って名前が悪い。
ほんとは<背景>なんかじゃなく、<母胎>とか<源>とか呼ぶべきものなのだ。
パリ近郊に出かけて、「印象派の絵そのままの風景、光」とか形容する人がよくいるけど・・・逆だろうそれは。そういう風景が、光があったから、それで印象派の絵が生まれてきたのだ。
絵でも文学作品でも何でも、それを生み出した土地のなかに身をおいてはじめて分かることがある。そういうすばらしいものがなぜ生まれえたのか、それを生み出すのにどういうものが必要だったのか。
人がアートを生み出すのじゃない。人は、与えられるのでなければ何ひとつ生み出せはしない。
メルヴィル。「土地が人間をつくるのだ」<マーディ>。
ゆえに、我々はそれを敷衍してこのように言えるはずだと思う。
「土地がアートを生み出すのだ」と。・・・