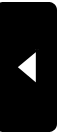2014年01月29日
追憶
このころほんとにこういう感じが好きだったな。ほとんど次とかぶるけど。
詞華集カフェ・ジュヌヴィエーヴ 3
追憶
静かな雨の日の午後。うす暗い室内。
レースのカーテンのかかった窓。
窓辺に置かれた書斎机、紙と鵞ペンとインク壺。
空き瓶にさしたかすみ草。
鋳鉄製の背の高いベッド。
部屋の中のものをまるく映し出している石油ランプのほや。
静寂の中に、遠い記憶がふと呼び覚まされる。
霧の散歩道。すっかり葉を落とした木々のこずえ。
雨粒をいっぱい散りばめたくもの巣。
手をつっこんだポケットのぬくもり。
ゆっくり歩いてゆくコートの後ろ姿。
古いレンガの橋。二つのアーチが揺れ動く水に映って眼鏡のように見えるから、眼鏡橋という名前だ。
手すりに身をもたれて、川の中に石を投げ入れている小さな子供。
ぬれた石畳。
灰色の縞猫がたたずんでいる、古風な装飾の窓。
路上のスミレ売り。
新聞屋の店頭を飾る絵はがき。
やわらかなオレンジ色の光を通りに投げかけている街角のカフェ。
ガラスごしのほおづえ。
少し曇りの出た銀のミルク入れ。
流れおちる雨にぼやけてかすむ往来の人影。
飛び立つ鳩の群れ、びしょぬれの青銅の騎士。
夕やみの中に浮かびあがる街灯の光。
大通りを行き交う色とりどりの傘。
うす灰色の空をふるわせてゆく 時計台の鐘のひびき。
(1993)
詞華集カフェ・ジュヌヴィエーヴ 3
追憶
静かな雨の日の午後。うす暗い室内。
レースのカーテンのかかった窓。
窓辺に置かれた書斎机、紙と鵞ペンとインク壺。
空き瓶にさしたかすみ草。
鋳鉄製の背の高いベッド。
部屋の中のものをまるく映し出している石油ランプのほや。
静寂の中に、遠い記憶がふと呼び覚まされる。
霧の散歩道。すっかり葉を落とした木々のこずえ。
雨粒をいっぱい散りばめたくもの巣。
手をつっこんだポケットのぬくもり。
ゆっくり歩いてゆくコートの後ろ姿。
古いレンガの橋。二つのアーチが揺れ動く水に映って眼鏡のように見えるから、眼鏡橋という名前だ。
手すりに身をもたれて、川の中に石を投げ入れている小さな子供。
ぬれた石畳。
灰色の縞猫がたたずんでいる、古風な装飾の窓。
路上のスミレ売り。
新聞屋の店頭を飾る絵はがき。
やわらかなオレンジ色の光を通りに投げかけている街角のカフェ。
ガラスごしのほおづえ。
少し曇りの出た銀のミルク入れ。
流れおちる雨にぼやけてかすむ往来の人影。
飛び立つ鳩の群れ、びしょぬれの青銅の騎士。
夕やみの中に浮かびあがる街灯の光。
大通りを行き交う色とりどりの傘。
うす灰色の空をふるわせてゆく 時計台の鐘のひびき。
(1993)
2014年01月29日
カフェ・ジュヌヴィエーヴ
このころの夢や愛していたイメージを、ぎゅっと詰めこんだブーケのような小品。そのひとつは<ベルベット・イースター>。
詞華集カフェ・ジュヌヴィエーヴ 4
カフェ・ジュヌヴィエーヴ
日曜日、朝。曇り。
明け方まで降っていた霧雨が、
下町の古びた家並をしっくりと溶けあわせている。
少しくたびれたレースのカーテンごしにさすうす暗い光のなかで、
イレーヌはしばらくまどろんでいた。
それからゆっくりと起き上がり、ベッドの上で片膝を抱えて、
何を見るでもなく 部屋の一隅をぼんやりと眺める。
こういう天気の日には、この部屋の中に沈澱している過ぎ去った時代の感じが殊更強まるように思われる。
祖母の記憶―蜂蜜入り石鹸の匂い。
ここは、祖母が亡くなるまで祖母の部屋だった。
この部屋にあるものも大方はみな祖母のものだ。
鋳鉄製の背の高いベッド、洋服だんす、こわれたランプ。
少し曇りのでた、どっしりとした鏡台―埃をかぶったカスミ草がひと束、
ジャムの空き壜にさしてある。
それから、イレーヌの着ている昔風の白いねまきも。
祖母はおしゃれな人で、そんなに暮らし向きもよくなかったのに、
ブローチやネックレスやレースの手袋など、優雅で古典的な品々をたくさんもっていた。
イレーヌも、時どきはそういうものを眺めて楽しむけれど、
自分で身につけることはめったにない。
イレーヌは、ようやくベッドから降りると、
洋服だんすの中から細身の黒いワンピースと、淡いすもも色のカーディガンを選び出した。
それから、つば広の白い帽子を取り出して、鏡に向かっていろいろかぶり方を試してみる。
やがてジョルジュがやってきて、二人は連れだって出掛ける。
彼らはぶらぶらと街を抜け、野原や小麦畑のあいだの細い小径を通って歩いていく。
*
こういうおだやかな曇りの日には、ものごとの美しさがもっとも正直に、はっきりと見える。
緑色の海に浮かぶ星々のように、生い茂る雑草にまじって咲くマーガレット。
矢車草、あの少し紫がかった、深く澄んであざやかな青。
咲き乱れる真っ赤なけしの花びら。
農家の庭先にはつるバラ、ライラック、すずらんに色とりどりのアネモネ。
青い菫に忘れな草、足もとにぬれるクローバー。
川岸に芽吹く柳のみずみずしさ。
静かな川面。
遠くの森の微妙な色あい―ところどころ、白っぽい淡い緑がまじる。
遠くからのぞむ街の風景も、たしかに美しい。
彼らは来た道とは別の道を通って街へ戻る。
*
通りから少し外れた街角にある静かなカフェ、ジュヌヴィエーヴ。
飾り気のない石造りの入り口の両脇には、髪を結い、流れるような衣をまとった美しいブロンズの女性像が据えられて、
それぞれまるいガラスの月を―水瓶をかかげるように片方の肩にのせて―かかげている。
今日のような少しうす暗い日には、昼間からこのガラスの月に灯りがともされて、石畳にやわらかい光を投げかけている。
ジョルジュとイレーヌは窓際に近いテーブルにつき、サンドウィッチとコーヒーを注文する。
古時計がものうげにチクタクいうのをききながら頬杖をついて、道ゆく人々をただぼんやりと眺める。
こころよいざわめき。銀製のポット。
使いこまれた円テーブルのふちのなめらかさ。
カフェ・ジュヌヴィエーヴを出るころ、静かに雨が降り出す。
二人はジョルジュのこうもり傘を広げ、表通りを冷やかして歩く。
絵はがき。ティーセット。レコード。
街角の新聞売り。ベタベタと貼られた広告塔。
うす青いろの夕闇に浮かびあがる街灯の光。
往き交う人びと。
ワルツを踊るようにくるくると流れてゆく雨傘たち。
(1993?)
詞華集カフェ・ジュヌヴィエーヴ 4
カフェ・ジュヌヴィエーヴ
日曜日、朝。曇り。
明け方まで降っていた霧雨が、
下町の古びた家並をしっくりと溶けあわせている。
少しくたびれたレースのカーテンごしにさすうす暗い光のなかで、
イレーヌはしばらくまどろんでいた。
それからゆっくりと起き上がり、ベッドの上で片膝を抱えて、
何を見るでもなく 部屋の一隅をぼんやりと眺める。
こういう天気の日には、この部屋の中に沈澱している過ぎ去った時代の感じが殊更強まるように思われる。
祖母の記憶―蜂蜜入り石鹸の匂い。
ここは、祖母が亡くなるまで祖母の部屋だった。
この部屋にあるものも大方はみな祖母のものだ。
鋳鉄製の背の高いベッド、洋服だんす、こわれたランプ。
少し曇りのでた、どっしりとした鏡台―埃をかぶったカスミ草がひと束、
ジャムの空き壜にさしてある。
それから、イレーヌの着ている昔風の白いねまきも。
祖母はおしゃれな人で、そんなに暮らし向きもよくなかったのに、
ブローチやネックレスやレースの手袋など、優雅で古典的な品々をたくさんもっていた。
イレーヌも、時どきはそういうものを眺めて楽しむけれど、
自分で身につけることはめったにない。
イレーヌは、ようやくベッドから降りると、
洋服だんすの中から細身の黒いワンピースと、淡いすもも色のカーディガンを選び出した。
それから、つば広の白い帽子を取り出して、鏡に向かっていろいろかぶり方を試してみる。
やがてジョルジュがやってきて、二人は連れだって出掛ける。
彼らはぶらぶらと街を抜け、野原や小麦畑のあいだの細い小径を通って歩いていく。
*
こういうおだやかな曇りの日には、ものごとの美しさがもっとも正直に、はっきりと見える。
緑色の海に浮かぶ星々のように、生い茂る雑草にまじって咲くマーガレット。
矢車草、あの少し紫がかった、深く澄んであざやかな青。
咲き乱れる真っ赤なけしの花びら。
農家の庭先にはつるバラ、ライラック、すずらんに色とりどりのアネモネ。
青い菫に忘れな草、足もとにぬれるクローバー。
川岸に芽吹く柳のみずみずしさ。
静かな川面。
遠くの森の微妙な色あい―ところどころ、白っぽい淡い緑がまじる。
遠くからのぞむ街の風景も、たしかに美しい。
彼らは来た道とは別の道を通って街へ戻る。
*
通りから少し外れた街角にある静かなカフェ、ジュヌヴィエーヴ。
飾り気のない石造りの入り口の両脇には、髪を結い、流れるような衣をまとった美しいブロンズの女性像が据えられて、
それぞれまるいガラスの月を―水瓶をかかげるように片方の肩にのせて―かかげている。
今日のような少しうす暗い日には、昼間からこのガラスの月に灯りがともされて、石畳にやわらかい光を投げかけている。
ジョルジュとイレーヌは窓際に近いテーブルにつき、サンドウィッチとコーヒーを注文する。
古時計がものうげにチクタクいうのをききながら頬杖をついて、道ゆく人々をただぼんやりと眺める。
こころよいざわめき。銀製のポット。
使いこまれた円テーブルのふちのなめらかさ。
カフェ・ジュヌヴィエーヴを出るころ、静かに雨が降り出す。
二人はジョルジュのこうもり傘を広げ、表通りを冷やかして歩く。
絵はがき。ティーセット。レコード。
街角の新聞売り。ベタベタと貼られた広告塔。
うす青いろの夕闇に浮かびあがる街灯の光。
往き交う人びと。
ワルツを踊るようにくるくると流れてゆく雨傘たち。
(1993?)
2014年01月29日
蝋燭
このころから、電気がきらいでできるだけ蝋燭を使っていた。
詞華集カフェ・ジュヌヴィエーヴ 5
蝋燭
今晩はまったく、普通の寒さじゃない。
寝床の床をはだしで歩くと、もう足の感覚がなくなって、冷たいよりもずきずきと痛い。
ぼくの寝室はまるで北極のようだよ。
しかし、この暗やみの中に灯る一本の蝋燭の、何と美しく、心安らぐことか! それは凍てついた夜の海の灯台、さまよう船をみちびき、あたたかな休息を約束する光だ。
この金色の炎、ほのかに光る十字、刻一刻とかたちを変えるふち飾り。
りんごの蜜のように 半ば透き通って。
夜な夜なあらゆる屋根の下で灯される、こんな平凡な蝋燭こそ、きっと世界でもっともすばらしいものの一つなのだ。
そしてそのすばらしさはおそらく、人が生まれてきて、頭が真っ白になるまで夜ごと枕元に灯し続けても、その快さが変わらないことにあるのだ。
このなつかしい、素朴なかたちには、たくさんの人生が刻まれている・・・
(1993)
詞華集カフェ・ジュヌヴィエーヴ 5
蝋燭
今晩はまったく、普通の寒さじゃない。
寝床の床をはだしで歩くと、もう足の感覚がなくなって、冷たいよりもずきずきと痛い。
ぼくの寝室はまるで北極のようだよ。
しかし、この暗やみの中に灯る一本の蝋燭の、何と美しく、心安らぐことか! それは凍てついた夜の海の灯台、さまよう船をみちびき、あたたかな休息を約束する光だ。
この金色の炎、ほのかに光る十字、刻一刻とかたちを変えるふち飾り。
りんごの蜜のように 半ば透き通って。
夜な夜なあらゆる屋根の下で灯される、こんな平凡な蝋燭こそ、きっと世界でもっともすばらしいものの一つなのだ。
そしてそのすばらしさはおそらく、人が生まれてきて、頭が真っ白になるまで夜ごと枕元に灯し続けても、その快さが変わらないことにあるのだ。
このなつかしい、素朴なかたちには、たくさんの人生が刻まれている・・・
(1993)